農山村ではだれもが、かけがえのない存在だ
若者たちの「進路創造」新段階
目次
◆国の予算に左右されず「田舎で働き隊!」実施!
◆農産物と雇用――1995年の大転換
◆若者の4割が定住する「緑のふるさと協力隊」
◆農家が支援する若者の「進路創造」
◆縦割り政策を地域で横につなぐ
▲目次へ戻る
不況・雇用不安のなか、農業や林業、水産業への就業を希望する人々が急増し、自治体や関係団体による就業相談会も盛況である。国でも、農林水産省が、農山漁村で働きたい人材を都市から地方に派遣する「田舎で働き隊!」(農村活性化人材育成派遣支援モデル事業)を2008年度中から実施すると発表した。08年度中は10日間程度の「きっかけコース」の短期派遣を約800人、09年度は最長1年間派遣の「おためしコース」を約50人予定し、2月16日まで仲介機関(NPO法人・大学・観光協会・農漁協・森林組合など)を公募している。総務省も09年度の事業として、農山漁村自治体が都市の若者ら数百人を「地域おこし協力隊員」(仮称)として募集し、1〜3年程度農山漁村で働いてもらう「地域力創造プラン」を発表した。
昨年8月発表の総務省「集落支援員制度」と併せ、これらの施策を金融危機・雇用崩壊による失業者・内定取消し者を吸収する「緑のニューディール政策」とする報道もあるが、一時的な対症療法ではなく、グローバリズムに振り回されない農業と地域経済、地域の創造にむけた新しい人の流れを、むらから、地域からつくる機会として、活かしたい。
▲目次へ戻る
国の予算に左右されず「田舎で働き隊!」実施!
「田舎で働き隊!」の「きっかけコース」約800人には15万円を上限とする旅費と、一日当たり7000円の研修手当の支給が予定され、約10億円の予算が見込まれている。一方、「おためしコース」約50人には月額14万円の研修手当支給で予算は約2億円。これにいち早く名乗りを挙げ、隊員を募集しているNPO法人に、熊本県菊池市の「きらり水源村」がある。廃校となった中学校校舎の活用のために校区330戸の住民で結成したNPOで、校舎を改修した「きくちふるさと水源交流館」を拠点に、都市の親子が1年を通じて米づくり、食べものづくりを中心に農山村の生活文化を体験する「菊池おいしい村づくり」、地区の伝統芸能を伝える「きらり神楽教室」、農産物の加工や直売、水源地元学による地域資源マップづくりなどの活動を行なってきた。
水源村ではこの3月、菊池市や熊本県と協力し、水源交流館を舞台に10日間3コースの「きらり水源村 田舎で働き隊!」を実施する。農水省の「きっかけコース」を活用する取り組みだが、これは平成20年度(第2号)補正予算の政府原案に基づいており、「定額給付金」がらみの国会次第では補正予算が成立せず、「田舎で働き隊!」を実施しても国から費用が支給されない危険性もある。しかし、水源村では一人5万円〜7万円の参加費と旅費を自己負担してでも参加したい若者を1月20日時点ですでに10数名確保し、実施を決めている。そして予算が成立し、水源村が「認定研修生」と認めた場合に、「研修参加による日当補助、及び交通費補助」を支給するとしている。水源村では国の予算がどうなろうとも、「働き隊!」を実施するのだ。
水源村事務局長の小林和彦さんは1974年埼玉県生まれの34歳。國學院大学経済学部在学中には神社本庁主催の「千年の森づくり」、小野田自然塾のキャンプリーダーを体験し、96年から国内外で共同生活をしながらさまざまなボランティア活動やグループ活動を行なうNGO組織「NICE」(日本国際ワークキャンプセンター)事務局長として活躍、04年に「きらり水源村」の募集に応じて事務局長となった。今回の「働き隊!」参加希望者の多くは、小林さんが正月に埼玉に帰省するついでにNICEの関西・関東地方での忘・新年会に参加して誘った学生たちだ。
小林さんが水源村事務局長を引き受けたのは、農山村のお年寄りから「お金を使わなくとも生きていける知恵や技」を受け継ぐには「あと10年が限度」と考え、「5年で受け継ぎ、5年で下の世代に伝えよう」という思いからだという。その前段階の5年が過ぎようとしているとき「働き隊!」事業のニュースが流れた。現在水源村では有給スタッフ5名が働いているが、小林さんは、新たな雇用の創出、さらには事務局長後継者の育成のためにこの事業を活用しようと考えたのだ。
▲目次へ戻る
農産物と雇用――1995年の大転換
「田舎で働き隊!」受け入れに名乗りを挙げている仲介機関には他に、山梨県北杜市の「NPO法人えがおつなげて」、千葉県鴨川市の「NPO法人大山千枚田保存会」などがあるが、きらり水源村も含め、これらの団体の特徴は、35歳以下の若者が中心となっていることだ。1月8日のNHK総合テレビ「クローズアップ現代」――「故郷はよみがえるか―検証・過疎対策の大転換」――で集落支援員のモデルとして紹介された新潟県上越市の「NPO法人かみえちご山里ファン倶楽部」、島根県中山間地域研究センター派遣の「里山プランナー」も35歳以下が中心である。
なぜ、「35歳以下」なのか――農文協発行の『増刊現代農業』では、若者たちの動きに早くから注目し、2005年8月増刊では『若者はなぜ、農山村に向かうのか』を特集。同年の本誌10月号では同タイトルの「主張」をまとめ、次のように述べた。
「『若者はなぜ、農山村に向かうのか』の企画・取材で若者の後を追ううち、彼らの年齢が圧倒的に32歳前後であることに気づき、なぜそうなのかを調べてみた。そして慄然とした。日経連が『新時代の日本的経営――雇用ポートフォリオ』なる雇用のガイドラインを発表したのが1995年。まさに彼らが大学を卒業した年である。そこでは『雇用の柔軟化』として(1)長期蓄積能力活用型(将来の幹部候補として長期雇用が基本)(2)高度専門能力活用型(専門的能力を持ち、必ずしも長期雇用を前提にしない)(3)雇用柔軟型(有期の雇用契約で、職務に応じて柔軟に対応)と、雇用が3タイプに分けられた。不況で企業の採用数が減っただけではなく、雇用の形態そのものが終身雇用・年功序列の時代から大きく変化していたのだ。連合などの労働界もそれを許容した。こうして正社員は激減し、『安価で交換可能なパーツ労働力』として派遣・契約社員、パート・アルバイトが大幅に増加することになった。」
1995年という年は、若者の雇用が激変した年であるだけでなく、WTO発足の年でもあり、グローバリズムが急激に加速した年でもあった(ちなみに前年の94年に「就職氷河期」「価格破壊」が流行語大賞にノミネートされていた)。農村にとっては、食管法が廃止されるとともに、ミニマム・アクセス米の輸入が開始され、以降、米価は下落する一方となった。労働市場の自由化とともに、農産物市場の自由化が加速した年が95年だった。
だが農村では、市場原理の激化に抗するように、女性や高齢者を中心として、朝市、産直、直売所、グリーンツーリズム、農村レストラン、定年帰農、地元学、食の文化祭、食農教育、棚田保全などの動きがつぎつぎに起きた。そんな動きに刺激されて農山村に向かった若者たちは、むらの高齢者や女性の知恵や技、働くその姿に「代替不可能な労働」を発見し、大きな魅力を感じて活動をともにするようになった。
▲目次へ戻る
若者の4割が定住する「緑のふるさと協力隊」
今回の「田舎で働き隊!」「地域おこし協力隊」の典型的なモデルとなったのは、1994年から東京の「NPO法人地球緑化センター」と地方自治体がすすめてきた「緑のふるさと協力隊」である。農山村に関心をもつ若者を、地域活性化をめざす農山村に1年間派遣するもので、これまでの15年間に男女384人が派遣されている。期間中、隊員は原則として集落に家を借り、農林畜産業や直売所、道の駅、特産品開発、グリーンツーリズムなどのイベントを手伝い、支給される月5万円の生活費で暮らす。隊員たちが派遣先で学んだことを発信する「ふるさと通信」にはこんな声が綴られている。
「鮫川村は『豆で達者な村づくり』として、豆で村おこしをしている。全量村民がつくり、全量村内で加工、販売する。地産地消でもあり、そうすることで、村のお年寄りの健康づくりと利益を上げている。それが村として生き残る方法だった。農村の暮らしはとてもゆっくりと過ぎてゆくものだと思っていたけど、村として存続するためには都市以上にパワーが必要だった。本当によく働く人が多い。それは村のため、村民のためという概念があるからだと思う」(福島県鮫川村派遣・伊藤真之さん・21歳)
「『それぞれがそれぞれに集まって、すべきことをする』。そんな風土がここにはあった。これは全員が全員、自分の役割を知っているためにできることなのだろう。たとえば、たまたまそこにいた人が集まり、話の流れで何かをしようと企画する。自然とそのメンバーで実行委員会が立ち上がり、次第に準備が当たり前に進んでいく。ふと立ち止まってみると、それにはたしかにそこにいる全員が必要で、周到に計算されたようにそれは充分だったりした。そしてそのなかには、まだ来たばかりの自分がいて、なすべきことをしたりしている。そんなとき、何が自分に求められていて、いま何をなすべきか、不思議なくらいにそれはわかりきっていた。『いらない人間は誰ひとりいない』。ある人に言われた。そんな言葉の意味がやっとわかった」(福井県池田町派遣・松浦伸也さん・23歳)
「緑のふるさと協力隊」の派遣期間終了後の定着率は約四割。その高さが国会で話題になったこともあったが、たとえ終了後に都市に戻ったとしても元派遣先の市町村や集落のファンとして農産物や加工品のPRを手伝ったり、台風被災時にまっさきにボランティアとしてかけつけたりするという。
群馬県上野村にはこれまでの14年間に32人が派遣され、うち8人がいまも村に暮らしている。上野村には元協力隊とは別に村外から移り住んだIターン組が150人余りいるが、上野村と東京を行き来する暮らしを35年続けている哲学者の内山節さんは、今年元日の朝日新聞(群馬県版)のインタビュー記事で次のように述べている。
「効率を最優先する市場経済の拡大で、われわれはみな代替可能な労働力になってしまった。反面、支え合うのが当たり前な農山村では誰もがかけがえのない存在だ」「この15年ほどで若い世代は、市場システムに忠実に従っても安定が保証されないと感じるようになった。農山村が、かけがえのない自分を確認できる場所だと気づく人は、若者たちを中心に、確実に増えている」
▲目次へ戻る
農家が支援する若者の「進路創造」
「いらない人間は誰ひとりいない」こと、そして自分が「かけがえのない存在」であることを若者に感じさせ、ともに村づくりの仲間として支援する農家や集落の活動も全国各地で、数多く始まっている。国の制度を上手に活用するとともに自前で資金を集め、若者たちの仕事づくりを支援する農家があちこちで生まれているのだ。
たとえば福岡県黒木町の椿原寿之さん・宮園福夫さん。椿原さんらは、都市と農山村の交流を通して山村の自然を守ろうと、1994年に「山村塾」を立ち上げた。同年から始まった中山間地域等直接支払制度の交付金とともに、都市部の約100家族からなる山村塾会員からのカンパ、会費や行事参加費の一部などで「ヤマヤマ基金」を創出し、2000年からスタッフとして働いている、九州芸術工科大学卒業の32歳・小森耕太さんの賃金を捻出している。小森さんには賃金以外に農作業や山仕事の日当、イベントのコーディネート料などの収入もある。
山村塾では昨年9月1日から11月19日まで、海外から3名、国内から6名の参加で遊歩道や森林整備、地域行事や国際ワークキャンプをサポートする「里山80日ボランティア」を行なった。小森さんとともに80日間スタッフとして活動を支えたのは、東京の成蹊大学4年生・松本裕也さん。卒業後いったんは就職するものの、いずれ農村で山村塾のような活動に従事したいと考えているという。
滋賀県湖北町では昨年、「家も建てる農家」の松本茂夫さんと「米もつくる大工」の清水陽介さんが、「農業×建築」の技を身につければ=手に職をもてば、これからの農村で自由な時間と安定した収入が得られると、年間2人の若者を受け入れ、月10万円の給与を支払い、3年目の自活を促す「どっぽ村プロジェクト」をスタートさせた。ここにはすでに農業も建築もできる若者が2人いて、その1人村上悟さんは、どっぽ村のコミュニケーションサポート(連絡調整・広報補助)を引き受けている。村上さんは滋賀県立大学大学院で自然環境保全と地域経済活性化の両立を学んだ32歳。大学院修了後は茨城県の「NPO法人アサザ基金」で4年間働いた後、湖北町に隣接する余呉町に住み、「農村デザインアトリエ 夢現創舎」を個人事業者として営むだけでなく、滋賀県北部地域の農商工連携を進める「NPO法人湖北えぇもんづくり本舗」の事務局、環境専門生協「滋賀県環境生活協同組合」の非常勤職員としても働いている。
山村塾の小森さんやどっぽ村の村上さんのように、いま、農山村で活躍する若者の特徴は、複数の仕事の組み合わせで収入を得ていることだ。松本さんはこう話す。
「単品目から多品目へ。単一の仕事の中で効率を上げる『サラリーマン』的な仕事観から、複数の仕事を組み合わせて総合的に効率を上げる『百姓』的な仕事観への転換が、田舎で生活していくために重要な鍵になると思いますし、その転換の先には、都市と農村が調和した新たな社会のあり方が開けてくると思います」
農家の支援を得ながら、サラリーマンや公務員といった既存の進路の「選択」ではなく、新たな進路を「創造」してきた若者たち。そんな若者たちが、後に続く世代を呼び寄せ、ともに地域づくりの役割を担おうとしているのが「いま」という時代なのだ。
▲目次へ戻る
縦割り政策を地域で横につなぐ
京都府綾部市、長野県泰阜村、岐阜県高山市は来年度から新たに「協力隊」を受け入れることを決定した。きびしい地方財政の中、1人当たり約150万円かかる「緑のふるさと協力隊」受け入れ費用を自治体が負担するのは困難がともなう。これを可能にしたのは、国の特別交付税で措置される集落支援員制度を活用することであった。
一見縦割りに見える国の施策を、地域という面で横につなぎ、活用していくこともできる。農水省の来年度の「田舎で働き隊!」おためしコースは月14万円の研修手当のうち国の補助は2分の1だが、総務省の集落支援員制度や地域おこし協力隊制度と組み合わせて残り2分の1を手当てすることも可能になるかもしれないという。
かみえちご山里ファン倶楽部事務局長(当時)の中川幹太さんは、前掲『若者はなぜ、農山村に向かうのか』で次のように書いていた。
「小さな町村は、国の縦割り政策を、微弱な力ながらも地域という横でつないでいたのですが、平成の大合併により、それも破壊されました。地域を大局的に見る、つまり村を『クニ』と見立てて対策を打っていく役割と機能が、NPOにますます必要になってきています」
ここでいう「クニ」とは、本欄「主張」がこれまで「校区コミュニティ」「地域コミュニティ」と呼んできたような、従来の町村区分より小さないくつかの集落の集まりのことである。そんなコミュニティづくりに生きがいを感じる若者を、農家や住民が自前の資金で、都市住民からのカンパで、そして自治体や国の資金を縦横に生かして育てていく。「いま」という時代はそんな時代でもあるのだ。
(農文協論説委員会)
■お知らせ「集落支援員全国交流集会――若者が集落の元気をつくる」(主催・中山間地域フォーラム 共催・地球緑化センター・農文協) 2月28日(土曜)13時半〜17時 東京明治大学リバティータワー
関連リンク
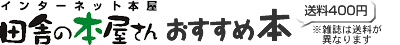
 |
『若者はなぜ、農山村に向かうのか』 戦後60年、農山村をまもり抜いた祖父母世代に感動、その知恵と技の消滅のスピードと競い合うように農山村の「暮らし」に学び、都市生活者や子どもたちへ伝える「仕事」をおこした若者たち――若者の求める居場所と役割、暮らしと仕事は農山村にあった!
[本を詳しく見る]
|
 |
『写真物語 ナカノマタン』NPO法人かみえちご山里ファン倶楽部 新潟県上越市中ノ俣は50戸90人の小さなむらでいわゆる「限界集落」。「地域に元気を取り戻そう」と住民たちが昔ながらの農業と暮らしを再現、その持続可能な知恵と技を都市から移り住んだ若者たちが記録した。
[本を詳しく見る]
|
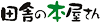
|

