農耕的自然が子どもの感性を育む
自然を教科書にするための手引き『復刊 自然の観察』
目次
◆農家は『自然の観察』をこう読んだ
◆幻の本『自然の観察』のねらい
◆麦畑と虫とりの授業
◆学級園や飼育小屋の役割
◆「科学的精神」とは農家の営みそのもの
◆身近な自然を豊かにすることから
先月号に登場した茨城の米川二三江さんは、農家に嫁いで最初のうちは畑の虫のことも病気のことも何も知らなかったという。虫や病気の葉っぱを見つけては、そのままポケットに入れて持ち帰り、せっせと図鑑をめくるうちに詳しくなり、さらには草と虫との不思議な関係にも気づくようになった。いまでは、アオムシがつかないスギナ汁や、ハコベにおびき寄せてのヨトウムシ退治など、ユニークな防除術をつぎつぎあみ出す達人である。米川さんのような農家が地元の小学校の「畑の先生」をやったら、さぞや子どもたちは夢中になることだろう。
そんな実践的で創意豊かな農家の発想をさらに広げてくれそうな手引き書が最近復刊され、話題になっている。その名は『自然の観察』。約70年前の昭和16年から17年にかけて文部省から5分冊で発行されたものの、敗戦後の昭和21年、GHQの専門部の指示によって、その革新的な内容にもかかわらず学校現場で焼却処分されてしまった、幻の名著といわれる本である。
▲目次へ戻る
農家は『自然の観察』をこう読んだ
このたび農文協から復刊された『自然の観察』では原本の5分冊を1巻にまとめ、現代表記とし、解説・改題がついた。まずはこの『復刊 自然の観察』を読んだ栃木県の農家・上野長一さんの感想文を紹介しよう。上野さんは数多くの米の品種を種モミのときから混ぜて混植する「色々米」という斬新な稲作に取り組んでいる方だ。
「『自然の観察』を拝読させていただき、私が小学校の時と照らし合わせてはっと気づいたことがあります。今から50年前の小学生のとき、午前中は教室の中で学び、午後は教室外に出て、体育、図工、写生、または林の中で四季折々の活動をした――、そんな覚えしかないのです。午後の授業は楽しかったですね。花壇の手入れ、池のそうじ、庭木の手入れ、ときには林に入り、川に入り、さまざまな生きものたちとの学びがありました。そんな授業の内容と、この『自然の観察』の内容が重なりあいました。
今や農業技術はマニュアル化され、肥料や農薬を作物の生育に合わせて施す技術が整えられています。それは百姓自らの作物に対する観察力がなくなっているからなのかもしれません。今の技術は湿度や光、諸々の環境を作物がよく育つであろうと思うところにセッティングし、作物を収量ベースでのみ考えてしまっています。そこには生命の折り合い、重なりあい、連鎖を見る目はなく、作物のみを見る目だけを養ってしまっているのではないでしょうか。『観察の目』は百姓の仕事として、作物の次への感覚を楽しく育てるためのステップであると感じます。
この本は百姓にも観察に目を向けさせてくれ、生きものたちのかかわりあいのおもしろさとその感じ方を教えてくれます。
子どもたちに農業を教えるときも、ものごとを覚えさせること以上に、自然への感性、感覚、気づきといったことを大事にし、次へのキッカケづくりをしたい気がします」
▲目次へ戻る
幻の本『自然の観察』のねらい
そもそもこの『自然の観察』という本はどういう経緯で生まれたのだろうか。昭和16年、17年といえば、国じゅうが戦時体制に向かい、尋常小学校は国民学校と名前を変え、子どもたちが「少国民」と呼ばれるようになった時代だ。このころから「皇国」に奉仕し、銃後を支える国民の育成が教育の目標となっていく。しかし、ちょうどこのころ低学年理科では、自然に親しみながら学ぶ「自然の観察」という革新的な新教科がスタートし、普及のための手引き書まで配布されていた。それが『自然の観察』だ。
「自然の観察」という新教科はそれまで小学校4年生以上で行なわれていた尋常小学校理科があまりにも知識の伝授に偏っていたことへの反省から生まれた。それまでの理科の教科書といえば、「馬とは毛がこまかに生えている。頭には2つの鼻のあなと、大きな口とがある」式のものであり、授業はもっぱら教師がこの教科書の知識を授ける形で行なわれた。つまり、理科はおおかたの子どもたちにとっては退屈な暗記科目だったのである。
これに対して、「自然の観察」では小学校低学年から自然に親しみながら科学的精神を育てようとした。編纂の中心となった岡現次郎(当時の文部省図書監修官)はこう述べている。
「小学校低学年くらいまでの子どもは自然と自分を切り離さず、一体のものとしてとらえている。自然に親しみ、自然を愛好し、自然に驚異の目をみはり、自然のありのままの姿をつかむというような自然に対する態度は、このような『主客未分化』の時期の指導が、きわめて重要な意義をもつ。知情意一体となって自然にはたらきかけるには、この時期をはずしてはほとんど不可能」であると。その上に健全な科学的精神が宿るというわけである。
至極まっとうな考え方ではないだろうか。
そのうえ「自然の観察」では児童用の教科書はつくられなかった。なまじ教科書をつくってしまうと、教師は野外に子どもを連れ出すことなく、教科書を読むだけで授業を済ませる恐れがあると考えたからだ。教師が予期せぬ質問がでる野外学習より座学を「与し易し」と見るのは今も昔も同じ。当時の文部省の見識はなかなかのものであった。
▲目次へ戻る
麦畑と虫とりの授業
『自然の観察』がすすめる授業の中身を少しだけ紹介してみよう。授業は1年から3年までそれぞれ新学期の春からはじまって、翌月の3月まで、四季の自然の変化と子どもの成長に沿って、全部で71課にわたる。授業時間は1、2時間で終わるものもあれば、1日かかるものもある。
たとえば、1年生第11課「麦畑と虫とり」。
この授業は「6月の野山で、麦の黄色にみのった有り様や麦のとり入れを見せ、また、草むらの中などに虫を探し、これを飼わせ、自然の中の営みに関心を持たせる」ことを目的として行なわれた。時数は1日と1時間。
麦の刈るころを見はからって教師は子どもたちを野山につれだす。麦畑に着いたら、畑一面が黄色になり、森や林や山が濃淡さまざまの緑の情景に彩られている情景に目をとめさせ、4、5月ごろの青々とした麦畑がすっかり変わったことに気づかせる。麦畑のあぜに立って、教師と子どもが代わる代わる、大きくなった麦と丈比べをしたり、ウネの間をのぞかせて、きれいに並んだ麦のウネを見せたり、ウネ間のダイズ・サツマイモ・キュウリなどの名前を問うたりする。大麦と小麦の穂の“のぎ”の長さの違いに気づかせ、麦の穂が吹く風に揺れて立てるささやかな音に耳をそばだてる。途中、麦が倒伏しているところがあれば原因を考えさせ、穂発芽しているようすに注意を向けさせる。
農家が刈り取り・麦こきをしているところに出会ったら、邪魔にならないようにゆっくり見せ、麦こきのあとのムギワラを分けてもらう(あとで「しゃぼん玉遊び」の課で使う)。
野原や林、アゼ道など、虫がたくさんいそうな場所に着いたら、組ごとに自由に虫をとらせる。道や畑のすみや、林の下などの落葉やちりの積もっているようなところにいる虫、草木の枝や葉の上にいる虫、地面にいる虫、麦畑や近くの野菜畑にいる虫など。たくさんの虫を集めたり、虫の名前を覚えさせたりするのが目的ではない。どんなところにどんな虫がいて、どんな動き方をしているか、虫と環境との関係、成虫・幼虫・卵の関係、作物と虫との関係に関心と注意を向けるように仕向けるのである。
集めた虫は学校に持ち帰り、育てるのだが、その際、子どもたちが「こうすれば虫が喜ぶだろう」とか「長生きするだろう」という気持ちで、いろいろ工夫することが大切である。飼い方のよりどころは虫が野山にいたときと同じようにしてやることである。林の落葉の下にいた虫には、びんの中に落葉や土を入れてやり、菜の葉にいた虫には菜の葉を与えてやる。そういうことに子ども自身が気づくよう教師は子どもたちを指導せよ、とこの本には書いてある。
このように『自然の観察』では農作業の営みを含めた季節の自然の移り変わりを子どもたちに自在に感じとらせながら、虫を集め、飼うことをとおして、子どもたちに虫の生態に気づかせ、問題解決する力を育てようとしている。
ここでは、教師が虫の名前や飼い方などを知識として教えることは厳に戒められ、子どもたちの「第一印象」と子ども自身による創意工夫が尊重されていた。
▲目次へ戻る
学級園や飼育小屋の役割
『自然の観察』では作物の栽培や動物の飼育も重視されている。
たとえば2年生第3課「春の種まき」では、学級全体で共同して学校の10m²の畑にヘチマを植えるとともに、四人組で4m²区画の畑を分担してトウモロコシを栽培する。
ヘチマ畑では、土のなかの石ころや草の根を取りのぞき、堆肥や灰をいれ、教師が手伝いながらまき床をつくる。ヘチマのタネを子どもたちに2粒ずつ配り、黒くて表面がざらざらしたタネのようすを観察させ、アサガオなどのタネまきのときなどを思い出させて、どのくらいの深さにタネをまいたらいいか考えさせる。また、タネのどこから芽が出てくるかを考えさせ、実際に確かめるために植木鉢にさまざまな向きにタネをまいてみる。その後は、ヘチマ棚の手入れや除草、ヘチマ水とり、さらにタネとりまで、授業は続いていく。
学校の畑は6年生まで続けて使っていくものとされ、低学年ではむずかしい農作業は上級生の力も借りた。この2年生の「春の種まき」の授業でも鍬をつかって畑を荒起こししたり、追肥として下肥をかけるような作業は上級生の仕事と注記されている。こうした上級生の頼もしいようすも見ながら、やがて自分たちも畑の裁量をまかされることを聞き、2年生は意欲をかきたてるのである。
『自然の観察』ではトリ小屋、ウサギ小屋が随所に出てきて重要な役割を果たしている。虫とりや草遊びのため野外に出かけたとき、ニワトリやウサギのエサを持ち帰るような活動につなげるだけでなく、「寒さと暖かさ」の学習では日だまりのニワトリを観察したり、ウサギの体温や自分の着物の中の温度をはかったりして、毛や着物が寒さを防ぐ工夫であることに気づかせている。学習したことは日常生活にも大いに役立つ。
▲目次へ戻る
「科学的精神」とは農家の営みそのもの
「自然の観察」が尋常小学校理科への反省から科学的精神を養うためにスタートしたことはすでに述べた。その科学的精神とは、「自然のありのままの姿をつかみ、自然の理法(「すじみち」と「ことわり」)を見いだし、わきまえ、これに従い、さらに新たなるものを創造しようとする精神」とされている。
この科学的精神のとらえ方には、岡現次郎が師事していた橋田邦彦の思想が色濃く反映していた。橋田邦彦は生理学者・医学者であり、道元を研究しながら、科学と禅の思想の融合を試みていた。橋田は近衛・東条内閣の文部大臣を務め、戦後、GHQによってA級戦犯容疑者として指名を受け、服毒自殺した悲劇の人物である。
橋田は自然科学についての講話のなかで、自然科学の研究とは観察・実験・観測の3つがあるが、それがすべて広い意味の観察に含まれること、そこで「観るということ」は物心一如、主客未分という立場にあるという(『行としての科学』)。人間は、あたかも宇宙の外から観るごとく自然を観ているのではないというのだ。橋田はこう述べる。
「自然というものは人間をして人間たらしめているのでありますが、われわれは自然のそういう動き方をいっそう適切ならしめるよう自然に働きかけるのであります。われわれは自然の中の単なる存在としてではなく、『自然』に向かって人間としての働きかけをしているのであります。要するに自然はたえず人間に働きかけ、人間は自然に働きかけているのであります。しかし言うまでもなく、われわれが自然に働きかける場合に、自然の働きを不自然たらしめるように働きかけているのではありません。自然というものが人間を育むのにもっとも都合のよいように、進んで人を人たらしめるにはそうあらなければならないように、働きかけているのであります。」(『科学の日本的把握』)
このとき橋田は主に自然科学者を思い描いていたようだが、この態度はまさに農家の営みそのものを表現しているといえるのではないだろうか。農家は地域自然に働きかけ、働きかけるなかで自然に学び、地域自然を活かすように農業と暮らしを築いてきた。そこには、先の上野さんいう、「生命の折り合い、重なりあい、連鎖を見る目」があり、「百姓の仕事として、作物の次への感覚」があった。
今月号では、ミツバチ不足が深刻化するなかで、緊急企画「飼うぞ 殖やすぞ ミツバチ」を組んだ。「交配バチの使い捨て時代は終わった」として自分でハチを飼い始めた農家には、「連鎖を見る目」があり、「作物の次への感覚」にむけた「観察の目」が息づいている。
福島県のリンゴ農家の大竹邦弘さんは、「リンゴの花の中にすっぽり潜って花粉を集め、気温が低くてもよく働く」マメコバチを増やすために、スモモの放任園や菜の花を活用している。マメコバチと花々、天敵ダニとのかかわりなどをめぐる豊かな観察眼が、これを支えている。
「自然の観察」の底を流れる自然観はこのように農家と自然との関係と通じるものであった。
従来の尋常小学校理科の教科書が、明治維新以来の文明開化主義の思想によって、国民に未知の自然科学を啓蒙・普及しようとしていたのに対して、『自然の観察』は地域の自然に学ぶための手引き書であり、教科書は自然そのものだったのである。ここでいう自然とは、人間の手が入った里山的な自然――農家によって働きかけ、働きかけ返されることで形成された農耕的自然のことだ。
自然と人間(農家)との関係とも通じる「関係の学」が「自然の観察」、すなわち日本的理科の原点なのである。
それがすべての教科の基礎にすわったとき、教育は大きく変わるのではないだろうか。
▲目次へ戻る
身近な自然を豊かにすることから
ここ数年、地元の小学校で田んぼの先生を務めてきた上野さんは、子どもたちへの教えかたを変えてきたという。
「最初は稲の一番良い姿を見せることが良い学習だと思って取り組んでいましたが、それではだめなことに気づきました。今は生徒たちにやらせることを一度こうしてくださいと説明したら、もうあまり口を出さずにおります。そして次の段階、種まきを自主的にやらせたら、できた稲で学びを深くしたいと思っています。
自分なりに苗を育てれば、その後の生育を観察しようとする気持ちも強くなります。労働だけ、作業だけの体験ではなく、次への行動なり関心なりを引き出したいと思っているのです」(感想文の続き)
ところで、「自然の観察」が連れ出す野外とは当時の東京近郊の自然が想定されていた。つまり、近郊の公園や里山、田畑である。しかし、近年もっとも変わってしまったのがこうした近郊の里山の自然でもある。この本が出たころは田んぼや用水にはいくらでもいたゲンゴロウやタガメはおろか、ドジョウやメダカでさえもいまではめっきり少なくなった。「自然の観察」のような教育をいま実現するためには、田畑やその周辺の里山の自然の豊かさを取り戻さなければならない。
上野さんは3年前、田んぼと排水路のあいだを生きものが行き来できるように魚道をつくった。アゼ草は田植え直前まで刈らずに、草の美しさを楽しむようにしている。冬も水を湛えた田んぼにはハクチョウが羽を休めるようになった。このような、生産効率一辺倒の圃場整備を見直し、生きもののにぎわいを取り戻そうという動きは各地で起こっている。
身近な自然を取り戻し、地元の学校の先生を助けて新しい「自然の観察」を創る――今、それができるのは農家しかいない。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
(注)『復刊 自然の観察』日置光久・露木和男・一寸木肇・村山哲哉編集・解説/A5判548頁/定価4935円(税込)/農文協刊
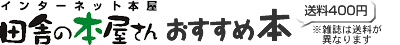
 |
『復刊 自然の観察』 いまよみがえる昭和16年の幻の名著。小学校低学年理科向けの教師用書として文部省が発行。身近な自然にふれ、子ども自ら学ぶ手引き。
「自然の観察に教科書は不要。強いてつくれば教師は教科書で指導して、子どもを野外に連れ出すことをしなくなる」という趣旨から、教師用のみを作成。それまでの知識伝授型の尋常小学校理科の発想を大胆に転換した「日本型理科」の原点がここにある。常用漢字、現代表記で復刊。平成20年告示・学習指導要領小学校理科との対照表付き。
[本を詳しく見る]
|
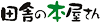
|









