|
2010年12月 No151
特集:思春期の不定愁訴 |
||
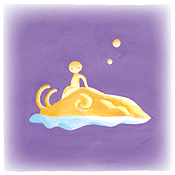 |
||
不定愁訴とは、頭やお腹が痛い、疲れやすい、気持ちが悪い、朝起きられないなどなどの原因のはっきりしない症状を訴えること。保健室には、こうした不定愁訴を抱えてやってくる子どもたちが多いが、とくに小学校高学年から中学校・高校にかけての思春期の子どもたちは、不定愁訴を訴えて保健室に殺到する。捉えどころがないだけに<どう対応すればよいか困る不定愁訴について、その原因や子どもへの対し方を考える。 |

|
2010年12月 No151
特集:思春期の不定愁訴 |
||
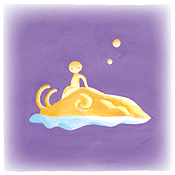 |
||
不定愁訴とは、頭やお腹が痛い、疲れやすい、気持ちが悪い、朝起きられないなどなどの原因のはっきりしない症状を訴えること。保健室には、こうした不定愁訴を抱えてやってくる子どもたちが多いが、とくに小学校高学年から中学校・高校にかけての思春期の子どもたちは、不定愁訴を訴えて保健室に殺到する。捉えどころがないだけに<どう対応すればよいか困る不定愁訴について、その原因や子どもへの対し方を考える。 |