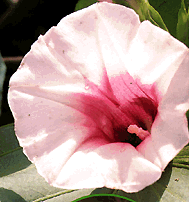 《さつまいもの栽培条件》
《さつまいもの栽培条件》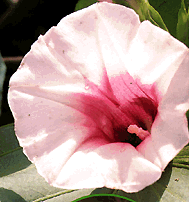 《さつまいもの栽培条件》
《さつまいもの栽培条件》
・生育適温は20〜35℃で、年平均気温が10℃以上で、 生育期間の積算温度3000℃以上が必要です。このた
め東北の福島、宮城、北陸の新潟以南が適地です。
・いもの形成には、1日11〜12時間の日照時間が最適 で、7時間以下ではいもの肥大が阻害されます。
・生育期間中 470mm程度の降雨量、土中水分60〜70% の湿度のやや乾燥した土地、気候が最適とされています。
・乾燥には強く、砂土地、火山灰土など、土壌を選ば ずによく生育しますが、滞水、冠水害には大変弱い
ので畝(うね)を高くするなどの工夫が必要です。
1.育苗
 まず、健全な種いもを準備し、消毒します。そして30℃前後で
3〜5日間、適当な湿度を与えて催芽処理を施します。これを、あらかじめ準備した苗床に、あたまを揃えて並べます。これを伏込みと呼びます。伏込み後は、頂部が隠れる程度に覆土し、萌芽後は日中22〜25℃、夜間18℃程度に保ちます。平均的には、40日前後で苗長25〜30cmで7〜8節、葉が充分に展開しているものを、地ぎわの2節を残して1本ずつていねいに切り取ります。採苗は、早掘り栽培などでは、2〜3回、普通栽培では3〜4回行います。最近では、生長点培養を利用したウイルスフリー苗(バイオ苗)利用することが多くなりました。収量が増え、いもの皮の色がたいへん鮮やかになるためです。
まず、健全な種いもを準備し、消毒します。そして30℃前後で
3〜5日間、適当な湿度を与えて催芽処理を施します。これを、あらかじめ準備した苗床に、あたまを揃えて並べます。これを伏込みと呼びます。伏込み後は、頂部が隠れる程度に覆土し、萌芽後は日中22〜25℃、夜間18℃程度に保ちます。平均的には、40日前後で苗長25〜30cmで7〜8節、葉が充分に展開しているものを、地ぎわの2節を残して1本ずつていねいに切り取ります。採苗は、早掘り栽培などでは、2〜3回、普通栽培では3〜4回行います。最近では、生長点培養を利用したウイルスフリー苗(バイオ苗)利用することが多くなりました。収量が増え、いもの皮の色がたいへん鮮やかになるためです。
2.圃場準備
 ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウなどの土壌病害虫の被害にあうと、生育障害や奇形などで商品価値がなくなります。輪作やラッカセイなどの拮抗作物の導入だけでは抑えられないことも多いので、薬剤で土壌消毒します。次に通気性と水はけを良くするために耕起します。この時に、同時に施肥も行います。そして、土壌の乾燥しているときに畝を作るのですが、肥沃地や多湿地は高畦とし、やせ地や乾燥地は低畦とします。畦が高い方が、通気性や葉の受光態勢が向上し、増収するからです。
ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウなどの土壌病害虫の被害にあうと、生育障害や奇形などで商品価値がなくなります。輪作やラッカセイなどの拮抗作物の導入だけでは抑えられないことも多いので、薬剤で土壌消毒します。次に通気性と水はけを良くするために耕起します。この時に、同時に施肥も行います。そして、土壌の乾燥しているときに畝を作るのですが、肥沃地や多湿地は高畦とし、やせ地や乾燥地は低畦とします。畦が高い方が、通気性や葉の受光態勢が向上し、増収するからです。
3.植付け
 地温18℃以上であれば早植えほど収量性は高いのですが、早す
ぎても障害がでます。早植えの限界は、一般的には、九州など西 日本では4月下旬、関東など東日本では5月上旬から下旬、東北では5月下旬です。苗の植付け方法には、水平植え、改良水平植え、舟底植えなど、暖地の大苗むきのものと、釣針植え、斜め植え、直立植えなど短い苗の密植、ポリマルチ栽培に向く方法があります。裁植密度は、80cmの畦幅で株間は35cmが標準で、でん粉原料や加工食品用は10a当たり3500本、青果用では4000本程度が目安です。
地温18℃以上であれば早植えほど収量性は高いのですが、早す
ぎても障害がでます。早植えの限界は、一般的には、九州など西 日本では4月下旬、関東など東日本では5月上旬から下旬、東北では5月下旬です。苗の植付け方法には、水平植え、改良水平植え、舟底植えなど、暖地の大苗むきのものと、釣針植え、斜め植え、直立植えなど短い苗の密植、ポリマルチ栽培に向く方法があります。裁植密度は、80cmの畦幅で株間は35cmが標準で、でん粉原料や加工食品用は10a当たり3500本、青果用では4000本程度が目安です。
4.施肥
窒素が多いと地上部だけが茂りすぎる「つるぼけ」になりますし、カリを多量に 必要とするので、普通栽培では10a当たり窒素3〜6kg、りん酸4〜8kg、カリ8 〜12kg程度を施用します。窒素は生育初期〜中期の地上部の生育の盛んな時期に充分吸収させ、後期には吸収を押さえていもの肥大を促します。りん酸は初期に充分吸収させて根張りをよくし、カリは全期間吸収できるようにするため、深層施肥や緩効性肥料を使用します。また、堆きゅう肥を施用すると土壌の物理性改善との相乗効果によって、たいへん大きな効果があります。
5.生育管理
雑草には強い作物なのですが、生育初期には被害を受けるので、植付け前に除草剤 を利用して防除し、植付後は、中耕・培土などの管理作業と併せて作業します。耕・培土は、地上部の生育を促進して、いもの肥大を良くするのと雑草防除の効果があり ます。植付後30日以内にカルチベーターなどでや1〜2回行います。さつまいもは、 病害虫の発生は比較的少ないのですが、それでも蔓割病、黒斑病、黒星病など、イモ コガ、ナカジロシタバ、コガネムシ類、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウなど の被害があるので、発生予察に注意して防除します。
6.収穫
 収穫時期は、関東では10月上旬〜11月上旬、九州では9月下旬
〜11月下旬が目安です。収穫作業は、つる切り、掘取り、調製、出荷販売、貯蔵という過程に分れてますが、近年ではマルチ栽培が増えたために「マルチ剥ぎ」の作業が必要で、つる切りとマルチ剥ぎを同時に行う機械も開発されています。また、収穫は植え付けと並んでさつまいも栽培でもっとも時間のかかる作業で、最近は青果用の小型の乗用型掘り取り機が普及しています。また、加工食品用やでん粉原料用に利用可能な、自走式の大型の収穫機も開発されています。
収穫時期は、関東では10月上旬〜11月上旬、九州では9月下旬
〜11月下旬が目安です。収穫作業は、つる切り、掘取り、調製、出荷販売、貯蔵という過程に分れてますが、近年ではマルチ栽培が増えたために「マルチ剥ぎ」の作業が必要で、つる切りとマルチ剥ぎを同時に行う機械も開発されています。また、収穫は植え付けと並んでさつまいも栽培でもっとも時間のかかる作業で、最近は青果用の小型の乗用型掘り取り機が普及しています。また、加工食品用やでん粉原料用に利用可能な、自走式の大型の収穫機も開発されています。
7.貯蔵
貯蔵適温は13〜15℃、湿度が80〜90%です。貯蔵法としては、土中貯蔵、地穴 貯蔵、電熱を利用するキュアリング貯蔵、室内貯蔵などがあります。従来は農家個人による地下穴式の貯蔵が多かったのですが、今では、生産団地の大型化や青果用の周年出荷のために大型の室内(コンテナ)貯蔵が一般的となっています。
8.輪作体系
さつまいもは連作が可能で、土壌病害虫が少ないため、栽培は容易です。むしろ連作したほうが品質がよくなるといわれ、食用栽培では連作が行なわれていることが多いのです。しかしながら、長く連作すると地力は低下し、減収します。このため、大豆、落花生、野菜などと2〜3年交互に輪作するか、夏作のさつまいもは固定して、前後作にタマネギ、キャベツ、ニンジン、ダイコンなどの野菜を入れた作付体系とするなどの工夫が必要になります。