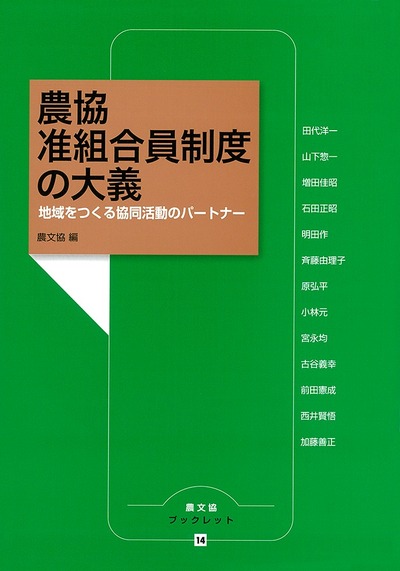主張
三つのJAに学ぶ 新規就農者が育つ仕掛けとは
目次
◆行政とともに、法人も巻き込んで「農+住」を支援
◆毎年、少しずつ確実に育っていく研修制度
◆体験農園から本格派まで、都市住民が「農家」になれる
◆農地の確保は、研修先農家の仲介で
農林水産省が2020年3月に発表した「農業構造の展望」によれば、これまでの傾向が続く場合、2015年に208万人いた農業就業者人口は2030年には131万人まで減少し、うち49歳以下が35万人から28万人に減少するという。JA全中による全JA調査も同様の趨勢を示しており、全中は「10年後には農業・地域・JAの基盤自体の持続可能性も懸念される」と警鐘を鳴らしている。
一方、農業・農村に新たな風が吹いているのも間違いないだろう。若者を中心に田園回帰志向が強まり、地域おこし協力隊は2018年度以降毎年5500人台が活躍、うち約6割が任期終了後も地域に定住し、半農半Xや継業といったかたちで地域の重要な担い手となっている。
新規自営農業就農者は4万人を維持し、49歳以下が主体の新規雇用就農者や新規参入者は増えている(農水省「新規就農者調査」)。この動きを、農業とむらを次代に引き継ぐことにつなげたい。
昨年10月に開催された第29回JA全国大会の決議は、5〜10年先の産地を担う次世代組合員として新規就農者を位置づけ、その支援を「次世代総点検運動」として重点化した。数値目標に基づき、新規就農支援や事業承継支援を通じて、次世代組合員を計画的かつ確実に創出しようというものだ。他方、中小・家族経営や半農半Xなど多様な担い手の育成や伴走支援の必要性も大きく掲げている。
これにむけ、何が求められるのだろうか。2月にオンラインで開催された「JA総合営農研究会」(*1)では、「未来へ向けて 多様な担い手をどう支えるか」をテーマに、果樹産地・野菜園芸産地・都市的地域の三つのJAから担い手支援の先進的な取り組みが報告された。以下、同研究会での報告と討議をもとに、多様な農の担い手と地域の未来について考えてみたい。
行政とともに、法人も巻き込んで「農+住」を支援
−−長野県JAみなみ信州
一つ目の事例報告はJAみなみ信州。長野県南端の14市町村をエリアとする中山間地JAで、「市田柿」が特に有名だ。JA担い手支援室所長の澤栁実也さんが、2017年から展開する「担い手就農プロデュース」の取り組みについて発表した。
これは、JAと各行政が別々に進めていた新規就農および移住・定住の誘致を、「農住」事業として官民一体で推進するものだ。
「農業を目指して南信州に来られる人は、『転職』と『移住』という二つの大きな決断と覚悟を持って来るわけです。迎え入れる我々も、農住事業のプロデューサーとして、責任あるサポートをしなければなりません。ただ『誰か来て農業をしてくれればいい』ではダメなのです」と澤栁さん。
「農住」に向け、農水省の「新規就農」と総務省の「移住定住事業」を活用する。これは表裏一体だが地方自治行政では区別しているところが多く、それが弊害となっている場面が少なくない。そこで南信州では本プロデュースを核と位置付けて「窓口ワンストップ体制」の構築を進めている。
管内で就農を希望する研修生は、いずれかの市町村の地域おこし協力隊に所属し、本プロデュースが建設した研修施設(ビニールハウス他)で推奨品目である「市田柿」と「夏秋キュウリ」の栽培実技を中心に2年間の就農研修に取り組む。研修修了後には所属市町村での就農を目指す。
加えて、管内の農業生産法人との連携を進める。行政とJAが一緒に動くことで安心感と連携が保てることが法人側のメリット。こうして、担い手就農プロデュースを母体として情報と課題を共有する地域協働が進む。
地元農家の樹園地を居抜きで継承する「第三者承継」にも取り組む。その際、特に優良・優秀な農家から、「継承後も何らかのかたちで関わりたい」「樹園地だけでなく技術も継承してほしい」という声が強い。そこでJAが推進しようとしているのが、園地を譲渡する農家が「オーナー」、新規就農者が「経営者」となって農業法人をつくる仕組みだ。オーナーは経営譲渡とともに引退もできるし、経営への参画や指導・サポートや手伝いなどで関わることもできる。
一方、兼業農家も大事にする。澤栁さんは言う。
「中山間地の当JAの場合、大規模といっても経営面積は約2haが限度です。もちろん専業農家の維持・持続は大切ですが、それだけでは管内の農地を守り切れません。むしろ、兼業農家が持続することによってこそ地域農業は持続してきたのではないか。1人の1haよりも、1人10a経営の10人を目指すことにより、地域が持続可能な農業エリアとして存続されるのではないでしょうか」
農地の荒廃を防ぎ、農地を維持するには兼業農家の働きが大きい。そして定年退職者には直売所を活用した販売農家として活躍してほしい。こうして地域における「農業と生活」を守っていきたいという。
毎年、少しずつ確実に育っていく研修制度
−−茨城県JAやさと
二番目のJAやさとは、茨城県旧八郷町(現在は石岡市に合併)をエリアとする野菜産地のJA。1998年に設立された有機栽培部会を中心に、有機農業および生協と提携した産直運動の先進地としても全国的に有名である。
そのJAやさと管内でも農業従事者は年々減ってきているのが実情だ。しかし、農業をやりたい人は必ずいる。地域内だけでなく外に目を向けよう!と、JAでは複数の研修制度を設けている。JAの出資法人「やさと菜苑(株)」代表取締役の高橋大さんがその全体像を発表した。
そのスタートは1999年に立ち上げた「ゆめファーム」。有機農業で新規就農を目指す人を対象に、「毎年、農家が増え、継続的に農業が営まれる、夢のような研修制度」をめざした。毎年1家族を受け入れ、JAが保有する圃場で、有機栽培部会の先輩たちによる実践的な研修を2年行なう。研修終了後は同部会員となってやさと地区内で就農することが条件だから、1年に1家族の部会員が増加していくことになる。生産物はすべてJAS有機野菜であり、研修1年目からJAの既存の販売先(90%以上が契約販売)に共同出荷できる。これまで20家族を受け入れ、全員が地域内で就農した。そのうち、家庭の事情で離脱せざるをえなかった3家族を除く全員が現在も農業を営んでいる。有機栽培部会の平均年齢は43.8歳。
そして2012年には「やさと菜苑(株)」を設立。こちらは有機栽培ではなく慣行栽培、施設栽培を主な対象にしている。地域の農地(畑)約16ha(うちハウス60a)を借り受け、露地の長ネギなどを中心に経営を行なう。ここで農業者としてやり遂げる強い意志があると認められた毎年1〜2名の就農希望者を従業員として雇用し、最大2年間研修する。直接経営により耕作放棄地の増加と農業生産額の減少に歯止めをかけつつ、研修生の受け入れ・育成も一体で行なおうという取り組みだ。
販路は90%以上が生協や量販店などとの契約栽培であり、販売先や品目は、JA本体とバッティングしないよう調整されている。会社設立後7年までに、新規就農希望者として16名を受け入れ、現在4名が研修中。すでに12名が石岡市内で農業者として自立し、全員が農業を続けている。就農率も定着率も100%という驚異の実績である。
さらに2016年には、農業担い手対策としてJAが野菜カットセンターを設立。新規就農者の大きな助けになっている。例えば長ネギは市場出荷だと9等級の規格があり、調製に夜までかかってしまうことも多いが、カットセンターは太・細の2等級しかないため、農家はより多くの時間を圃場での管理作業にあてることができる。
2017年にはNPO法人「アグリやさと」を立ち上げた。JAやさとのOBと現職で構成。廃校を活用した石岡市の体験型観光施設「朝日里山学校」の管理を市から受託。「朝日里山学校」を拠点に農業に関心を持つ若者の就農支援と都市農村交流活動を行なっている。「高い就農・定着率の秘訣は?」との質問に、「販売力ですね」と高橋さんは自信を見せた。たしかに「ゆめファーム」での有機栽培も「やさと菜苑」での慣行栽培も、目指す農業の形に応じた研修プログラムと圃場、指導者、そして販路が手厚く用意されている。新規就農希望者にとって頼れる研修制度だ。そこには農家から新規就農者へ、先輩から後輩への指導体制や情報提供を行なう環境づくりがあった。
体験農園から本格派まで、都市住民が「農家」になれる
−−神奈川県JAはだの
三つ目の事例は神奈川県秦野市をエリアとするJAはだの。組合長の宮永均さんが発表した。
同市は、かつて茶や葉タバコ、ラッカセイの一大専作産地だった。しかし1960年代以降急速に都市化が進み、市の人口16万5000人のうち農家戸数は1376戸(2015年)、その大半が兼業・自給的農家となった。JAの組合員構成も、正組合員2849人に対し准組合員1万1609人(21年12月末)と後者が圧倒的に多い。
そんなJAはだのでは、少量多品目・地産地消型、交流・観光型の都市農業の確立とともに、正組合員も准組合員も一体となった「食と農を基軸にした地域に根ざした協同組合」をめざし、次のような特徴的な「担い手」育成の仕組みを発展させてきた。いずれも、市民の農への参画を促し、関わりや関心の度合いに応じてステップアップしていける仕組みである。
その一つが、生産緑地を活用した体験型農園「名水湧く湧く農園」。土に触れたことのない初心者でも、園主農家の指導付きで年間20種類もの野菜栽培が体験できるというもので、近隣住民の憩いの場としても大人気だ。
自力で栽培に挑戦したいという人向けには、遊休農地をJAが借り受けて開設した市民農園「さわやか農園」がある。1区画100m2という破格の広さに加え、特徴的なのは、利用者はJAの准組合員になれば、ここで栽培した野菜をJAの直売所「じばさんず」で販売もできることだ。消費者だった地域住民が販売する側になるという仕組みである。約270人の利用者のうち80人がJAの准組合員となっている。「『共済に入ってください』と営業するよりも『市民農園を利用しませんか』のほうがずっと農協らしくていい」と宮永さん。
さらに本格就農を目指す人向けに、JAと市・農業委員会が共同で開設した「はだの都市農業支援センター」が運営する「はだの市民農業塾 新規就農コース」がある。2年間の実地研修で栽培の基礎から販売・経営まで学ぶもので、2006年の開設以来93人が修了、うち78人が就農した。そのうち55人は農外からの就農である。その成果だろう、秦野市内の専業農家数は1995年の1703戸から2005年には160戸に激減したが、2015年には240戸に増えている。
このなかで同JAに特徴的なのは、JAが何でも手を回すのではなく、「人が人を育てる」仕組みだ。たとえば、現在「はだの市民農業塾」の講師として新規就農希望者を指導している伊藤総司さんは、新規就農者として市外から移住してきた人である。「組合員を主体として運営し、組合員家族はもとより、可能な範囲で地域住民を包括した『協同組合が行う地域づくり』を目指したい」と宮永さんはいう(*2)。
農地の確保は、研修先農家の仲介で
JA総合営農研究会2日目には、「新規就農の最新動向と支援の課題」と題して、東京農業大学教授・堀部篤さんが問題提起した。
堀部さんらが新規就農動態の全国調査の長期動向と最新結果を分析したところによれば、新規就農者にとって最大の課題の一つが「農地の確保」(条件不利地しか借りられないなど)にあるという。
そこで大きな役割を担っているのが、新規就農者の研修先農家だ。研修先農家は、就農希望者がむらの一員としてやっていけるか見定め、研修を通じて農業技術やむらの慣習などを教え、就農に当たっては地域の農家や住民と相談・交渉のうえ農地の斡旋や住居の紹介などの世話をする。つまり新規参入者とむらとの橋渡し役である。このとき研修生が農地や住宅を確保できるかどうかは、地権者と研修先農家との信頼関係で決まる。つまり地権者は、研修生をではなく、「何かあったらオレが責任をとる」という身元引受人である研修先農家を信頼して土地を貸すのだ。
ここには、農村社会特有の「安心」を基礎にした関係、メンバー同士の長期的、安定的な関係があると堀部さんは指摘する。
しかしそんなとき、仲介者にもなる研修先農家の負担はかなり重い。実際、「10年の更新のとき、地権者が買い取りを希望したので、研修先農家がその農地を購入して就農者に貸した」とか、「就農予定者にすでに住宅ローンなどの借入があって農業資金を借りられなかったため、研修先農家が自分のハウスを貸してあげた」といったケースもあるという。
この問題の解決に向けた動きも出てきている。たとえば長野県のJA信州うえだでは、農家個人の代わりにJA出資法人が新規就農者とむらとの橋渡し役となって研修や農地斡旋をする仕組みをつくった。組織への信頼を担保に、多くの優良樹園地の確保を実現しているという。「安心」にむけ行政やJAなどの公的機関の役割も大きい。
*
1960年代の本誌編集長でもあった農業評論家の堀越久甫さんが当時、兼業化がすすむなかで、みんなが同じような農業をしている「等質社会」をつなぐ仕掛けがもはや状況と適合しなくなった、としてこう述べていた。
「私たちがいまなすべきことは、等質共同体をして異質共同体に変換して、共同体のもつ連帯を回復することである。そのためには、現存する〝仕掛け〟を棄てて(ないし大幅に変えて)、異質共同体の紐帯(結びつき)となる新しい〝仕掛け〟を考案することである」(堀越久甫著『村の中で村を考える』NHK出版、1979年)。
今日のむらは、さらに多様だ。農業法人や大規模農家から自給的農家、兼業農家、定年帰農者、半農半X、そして「関係人口」。これらの人々が農を核に関わり合う新しい「異質共同体」をつくれないだろうか。その「仕掛け」づくりこそ、農家やJAが大いに力を発揮する出番なのではないだろうか。
(農文協論説委員会)
*1 JA総合営農研究会(旧称JA|IT研究会) JA営農経済事業の革新と地域農業の再興をめざす研究会(代表委員・黒澤賢治)、約40JAが正会員。農文協はJA全中・JA全農と共同で事務局を務める。http://ja-it.net
*2 JAはだのが展開する新たな担い手育成の仕組みについて詳しくは、『農的暮らしをはじめる本 都市住民のためのJA活用術』(榊田みどり著、農文協刊)、および榊田さんによる本誌3月号p274〜の記事を参照