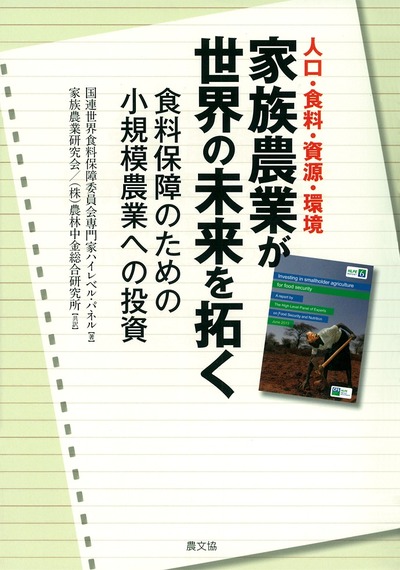主張
続・自然とともに平和をつくる
目次
◆アフガニスタンの平和は「水」でしかつくれない
◆先進国の二つの罪 化石資源の大量消費と軍事介入
◆大国が主導する時代は終焉に向かっている
◆「小農・家族農業」をめぐる国連の四つの国際年
◆SDGsの核心、アグロエコロジー
今から21年前、アメリカ軍を中心にアフガニスタンへの軍事侵攻が始まった。同年9月11日、アメリカで同時多発テロが発生、これへの報復的措置であった。この時、農文協では、「自然とともに平和をつくる」と題する『増刊現代農業』(2002年2月増刊)を発行した。
このアフガニスタン紛争は20年間に及び、この間アフガン市民4万6000人が犠牲となったといわれている。昨年、アメリカ軍の撤退、イスラム主義組織タリバンによる暫定政権の誕生という形で一応の収束をみたが、市民は干ばつの影響もあって大変きびしい状況におかれている。
そして今、プーチン大統領率いるロシア軍のウクライナ侵攻が世界を揺るがしている。連日、メディアから発信されるウクライナ市民や子供の悲惨な光景にだれもが心を痛めている。国際法秩序を否定し、悲惨な状況をもたらしているプーチンへの批判や怒りがつのっていく。しかしだからといって、アメリカ・NATОによる武器援助を受けての徹底抗戦に拍手喝采するという心情にもなれない。そんな人が多いだろう。戦争によって平和な世界がつくられるとは思えないからである。
もうそんな時代はやめにしたいと思う。
アフガニスタンの平和は「水」でしかつくれない
冒頭でふれた『増刊現代農業』のトップ記事は「アフガニスタンの平和は『水』でしかつくれない――1000本の井戸を掘るペシャワール会・中村哲さんに聞く」であった。
2019年12月4日、アフガニスタンで銃弾に倒れた中村哲さん。2000年のこの記事の当時は、アフガニスタンとの国境に近いパキスタンのペシャワールに拠点を置き、病院と10の診療所を設立して年間20万人の診療を行なっていた。中村さんはアフガニスタンの風土と暮らしから話を始める。
アフガニスタンには、「お金がなくても生きていけるが、雪がなくては生きていけない」ということわざがあるという。典型的な砂漠気候で、年間降水量は日本のわずか200分の1。そんなきびしい気候の中、人口の95%を占める農民が自給自足の農業と遊牧で生きてこられたのは、ヒンズークシ山脈を中心とする山岳地帯に降り積もった雪や氷河からの雪どけ水を、カレーズと呼ばれる地下用水路や井戸を掘って利用してきたからだった。山の雪が解け出して川となる夏に棚田や川沿いの水田で米をつくり、冬は小麦をつくる。地域共同体のもと半農半牧、あるいは遊牧の農業で、約2000万人が暮らしてきた。
そんな暮らしと地域は旧ソ連軍の侵攻(1979〜1992)と内戦で破壊され、そして2000年春からは未曽有の干ばつにさらされた。パキスタン西部、アフガニスタン全土、イラン・イラク北部、インド北部、中央アジア諸国、中国西部などで6000万人が被害を受け、なかでもアフガニスタンでは人口の大半の1200万人が被災。WHO(世界保健機関)が、「飢餓に直面する人が400万人、餓死線上にある人は100万人」と警告を発し続ける事態となった。
「水がなくなると衛生状態が悪くなり、各地で赤痢が大流行しました。『餓死』というのは空腹でばったり倒れるのではなく、栄養失調で体力が弱ったところに感染症などの病気に罹り、死んでしまうのです。真っ先に犠牲になるのは子どもやお年寄りです。治療する以前に、いのちをつなぐ水と食べものがない。『とにかく生きておんなさい! 病気は後で治すから』と言わざるを得ないような、悲惨きわまりない状況でした」
1本の井戸があれば何千人ものいのちが救える。中村さんたちは、「1年間で1000本の井戸を掘ろう」と目標を立て、2000年6月、アフガニスタン全域での井戸掘りを始めた。日本人の若者たちがアフガニスタン人スタッフ約700人の陣頭に立ち、村人を総動員して全力で井戸を掘り、既存の井戸の修復やカレーズの復旧も手掛けた。「水が出ると、村の人たちは『これで安心して村にいられる!』と心の底から喜んでくれます。人々の喜ぶ顔に励まされて私たちは作業地を拡大してきました。地下の水源そのものが枯渇の危機にあり、水位はどんどん下がっているので『掘っては枯れ掘っては枯れ』という状況ですが、それでも25万〜30万人の難民化を阻止してきました。東部の渓谷地帯では36カ所のカレーズの復旧に取り組み、このうち30カ所前後に水が戻りました。いったんは難民化して村を離れた1万5000人以上の農民たちが再び村に戻り、大干ばつで砂漠化した農地にカレーズから用水を引いて麦やトウモロコシを植え、以前と同じ自給自足の生活を営めるようになったのです。これは奇跡的なことでした」
先進国の二つの罪 化石資源の大量消費と軍事介入
「私がアフガンに来た18年前と比べると、この地を東西に横切るヒンズークシ山脈に降る雪の量が目に見えて減っています。それで雪どけ水の量も激減しています」と中村さん。アフガニスタンは「地球温暖化の最初の犠牲」という。「温暖化が炭酸ガスによるものかどうか私は知りませんが、いまの全世界的な工業化・産業化がつづく限り、起きうる現象でしょう。いま、直接的にはアフガニスタンや中央アジアの人びとがその被害者ですが、やがてツケは他の地域にも回ってくる。それはテロというツケであったり、難民が押し寄せてくるというツケであったり、いろいろだと思います」
経済成長をめざす先進国の化石資源の大量消費が地球の温暖化、気候変動を招き、途上国と呼ばれる国や地域ほどその被害を受ける。こうして生まれる地域の不安定化が地域紛争につながり、これに大国が武器の供与や輸出、軍事的介入をすることで、地域の状況はいっそう悪化する。
中村さんは、衆議院のテロ対策特別委員会に参考人として呼ばれたとき、自衛隊の派遣に対して「有害無益」と断じ、与党議員の「発言取り消しを」という求めにも頑として応じなかった。農業技術や水道技術の支援など、日本とアフガニスタンとの友好関係にふれ、中村さんはこう述べる。
「アフガニスタンは世界でもっとも親日的な国です。彼らは日本人を外国人と思っていません。どんな山奥に行っても皆、日露戦争とヒロシマ・ナガサキを知っています。『日本は50年以上も戦争をしていない。すごい国だ』と尊敬してくれます。
日本人であるがゆえにいのち拾いし、日本人であるがゆえにプロジェクトが進めやすかったという経験が私たちには多々あります。欧米の援助団体が逃げ帰った湾岸戦争の最中にぺシャワール会が現地で医療活動を続けられたのも、日本人であればこそでした」
「いますべきはですね、せっかく築かれた、これは私だけではなくて、日本が営々と百数十年かけて築いた一つの信頼感というのが現地で根づいておる。これをまず、崩さない。私たちの先輩の残してくれたものを大切にしながら、そして、抽象的になりますけれども、平和を待ち、その上でなにか建設的な事業をする、こうやって大きな国際的貢献、それもほかの国にできないような貢献ができるというふうに私は信じております」
そんな日本の平和への希求はどうなったのだろうか。中村さんはこんな言葉を残してくれた。
「今の日本がこれだけ浮薄な国になりつつあるのは、農業がなくなってきているからです。地についた自然とのふれあいがないからです。自然についての解説書はたくさんあっても、実際にメダカを手にしたり、イモムシやアメンボウを見たことのある人がどれだけいるでしょうか。日本全体が商業という人類にとってはいちばん上澄みの経済活動で生きており、つくっては消費することを繰り返さないと成り立たない社会になってしまっている。反対にアフガニスタンはむやみに消費するのはよくない社会です」
大国が主導する時代は終焉に向かっている
「グローバル・サウス」という言葉がある。直訳すればグローバル化のもとでの〝南〞で、国連などの機関がアフリカ、アジア、南米を指す地理的な区分としてこの用語を用いる場合があるが、最近では現代の資本主義のグローバル化によって負の影響を受けている世界中の場所や人々を指し、ベストセラーになった斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』でも、このグローバル・サウスという視点から気候変動問題の構造を描いている。
そして今、〝南〞が互いに認め合い連帯して新たな世界をつくるという展開が確実に進んでいる。
国連には193カ国が加盟し、非同盟諸国やその他の新興国が発言力を強め、さらに市民活動団体などの非政府組織や科学者たちが国際政治の場で影響力を強めている。
その象徴の一つが2017年7月、122カ国の賛成多数で採択された「核兵器禁止条約」である。人権や文化の多様性を重視し、貧困・飢餓の撲滅などを掲げた国連・SDGs(持続可能な開発目標)を押し上げているのも「発展途上国」と呼ばれる国々・国民である。ウクライナ侵攻のなかで国連の弱体化を問題にする声もあるが、大国主導ではない平等な国際関係、国際連携の必要性と現実性はいよいよ高まっている。
大国が軍事力で他国を支配しようという時代は終焉に向かっている。「ロシア軍の苦戦」の背景をたどっていくと、権力者プーチンには見えていない世界の変化があるのだと思う。そして、この世界の変化の主流に各国地域の生産と暮らしを左右する「小農・家族農業」をめぐる取り組みがあった。
「小農・家族農業」をめぐる国連の四つの国際年
2008年には世界的な食料危機と経済危機が勃発した。この時、多国籍アグリビジネスをはじめとするグローバル大企業の支配のなかで市場経済主義を進めた国・地域ほど、生産資材と穀物価格の高騰に苦しんだ。圧倒的多数を占める小規模家族経営が購入資材と輸入食料への依存を強めたからである。こうして国際社会は企業的農業をめざす市場原理モデルでは食料危機に対処できず、貧困の撲滅というミレニアム開発目標も達成できないことを確信したのである。
そして2014年、国連食糧農業機関(FAO)はこの年を「国際家族農業年」と定めた。FAOは輸出志向型の大企業が優遇される大規模経営偏重政策に反省を求め、「政策と公的投資による適切な支援が行なわれれば、食料保障、食料主権、経済成長、雇用創出、貧困削減、空間的・社会経済的不平等の是正に大きく貢献する能力が小規模農業には備わっている」とし、各国政府に対して、小規模家族農業を支援するよう要請した(注1)。その後、2019〜2028年を「家族農業の10年」と定めた。
そして2018年12月、国連総会は「小農と農村で働く人びとの権利宣言」(小農宣言)を採択した(注2)。国境を超えた農民運動組織ビア・カンペシーナ(スペイン語で「農民の道」の意味。73カ国の164組織で構成)が世界中の小農リーダーをインドネシアに集めてこの宣言の元をつくって以来、国連人権理事会などでの10年にわたる議論を経て実現した宣言である。
ちなみに、採決の結果は賛成121、反対8、棄権54。中南米やアフリカ、アジアなど、途上国の多くが賛成したのに対して、反対は英国、米国、オーストラリア、ニュージーランドなど。これらの国々に追随してヨーロッパの多くの国々が棄権、日本も棄権に回った。
反対する国々の攻撃対象となったのが、宣言のなかの「食料主権」「集団的権利」「土地・自然資源への権利」「種子への権利」にかかわる条文であった。そこには食料輸出国の論理や巨大アグリビジネス企業の利害が見え隠れする。
途上国を中心とする多数の賛成国は、たとえば「種子への権利」が知的所有権を侵害すると修正を求める米国・EUなどに対して、人権は知的所有権より上位の権利であると、毅然として主張を退けたという。それ以前からラテンアメリカなど各国の農民・市民は、育種者・育種企業の権限を大幅に強化して農民が種子を採種、保存、交換することを制限ないしは禁止するUPOV91(植物の新品種の保護に関する国際条約)、激しく抵抗していた(注3)。
一方、2015年は「国際土壌年」であった。FAOは、世界の土壌資源の33%が劣化し、人類が土壌に与える圧力は臨界極限に達しており、さらに、地球温暖化が土壌の水食、風食、砂漠化、土壌有機物の消耗などの土壌劣化を促進し、それがさらに温暖化を進めるという悪循環に強い危惧を示した(注4)。
この土壌劣化の多くは中央アジアやアフリカなどで問題となり、グローバル・サウスの構造そのものである。急速な近代化や輸出むけの単作的生産のもと、家族農業によって維持されてきた伝統的な土地利用が崩れた地域ほど、土壌劣化が深刻化する。だから「国際土壌年」と「国際家族農業年」は強く結びついている。
これに先立つ2012年は「国際協同組合年」であった。国連は、とくに途上国の発展には協同組合が欠かせないというメッセージを世界に発し、そこでは、欧米型の専門農協方式ではなく、家族農業を守る日本の総合農協が高く評価された。
SDGsの核心、アグロエコロジー
こうした新たな潮流のなかで2015年、国連総会は全会一致でSDGsを採択した。「17の目標」を掲げているが、その根幹には各国各地の持続的な農と食があり、これにむけ「アグロエコロジー」が注目されている。直訳すれば「農業生態学」「生態農業」。英国エセックス大学のプレティ教授らのグループが実施した長年にわたる大規模な実証実験の結果、化学農薬・化学肥料等を用いる工業的農業からこれを用いないアグロエコロジーに切り替えた場合、環境負荷を低減しながら土地生産性を1.8倍(地域・品目横断の平均値)にできることが明らかになった。これを受け、21世紀のあるべき農業の姿として、世界銀行や国連機関、EU等は2000年代末から小規模・家族農業によるアグロエコロジーを推奨している(関根佳恵「工業的スマート有機農業よりアグロエコロジーへの転換を」『季刊地域』22年冬、48号)。
そんな世界的潮流のなかに、日本の「みどりの食料システム戦略」もあるはずだ。「みどり戦略」のサブタイトルは、「食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現」だが、ここで「生産力の向上」を「食料自給率の向上」に、「持続性」を「環境負荷の軽減、耕地や地力、生物多様性の保全」ととらえ、そして「イノベーション」を「新結合」ととらえる。半農半Xや関係人口との新結合を加えて、次代が安心できる地球・地域環境と自給を基礎にした「食料システム」をつくっていく。
こうして自然とともに平和をつくる。自然とともに生きる地域とその世界的な連帯とともに平和をつくる。そんな時代に私たちは生きているのだと思う。
(農文協論説委員会)
参考文献 いずれも農文協刊
注1 『人口・食料・資源・環境 家族農業が世界の未来を拓く』国連世界食料保障委員会専門家ハイレベル・パネル著 家族農業研究会・農林中金総合研究所 共訳
注2 『よくわかる 国連「家族農業の10年」と「小農の権利宣言」』小規模家族農業ネットワークジャパン 編
注3 『種子法廃止でどうなる? 種子と品種の歴史と未来』農文協編
注4 国際土壌年記念出版『世界の土・日本の土は今 地球環境・異常気象・食料問題を土からみると』日本土壌肥料学会編
*また、『増刊現代農業』(2002年2月増刊)の中村哲さんの記事は、『季刊地域』20年春、41号にも再掲。