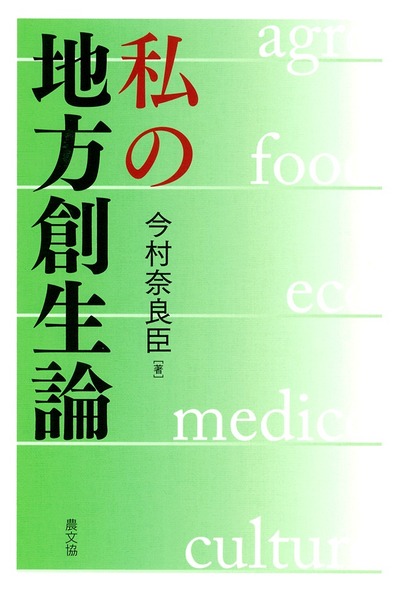主張
本気で「国民皆農」をめざす時代なのかもしれない
食料・農業・農村基本法の改正にむけて
目次
◆農業基本法の「構造政策」と農家の「抵抗」
◆国民的「理念」が求められた新基本法
◆生命総合産業としての農業を土台に農型社会を
◆基本法改正への提案・5氏の意見
政府は「食料・農業・農村基本法」の改正に向けて検討を進めることを決定し、これを受けて農水省は食料・農業・農村政策審議会のもとに基本法検証部会を立ち上げ、約1年かけて見直しの方向性をまとめるという。
その背景には「基幹的農業従事者」の半減など農業を取り巻くきびしい状況がある。食料自給率は低迷、中国の食料輸入の急増などで世界の穀物需給は「需要が供給を上回る」時代に入ったといわれ、そしてウクライナ戦争はアフリカなどの食料不足を激化させ、そしてわが国では穀物、飼料、肥料、エネルギーなどの輸入依存のリスクを表面化させた。気候変動への対策も必須の課題になっている。
食料、農業、農村のこれからを考えることは次世代の生き方・生存にもつながる国民的な課題である。
せっかくの機会である。この国の希望を紡ぎだす議論を進めたい。
農業基本法の「構造政策」と農家の「抵抗」
1961年(昭和36年)制定の「農業基本法」、1999年制定の「食料・農業・農村基本法」(新基本法)に続く、20年ぶり3度目の基本法の制定である。まずはこれまでの基本法を簡単に振り返っておこう。
日本が高度経済成長期に入る時期に制定・施行された「農業基本法」は、「農工間の所得格差の解消」という旗のもと、「農業近代化」の強力な推進を課題にした。①稲作の機械化、規模拡大、②輸入飼料を大量に使う多頭化・大規模畜産の振興、③麦や大豆を「安楽死」させ、野菜、果樹の拡大・単作的産地化を進めるもので、この背景には、食糧輸入の増大と工業発展のための労働力確保という財界の意向があった。
こうして農業近代化による「自立経営」の育成を促進し、これについていけない小さい農家は離農・離村してもらう。しかし、この「構造改革」は政府の思惑どおりには進まなかった。農家はイネを守りつつ、野菜、果樹、特産、中小規模の畜産など、自分や地域の条件に合う作目をプラスして家計に必要な程度の収益増加を図る「イネ+アルファ方式」、単作化に対して家族労力と地域自然を上手に生かす複合経営を追求し、「下からの近代化」を進めた。
イネの大増収運動にも取り組んだ。『現代農業』で連載した「片倉イナ作」は全国的な運動に発展。当時、米不足のもと目論まれていたカルフォルニア米の輸入を阻止し、日本の米の自給を確実なものにした。
そしてこの時期、農家の経営と暮らしを支える大きな柱になっていったのが兼業であった。高度経済成長期には農家所得も倍増した。農村と都市の所得格差の是正にむけて米価等の農産物価格支持制度が機能したし、出稼ぎやその後の農村工業の導入などで兼業収入も増えた。
農基法の産みの親とされる東畑精一博士が「自立経営をつくろうとする政策に対して、農家が総兼業化という方法で抵抗するとは思わなかった」と慨嘆し、「構造改革は失敗だった」と述べたことは有名である。農家は兼業によって先祖伝来の田畑を守り、むらを守ったのである。
国民的「理念」が求められた新基本法
1999年、「食料・農業・農村基本法」(新基本法)が制定された。新基本法が制定された1990年代は、直売所が各地に続々生まれ、農業体験、オーナー制、農家民宿、農村レストラン、地場産給食など、地域住民や都市民を巻き込む元気な取り組みが多彩に生まれた。一方、近代化をくぐり抜けた昭和ヒトケタ世代を中心に、「への字稲作」や米ヌカ利用など、作物の生命力や身近な自給資源を活かす「農家の技術」が多彩に花開いた。世界的には、1997年に温室効果ガスの削減目標を定めた京都議定書が採択されるなど、地球環境問題や生物多様性への関心が高まっていった時期でもある。
こうした背景のもと、新しい基本法は、狭義の農業政策にとどまらず、安全・安心な食料を供給する食料政策と、生態系の保全や防災など農業・農村の多面的機能を重視する農村地域政策を柱に、中山間地域を含む農業・農村の持続的な発展を総合的に進めようとした。消費者の役割、女性や高齢者の参画、都市と農村の交流なども盛り込まれ、旧基本法とちがい、新基本法は国民を強く意識し、国民が農業とどう向き合うかを問う姿勢が強かった。それだけに、新基本法の議論をリードするリーダーには強い「理念」が求められたのだろう。その理念は、この混迷の時代に未来を考えるための心のよりどころになるような気がする。
まずは、新基本法の制定にむけた諮問機関「食料・農業・農村基本問題調査会」の会長になった歴史学者の木村尚三郎氏。木村会長は「二十一世紀のわが国の方向を、『土と共に生きる農型社会』にすべきだ」と語り、そして、21世紀は女性の感性・感覚が重視される時代でもあり、さらに農村の個性的文化が都市をリードする時代だ、とも述べている。
生命総合産業としての農業を土台に農型社会を
一方、基本問題調査会の答申を受けて政策を検討する食料・農業・農村政策審議会の初代の会長を務めたのは今村奈良臣さんであった。東京大学の研究者でありながら、「まちむら交流きこう」の理事長や「全国農産物直売ネットワーク」の代表として農村に足しげく出かけた。農文協との関わりも深く理事として32年間、会長として7年間、農文協の活動を支えていただいた。
今村さんは政策審議会就任にあたって「次のような私なりの基本スタンスを、熟考のうえで腹に決めて、会長として臨むことにした」という。以下の5か条である。
1.農業は生命総合産業であり、農村はその創造の場である
2.食と農の距離を全力をあげて縮める
3.農業ほど人材を必要とする産業はない
4.トップ・ダウン農政から、ボトム・アップ農政への改革に全力をあげる
5.共益の追求を通して私益と公益の極大化をはかる
この今村さんの提言の核心について最後の単著になった『私の地方創生論』(2015年・農文協発行)をもとに、まとめてみよう。
「農業は生命総合産業であり、農村はその創造の場である」について。この提言の小項目には、食料自給率45%への向上と国民への安心・安定した食料供給とともに、農村がもつ保養・保健機能、都市・農村の交流によるとくに青少年への農と食の教育、さらに農村の伝統文化や先人の知恵の結晶を次世代に伝承し、豊かな心のよりどころを創るなどのことを挙げている。「生命総合産業」という言葉には、農業は食料生産だけにはとどまらない、暮らしをつくる特別な産業だという、本源的な農業のとらえ方があった。
その本源的な力を発揮するには「食と農の距離を全力をあげて縮める」ことが大事になる。農業の近代化・産業化のなかで遠くなってしまった食と農の距離を、直売所を中心に「地産地消」を進め、それを広げて都市民ともつながる。こうして生命総合産業たる農業と地域、そして国民の食生活を一体的に再生、創造する。そのためには、食と農をつなぎ地域をつくる企画力と実践力をもつ人材が必要。農政はそんな地域の人材によるボトム・アップ農政でなければならない。一方、生命総合産業の創造の場である農村は共益・共助の世界であり、その追求によってこそ個々の農家も国もよくなる。
こうした生命総合産業としての農業を土台に食も景観も医療・介護も文化も豊かに展開できる。これが今村さんの新しい農型社会にむけた思いであり構想であった。
基本法改正への提案・5氏の意見
新基本法のもと、日本型直接支払制度(多面的機能支払、環境保全型農業直接支払、中山間地域等直接支払)や農村都市交流、食育などの政策が生まれ、それなりの成果をあげてきた。「会長としての在任中、農政改革に全力をつくしたつもりではあったが、旧来からの農政システムの全面的改革は容易ではなかった。唯一ともいってよい斬新な改革は、『中山間地域等直接支払制度』の創設である」と今村さんは述懐している。
それでは、新しい基本法に何を期待するか、何を盛り込むべきか。国民的な議論にむけ、本誌の兄弟雑誌『季刊地域』では、次号で5人の方の意見による「食料・農業・農村基本法改正に提案」の小特集を組んだ。詳しくは『季刊地域』52号(2023年冬号)をぜひご覧いただくとして、ここではダイジェストしてみよう。
◆荒川隆さん(一般財団法人 食品産業センター理事長)
従来のパラダイムは激変した、平時でも有事でも、国民を飢えさせない食料安全保障政策が求められている。にも関わらず農業予算が減少の一途をたどってきた。
筆者が農水省に入省した82年、農水省予算は3兆7000億円でピークだったが、その後じりじりと減少を続け、今や2兆2000億円だ。この間、我が国のGDPも国の財政支出も、概ね2倍となっている。かつてGDP1%の制約で呻吟していた防衛予算に農水省予算が追い越されて久しいが、今や防衛予算の4割程度にまで低迷している。圧倒的な内外の競争条件格差に目をつぶり「農業を特別扱いせず、株式会社の参入など競争原理を働かせることが最良の処方箋だ」などとうそぶく財界の論調は無責任きわまりない。
◆柴田明夫さん((株)資源・食糧問題研究所代表)
そもそも、「食料・農業・農村基本法」は相互に相矛盾する三つの目標から成っている。
「食料」は、食料の自給率向上を目指し、多少コストがかかっても国内生産を拡大すること。一方「農業」は、市場経済下では儲かる農業を目指すことであって、そのために規模拡大―六次産業化(付加価値増)―輸出拡大といったアベノミクスの「攻めの農業」を実現することが目標となる。「農村」は、農業・農村の持つ多面的機能・多様性を発揮することが必要となる。
しかし、これらは同時には成立しない。政府が「農業」に力こぶを入れれば、一時的には優れた企業農業が育つ一方、地方の中小零細農業は減少し、結果として二極分化が進み、「農村」は疲弊し、多面的機能の発揮どころではない。SDGsもおぼつかない。
だが、ここで「食料」の増産に向けて、農業資源(農地、人、農業用水、水源涵養林、地域社会)をフル活用する方向に農政を切り換えるならば、「食料」「農業」「農村」がすべて連動するはずである。
◆蔦谷栄一さん(農的社会デザイン研究所代表 元農林中金総合研究所)
輸入が途絶するような不測の事態レベルでは、地域資源として確たる生産基盤を有することが要件であり、水田稲作がコアとなり、米を中心とした日本型食生活を基本に置く必要がある。そして水田を維持し、多面的機能を発揮させていくには、高齢化が進行する中で新規就農者の確保が絶対条件となり田園回帰が不可欠だ。
一方、食料自給には都市農業も欠かせない。市民が市民農園等により農業スキルを獲得し、援農、さらには担い手を獲得していくことが必要である。このため市民皆農・国民皆農に向けての「農あるまちづくり講座」さらには「協働農場」の展開等の各地での活動が欠かせない。
基本に置くべきは小さな自給圏の創出であり地方分散型の国家ビジョンなのであろう。
◆関根佳恵さん(愛知学院大学教授)
小規模・家族農業によるアグロエコロジーへの転換をと提言する。
国連や世界銀行は、科学者や市民社会団体とともに、アグロエコロジー(生態系と調和した持続可能な農と食のあり方)への転換を推奨している。その背景には、農業の生産性を土地生産性や労働生産性だけで測るのではなく、資源エネルギー生産性(資源エネルギーの単位投入量当たりの収量)や社会的生産性の視点から評価する機運の高まりがある。社会的生産性とは、小規模な家族農業が多数存在することにより創出される多面的価値により社会全体の生産性が増すことを指す。EUの共通農業政策も米国農務省も気候変動や環境汚染への対策と小規模経営への支援を強化する方針を打ち出している。
◆宇根豊さん(福岡県・百姓)
なぜ、まだ農業に進歩や発展、変化や革新を求めるのだろうか。「オタマジャクシの足が生えないうちは、田んぼの水は切らせない」という百姓の情愛は、「産業主義」では無駄なものと映る。そして現実は政治と経済で動いていると思い込むようになる。私たちの人生は、政治や経済ではとらえられない世界にこそ根を張っているから、豊かさは途切れない。
農を産業にしようとするのは、もうやめにしたい。カネにならない「めぐみ」をしっかり引き出して分かちあう農のシステムこそ、未来社会のモデルになるものだろう。基本法ではその気概を示してほしいものだ。
*
5人の提言を読んでいるうちに、本気で「国民皆農」をめざす時代なのかもしれないと思えてきた。
柴田さんがいうように「食料」に力点をおけば人と自然を存分に活かすことになり地域は元気に、賑やかになる。関根さんのアグロエコロジーは労働生産性より資源エネルギー生産性を大事にするから多くの人々の参加、共同作業が必要になるだろう。蔦屋さんはズバリ市民皆農・国民皆農を提言、そこでは農業スキルの獲得をめざす。そして荒川さんは、これをしっかり支える国の抜本的支援強化を求める。
「農型社会へ」という理念は、持続的な食料自給の必要性が強まるなかで、実践的な課題になってきたともいえる。この間の田園回帰の流れをさらに大きくし、新規就農者や半農半X、農に思いを寄せる「気持は農家」の人々まで重層的に国民皆農の世界をつくっていく。
そこでは宇根さんがいうように、政治や経済ではとらえられない豊かさが見いだされるのだろう。
(農文協論説委員会)