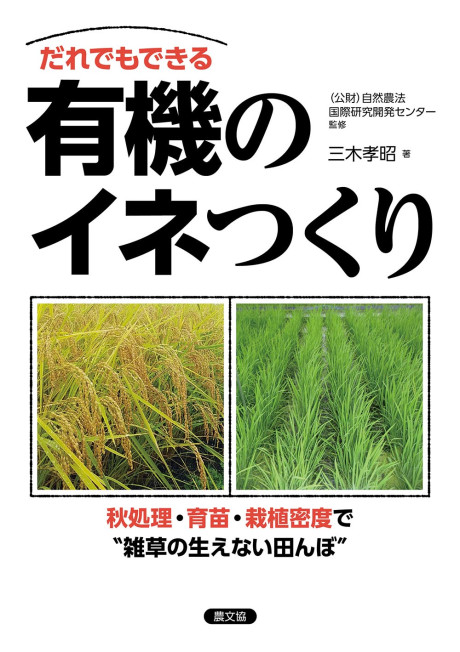主張
お米の値段、どうあるべきか
目次
◆高騰米価は農家にとってもびっくり
◆価格転嫁より直接支払い
◆直接支払いは生産・消費双方にメリット
◆農家を増やすための有機農業
◆農家を増やす所得補償を
高騰米価は農家にとってもびっくり
本誌8月号の特集は「農家がリアルに考えた米の適正価格」である。稲作農家には平野部で100haを超える水田を担う大規模経営もあれば、中山間地域で数十枚にも分かれた数haの棚田を守る小さい経営もある。有機農業やこだわりの栽培法もあれば慣行栽培もある。そこから生まれるお米は同じようで同じではない。それぞれの経営に応じた適正価格があることがよくわかる。
本誌と同時発売の増刊号『季刊地域』2025年夏62号でも、福島県二本松市の菅野正寿(すげのせいじ)さんが自分がつくる米の生産費を試算している。市が毎年公表する「農作業労働賃金標準額」をもとに計算した金額は玄米60kg当たり2万1120円。また、これを精米して5kg袋に詰めて販売する場合は、その手間や機械の償却費、包装費などを加えて3000円と試算している。このくらいの価格を適正と思う読者も多いのではないか。
一方、各地のJAでは、昨年産の「買い負け」の反省から、今年秋の集荷率を上げるため早々に概算金を発表するところが相次いだ。たとえばJA全農あきたでは、あきたこまちの概算金を1等米60kg2万4000円とした。通常なら、これにJAの手数料や流通経費、卸・小売段階のそれを加えても、1万2000円も上乗せすれば小売価格になるだろう。玄米3万6000円を白米5kgに換算すれば3300円ほど。3500円には収まりそうだ。
消費地では、農家の生産費補償が米価高騰の主因と思っている人が少なくないかもしれない。だが産地では、この間の5kg4000〜5000円超にもなる米価を求めているわけではない。
価格転嫁より直接支払い
ただし5kg3000円台では高くて買えない、という消費者もいる。1年余り前までは2000円前後で購入できたのだからなおさらだ。
東京科学大学が今年2月に全国の1万人を対象に行なった調査結果がある。それによれば「お金がなくて、一日中何も食べないことがあった」「十分な食べ物が買えずに体重が減ったことがあった」という経験を過去1年間でしたことがある人が、5人に2人以上もいたという。調査した同大の藤原武男・未来社会創成研究院長は、これを「食料危機層」と呼んでいる。収入以外にも、食や健康への優先度が低い、食べ物を売るスーパーや商店に行きにくい、などの要因が考えられるとはいうが、食料危機層は全体で43・8%にもなる。若年層、非都市部に多く、地域別では東北、九州で50%超になったという(朝日新聞ウェブ版・5月23日)。
農家は、資材・燃料費が値上がりする中で5kg2000円では米づくりが続けられない。だが物価高に苦しむのは消費者も同じ。とくに主食である米は安いほうが助かる。『季刊地域』62号では2人の研究者が、その解決策として政府の直接支払いによる所得補償を提案している。
その一人、明治大学の作山巧教授は次のように書いている。昨年来の米価上昇で価格転嫁が進んだという見方もあるが、「今回の農産物価格の上昇がもたらしたのは、消費者・実需者の理解に基づく円満な価格転嫁や国産品の購入ではなく、高価格に対する怨嗟の声と安い輸入品へのシフトだった」「そもそも価格転嫁の実現には、1消費者の所得向上、2輸入制限の存在、が前提」だという。
消費者の所得向上が実現していないのは前述のとおり。かろうじて残る米の関税も今回の高騰には役に立たず、アメリカ・台湾・中国・オーストラリア・タイから輸入米が次々入っている。
政府は、食品のコスト増の取引価格への転嫁を、流通加工業者の努力義務にする法律を成立させようとしている。だが、作山教授はこれに否定的だ。そもそも関税を撤廃したり低くしてきたことは価格転嫁の放棄を意味する。いくつもの貿易協定で自由化を進めておきながら価格転嫁を喧伝するのは「矛盾であり偽善に他ならない」と喝破する。
直接支払いは生産・消費双方にメリット
直接支払いによる所得補償というと、民主党政権が2010年に導入した「農業者戸別所得補償制度」が記憶に新しい。当時、10a当たり1万5000円の所得補償が原因で米価が下がったと言われたが、作山教授によればそれこそが直接支払いのメリット。「価格転嫁は生産者と消費者の対立を生むのに対して、生産者への直接支払いは、その利益の一部が価格低下を通じて消費者に帰属するため、生産者と消費者の両方にメリットがある」というのである。
石破総理もたびたび生産者への所得補償に言及している。だが、全面導入には否定的だ。導入するとしても「経営努力をする米農家」に限る、というような話をしている。想定しているのは、スマート農業を導入して経営規模を拡大する大規模層か。だが、10年20年にわたる低米価をしのぎ、今も米づくりを続ける農家は経営努力をしていないのだろうか。とくに2021〜22年は資材高騰が重なり、「時給10円」と言われる苦境を踏ん張ってきた。
政府が米の増産に舵を切り、大規模農家だけ支援して増産できたとしても、それは、畜産の飼料自給に貢献した飼料米・飼料イネを減らしたり、転作の大豆生産も減らすことになるだろう。それに、そうした犠牲のうえに何年か増産できたとしても、果たしてそれが続くかという疑問も残る。形を変えて続いていた「減反政策」が米不足を招いたという見方もあるが、根本的な問題は5月号の「主張」欄でもふれた「農家が足りない」ことだ。
農家を増やすための有機農業
ところで『季刊地域』62号の巻頭特集は「有機農業 点を面にする」である。その中に有機農業でむらににぎわいを取り戻そうと、地域の非農家住民と今年2月にNPOを設立した八木直樹さん(千葉県南房総市)の記事がある。
東京生まれの八木さんが28年前に就農した頃は兼業農家も多く、田植えやイネ刈り時期の農村は活気に満ちていた。しかし近年は農繁期でも人の姿が見えない。一方で八木さんは、有機農業をしながら地域に根ざした暮らしがしたいと訪ねてくる人が増えていることを肌で感じていた。そこで、非農家の住民を巻き込んで就農支援や農業体験の受け入れをする組織の立ち上げを決心した。
そのさなか地域を揺るがす事件が起きる。ある集落の中核農家が田植えの最中に亡くなり、別の集落では中核農家が翌年に耕作面積を大幅に減らすことがわかったのだ。これらの田んぼを引き継ぐ農家が足りない現実を目にして、設立を進めていた組織の必要性を確信したというのである。
特集には、八木さんのように「点を面にする」ため奮闘する人たちがたくさん登場する。富山県南砺市の「なべちゃん」こと渡辺吉一さんもその一人。地元のJAに勤めながら兼業で田んぼをつくっていた頃、高齢でリタイアする農家から引き継いだ、山の上の生きものいっぱいの田んぼに心を揺さぶられ、これを守ろうと決意したのが出発点だ。
定年退職を機に自然栽培を学び「なべちゃん農場」を始める。近所に、市役所勤めの傍ら飯米を自然栽培する市川孝弘さんという同志もできた。2人は一昨年、「2回代かき」で雑草を抑える技術を身につけ、反収を3俵から6俵に倍増させる。その様子を見ていた隣家の松本一茂さんも刺激を受け、朝、勤めに出る前にチェーン除草をして、やはり飯米を自然栽培するようになった。
化学農薬・化学肥料に頼らない有機農業はもはやブームと言ってもいいだろう。なべちゃんのところにも、そんな農業を学びたいと消費者が訪ねてくる。なべちゃんも八木さんと同じだ。やはり地元をにぎやかにしたい思いで、自然栽培の米づくりを体験できる「田んぼの教室」を3年前に始めた。その卒業生の中から、ここで暮らしたいと移住する人も2人現われた。なべちゃん、市川さん、そして移住者の2人は、今年一緒に法人組織を立ち上げ、自然栽培の米づくりを5haに広げる。
農家を増やす所得補償を
経営効率を高めるためには規模拡大。確かに理にかなっているのだろうが、農村は食料生産の場であると同時に暮らしの場であることを忘れていないだろうか。とくに水田は、水路の泥上げやアゼの草刈りを大勢の兼業農家が担うことで維持されてきた。大きい経営だけが田んぼを担う農村に、離農した農家は住み続けるだろうか。少数の大規模経営だけの農業で、田んぼを守り、田んぼがもつ生産以外の多面的な機能を維持できるだろうか。そしてその大規模経営が、何かの事情で経営を維持できなくなったら......。
米不足の解消は喫緊の課題だが、みどり戦略で2050年に有機農業を100万haに増やすことも政府が掲げた目標である。それが効率のよい大規模経営だけで実現できるとも思えない。
冒頭で紹介した二本松市の菅野正寿さんも、有機的な米づくりをしたいという市民を、1枚5〜6aの小さい田んぼの「棚田オーナー」として受け入れている。これからは「農家も市民も共同の力で米づくりを守る」時代だという。
菅野さんは同じ記事中で、中山間地域で米づくりをする農家の立場から「里山環境保全交付金」と名づけた直接支払いを提案している。菅野さんがつくる3ha余りの水田には小さい棚田がたくさんある。だが、冒頭で引用した試算には、棚田ゆえにかかる手間が十分に反映されていない。それに、防除は除草剤1回のみに抑えた米づくりを棚田で続けることが、多くの生きものを育んでいる。以前、視察で訪れたスイスでは、環境と観光資源の保全を一体化したような交付金が設けられていた。同様の制度を、農地保全のための中山間直接支払とは別に創設してはどうかというのだ。現状の環境保全型農業直接支払を拡充するようなイメージか。
農家が足りない農村の現場で、有機農業で米づくりをやってみたい、就農したいと田んぼにやって来る人たちは希望だと思う。お米の値段を支える制度は、農家をこれ以上減らさない、そして有機農業を守り立てるものでもありたい。
(農文協論説委員会)
*米の小売価格を下げるための直接支払いについては、特集の中で農家の薄井吉勝さん(2025年8月号p63)も具体的なアイデアを提案しています。一緒にご覧ください。