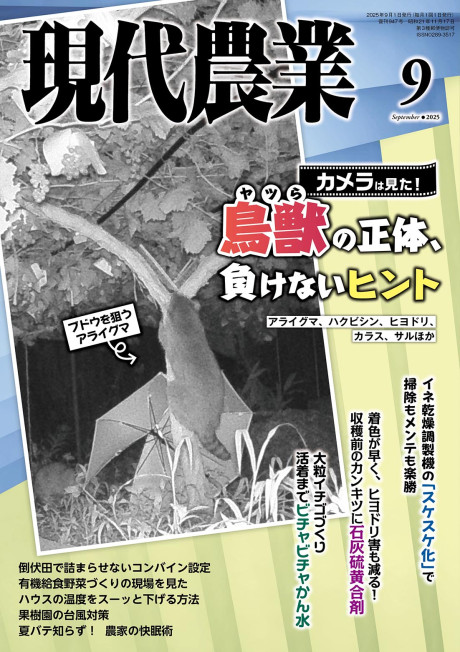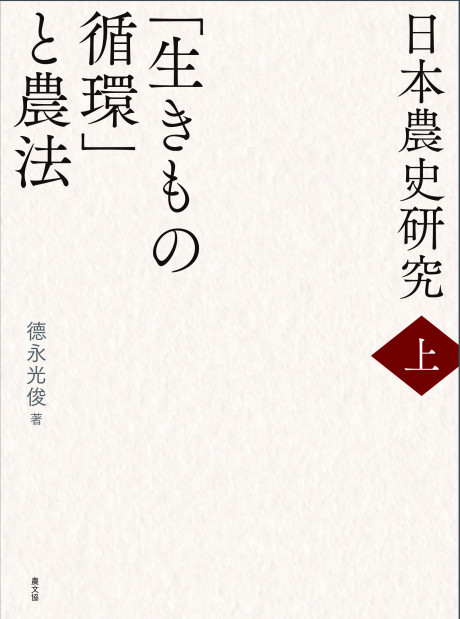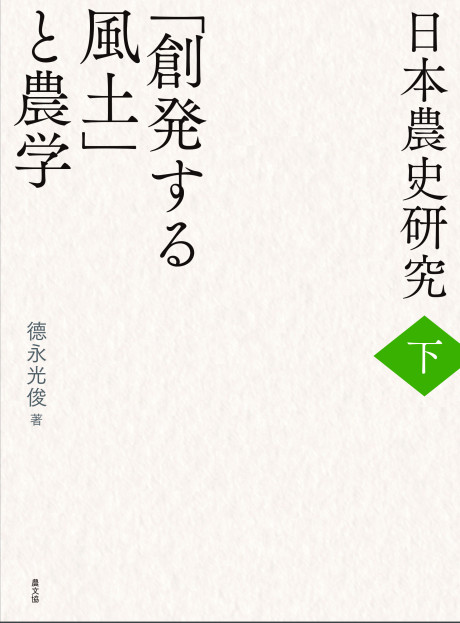主張
風土農法から有機農業を考える──『日本農史研究』をひもとく
目次
◆日本列島には風土農法の歴史が滔々と流れている
◆多様な風土に、生きものたちと農業者が協働する農法
◆農業と工業はどこが違うのか
◆風土農法、有機農業の基本は「待つ」
日本列島には風土農法の歴史が滔々と流れている
最近、農業はカタカナで語られることが多い。オーガニックやSDGs、リジェネラティブ......。だが、どこか違和感を覚える。違和感という言葉がピンとこなければ、落ち着かなさといってもよいかもしれない。その中身をあらっぽく言ってしまえばこんなふうだ。
人間の知識が増えたりカタカナ書きになったりしても作物が変わるわけではない。もちろん見え方は変わるのだが、作物そのものは変わらない。イネはイネ、ウシはウシだ。
農学者・德永光俊さんの新刊『日本農史研究 上・下』(農文協)は上巻『「生きもの循環」と農法』、下巻『「創発する風土」と農学』で計700ページとたいへん重厚な書である。膨大な文献や江戸農書と、それらの数多の著者をもとにまとめられている。德永さんは上巻の「はじめに」でこう言う。
「1973年にノルウェーのネスが唱え始めたディープ・エコロジー、最近では欧米のアグロ・エコロジーなどがもてはやされる。私が強調したいことは、こうした見方が日本列島の風土農法において、早くから存在していたという歴史的事実である。文字に書き残されている史資料から、遅くとも江戸農書、江戸期の思想家である安藤昌益に確認できる。地下水脈として現在まで滔々と流れ続けてきたのである」
日本列島には、ディープエコロジーやアグロエコロジーに先行して、同様の見方があったのだ。その滔々とした流れの一端を本書から紹介してみよう。
多様な風土に、生きものたちと農業者が協働する農法
本書の第一のキーワードは「風土」である。「風土」というと古くさいと言われるかもしれない。たしかに「風土」という言葉は古い。日本各地の地理や産物、地名の由来などを記した「風土記」が編述されたのはいまから千数百年前である。
そして、「風土」といえば、和辻哲郎の『風土』(1935)を思い出す人がほとんどではないだろうか。最近ではオギュスタン・ベルクの風土論を取り上げる人が多い。しかし、彼らの風土論では、比較文明論は論じられても、日本列島の農法史を具体的に描くことはできない。
德永さんはその証左として、地理学・民俗学の千葉徳爾による和辻批判を紹介する。
「和辻は日本の風土の特殊性として夏の大雨と冬の大雪という両面的な風土の二重性格をあげた。しかし、少しでも地理的な知識を厳密にもつ人ならば、それらを一カ所でともにもつ土地は日本にはほとんどないことを知っている。日本全体を一つの単位と認めるならば、このことは当たっているかもしれないが、冬大雪の積る地域は必ずしも夏の大雨が定期的に来襲する地方ではなく、逆もまた然りである」(千葉徳爾・籾山政子『風土論・生気候』、1979、朝倉書店)
哲学・倫理学であれば「モンスーン気候」でよい。しかし具体的な日本列島の農法を検討する場合には、地域的な多様性を問題にしなければならないというのだ。
本書で「風土」を語るうえでもっとも参照されているのが三澤勝衛(1885~1937)の風土論である。
三澤は、昭和戦前期に長野県で小中学校の教師をしながら地理学を研究した人物である。地域に根づいて、地域の暮らしを観察しながら、地域の人びとに役立つ独自の風土論を開拓した。農文協からは『三澤勝衛著作集 風土の発見と創造(全4巻)』も出版されている。
德永さんは、三澤風土論についての的確な説明として作物学者の栗原浩を引用する。
「風土とは、三沢勝衛氏の表現を借りると、大地と大気の接触面を基調とし、それにあらゆる生物を加味しているもので、その三者が互いに関係し合って完全な一体となった三位一体的なものである。彼の生態的な自然観のなかには人間が含まれており、そして風土が生きた系(システム)であることを認めている。
彼は、風土は高度に総合化された全一体であり、そうした風土をわれわれが実見・観察できるのは、土壌・植生(ここでは作物)、動物および人々によるとして、これら四種を『風土の表現体』と呼んでいる。ここで強調しておきたいことは、風土を細かく要素に区別するのでなく、全一体(ありのまま=具象)としてとらえようとしていること、統合された系(システム)としてみようとしている点である」(栗原浩『風土と環境―その視座のちがいから農耕を考える』、1988、農文協)
德永さんは、三澤の風土論で重要なのは「作物風土論」だという。「風土+栽培技術=作物の要求する風土」。人間中心の風土論でなく、作物中心の風土論である。そして、「風土農法」「風土農学」という言葉を德永さんは造語する。「風土農法」とは、多様な風土のもと、生きものたちと農業者の協働による農法をさし、「風土農学」とは、このそれぞれの土地の風土農法を支える農学のことをさす。德永さんは奈良盆地の農業を地道なフィールドワークによって実証的に研究し「大和農法」と名付けたが、それに対応する「大和農学」があるというのだ。
風土農法も風土農学も伝統にねざす。しかし固定したものではない。いやむしろ新しい技術の誕生や社会情勢の変化によって動いていく。そして重要なのは、風土は積み重なるものであるということ。本書では「層序」という言葉を使っているが、いまの農地の下にはその土地が開かれた当初の地層があるし、それまでつくっていた作物の影響や痕跡があったりするのは、ごくごくあたりまえの話だろう。
農業と工業はどこが違うのか
本書のもう一つのキーワードは「すき間」である。「すき間」とはなにか。それは、「農学が提案するあるべき農法」と「風土が求める農法」の「すき間」である。理論と実践のすき間といってもよい。
戦後農法論は西欧の農学を参考に「めざすべきモデル」を設定し、それとのズレを問題にしてきた。だが、それを鋭く批判し、前提からひっくり返してしまったのが守田志郎(1924~1977)だ。
守田は、農書研究でも知られる古島敏雄(1912~1995)の愛弟子である。にもかかわらず農業史家という「金の学問」の筆をいったん折り、農業者に寄り添う「鉛の学問」を目指すこととし、1977年に逝去するまで次々と問題作を連発した。守田により初めて「すき間」が自覚化され、そして西欧モデルが否定されたのである。
1971年に農文協から刊行した『農業は農業である』で守田は、画一化された品種への疑問、水田の絶対視への疑問を呈し、多肥の百年を見直して「土を軸に」と呼びかけた。これらの疑問や呼びかけは、現代でも通じるだろう。
德永さんは、守田が農業と工業の違いについて論じた次の箇所に注目する。
「作物や家畜の、生産と繁殖の過程での自然のいとなみや大小のうねりの中に身を置いて『待つ』ことのできる体質......『待つ』ことを静かに耐え、乱れのない呼吸を続ける、それができる人によってのみ農業というものが存在しうるのである」。「農家の人たちの生活における呼吸の、息をはくことが作業にあたるとすれば、『吸』にあたる『待つ』の行為」は、「稲が育ちやすいように田を作り、色々のことをととのえる。良くも悪くも、稲は自分で育つのである。農家の人たちが稲をこね上げて造るのではない」(守田志郎『農法』1972、農文協)
このように守田は、農業は整えることが基本となる調整労働なのだと主張するのだが、そこから『農法』の前年に守田が書いた『農業は農業である』の真意もみえてくる。守田が言う「農業は農業である」とは、「農業は空間を時間化する」の意味ではないか。守田の出版を支え続けた編集者の原田津(1932~2013)は、次のように述べている。
「工業の場合には、各部品を時系列的に作って完成させるのではなく、別々に同時進行で各部品を作って最後に一か所の空間に集めて横並びさせて完成させるのである。時間を並列させることによって時間を空間化させるのである。農業の場合にはそうはできない。一定の生育の『待つ』時間が必要だからである。さらには過去の労働の成果、例えば祖先が開墾した肥沃な耕地は現在に同時存在している。60年後の伐採を予測して山に杉を植える。現在の空間は未来の時間を経てやってくる空間と同時存在することになる。つまり、農業は空間を積み重ねることで空間を時間化する」(原田津『むらの原理 都市の原理』、1997、農文協)
農業においては、過去の仕事の成果は、現在の仕事に積み重ねられて、同時に存在する。未来に実現されるであろう仕事の成果は、現在の仕事に上積みされて、同時に存在する。現在の目の前に見えている空間に、過去と未来の目に見えない空間が、時間として積み重ねられ上積みされているのである。ここでの空間を風土と読み替えることも十分に可能だろう。農業はまさに風土産業なのである。
風土農法、有機農業の基本は「待つ」
風土農法の基本は「待つ」だと德永さんは言う。守田も言うように、「待つ」は農業の本質に関わる。「待つ」、受け身passiveの姿勢は、生きもの循環を実現させるものであり、古今東西を問わず、農業の基本的なありようである。
たしかに土づくりひとつとっても、「待つ」ことは欠かせない。堆肥が完熟するのを「待つ」、堆肥が土に馴染むのを「待つ」、肥効が現われるのを「待つ」。
有機農業の基本も「待つ」であり、「待つ」ことによって生まれる生きもの循環であろう。
生きもの循環の基本原理は、何も難しいことではない。日本列島で代々伝えられてきた「おかげさま・おたがいさま」「いただきます・ごちそうさま」の日常生活の和語の世界である。感謝して祈るのである。
カタカナでなくても農法や農学は語れる、いや、和語で語れてこそ本物の日本列島の農法・農学ではないだろうか。
(農文協論説委員会)
- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。
 現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
【主張】風土農法から有機農業を考える──『日本農史研究』をひもとく【現代農業VOICE】