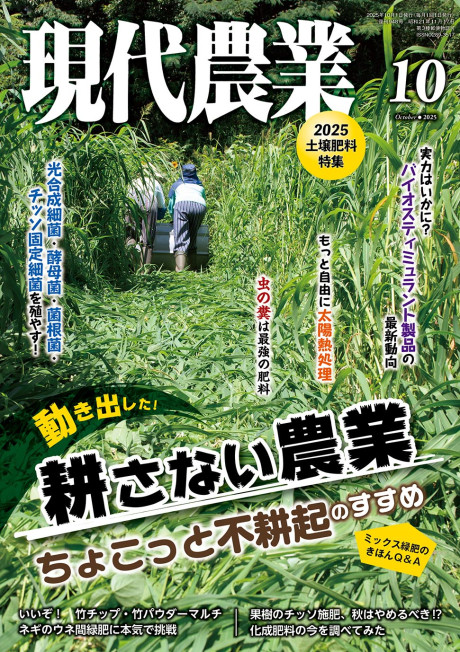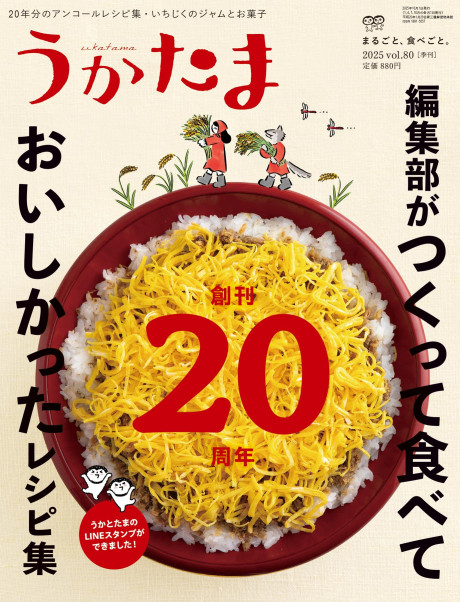主張
これからも、つくって食べる
目次
◆葉つきダイコンが買いたくなる
◆「手づくり」をめぐる20年
◆郷土料理は先人からの伝言
◆一緒に農家のほうを向いて進む
葉つきダイコンが買いたくなる
みなさん、ダイコン葉は好きだろうか。ゆでて刻んでご飯に混ぜて、菜飯にするとおいしいけれど、葉つきで放置するとダイコンの水分が失われやすいし、葉もすぐ黄色くなってしまうから、台所には持ち帰らず、畑で切り落とすという人も多いかもしれない。
買う側からすると、ダイコンが葉つきで売られていると「おっ」となる。が、すぐにわが家の狭い台所が頭をよぎって手が止まる。それによく見ると、カブの葉と違って表面の繊毛がかなりトゲトゲしているし、株元付近はいかにも屈強そうで、ゆでてもやわらかくならないのでは、と思わせる。「生ゴミが増えると嫌だから今日はやめておこう......」と、たいていこうしてあきらめてしまう。
育てる側からすると文字通り「捨てるほどある」ものだが、買う側にとってダイコン葉は気軽に入手できる食材ではない。それをわかったうえで、『うかたま』で食べ方を紹介したことがある。
季刊『うかたま』は、2025年秋号で創刊20周年を迎える農文協の食の雑誌だ。しばしば「『現代農業』の妹分」と名乗っているが、読者は農家より「消費者」のほうが多い。あるとき読者アンケートで「直接農産物を買ったり、農園に体験や援農に行くなど、農家と直接つながりはありますか?」と聞いたら、「わが家は農家です」とか、「親戚や友人知人に農家がいる」という回答がある一方で、「つながりはほとんどない」と答えた人が最も多かった。
話は戻って、ダイコン葉の食べ方を教えてくれたのは、現在『うかたま』で「鴨志田農園の畑ごはん」を連載している東京都三鷹市の農家・鴨志田佑衣さんだ。
「ダイコン葉は、葉が元気なうちに根から切り離し、細かく刻みます。そこに、全体がしんなりするくらい塩をふり、15分ほどおいたら軽くしぼって水を切ります。蓋つきの容器に入れて冷蔵庫で、1週間くらいもちます」
こうして保存しておくと、黄色くしおれることもなく、ちょっと緑がほしいときに便利なのだとか。ネギの代わりに味噌汁や納豆に入れてもいいし、炒め物の彩りに加えてもいい。シャキッとした食感で、辛みや青臭さもない。青菜の少ない時期にはとても重宝するという。記事では水餃子やちらし寿司の具にするレシピも紹介した。
鴨志田さんの連載では毎号、農家ならではの食材をテーマにしたレシピを紹介してもらっている。これまで取り上げたのは、キクイモ、干しダイコン、シュンギク、モロヘイヤ、カキ、菜っ葉、新ショウガなど、どれも農家なら困るほど手にすることがある食材だが、農家でなければ「たっぷりある」という状況にはならなさそうなものもある。
ダイコン葉を紹介したとき、「さっそくつくってみました」と感想を送ってくれたのはやはり農家の読者が多かったが、農家以外の読者からも、「葉つきのダイコンを選んで買いたい」そして、「葉っぱを食べたいから、自分でも育ててみたい」という声が届いた。
自分で育てているからこそ楽しめる農家のレシピを見て、畑のある暮らしっていいな、と感じる都会の読者は意外と多い。「どっさり」や「その時期にしかない」ものでつくる料理や保存食は、農家にとっては無駄なく食べ切るための実用情報だが、都会の読者にとっては、豊かな農家の世界に触れるきっかけになるものらしい。編集部としては、「どっさりある」読者と「買わないと手に入らない」読者、どちらに向けて企画を立てればよいのか悩むこともある。これまで、結局どっちつかずになってしまったりもしたのだが、ここ1年ほどで腹が決まった。
「手づくり」をめぐる20年
『うかたま』が創刊した2006年前後は、食育基本法が制定され、学校や行政、食品企業などの間でも、「食育」が一種のブームとなっていた。そんななか『うかたま』は子育て世代の女性向けの食育の雑誌というねらいでつくられた。ただし食育といっても、農文協的な解釈で、農山漁村で昔から食べられてきた食や、そのまわりにある文化や風習を伝える、という役割を果たすことを目的とした。
創刊時から誌面で意識してきたのは、だしの素やめんつゆのような市販の風味調味料、合わせ調味料は使わない、電子レンジなどの電化製品の使用はできるだけ控える、食材は旬のものを選ぶ、といったことだ。もちろん、それらを否定しているわけではないのだが、短時間で安く簡単にできる料理や、市販品の上手な使い方を紹介する雑誌は他にも山ほどある。
伝えたいのは、畑の作物や山野でとれた自然の恵みをおいしく食べるための知恵や工夫、そして何より、自分で手を動かすことの楽しさだ。2000年代前半は、「スローライフ」という言葉と概念が一般に広がり、都会でも味噌づくりをしたり、家庭菜園をするようなライフスタイルが注目された。『うかたま』はそんななかで、農村に昔からある「手づくり」に触れられる雑誌として、とくに都会の読者から支持を得た。2011年の東日本大震災以降は、消費するだけの生活の不安定さに多くの人が危機感を抱き、自給的な暮らしにより関心が高まった。
令和の現在、各地で開かれる味噌づくりの講座などは相変わらず人気で、自給的な暮らしは生き方のひとつの選択肢になっている。ただ、ここ数年、「市販品に頼り過ぎず、自分でつくれるものは手づくりしよう」と大きな声でいうと、「そんなに余裕のある人ばかりじゃない」「手づくりの強要に傷つく人もいる」などと思わぬ方向から非難されることがあり、やや戸惑ってもいる。仕事は忙しいし、物価は上がり続けるし、時間やお金をいかに効率的に使うか、タイパやコスパのいいレシピや暮らし術がもてはやされる背景はよくわかる。でも果たして、手づくりは余裕のある人の道楽や特権でしかないのだろうか。時間をかけて素材から料理をしたり、味噌や梅干しを手づくりすることは、ただの自己満足なのだろうか。
郷土料理は先人からの伝言
「これからも、つくって食べる。」というのは、9月発売『うかたま』創刊20周年号の特集テーマだ。当たり前だったはずの「つくって食べる」が揺らいでいる今だからこそ、あらためて言葉にしたいと考えた。
「郷土料理には先人の知恵が詰まっている。つながってきた知恵と工夫を『レシピ』にして伝えることが、自分の仕事」と特集内で話してくれたのは、高知と東京で2拠点生活を送る料理家の小島喜和さんだ。祖父母の家がある土佐清水市で月に1度料理教室を開催し、高知県で昔から食べられてきた四季折々の郷土料理を習得することを目標に、1期2年の連続講座を開き、今年で6年目になる。
取材に訪れた6月のメニューは、「キビナゴとリュウキュウの酢の物」「メジカのなまり節と大根抜き菜の和え物」「野ぜりの白和え」「淡竹と茗荷のお寿司」「チャンバラ貝の塩ゆで」「淡竹とニナのからし酢味噌和え」など。ずらりと並ぶとごちそうだが、それぞれ初夏の高知では身近な食材で、どれも家庭で普通につくられてきた料理だという。リュウキュウは、全国的にはハスイモと呼ばれるサトイモ科の植物で、大きな葉を落として茎を食べる。かたいスポンジ状で、皮をむいて塩でもむと、しんなりやわらかくなる。塩もみしたら、人差し指ほどの長さのニシン科の魚、キビナゴと和えて酢の物にする。キビナゴも初夏の味。手で頭と内臓を取り、背開きにして酢で締める。
リュウキュウはこの時期、高知県ではスーパーでも売られているが、地元の人からすると「その辺に生えているもの」もしくは「おすそ分けされるもの」という認識らしい。「そこらに生えているものがおいしく利用できるってこと、どこの地方にもあるでしょうね」と小島さん。「素材をいかして最低限の調味料でつくれるものこそ日常の料理。でも、ささやかな料理ほどつくらなくなると消えてしまう。こういうものを伝えていかなくては」
旬の食材をどうおいしく食べるか、保存して長くもたせるか、郷土料理はその土地で生き抜くために私たちに残された伝言だ。何でも買って済ませられる時代になり、身近な旬の食材に敏感でなくても暮らしに困ることはない。でもここでつくって食べていかないと、先人がつないできたものを次に受け渡すことはできなくなってしまう。
一緒に農家のほうを向いて進む
2024年夏頃から始まった「令和の米騒動」は、『うかたま』読者にも少なからず影響があった。いつも生協で注文している米が、急に抽選販売になったという読者からは、「米不足は結局何が原因だったのか知りたい。消費者である自分にできることはあるのか」というハガキが届いた。今号でこれに答えてくれたのが、新潟県上越市の山間地で稲作中心の農業を営む、鴫谷幸彦さんだ。
米不足については、農協が悪いとか卸が悪いとか国の計算ミスだとか、いやいや地球温暖化が原因だとか、報道がじつにかまびすしいが、鴫谷さんは「農家が足りない」ことこそが根本原因だと感じている。長年かけて、農家を減らしてきた農政が、農家のやる気をそぎ、単収も減らした。耕作放棄地も増やした。
では、食べる側にできることは?と聞くと、鴫谷さんは「自炊すること」と応えてくれた。みんなが普通に米を炊く世の中なら、米はなくてもいいね、なんてことにならず、田んぼもなくならない。米を炊き味噌汁をつくって食べる昔ながらの食生活が当たり前ではなくなることは、田んぼの危機だ。農家や農村とつながりがなくても、毎日ご飯を炊いて食べることが、田んぼを守ることにつながっているのだ。「食べる側」にいる人全員に、知ってほしい。
農家と農村がずっと続いていくために、役に立つものをつくることが農文協の使命だ。『うかたま』には何ができるだろうか。自分の暮らしを人まかせにしないために、「手づくり」の知恵や技を共有する。先人がつないできた郷土料理という伝言を、現代でもつくりやすいレシピに変えて紹介し続ける。ご飯を炊いて食べたくなる、台所に立つのが楽しくなるような情報で読者をとにかく盛り上げる。そして、米の向こうには田んぼが、味噌汁の向こうには畑があることを伝えていく......。今はまだ農家や農村と接点がなくても、農村のほうを向いている人がたくさんいる。『うかたま』はそんな彼らと一緒に、農家のほうを向いて進んでいこうと思う。
(農文協論説委員会)
- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。
 現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
【主張】これからも、つくって食べる──季刊『うかたま』創刊20周年【現代農業VOICE】