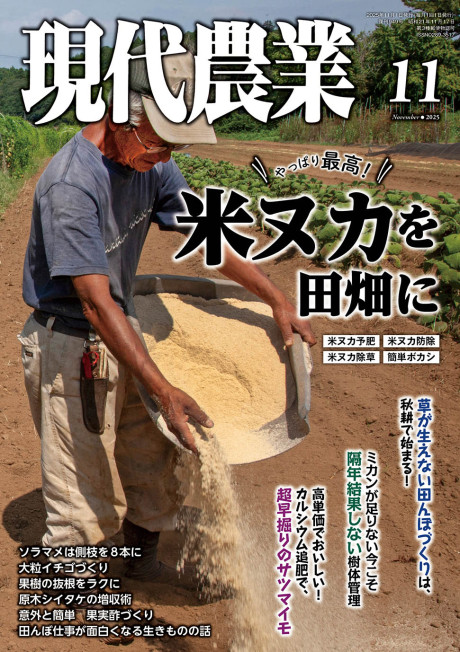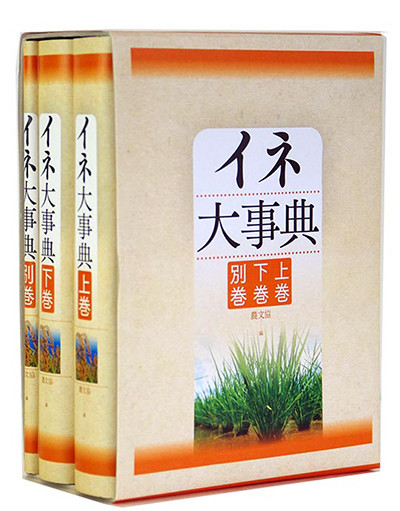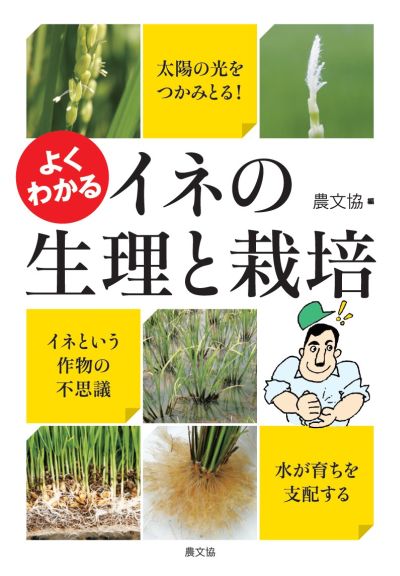主張
農家がいつまでも自由に元気に農業ができる世に──農文協の本を売ってきた36年
目次
◆まだまだ本も捨てたもんじゃない
◆「農家の発想で」本を出す
◆農家に育てられ、励まされ
◆農家農村のあり方を、農外へ伝える
◆イネの本が売れている
まだまだ本も捨てたもんじゃない
「コロナ禍も一息つき」が常套句になりつつある昨今、イベントや展示会が盛況になっている。農業の分野でも、各県での農業機械・資材の展示会のほか、東京国際展示場や幕張メッセでの大規模なイベントも多い。先日、熊本県での大規模な展示会に農文協も出展したが、国内はもちろん海外のメーカーも結構来ていて大盛況だった。来場者は、農家や農業法人、新規参入を目指す若い人から定年退職・転職組などさまざまで、企業人も多い。
農文協は、こういうとき『現代農業』を始めとする雑誌や大事典類、新刊書籍をズラリとならべ、ルーラル電子図書館のデモも行なうが、売れ行きは悪くはない。海外から新しい情報を求めて来場する人も少なくなく、とりわけ中国からの来場者は熱心で、山のように本を抱えて数万円分を爆買いする方も珍しくない。昨今の中国では翻訳アプリが急激に浸透しているようで、その場で目次をスマホで読み込むと、数十秒で翻訳されてくる。正確性にはやや疑問もあるようだが、大きな事典類も、そうやって確認して購入を決めている方が多かった。SNSが盛んでネット社会のイメージも強い中国だが、信頼できる情報はやはり「本」なのだ。農業技術は日本の出版物、とりわけ農文協の本が当てにされている、と強く感じた。周囲の農業資材の出展社も驚いていて、「本も、まだまだ捨てたもんじゃないですね」と言ってくれた。
「農家の発想で」本を出す
農文協はずっと、農村読書運動に力を入れてきた団体だ。戦後、再建したばかりの農文協の理事に、浪江虔という人物がいた。戦前から農村の図書館運動に尽力してきた浪江は、当時の農業書は研究者向けのものしかなく、農家が現場で使える技術書がない、だから農文協は農家の立場になって本をつくるべき、と主張。自ら『誰にもわかる肥料の知識』という本を執筆して10万部を超えるベストセラーになった。この本では、たとえば「野にあるコエダメが日よけもフタもない状態に置かれていると、成分はどんどん逃げていくのです。もし、村うちの誰かが穴のあいた硫安のカマスを荷車に積んでサラサラとこぼしながら曳いていったら、あなた方は必ず注意しますよね? それと同じなんです」(要約)という具合に「脱窒現象」を説明。「科学的な知識を徹底的にわかりやすく表現する」というこの浪江の手法は、その後の農文協の本づくりの原点となっていった。
さらにその後、本誌が『農村文化』から『現代農業』に改題されたとき(1960年)の初代編集長でもあった堀越久甫は、「文章、表現をやさしくわかりやすくするのはよいが、伝えるべきは『科学的な知識』だけではない。本の読者である農家は学者や文化人ほどの知識はないが、その経験の中には珠玉の尊いものがある。それをつかんで表現する『現場主義』の方法をとりたい」として、農家に取材し、農家が多く登場する雑誌『現代農業』の礎を築いた。こうして農文協の出版物はすべて、農家の技術を伝える、もしくは「農家の発想で」農学の成果を活かす、という精神を底流に持つものになっていった。
農家に育てられ、励まされ
読書とはなにか? 本を読むことを通じて自己変革する。その動きが広がることで、世の中が変わっていく。農文協の本を広めることが、農家や農業、農村を変える。ひいてはそれが日本の社会や環境がよくなることに通じると思い、36年普及職(営業職)に従事してきた。農家の「収穫量を増やしたい」「品質のいいものを上手につくりたい」、あるいは「手を抜きたい、ラクしたい」などのさまざまな気持ちに共感し、潜在的な生産意欲や学習意欲、向上心に触れながら普及してきた。いや、普及は必ずしも「売る・買う」の関係だけでなく、会って話すだけでも人は前向きになれるし、なる。ましてや農作物や生きもののことを介して話すと、その力は一層増す。そしてそれはそのまま、普及する側の自分にも返ってくる。これまで十万人近い人に会って話し、本を勧める仕事をしてきたが、そのたびどれだけ自分の生き方に影響を受けたかは、計りしれない。
若い頃のことはよく覚えていて、入会1年目に訪問したのは新潟県旧豊栄市の小規模な牛飼い農家だった。平日の昼間だったが、小学生の子供が家にいた。今日は牛飼いにとって大事な家族総出の作業の日で、手伝いをさせるために学校を休ませたという。だがこのことを、あらかじめ小学校の担任に話すと「それはダメだ、休ませないでください」といわれ、かなりの話し合いをしたという。農家は「現代農業さん、どう思う? 当然のことでしょ」と言ったが、教員を父に持つ自分には、家族総出の農作業のために学校を休ませるという発想はなく、このときとても驚いた。病気でもないのに学校を休むなんて考えたこともなく、家族労働というものを初めて知った出来事だった。子供と学校、家族経営、生業、共同作業、情操教育、食農教育(当時はこの言葉はまだなかったが)など、一度にいろいろなことを考えさせられた。
1年目には他にも、『現代農業』が大好きな若手の有機農家で歓迎していただき、長く話し込んだ末、友達感覚で思わず失礼なことを言ってしまい、その瞬間ぴしゃりと叱られたことも印象に残っている。怒鳴って追い出すでもなく、毅然と強い意志でたしなめられたのは、その方の人格もあろうが、根本は農文協への信頼感からだったのだと今は思う。『現代農業』を出している農文協への信頼感、先輩方が培ってきたものがあったればこそ、その組織への新入りの無理解を、きちんと諭してくれたんだと思う。
また、「農文協があるから頑張れる」と言われたことも一度や二度ではない。「農文協が『現代農業』を持って元気に農村をまわっている間は、日本の農業まだまだ大丈夫だな、頑張れるよ」と、1年に一度そんなことを言ってくれる農家に会えるだけで、こちらも頑張れた。そうハッキリ言ってくれなくても、孫のように接してくれる農家のばあちゃんに会うだけで、こちらが励まされた。
90年代には、「俺らの代わりに、消費者に発信してくれ」と、よく言われた。減反、牛肉オレンジの自由化。バブルの余波の中、都会では農業バッシングも強まった時代だった。かたや食の安全が注目され、有機農産物や抗アレルギー食品への関心も高まった。だが農家農村から若い人は出ていき、農家には後継ぎがいなくなった。
そんななか、「俺らは頑張っていると、消費者に発信してくれ。あんたら若い農文協の人に託しているよ」。そう言って「お互い頑張ろう」と、励ましてくれた和歌山の農協の組合長のことが忘れられない。
農家農村のあり方を、農外へ伝える
その後は大阪や東京など都市部を担当することが多くなり、大学や高校、図書館、書店へ普及する機会が増えた。
2000年前後の農文協の出版物は、完結した「日本の食生活全集」をはじめとして、さまざまなラインナップがあった。「人づくり風土記」「日本農書全集」「世界の食料・世界の農村」などの大型全集、稲作や野菜の大百科シリーズ、「そだててあそぼう」をはじめとする絵本シリーズ、集落営農や食についてのビデオなどのほか、多様な単行本もあった。それらを都市部で普及することは、まさに「農村から都市へ働きかける」ことだった。
個人的に力を入れたのは「日本農書全集」だ。江戸時代、子孫に残すために書かれた全国各地の農業技術書。たった300年前のものなのだが、現代人にはこれが読めない。そこでこれらを現代語訳して誰でも読めるように編集したものが日本農書全集だ。間違いなく農業国家だった江戸時代の米や麦、野菜や特産物の栽培技術はもちろん、水利・土木技術、ほかに、農産加工、林業、漁業、そして『開発と保全』『災害と復興』などの巻もある。記述からは、生産と生活が一体となった常民の暮らしのありよう、心得、生き方、ものの見方全般が読み取れる第一級の歴史資料なのだが、いかんせん高価だ。全72巻40万円以上もする全集で、普及は断られることも多かったが、大学では農学部だけではなく、歴史学はもちろん、民俗学、生活史、文化人類学、食物史等々幅広い分野の人を訪ねた。農文協としても、赤字覚悟で四半世紀をかけて送り出した企画だったが、世の評価はきわめて高く、「この本は絶対必要」と入れてくれる図書館司書や先生にもたくさん出会えた。
日本農書全集は、今はルーラル電子図書館にも収録されており、会員になれば全国どこでも誰でも読める。農薬も化学肥料もなかった江戸時代に、農家はいかに自然の力を引き出しながら農業をやっていたのか。今注目の有機農業の書としても読める。本誌連載中の高内実さんの「今に活かせる、江戸農書の栽培技術」(p248)も、まさにそんな記事だ。農書を広めることが、先述の和歌山の組合長の願いと一致していたかはわからない。ただ一つ言えることは、農文協の出版物を普及することで、農業・農村のあり方を世に発信してきたつもりだ、ということだ。
イネの本が売れている
話は変わるが、昨年来イネ関連の本が売れている。基礎技術本『イネの生理と栽培』はもちろん、3万円超の『イネ大事典』も注文が増えていて、昨年の倍のペースで売れている。米不足の報道を受けて、農家の静かな増産意欲に火がついているのを、本の売れ行きを見て感じる。米価高騰も背景にはあるだろうが、主食の米が足りていないとなれば、「任せとけ」「一肌脱ぐか」とばかりに立ち上がった頼もしい農家が全国のあちこちにいるということだ。
米政策は、風雲急を告げている。意欲ある農家も参入したい若者もいるのに経営の見通しが立たず、それを許さないできた稲作の状況を、ここでどう変えていくのか。
日本の国土で農家がいつまでも自由に元気に創意工夫し、イネを野菜を果樹を花をつくり、家畜を飼い続けられるように。その一助になるような本を制作し、普及し続ける団体でありたいと強く思う。農文協の職員がお邪魔したときは、叱咤激励と共にご支援をお願いしたい。読者のみなさま、たたかいは続きます。一緒に日本の農業を守り、発展させていきましょう。
(農文協論説委員会)