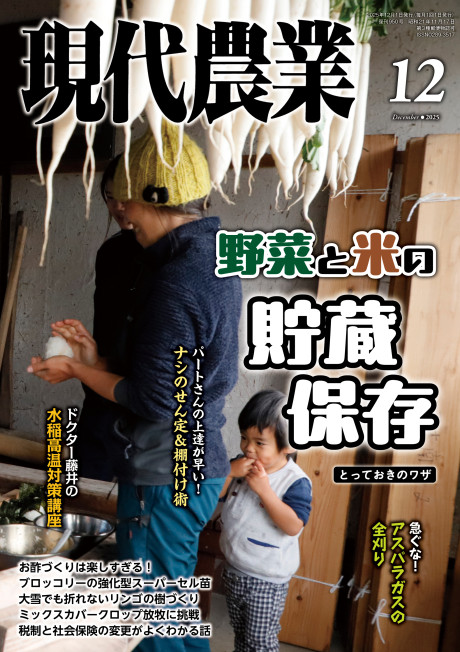主張
「お米と田んぼの誘引力」が小さい米づくり人口、お米関係人口を増やす
目次
◆3万円の概算金の陰で起きていること
◆田んぼの誘引力で「関係人口」を育てたい
◆「お米の学びなおし」で田んぼを守る
◆地域の困りごとに「自給家族」の力を借りる
◆米騒動の先に何を起こせるか
3万円の概算金の陰で起きていること
昨年夏に始まった「令和の米騒動」。米不足による店頭価格の高騰から政府の備蓄米放出へと続き、この秋にはJA概算金の大幅アップがマスコミで報道された。主力銘柄は軒並み3万円台となり、前年と比べて7~8割もアップしている。1俵3万円の概算金は、農家にとって喜ばしい半面、不安も大きいだろう。スーパーの店頭で5kg4000円を上まわる米ばかりになると輸入米が増える。消費者の米離れも心配だ。
JAがとれ秋に農家に支払う概算金は、その年の米価の基準となってきた。そこへ新たに参入した業者が、概算金に上乗せした金額を提示し、集荷競争がヒートアップ。それが結果的に今年の概算金を吊り上げたといわれている。逆に11年前の2014年は、米余りムードを背景に概算金が1万円を割るほど下落して農家を苦しめた。概算金が米価決定のベースになることには問題が多く、今後は260ページでJAグループ鳥取が掲げる「米の生産費払い」のような仕組みが必要だろう。米の需給見通しや相場動向よりも生産コストを基礎に支払い額を決める考え方だ。
また、農家にも消費者にも納得がいく米価であるためには、8月号の主張欄で取り上げた、直接支払いによって農家の所得を保障するような新制度が必要だろう。
ところで米騒動の陰では、新たに米づくりを始める人を増やしたり、米の産直を進化させるような動きが各地で起きている。本誌の増刊『季刊地域』ではこれを「お米と田んぼの誘引力」と呼んで、2025年秋号(63号)で特集した。それは必ずしも米騒動をきっかけに起きたわけではない。だが、中山間地域の米づくりや、農村と都市、生産者と消費者の関係に変革をもたらす動きであり、後から思い返せば令和の米騒動がその象徴となるかもしれない。
以下、『季刊地域』秋号の内容にふれながら、米騒動の次を考えてみたい。
田んぼの誘引力で「関係人口」を育てたい
柘植賢志さん(49歳)は今年、人生初の米づくりに挑戦した。島根県の中山間地・邑南町に暮らすいわゆる土地持ち非農家。ところが、田んぼ40aを預けていた方が昨年秋に亡くなり、息子さんから「もうできんけぇ」とその田んぼを返されることになった。
米づくりの経験も機械も道具もない柘植さんには、40aは途方もない広さに感じたとか。奥さんに相談すると、機械がないなら「まず牛を飼わなきゃってことね」と笑われた。だが、近所の人がトラクタや田植え機を貸してくれ、日焼けで真っ黒になって試行錯誤しているとアドバイスもくれた。それに「おおなんお米つくり隊」と称して、SNSで田植え体験の募集をすると、県内の松江市や広島市などから30人もの家族連れがやって来た。
これには、柘植さんを助けてくれた近所の農家も喜んだ。その人が言うには「米づくりは誰かが近くにいるだけでモチベーションが上がる」とか。一番たいへんな草刈りを手伝ってくれる仲間も現われ、柘植さんは田んぼの誘引力を実感する。そして「田んぼというフィールドを通じて田舎と都会をつなぎ、『関係人口』を育てていけたら」と書いている。
人生初の米づくりは急展開。柘植さんは、食料生産にとどまらない田んぼが持つ力、米農家の息子に生まれた自分の使命を見つけたかのようである。
「お米の学びなおし」で田んぼを守る
今年の春、「お米の学びなおし講習会」を始めたのは熊本県津奈木町。機械作業などを担い手に委託する兼業農家に、米づくりに戻ってきてもらおうという試みだ。
津奈木町も中山間地。狭い田んぼがたくさんある。兼業農家からそんな田んぼの機械作業を請け負ってきたのが(株)アグリ津奈木の代表・坂口信行さん。学びなおし講習会の発起人だ。年々進む高齢化とともに、アグリ津奈木に作業委託される田んぼが増えたが、もう「パンク状態」。法人だけでは地域の水田を守ることはできない。坂口さんが町と相談し、自分の田んぼで自分で米づくりをする農家を増やそうと始まったのがこの講習会である。
受講者は勤め人が多いので、日曜日の午前中に開催する。編集部が7月に取材した3回目の講習会は、除草剤の使い方と獣害対策の電気柵の設置法がテーマだった。講師役は、坂口さんのほか熊本県の農業改良普及員が務める。受講者は24人で、米づくり未経験の人もいれば、家族と一緒に見よう見まねで作業するだけだったという人もいた。座学も実習も真剣な面持ちで聞く姿が印象的だった。
津奈木町の講習会の人気ぶりは近隣市町村にも伝わり、来年はうちでもやりたいという相談が県にいくつも寄せられているそうだ。
近年、農家が急速に減っているのは本誌の読者も感じていることだろう。なかでも稲作農家は、2005年には140万戸あったのが20年には69万9000戸とわずか15年で半減した。まもなく公表される25年の農業センサスでは50万戸をキープできているだろうか。
米不足を受け、25年の主食用米の作付けは前年より8・6%、10万8000ha増えている。その代わり、飼料用米やWCS用イネ、ダイズ、ムギなどが減った。令和の米騒動が明らかにしたのは、長く続いた低米価のもと、ギリギリのところで踏ん張ってきた稲作農家が、転作作物と組み合わせてなんとか米の自給を維持してきた実態だ。米が足りないといっても、すぐに田んぼが増やせるわけではない。食料自給率向上につながる飼料用の米やイネ、豆腐や味噌、納豆に使われる国産大豆、最近はうどん類だけでなくパン用にも定着した国産小麦が、主食用米増産の引き換えになっている。
いくら担い手がスマート農業で規模拡大を頑張っても、カバーできるのは平場の条件のよいところだろう。柘植さんのような農家が現われていること、学びなおし講習会のような試みが始まっていることが、中山間の田んぼを守る力になりそうな気がする。
2月号の主張欄で紹介した愛知県豊田市敷島地区の「自給家族」にも今年変化があった。自給家族とは米産直の仕組みで、お米を通じて生産者と消費者が疑似家族になること。消費者は米づくりにかかる費用を米代金として前払いし、自給の喜びもリスクも生産者と分かち合う。19年に敷島地区の一部・押井町で始まり、24年には農村RMOしきしまの家運営協議会が事務局となって敷島全体に広がった。
24年は高齢者を中心に18人の農家で約100家族分150俵の自給家族米を増やしたが、今年は新規就農の若手3人を中心に130家族分200俵をさらに生産。これで合計契約数は330家族分520俵にも増えた。
米騒動の影響もあり、新規の130家族の枠は募集開始からわずか5カ月で埋まってしまった。しかも契約価格を見直して、前年までより30%高い、1俵3万9000円に値上げしたにもかかわらず、だ。この仕組みを考えたしきしまの家運営協議会事務局長の鈴木辰吉さんによると、自給家族メンバーにはオンラインで「家族会議」を開いて納得してもらったそうだ。
今年は、この「家族」のあり方を考え直す出来事がもう一つあった。補助金で獣害対策の柵を設けることができたのはいいが、行政の設置確認の日までに作業が間に合わない――。頭を抱えて自給家族に声をかけると、なんと5日間でのべ50人もの人が駆け付けてくれたのだ。真冬の手がかじかむ季節に、重い柵を運んだり杭を打ったりを無報酬でやってくれる人がこんなにいるとは! 「自給家族だから当然。こういう機会を待っていた」という参加者もいて、鈴木さんは感激したそうだ。
これまでも「家族」を招いての交流イベントは開いてきた。しかし、農作業など機械を使う日頃の仕事は危険だからと、希望者がいても断っていた。その考えが、この一件で変わったという。斜面の多いアゼ草刈り、放置竹林の整備など、自分たちが困っていることを助けてもらおう、と。そして、その作業を米代金に充てられるポイント制にして参加者に還元する。本格開始は来年からだが、9月と10月に自給家族向け草刈り講習会を開いた。
米騒動の先に何を起こせるか
昨年は、食料・農業・農村基本法が25年ぶりに改正された。それに基づく食料・農業・農村基本計画が今年4月から始動している。この基本計画では、農村振興のためには農業の担い手以外に多様な人材を呼び込むことが必要だと書かれてはいるものの、農業のほうは相変わらずの担い手主義。農地の7割を担い手に集積する目標が新たに設定された。
農水省は市町村が「地域計画」を立てる際にも、経営規模の大小を問わず「農業を担う者」ごとに利用する農地を地図に定める、と言っている。「農業を担う者」には小規模の家族農業や半農半Xなども含むという。だが、今でもすでに6割ある集積率をさらに引き上げれば農家はいっそう減るだろう。小さい農業や多様な人材を位置づけることと7割集積の目標がちぐはぐに思えてならない。農村は農業だけでなく人々が暮らしを営む場。いったいどんな農村の姿を思い描いているのだろうか。
現状でも市町村は、地域計画の目標地図が耕作者で埋まらない事態に直面している。それは、少数の担い手だけでは農地を維持できない、農家が足りないことを表わしているのではないだろうか。現場の市町村はそれを肌で感じているからこそ、「お米の学びなおし講習会」をうちでも開きたいと思うのだろう。
今回の米騒動が、米の値上がりだけクローズアップされて終わるのは残念だ。前回の米騒動といえば、1993年の「平成5年の大冷害」による米不足が思い出される。翌年、奮起した農家は「1俵増収」に励み、米不足を機に農家とつながる消費者が増えて、米の産直が盛んになった。農産物の直売所も全国に広がった。
では、令和の米騒動の先は? 小さい米づくりを始める人や、米を農家から買うだけでなく田んぼへ出かける「お米関係人口」が増えて、農村と都市が互いに支え合う関係づくりが進むことを期待したい。
(農文協論説委員会)