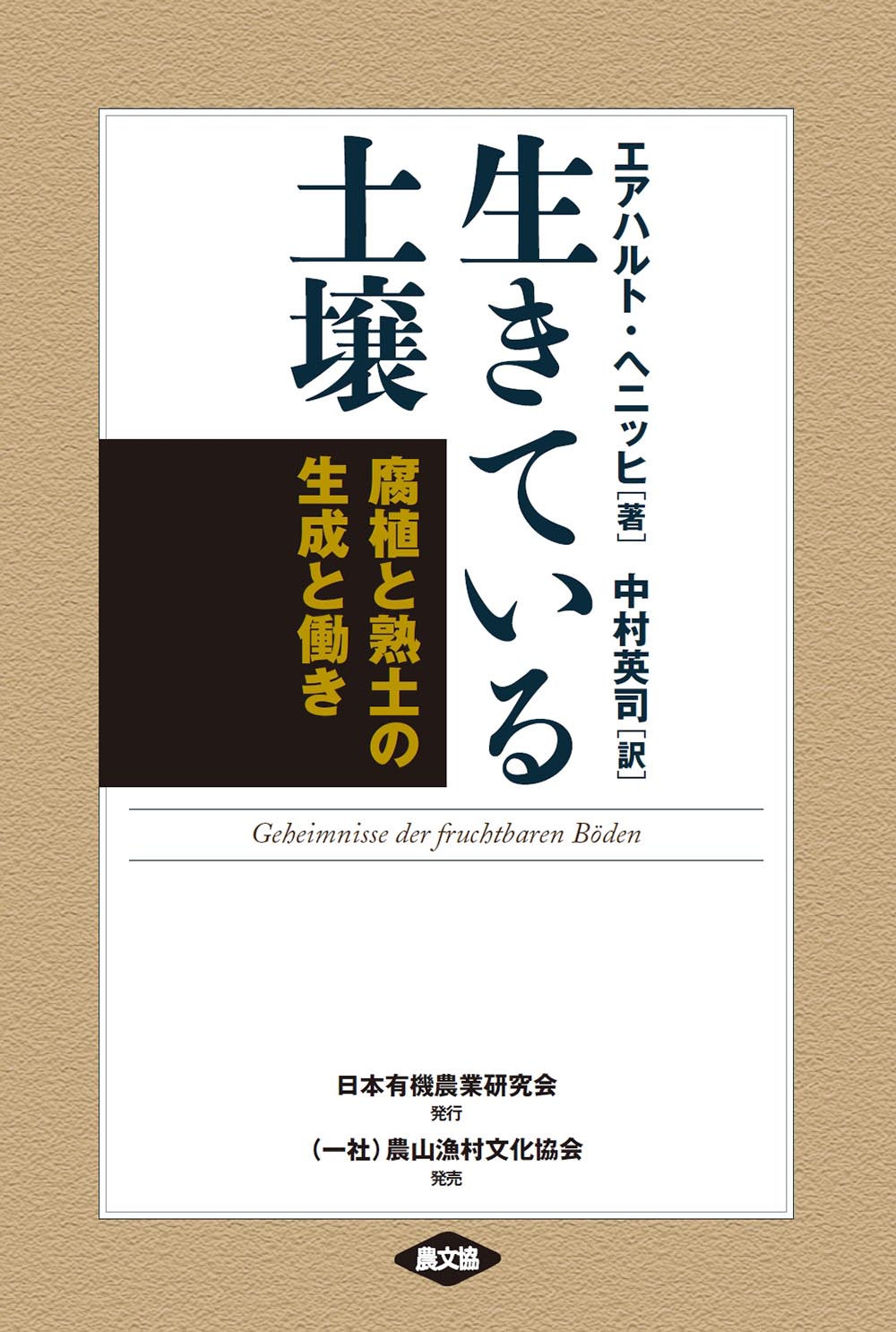主張
「地力アップ」で異常気象に負けない、肥料を減らす
『地力アップ大事典』の科学的知見が今、頼りになる
目次
◆堆肥とは違う、緑肥の「地力アップ効果」に注目
◆堆肥と肥料を一緒に施用できる地力アップ型肥料
◆古くて新しいバイオスティミュラント
◆世界的にも注目される「土ごと発酵方式」
『地力アップ大事典』(農文協刊)が完成した。およそ1200ページ、国・県の土壌肥料研究者を中心に執筆陣約150名に及ぶ大作だ。
サブタイトルは「有機物資源の活用で土づくり」だが、あえて「地力アップ」を前面に掲げたのは、土壌の総合的な力=地力を高めることが、従来にも増して経営、地域、そして地球規模の気候変動を抑えるうえで、たいへん大事になってきたからである。
大雨やゲリラ豪雨、猛暑や干ばつなどの気候変動に強い生育を実現し、あわせて化学肥料を減らす。これを可能とする地力アップが、経営を守る要になってきた。
そこには地域の力も求められる。かつての自給的な有機物利用の時代と違い、今では家畜糞尿は偏在し、地域を見渡せば林業やキノコ業、食品加工業、水産業などから出てくる有機廃棄物や竹などの未利用資源がいろいろある。これらを地域の力で、新たな技術もいかして有効に活用できれば、地力アップとともに地域力のアップにもつながる。
そして、地力アップのための有機物活用は「炭素貯留」を高め、大気中の炭酸ガスを減らし、地球温暖化の抑制に貢献する。この大事典掲載記事の一つ〈地球温暖化と土壌炭素循環メカニズムの変化〉(以下、執筆者割愛)では、こう指摘している。
現代の土壌中の炭素総量は地球全体で1兆5000億t。これは大気中の2倍、陸上植生の3倍にもなる。土壌炭素は地球環境の変化と関係する最も重要な炭素貯蔵庫だが、先史時代から現在までに土壌有機物の減少で放出された炭素量は5000憶tと見込まれている。温暖化防止から見ても、農地の土壌有機物含量の維持増進は重要であり、「持続的な農業生産のための適切な施用」によってこれを進める必要がある、という内容だ。
有機物の適切な利用は簡単な話ではない。有機物の種類や施用法によって微生物による分解の仕方や団粒形成などの効果が違い、土質や気候などの地域条件によっても変わってくる。通気性の悪い土壌に分解しやすい有機物を多量施用すると腐敗して根を傷めるし、有機物の肥料分によって肥料バランスが崩れることもある。有機物の入手や利用にあまりお金や手間をかけられないという、経営的な事情もある。
そんな有機物利用の課題や疑問に応え、異常気象に負けない排水性・通気性と保水力を備え、さらに安心して化学肥料を減らせる土をつくる。これに向けてこの間、試験研究も進展し、市販有機物資材の開発も進んでいる。
その集大成として『地力アップ大事典』が出来上がった。「みどり戦略」が掲げた化学肥料使用量3割減や有機農業の大幅拡大を現場で進めるための実践書としても、役立てていただけると思う。
堆肥とは違う、緑肥の「地力アップ効果」に注目
この事典の一番の特徴は、地域の有機物資源から市販有機質肥料まで、その特性と利用法を網羅したことである。素材の組成や肥料成分、施用効果や利用上の留意点などを素材ごとに知ることができる。
「生きた有機物」である緑肥にも力を入れた。利用方法にゆとりが生まれた農地が増えるなか、堆肥利用に比べて手間や経費がかからない緑肥への関心が高まっているからだ。〈緑肥作物の土つくり・減肥効果〉の記事では、ソルガム、エンバク、マメ科のヘアリーベッチなどを素材に、地力アップ効果がかなり大きいことを実証的に示した。その要点を列記すると以下のようだ。
まずは土壌有機物の蓄積効果。これが意外に大きい。育ったソルガムをすき込み、1年後に調べた結果では、牛糞堆肥反当1.4tと同程度の蓄積効果が期待できた。
土壌団粒の促進効果も高い。緑肥は新鮮な有機物。各種緑肥をすき込んだ圃場では土壌微生物の活性が高まり、2mm以上の大きな耐水性団粒の割合が多くなった。
堆肥や機械では難しい下層土改良の効果が高いのも、根が深く張る緑肥の特徴だ。エンバクの緑肥では、耕盤と呼ばれる深さ15〜30cmの硬い層の緻密度が低くなり、その下の層も隙間が増え、土壌構造が発達。そこに育てたコマツナの根は耕盤層を越えて深くまで伸びていた。ヘアリーベッチを導入したネギ畑では、降雨後のウネ間の水のたまり具合が、緑肥なしとは明らかに違っていた。この様子はカラー口絵のページでも紹介。団粒、土壌構造の発達で土壌の保水性も高まり、根も深く伸び、長雨にも乾燥害にも強くなる。
減肥効果も期待できる。根が深く張る緑肥は、雨で下層に流亡したチッソ(硝酸態チッソ)やカリ、リン酸などを吸い上げる。マメ科緑肥では、これに加えて根粒菌が空中チッソを取り込む。緑肥の根は有機酸やホスファターゼと呼ばれる土壌酵素を分泌し難溶性のリンを溶かして吸収。アブラナ科以外の緑肥には菌根菌が共生して、リンの溶解・吸収を強める。さらに、緑肥のすき込みでリン溶解菌やカリ溶解菌も増える。結果として、リン酸肥沃度が低い圃場であっても、緑肥の種類を選べば10a当たり4kg程度のリン酸を供給できるという。これは、多くの作物のリン酸の吸収量に匹敵する。
減肥実証試験結果の紹介記事では、キャベツ・レタスでのソルガム、レタスでのエンバク、レタスでの越冬ライムギ、各種作物でのヘアリーベッチ、キャベツでのクロタラリア、タマネギでの緑肥の混播などがあり、おおむね3〜5割の減肥が可能としているが、条件によっても変わる。緑肥の種類選択や、すき込む時期など、効果的な方法を検討するヒントにもなる。
緑肥にはほかに、センチュウ害や土壌病害、雑草害の抑制、風食水食など土壌侵食の防止、さらには景観の美化までいろんな効果がある。緑肥をどう活用するか、地力アップに向けおおいに工夫したい。
堆肥と肥料を一緒に施用できる地力アップ型肥料
家畜糞堆肥を連用している畑の養分バランスを、緑肥を組み入れて整えることもできる。有機物利用では組み合わせが大事だ。ワラなど炭素が多い(C/N比が高い)素材と、チッソの多い家畜糞尿を混ぜて発酵させるのが、堆肥つくりの基本になってきた。地域の有機物をいかすには、素材の肥料成分やC/N比などの特性をつかみ、他の素材と上手に組み合わることがポイントになる。
事典では、各種素材の特性と利用法に加え、生ゴミ+牛糞+せん定クズ、鶏糞+焼酎廃液といった組み合わせや「堆肥融合技術」のコーナーを設けた。
注目なのは、堆肥と化学肥料を組み合わせる「混合堆肥複合肥料」である。背景には、肥料散布機での散布が可能な堆肥ペレット(造粒)化技術の進展があり、この事典でも〈堆肥の成型化(ペレット化)と使い方〉〈食品残渣のペレット肥料化と利用〉などの記事を掲載した。
この堆肥ペレット化の技術を生かし、化学肥料を混合したのが「混合堆肥複合肥料」である。〈混合堆肥複合肥料の製造と利用〉によると、国内の生産実績は2013年度の233tから17年度には6392tに大幅拡大。20年10月現在、85銘柄が普通肥料登録されている。
この混合堆肥複合肥料には輸送や利用のしやすさに加え、以下のような利点がある。
堆肥と肥料を別々に施用する従来のやり方のほうが、堆肥施用量自体は多いので有機物供給効果は高い。しかし堆肥由来の成分量が過剰施用となる場合が多く、土壌養分バランスの不均衡を生じやすい。これに対して混合堆肥複合肥料は各肥料成分を明記・保証しており、施用成分量を正確に把握できるので、このような危険性は小さい。また、有機化成肥料や有機配合肥料と比べた場合には、炭素残存量が多く、有機物供給効果が高いことが確認されている。
化学肥料の効果の面にも違いが出てくる。有機物(堆肥)と混合された後に造粒されるため、施用後、土壌でのアンモニアから硝酸への変化がゆっくりになり、おかげで降雨による硝酸態チッソの流亡が減少。チッソの利用率が向上し、チッソ流亡にともなう塩基の溶脱と土壌pHの変動も抑制される。
リン酸も効きやすくなる。造粒することで堆肥由来のリン酸成分と土壌との接触が減り、土壌によるリン酸固定が抑制されるからだ。
そして2020年12月の肥料制度見直しで、新たな動きが起きた。それまでは、この混合堆肥複合肥料に使える堆肥はC/N比15以下、量は全体の50%以下など、厳しい条件があったのだが、新しい「指定混合肥料」として、普通の堆肥と化学肥料を混合することが可能となった。これにより、国内で最も流通量の多い牛糞堆肥が「混合肥料」に使えるようになったことが画期的だ。
新しい「混合肥料」が広く流通するのはこれからだが、注目は集まっている。従来の混合堆肥複合肥料ともども、有機物による土壌改良効果と減肥効果の両方を期待できる地力アップ型肥料といえよう。これらだけで必要な有機物をまかなうことは難しいだろうが、飼料自給の強化ともに日本の畜産の課題である糞尿の効果的な活用に向け、地域資源活用肥料として生かしたい。
古くて新しいバイオスティミュラント
事典には、「バイオスティミュラント」という最近話題の技術研究も収録した。〈バイオスティミュラントの定義とその意義〉によると、直訳は「生物刺激材」。「植物の健全さ、ストレスへの耐性、収量と品質、収穫後の状態および貯蔵などについて、植物に良好な影響を与えるもの」であり、「農薬でも、肥料でも、土壌改良材でもない新しい農業資材」である。ただし、生産現場では古くから使われてきた資材も少なくなく、「古くからある資材を新たな枠組みに定義づけた農業資材」でもある。カラー口絵で、その効果例を紹介した。
たとえばボカシ肥に発根促進作用があることは、経験的に知られてきた。このボカシ肥には乳酸菌の代謝物・フェニル乳酸が含まれており、これを資材化してアズキに施用すると不定根の発根が促進された。また、大豆粕由来のペプチドを与えたコマツナの根毛は明らかに増加。さらに、『現代農業』でも特集した話だが、酢の主成分である酢酸は傷害応答ホルモンのジャスモン酸の合成を促進し、作物を乾燥・高温に強くする。さらに、ビール醸造の副産物から得られる「ビール酵母細胞壁」には、病害抵抗性誘導や発根促進効果がある。
これらのほか、〈トレハロースによるピーマン、ナスの低温・高温耐性効果〉〈高機能液肥の組合わせ散布〉〈タケニグサ抽出物による耐暑性向上効果〉〈タンパク質に着目した植物の温度ストレス緩和技術〉〈葉の香りによる作物の高温耐性の向上〉〈微量要素による作物の免疫力向上効果〉などを掲載。
これらは、1月号「農家の菌活」で紹介した各種微生物の働きや、「菌は死んでも役に立つ」理由に新たな光を当て、農家の身近な有機物利用のヒントにもなりそうだ。
そのほか、地力チッソや土の肥沃度の新しい測り方、土壌微生物の多様性・活性診断技術なども収録。いずれも「地力アップ大事典」ならではの項目といえる。
世界的にも注目される「土ごと発酵方式」
最後に、耕し方も関係する「有機物の施用法」について触れたい。
「不耕起と有機物表面施用による土壌改善」のコーナーに、〈不耕起土壌の孔隙構造とその機能〉〈長期不耕起直播水田の土壌の特徴と生産性〉〈不耕起畑・水田とコムギ・イネ根圏の微生物フロラと酵素活性〉〈冬作カバークロップによる土壌の物理性とリン酸供給の改善〉を収録。先に緑肥の根による土壌構造の改善について触れたが、ここでは根がつくる根穴構造に注目し、これを生かす不耕起や有機物マルチをめぐる研究成果を紹介した。
また、「『現代農業』セレクト技術」として以下の六つの農家事例も収録。有機物マルチや、通気性よい土壌の表層で有機物を分解させる「土ごと発酵方式」は、『現代農業』がずっと注目してきた技術だ。
有機物マルチや土ごと発酵は利用する有機物も使い方も自由度が高く、多様な工夫にあふれている。これをめぐり、もう一冊、ぜひご覧いただきたい本がある。
エアハルト・ヘニッヒ著『生きている土壌』(中村英司訳、日本有機農業研究会発行・農文協発売)。ヘニッヒはドイツの有機農業の技術の体系化と農家の組織化に尽力し、1994年に本書(原題「豊かな土壌の秘密」)を書き上げた。原著ドイツ語版も英訳版も版を重ね、待望の日本語版が2009年に出版され、このたび新装版が発行になった。
この本でヘニッヒが勧める土つくりは、有機物マルチ方式であり、土ごと発酵方式なのある。家畜の厩肥をプラウですき込むのがヨーロッパの土つくりの常識と思い込まされていたが、どうもそうでないらしい。
ヘニッヒは「新鮮な厩肥は土の表面でコンポスト化(堆肥化)するのが一番よい」とし、「少量ずつ、表土でコンポスト化することは、慣行農業から有機農業に転換する手はじめとなる」とさえ述べている。さらに「有機物で地表をマルチすることは、熟土形成を最適な状態にしてくれるだろう」として、「有機物や植物による地表のマルチは、農耕の諸問題の多くを解決してくれる」と強調している。
本書『生きている土壌』の副題は「腐植と熟土の生成と働き」。ヘニッヒは、この「熟土」に「細胞熟土」と「プラズマ熟土」の二つがあるという。簡単にいうと、「細胞熟土」とは、未分解有機物をエサに土壌動物・微生物が活発に活動している土壌(分解層)。これに対し、有機物が分解してできた腐植物質と粘土とが結合し、腐植粘土複合体が形成され、団粒構造が発達した土(合成層)が「プラズマ熟土」である。合成層では根圏微生物が活性化し、リンを可溶化、根の生長に役立つ活性物質やビタミン、アミノ酸などの養分を生成する。チッソ固定菌の活動も活発になる。
有機物マルチや土ごと発酵は、ヘニッヒ流にいえば、分解層の活性化によって豊かな合成層を形成する方法ということになる。
*
有機物による土づくりは多様で、そこには農家の経験と観察眼が生かされる。それを土台に科学的知見も生かして地力アップを豊かに進めたい。
(農文協論説委員会)