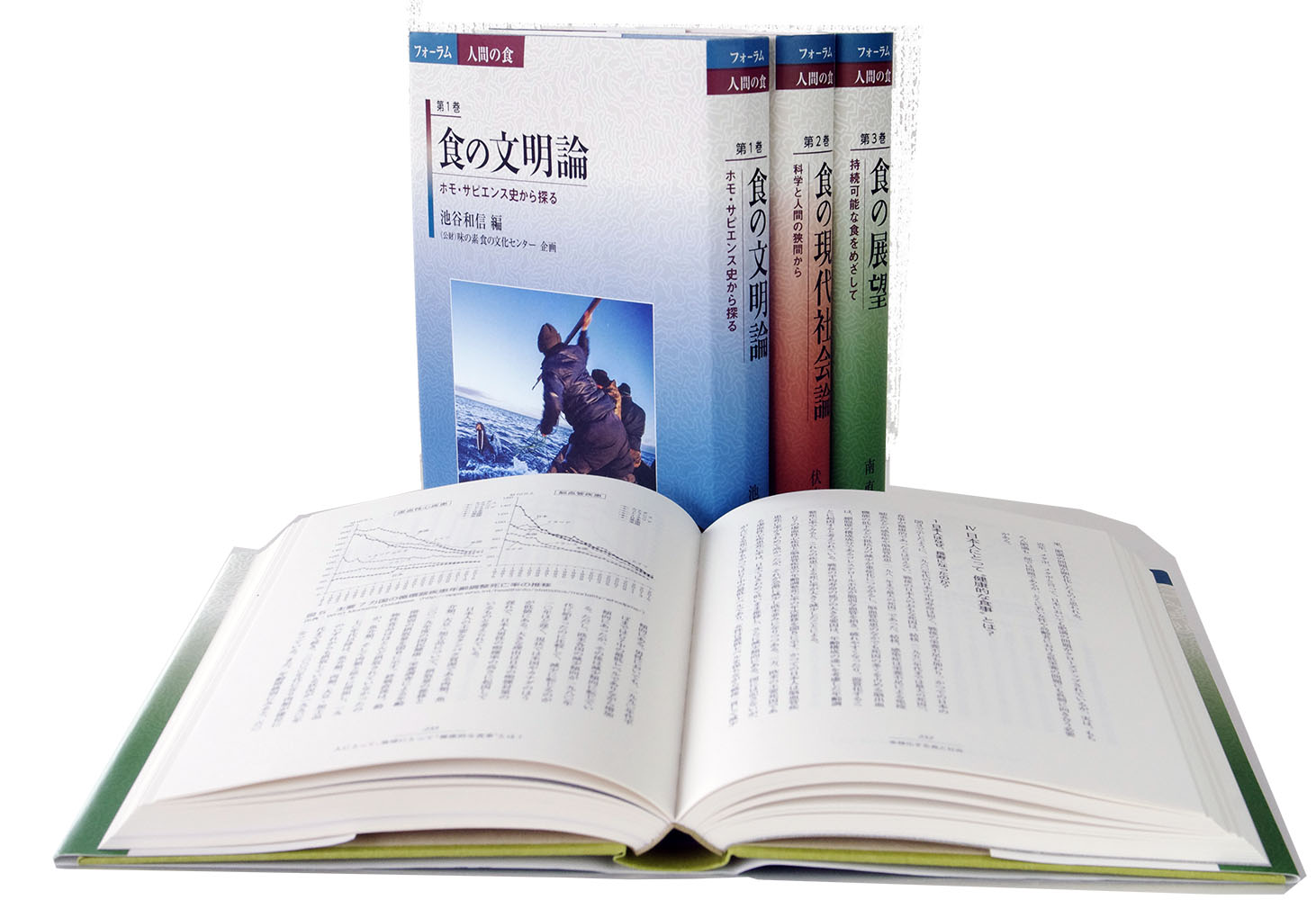主張
農家の料理をどんどん広めよう
人類の持続が危うい時代にこそ
目次
◆くじら汁の記憶
◆似ているようで違うから面白い
◆食を伝えて農を守る
◆人類の未来は食から見える「フォーラム 人間の食」
◆日々の営みにこそ価値がある
くじら汁の記憶
日本海側の東北から北陸にかけての読者には懐かしいだろう夏の味噌汁に「くじら汁」がある。新潟では塩くじら(塩漬けにしたくじらの脂皮)とユウガオ、ナスがよく入る。夏のスタミナ源として県全域で食べられ、土用にくじら汁を食べると、眉に脂がにじみ出て農作業のときに汗が目に入らないと言い伝えられてきた。そんな農家の肌感覚とともに伝わる味だ。
これは2021年に完結した「全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理」全16巻の中の『汁もの』に掲載されている。(一社)日本調理科学会の企画編集によるこの全集では、昭和35〜45年頃に地域に定着していた家庭料理をすべての都道府県で聞き書き調査し、レシピと共に記録した。その数約1400品。昨年からは、ルーラル電子図書館でも閲覧できるようになった。
似ているようで違うから面白い
今年、このルーラル電子図書館の「伝え継ぐ 日本の家庭料理」コーナーに「WEB限定」の料理が追加されている。6月までに約180品。続いて7月に約200品、秋にももう一度追加がされて、最終的に約1900品のデータベースとなる。紙の本では、ページ数と値段の制約があり、調査した料理のすべてを掲載することができなかったのだが、その分をネットで補う形だ。
WEB限定で追加された料理の中に、新潟の隣、山形の「くじら汁」がある。新潟と同様に夏バテ防止の味噌汁で、こちらはジャガイモやナスが入る。県中央部の村山盆地に位置する大江町では、夏休み中の子ども会でいるか汁(くじら汁)をつくったのが、秋の芋煮会と並ぶ思い出だという。さらに、福島のくじら汁も追加された。ジャガイモとタマネギが必ず入り、県内では会津地方だけに伝わる。昭和40年代初め頃まで、縄で縛られた塩まみれのくじらを新潟から行商が売りに来ていたという。
じつは、ルーラル電子図書館の「伝え継ぐ 日本の家庭料理」で「くじら」を検索すると、佐賀、長崎、山口、島根、大阪、和歌山といった西日本の料理が多く出てくる。だが、夏に塩くじらの味噌汁を食べるのは東日本の日本海側に多いらしいことがわかる。新潟の記事によると北前船によって西日本の捕鯨地から伝わり、江戸末期から明治期には庶民に普及したという。北海道のにしんが東北から西日本にまで広がったのとちょうど逆方向の物の流れが想像できる。塩くじらも身欠きにしんも貴重な保存食で、海から遠い内陸部で重宝された。全国規模で流通する食材がそれぞれの地域の産物と出会い、その土地ならではの味となり地域の思い出と結びつく。好きな言葉で検索できることで、紙の本とはまた違った角度から、日本の、そしてわが町の食文化や歴史が見えてくるのが面白い。
食を伝えて農を守る
ルーラル電子図書館では、大正末〜昭和初期の暮らしを聞き書きした「日本の食生活全集」全50巻も閲覧できる。「伝え継ぐ 日本の家庭料理」との横断検索もでき、「くじら」で400件以上の記事が見つかる。全国の広がりだけでなく、戦前と戦後の変化も見えてきて、興味は尽きない。
「日本の食生活全集」は1984年から1993年にかけての発行。今から30〜40年前のことで、光栄なことに、日本の食文化を記録した第一級の資料という評価を得ることができた。しかしそもそもの刊行の目的は、輸入自由化と日本人の食生活の変化、そして農村で進む自給的循環型の農業から大規模化・多投入の選択的拡大路線への変化に対する異議申し立てだった。暮らしは地域の風土と産物に根ざしたものでありたいという願いを、農業だけの問題としてではなく、食という誰もが避けて通れない日々の営みを通じて訴える。そのために農文協は本を出版し、全国民への宣伝販売に努めた。
この取り組みは一過性で終わるものではない。刊行時の読者の次やその次の世代が、いまや子育てや仕事・研究の中心を担う時代になっている。若い世代の情報源は紙の本よりネットやSNSだ。伝えたい暮らしの根っこの部分は変わらないが、時代に応じて聞き書き中心からレシピ化に比重を移したり、データベースとしてさまざまな関心から読めるようにしたり、電子書籍で読めるようにもした(*)。「不易流行」の精神で、変わらずに伝えたいものを、伝え方を変えながら提供し続けていきたいと考えるからだ。
*「全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理」の電子書籍版はアマゾン等のネット書店で配信中。「日本の食生活全集」の電子書籍版は現在のところ大学図書館・公共図書館などへの配信のみだが、モノクロだった写真がカラー化された。
人類の未来は食から見える「フォーラム 人間の食」
農文協が農家の暮らしと食べ方をしつこく普及するのは、今、農家への期待が高まっているからでもある。
この4月に3年がかりで「フォーラム 人間の食」全3巻が完結した。これは(公財)味の素食の文化センターが主催する食の文化フォーラム40周年を記念した出版で、第一線の食文化研究者が3年にわたって共通のテーマの下に多角的な議論を行ない、新たに書き下ろした論集だ。日本の食文化研究の道を切り拓き牽引してきた学際的活動の到達点と、これからの出発点を示す作品になっている。
そして、1巻約450ページの大部な3巻を読むと、これはやや身びいきかもしれないが、あちこちで「そうそう、だからこれからは農家の出番だ」と思えるのだ。
例えば第1巻『食の文明論』の第6章「調理と料理」(江原絢子・東京家政学院大学名誉教授)では、明治初期の文献『斐太後風土記』で岐阜県飛騨の農山村におけるトチやナラ、カタクリやイノシシやクマやアユなど、狩猟採集によって得られた資源を食べられるように加工する知恵や技術を〝始原的調理〞と呼んで生きる力の源泉を見ている。そして結論近くでこんなことを述べている。
「われわれは、便利な道具や調理済食品などをこれからも利用するであろう。しかし、どれだけ便利になっても、自分の時間と身体と心を使って『調理』する能力を獲得しなければ、生きる力や喜びや自信にはつながらず、社会が提供する便利な道具などを主体的に選択する能力がないまま逆に使われる立場に置かれるのではないかという気がする」。まったく同感で、身近な野山の自然を生かした農産加工は、人間が生きるための〝始原的調理〞を今に伝えるものだと思う。だから、手づくり加工品を披露する農家は皆、自慢げなドヤ顔を見せてくれるのだろう。
また、最近はやりの菜食主義「ヴィーガン」は肉食を動物虐待だと糾弾するのが現代的だが、第2巻『食の現代社会論』第8章「食の倫理とヴィーガンの問いかけ」(北山晴一・立教大学名誉教授)はそれを痛烈に批判する。「そもそも、動物だからダメ、植物ならよいという区分自体が、私たち人間が勝手に立てた基準、人間のイデア(観念)でしかないことは明白であろう。私たち人間は、動物であれ植物であれ、他の生き物の命を取ることによってしか生命をつないでいくことができないこと、さらにいえば、ヴィーガンであろうとなかろうと、私たち人間はみな、生きている限り、この生と死の連鎖(中略)から逃れることなどできないことを思い起こすべきであろう」。人間もいのちの循環の一部であり、無機物も含めたさらに大きな循環の中でいのちが生まれ、朽ちて、次のいのちの形につながっていくことを、実感として知っているのは農家に違いない。ヴィーガンの問題提起を超えて、培養肉のような「いのちのない肉」に人類の未来を託すのではない道は、やはり農山漁村から発信するべきだと強く思う。
日々の営みにこそ価値がある
さらに、第3巻『食の展望』のカラー企画「未来のあるべき食の姿」(南直人・立命館大学教授)では、世界の人口が18世紀の産業革命を境に爆発的に増加し、当時の約7億人があっという間に80億人に達したことが示される。それを支えた食料生産の代償として世界の砂漠化、環境悪化が進み、生物種の絶滅速度とチッソ・リンの循環の破綻はすでに地球の限界を超えてしまっている。それでも、有機農業や市民農園などで持続可能な食の生産を広げ、在来作物や伝統食を保護・継承・育成する方向に希望を見る。最後は「一人ひとりの食行動が未来をつくる」と、食を通すことで人類の課題が自分事になることを示す。
◇
こんな時代だからこそ、農家の日々の営みそのものへの関心が高まるのだろう。本誌のきょうだい誌で非農家の読者も多い季刊『うかたま』の記事では、このところ農家が農家らしく暮らしている様子が好評だ。旬の野菜をシンプルに食べるレシピや、季節の手づくり加工品などに自然や作物と生きる農家の知恵や技術を感じ、それを知りたいという人が増えている。9月には30人近い農家の発想や工夫がぎっしり詰まった『別冊うかたま 農家に聞いたいちばんおいしい野菜のレシピ 秋から冬』も発行される。
農文協はこれからも、農家が農家らしい食のあり方を受け継ぎ、農家らしい方法で時代に合わせて行く姿をさまざまな方法で伝え続けたいと考えている。
(農文協論説委員会)
- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。
 現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
【主張】農家の料理をどんどん広めよう 人類の持続が危うい時代にこそ【現代農業VOICE】