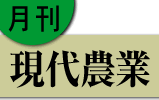 |
|
|
||||||||||||||
|
|
筆者と種子選別機(左:1号機、右:2号機)(写真提供:農研機構北海道農業研究センター。以下*も) 3Dプリンタで念願のキャベツ種子選別機が実現!
北海道・高橋光男
種子の直径1㎜以下の違いで生育差
北海道芽室町で畑作農家を営んでいます。小麦やビートのほかに、キャベツやナガイモ、ニンジン、ブロッコリーなどの野菜を栽培しています。中でもキャベツの栽培は30年以上になります。20年くらい前にセル成型苗や野菜移植機を導入し、さらに農機メーカーや試験場とキャベツ収穫機の開発にも取り組みました。収穫機は3年前に実用化され、現在は機械収穫で約5ha、主に加工業務用に出荷しています。
キャベツは一つ一つの生育にばらつきがあります。手どり収穫では何回かに分けて収穫できますが、機械収穫では、生育の遅いものも一度に収穫しなければならず、どうしてもロスが出ます。生育のばらつきを抑えることが必要だと考えていました。
種子選別による苗の生育の違い。大きい種子のほうが生育旺盛(*) 15年前、試験場との栽培試験で、コーティング種子のサイズによっても発芽や初期生育がばらつく可能性があるとわかりました。コーティング種子は直径3~4㎜程度ですが、そのわずかな差を揃えることで、生育を均一にできるのではと考えました。そこで、市販のふるい網を購入して試しましたが、使っているうちに網目がゆがんで、1㎜以下の違いは選別できませんでした。専用の選別機もありましたが非常に高価ですし、自分で作るにも専用の機械や熟練した技術が必要で、なかなか実現できずにいました。
1号機はほとんどの部品が3Dプリンタ製 3Dプリンタで1号機を製作
2年前、3Dプリンタの存在を知りました。パソコンで設計したデータどおりに精度の高いものづくりができるということで、これなら念願の選別機が製作できるのではと考えました。そこで、試験場と協力して3Dプリンタによる選別機の製作に挑戦しました。
最初に製作した1号機は、種子が切れ目のついたレールの上を転がって、切れ目の幅より小さい種子は途中で下に落ち、一番下に大きい種子だけが集まるという簡単な仕組みです。
切れ目のついたレールや種子を送り出すロール部分の複雑な形状の部品など、1号機はほとんどを3Dプリンタで作りました。その他、モーターやモーターを制御するマイコンボードも利用しましたが、3Dプリンタの樹脂代とあわせても約1万円でできました。
実際に選別機で小さい種子と大きい種子を選別して育苗してみると、大きい種子は育苗時も移植後も生育旺盛で、明らかな違いが出ました。
2号機も微調整が必要な部品(○部分)を3Dプリンタで作った 種子選別機の動く様子が、ルーラル電子図書館でご覧になれます。
詰まりを改善した2号機も完成
1号機は詰まりさえなければ、5000粒を7~8分で選別できます。しかし、たまに選別レールの切れ目に種子が詰まることがあり、選別中はずっと見ていなければなりませんでした。そこで翌シーズンに、2号機を製作しました。
2号機では、詰まりを防ぐため、2本の回転軸の間を種子が転がる仕組みの選別レールに変更しました。回転軸は3Dプリンタで精度よく作るのが難しかったので、金属製の軸をネットで入手して使用しました。ただし、組み立て時に回転軸を等間隔に並べる必要がありました。そこで3Dプリンタを利用し、適当な治具やベアリングホルダを作ることで、0・1㎜以下の誤差で組み立てられました。2号機は詰まりもなくなり、さらにラクに選別できるようになりました。来年はブロッコリーでも挑戦したいと考えています。
身近になってきた3Dプリンタ
樹脂(フィラメント)を層状に積み重ねながら、立体物を造形できる3Dプリンタ。立体物の設計はパソコンを利用して行なう。
積層の仕組みや使用できる樹脂の種類によって価格もさまざまだが、数万円で買える安価な3Dプリンタも登場し、より身近になってきている。今回の事例で使用された3Dプリンタは、プラスチック製の樹脂を使用するもので、最小積層ピッチは0.1㎜と精度の高いプリントが可能。
今回使用された3Dプリンタ Replicator2X(MakerBot社)(*) (北海道芽室町)
特集:至極の育苗培土
自家配合で至極の育苗培土/モミガラで軽い培土/病気に強くなる培土/酸化鉄コーティング直播/温度管理にメリハリをつけろ/せん定を教えるノウハウ/農家の税金対策2017 ほか。 [本を詳しく見る]