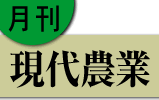 |
|
|
||||||||||||||
|
|
どんどん広がる、やっかいな竹やぶ。
放っておけば獣害の温床にもなる。
どうせならかしこく切って、おいしく食べて、ひと稼ぎ。
1m切りも各地で進化中――。
管理を続けた竹林は明るく、いいタケノコが生まれる(218ページ)(八島哲郎撮影)
放置竹林を稼げる山に!
竹チップを全面に敷いて、冬に1kg4000円の白子タケノコ静岡・宮沢圭輔

早出しの白子タケノコ。3月初旬まで、地元の八百屋さんを通じて料亭などに1kg4000〜5000円で販売する
地元の高校卒業後、波乗りを主体に生活し、インドネシアやオーストラリアに滞在した。種子島で自給自足の生活も体験するなか、生活ゴミで汚染されてゆく途上国の環境問題に関心を持ち、26歳で地元の静岡大学に入学した。
環境学などを専攻し、社会問題には法律や制度のあり方が大きく関わることを知り、大学4年のときに市議会議員に立候補。当時、最年少の学生議員となった。
3年前に議員を辞職したが、現職時代に里山が竹林に覆われて困っている住民の姿を目の当たりにしたため、放置竹林の改善に取り組み始めた。放置竹林を整備して希少価値の高いタケノコを出荷する手法を開発し、自らの収入源の一つとするべく新規就農者となった。現在は「里山友の会」という組織を立ち上げ、タケノコを出荷している。

筆者(左)とボランティアで手伝いに来てくれる間宮一裕さん(江平龍宣撮影、以下Eも)
稼げれば、人は竹林に入る
日本古来の竹は真竹である。孟宗竹は約280年前に中国から食用として渡来した。孟宗竹は樹勢も強く、管理が簡易であるため、地下茎の根を分配することで全国各地に広がった。地下茎の伸長は年に5mともいわれ、ネズミ算式に拡大する。細工や日用品に竹が使われている時期には重宝されたが、現在ではプラスチック製品が取って代わり、タケノコは安価な中国産に市場を奪われていった。
市場価値が低いから、手が入らない。逆に、竹林で稼ぐことができれば、人は山に入る。一般的なタケノコは4月のひと月で全体の80%が地中から芽吹く。タケノコ市場は飽和状態になり、玄関先に積まれて「タダでも要らない」状況が起きる。
一方で、タケノコほど価格変動幅が大きい農産物も少ない。初物や正月時期から市場に出回る数の少ない2月までは、100g当たりの単価は10倍、20倍となっている。キャベツが品薄でも10倍にはならない。タケノコは促成栽培ができないからである。タケノコの出荷時期を早められれば、稼げる農作物となるのではないか?

40年以上放置された竹林。もともとは石垣イチゴのハウスだったが、豪雨災害で土砂に埋め尽くされ、竹がはびこった

整備して3年目のようす。10a100〜150本に間引いたが、もともと放置されてひょろっと伸びた竹を親竹としているので、前年の台風で傾いた竹も多い(E)
40年以上放置された竹林を借りる
静岡市内で半年間、早出しの適地を探し求めた。南向き、平地もしくは緩やかな斜面で凍結しない環境、林地内に散水設備を設置できることを条件とした。結果、日本平と呼ばれる丘の南向き、暖房を使わずにイチゴの促成栽培ができる土地の一角に、40年以上放置されていたやっかいな竹林を見つけた。1974年の七夕豪雨災害によって、土砂で埋め尽くされた石垣イチゴの跡地。手前50mは雑木と雑草で荒れ放題、奥はイノシシの住みかと化した孟宗竹と真竹の放置竹林であった。
手前から重機を入れ、石垣イチゴの跡地と雑木を撤去。道を造成し、荒れ放題の竹林にたどりついた。枯れ竹が四方八方に絡み合い、親竹として活かせる竹もわずかであった。

放置竹林の中のようす。孟宗竹だが細いものが多く、枯れた竹も散乱していた
地表から2、3cm下で春を待つ
早出しタケノコの理論を探るべく、タケノコに関するさまざまな書籍を乱読した。地下茎にタケノコの芽を付けるのは秋口からであり、そこから春にかけて肥大してゆくとある。肥大には、水、温度、土、太陽などが影響し、それらの刺激で早期収穫が可能と記載してあった。
まず、枯れ竹や不必要な竹を間伐し、日射量を増やす。そして「雨後のタケノコ」ならばと、竹林内の農業用配管に蛇口を付けて散水設備を整え、冬期にかん水をした。あるいは、竹林の地表面にマルチを敷き詰めて保温もした。いずれも結果は出なかった。
そんななか、タケノコの習性として、地表面から2、3cm下まで伸びて春の訪れを待機することに目を付けた。待機中のタケノコの上に土を盛れば、地中でさらに大きく育つのではないか? そこで、怪しい箇所を掘り起こし、小さなタケノコを見つけては、その上に堆肥と土を盛って工事用のカラーコーンを被せる実験をした。すると確かにカラーコーンの下のタケノコは、寒い時期に地表面から2、3cm下の位置までググッと伸び、そこで春を待つことがわかった。

マルチを張って地温上昇効果を期待したが、結果は出なかった。南向きの緩やかな傾斜地。奥に見えるのは石垣イチゴのハウス
竹林内でチップ化して散布
しかし、いちいち地中にあるタケノコの芽を探すのは容易ではない。それならばと、放置竹林内に無数に存在する枯れ竹や不要な竹をチップ化して、散布すれば地表面全体をかさ上げすることになり、肥大化を促進できると考えた。
12月下旬、チッパーを竹林内に持ち込み、間伐した竹をその場でチップ化して均していった。そのさい、チップの山から湯気が立っていることに気付く。発酵熱を帯びており、地温を測ると、12〜1月にもかかわらず50℃以上となり、それが2週間ほど続いた。
ある書籍に、タケノコが地表面に芽を出すのは積算温度で1350℃との記載があり、「これだ!」と確信した。放置竹林にしかない、不要な竹をひたすら破砕し、散布し続けた。チッソ不足にならないよう堆肥を10a2t程度入れ、竹チップと一緒に積んだ。切った竹を持ち運んだりはしないから、作業効率はよい。1年目は1.5人の人員で、1カ月程度をかけて30a分の放置竹林を整備した。不要な竹が片付き、地温も上がり、きれいな竹林へと変貌させる。一石三鳥の「竹チップ農法」である。

竹林内にチッパーを持ち込み、その場で竹を粉砕していった
ナシのような味と食感
ちなみにタケノコの付加価値は、早く出すことだけではない。「地割れ掘り」と呼ばれるように、地表面に芽を出す前のタケノコがよいとされる。なぜか?
タケノコは芽を出して、日光を浴びた瞬間に栄養素である糖質をエグミに換え、動物からの食害を防ぐ。だから、日の光を浴びずに収穫したタケノコは甘みが強く、エグミが少ない。私のつくるタケノコはその場で生でも食べることができ、味と食感はまるでナシのよう。「白子タケノコ」と呼ばれるものである。
地表面に竹チップの層を積むことで、日光を浴びずに肥大させることができるからである。通常のタケノコは、地下茎から芽を出し、地表面から2、3cm下まで伸びたところで待機するため、地割れ掘りで収穫しても長さが10cm、重さも200〜300gがせいぜいだが、竹チップ農法では多くが500g〜1kgと大きなタケノコが収穫できた。1、2月の段階で1kgのサイズが揃った白子タケノコの姿は圧巻である。

昨年11月初旬に新しく竹チップを敷き詰めた放置竹林。西向きで早出しには好条件といえないが、年内からタケノコが発生。ただし、販売には早すぎるのでチップを敷くのは1月以降がよさそう(E)
カブトムシが耕し、キノコが生える
ただし、翌年以降は竹チップの発酵が進んで前年に積んだ層が低くなる。発酵熱による地温上昇効果も見込めない。それでも、2年目となった昨シーズンはチップの追加散布をほとんどせずに、初年度と遜色ない早出しの白子タケノコを出荷できた。

もともとの地面からチップの厚みを測ると16cmあった。タケノコは元の地上部を超えて育っているが、皮も先端も白いままだ(2月5日撮影、E)
竹チップを敷くと、地中でタケノコが大きくなる
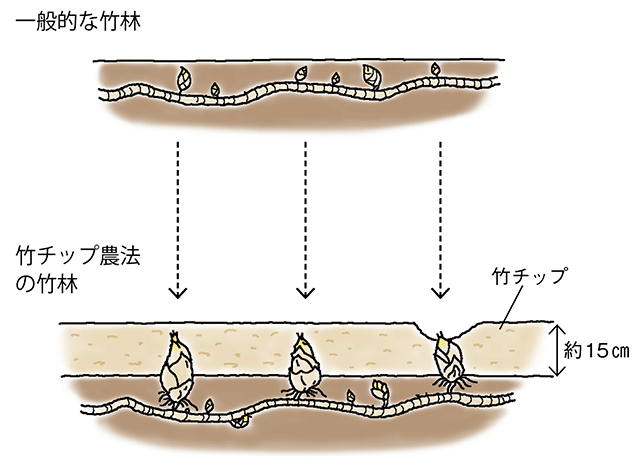
タケノコは地面の2、3cm下まで伸びたら春が来るまで待機する。竹チップを敷き詰めて地表面を高くすれば、大きくて白いタケノコを収穫できる
3年目となった今シーズン。諸事情で竹チップを追加しなかったので、若干生育は遅くなっているが、別な意味で興味深い現象が起きている。
前述のように現在の圃場は40年以上前の土砂災害で被害を受けた場所である。もともとの土壌もあるが、砂利層でタケノコ栽培に適した土壌とはいえなかった。それが3年目を迎え、一歩足を踏み入れるとパウダースノーの雪山のように自身の体重で沈み込む土壌となっている。
その立役者がカブトムシの幼虫だ。竹のチップを竹林の全体に散布したことでカブトムシの産卵場となり、竹林の土を幼虫が耕し、その糞で土が肥えている。竹チップで不足したチッソ分はカブトムシの幼虫が提供してくれているのだ。自然の力による補完能力を実感している。秋には幻のキノコと呼ばれるキヌガサタケも生えてきた。
今シーズン、竹チップ農法1年目の竹林では、なんと11月15日からタケノコを収穫している。初物のシーズンよりも早すぎて、価格がつかなかった。1月は1kg4000円で八百屋さんに卸しているが、早出しの白子タケノコの需要が高く、高値がつくのは2月から3月初旬。この時期、毎日わずか数kgの出荷で2万〜3万円の収入を得られる。放置竹林は収入源となるのである。(静岡県静岡市)

もともとの地面からチップの厚みを測ると16cmあった。タケノコは元の地上部を超えて育っているが、皮も先端も白いままだ(2月5日撮影、E)

足で踏むとふかふかだ(E)

10月下旬に幻のキノコといわれるキヌガサタケが発生した
京都の白子タケノコ
粘土で覆って光を断つ京都府木津川市・東川 弘さん
約7反歩でタケノコを生産しています。9月で86歳になるから、栽培歴は60年以上やなあ。京都では、真っ白な白子タケノコをつくるために、毎年冬に竹林の表面に粘土を入れてます。空気と光が入ると皮が黒くなるから、それらを遮断するためですな。それと、粘土で覆うとタケノコが顔を出す前に地面にヒビが入りますやろ、掘り取りのサインになりますねや。
*
ただし、粘土ばっかりやと雨でぐちゃぐちゃになってヒビ割れがわからなくなるから、4割ほど山砂を混ぜたんが一番ええ。うちの場合、竹林から200mほどの山で粘土と山砂がとれるから、バックホーと2tダンプを使って竹林に運びます。竹林内には一輪車で運び込んで、1mおきくらいに盛っていく。一輪車も50kgの重さになるから、踏圧で地面が締まらんように、踏み板を100mくらい並べて、その上を通る。最後は鍬で均して厚さ2cmほどの層にするんですわ。それで、2、3月に雨が降ると土が落ち着いて地面にフタがされるわけ。毎年2反ほどの竹林に、山土を50tほど。息子と孫も含めて5人がかりの作業ですわ。
*
もちろん、それだけやないですよ。収穫後のお礼肥と秋肥で油粕をやる。9月頃には7年経った親竹を間伐して光が十分に入って地温が上がるようにする。2坪に1本くらいかなあ。7〜10月には土手草やワラを全面に敷いて保温・保湿……。それで冬に粘土を入れて、ようやっと3月20日頃から収穫。こうして手をかけて先が黄色くて真っ白なタケノコを掘らんと、一流の値段にはなりませんわ。(談)
ざる・かご・竹竿・和傘・竹皮編など竹の工芸品満載の新刊『生活工芸双書 竹』(農文協、3000円+税)が発売されました。
取材時の動画が、ルーラル電子図書館でご覧になれます。「編集部取材ビデオ」から。

特集:切って食べて 竹やぶを減らす
自作の苗踏みローラー大集合/水を制してタマネギ9tどり/今年は防ぐリンゴ黒星病/北国の竹林整備/イノシシをフェンスで撃退/食い止まりのない牛をつくる/山菜のペットボトル漬け/種苗法 農家の自家増殖「原則禁止」に異議あり! ほか。 [本を詳しく見る]『DVDブック 竹 徹底活用術』農文協 編 荒れた竹林が増え田畑や集落まで侵食する厄介者の竹だが、1日1m伸びるといわれるその旺盛な生命力を逆に利用する動きが各地に出てきた。青竹を粉砕した竹パウダーを田畑の肥料や家畜のエサにすると生育がガラリと変わり「病気に強くなる、おいしくなる」の声が続々。竹で乳酸菌や酵母菌を殖やす方法、竹林での土着菌採取法、荒れた竹林管理法の記事の他、竹林の中で竹炭をやく方法や、話題沸騰「竹は1mの高さで切ると根まで枯れる」の実際、安く手作りできる竹パウダー製造機、人気の竹テントの作り方などは、DVD67分にも収録。 [本を詳しく見る]
『新特産シリーズ タケノコ 栽培・加工から竹材活用まで』野中重之 著 ウラ止めなど集約管理による収穫・出荷の前進化、消費の核家族化に応える小型化、客土による高品質化(軟白栽培)、高齢者・女性向きの穂先タケノコ、観光タケノコ園、竹林オーナー制など収益アップ・省力化を追究。 [本を詳しく見る]