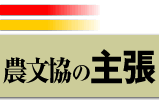 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1996年1月号
|
|
農家が自由に米を売れることの意味 ――産直が主導する新しい市場原理が21世紀をつくる 日本の農耕が始まって以来、初めて農家が自由に米を販売できる新しい時代が始まった。今年がその元年である。 古くは班田収 授法、江戸時代には領主の年貢米の取り立て、明治以降は地主の小作米の取り立て、そして昭和17年の食管法以降は供出米の供出と、有史以来、支配者は権力によって米を支配し、米によって農家を支配してきた。 まことに、不思議な事だが、瑞穂国で瑞穂(みずみずしい稲の穂)を作っている農家が、その瑞穂を自由に売った経験は史上皆無なのである。その瑞穂国の農家が今年から、米を自由に売れる時代に入った。まさに歴史の画期といわねばならない。 この画期の歴史的な意味をどのように把握したらよいのか。この画期によって、農家が米を売ることによって、どのような新しい時代が日本に訪れるのか。新年に当たってそのことについて考えてみよう。 ◆旧態依然たる発想はやめよう
米が権力による支配から自由になったことを学者・官僚・評論家・ジャーナリストたちは口を揃えて次のようにいう。「米は自由競争の一般商品と化した」。国際化時代の今日、「米の生産規模を拡大し、生産コストをダウンすることによって、国際競争力を強めなければならない」。「そのための施策を講ずべきである。米価に対する助成や米についての「保護」「規制」は全面的に撤廃すべきである。それが先進国日本としての国際的責務である」等々。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |