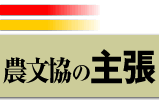 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1996年7月号
|
|
米産直を核に
新しい食品流通を創り出そう 6月1日、米販売業自由化の火ぶたが切って落とされた。新食糧法に基づく米販売業の登録制への移行で量販店やコンビに、酒店などを中心にした新規参入組は店舗数で約16万軒。今までの約9万軒から25万軒前後へと3倍弱の激増だ。同じく登録制となった卸会社も既存の約280社から350社へと急増。折しも自主流通米価格形成センターでの平成7年産自主流通米の最後の入札を今月中・下旬に控え、「その仕入れの成否が自由化後の卸、小売段階の競争を左右する」との思惑も手伝い「取引先の開拓、確保を目指し、卸、小売入り乱れての陣取り合戦が既に始まっ」ており「人気銘柄米は競争率が上がり高値落札となる公算が大きいとの見方が支配的だ」(「日経」5月16日付)。 実際、旧自由米相場に当たる業者間相対取引価格も4月以降ジリ高を続け3%前後の値上がりを見せており、この種の報道は、本誌が読者のお手もとに届く頃にはもっともっと多くなっているだろう。 自由化による販売競争の激化がまずは仕入れ競争に現われ、人気銘柄中心とはいえ「相場」が強含んでいることは生産者サイドにとってもひとまず安心といったところだろうか。 しかし、1寸先は闇というのが相場の世界。とりわけ食料のばあい、ちょっとした天候の変動も敏感に市況に反映し、大きく値振れするのが特徴だ。半年先はおろか、1カ月先だってわかったものではない。 わが国では既に江戸時代。幕府公認のもと、米の先物市場ができていて、そこは米商人、業者たちのリスクヘッジの場にも投機の場にもなっていた。その中から数々の相場格言も生まれたが、「相場は相場に聞け」という言葉に象徴されるように、明日のことは本当のところ誰もわからないのである。わからないから値がつくという不思議な世界なのだが、しかしというかだからというか、当然そこには少なくない「相場巧者」が輩出し、農民や「市民」の怨念の対象になったりもした。 ◆「市場」を動かすもうひとつの市場を
新食糧法によって自由化された新しい米市場はどんな姿になるのだろうか。ここでは、先物市場のような投機色の強い相場はまだできてはいない。しかし、「より需給実勢を反映した価格形成の場を」という趣旨のもと、値幅制限の緩和と基準価格の頻繁な改定、取引参加者の拡大、入札回数の増大など、センターでの価格形成のしくみがより〃弾力化〃する方向に改定されたのは周知のとおりだ。そしてここには、商売にかけては海千山千、国際的な穀物先物相場でも十分な鍛練を積んできた相場巧者=巨大商社が卸や小売として取引に参入してくる。まさに半年先はおろか、1カ月先だってわかったものではない鉄火場的自由市場の世界がくり広げられる可能性が確実に強まっていくといえるだろう。そして、冒頭に紹介したような予測や憶測、見通しの報道もより頻繁に出されるようになるにちがいない。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |