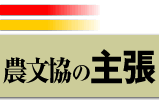 |
|
|
||||||||||||||
| 擾暥嫤僩僢僾亜庡挘亜
1997擭7寧崋
|
|
偄傑丄抧堟傪嫽偡愨岲偺帪婜 敪憐傪曄偊傞係偮偺億僀儞僩 崅楊幰乛抧堟巗応乛嫵堢乛僱僢僩儚乕僋 栚師 仧擔杮堦偺崅楊幰懞傪偮偔傠偆 仧乽抧堟偺壙抣乿傪敪尒偟丄崅傔丄廧傒傗偡偄擾懞嬻娫傪偮偔傞 仧彫拞妛峑偺惗搆偼姶摦偲僪儔儅偺庼嬈傪媮傔偰偄傞 仧乽抧堟乿偲乽妛峑乿偲偺僱僢僩儚乕僋傪 丂尰峴偺擾嬈婎杮朄偑惂掕偝傟傞傑偊偵丄傑偢憤棟晎偵乽擾椦嫏嬈婎杮栤戣挷嵏夛乿偑愝偗傜傟偨丅偙偺係寧偵丄摨偠偔憤棟晎偵乽婎杮栤戣挷嵏夛乿偑愝抲偝傟偨偑丄偦偺柤徧偼乽怘椏丒擾嬈丒擾懞婎杮栤戣挷嵏夛乿偵側偭偰偄傞丅俀擭屻偵惂掕偑梊憐偝傟傞怴擾婎朄偼丄擾嬈偩偗偱側偔擾懞偲偄偆帇揰偐傜傕専摙偝傟傞偱偁傠偆偙偲偑偙傟偱傢偐傞丅偙偺揰偵偮偄偰偼傢傟傢傟傕憹姧崋亀怴擾婎朄偵採埬偡傞亁偱戝偄偵採尵偟偨偲偙傠偩丅 丂偟偐偟丄擾嶳嫏懞傪抧堟幮夛偲偡傞巗挰懞偼丄偦傫側怴擾婎朄偺棫朄摦岦偵嵍塃偝傟偢偵丄偙傟偐傜偺幮夛偺偁傝曽傪尒捠偟偰丄抧堟怓朙偐側乽擾嶳嫏懞抧堟宍惉寁夋乿傪棫偰丄幚峴偟偰偄偔偙偲偺傎偆偑戝愗偩偲巚偆丅偦偺億僀儞僩偼偮偓偺係崁栚偱偁傞丅 丂戞堦偵丄崅楊幰傪妶偐偡偙偲丅崅楊幰偺懡條側屄惈丒擻椡傪妶偐偣傞忦審偲婡夛乮楯摥巗応乯傪偮偔傞偙偲偱偁傞丅崱傑偱偺傛偆側婇嬈桿抳偵傛偭偰屬梡傪憹戝偝偣傞偺偱偼側偄丅抧堟帺慠傪妶偐偟丄偦偙偵偟偐側偄嶻嬈丄崙嵺壔偵晧偗側偄嶻嬈傪嫽偡偙偲偵傛偭偰丄偦傟偼壜擻偱偁傞丅 丂戞擇偵丄偦偺巗挰懞偵偟偐側偄屌桳偺乽抧堟壙抣乿偵傛傞抧堟乮暔嶻乯巗応傪嫽偡偙偲丅崱傑偱偺傛偆偵戝検惗嶻偺儘僢僩偲僐僗僩僟僂儞偵傛偭偰懠嶻抧偲彑晧偡傞偺偱偼側偄丅抧堟屌桳偺壙抣娤丒枴妎丒岲傒偵懳墳偡傞抧堟暔嶻傪嫽偟丄懡條側棳捠儖乕僩傪巊偭偰峀傔偰偄偔偺偱偁傞丅 丂戞嶰偵丄怘傋暔偲擾嬈偺抧堟嫵堢傪嫽偡偙偲丅崱傑偱擾懞偼乽擾岺娫偺強摼嬒峵乿傪栚巜偟偰搒夛偺巕偳傕傪偮偔傞偺偵擬怱偱偁偭偨丅偟偐偟丄屘嫿偺惗嶻丒惗妶偺尨懱尡偑幐傢傟偨崱丄晛曊揑丒壢妛揑側嫵堢偱偼乽妛傇堄梸乿乽惗偒傞椡乿偑堢傔側偄偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅怘傋暔偲擾嬈偲偄偆偒傢傔偰屄惈揑側傕偺偺帩偮嫵堢椡傪丄擾懞嬻娫偲偄偆嫵堢娐嫬偺側偐偱偮偔偭偰偄偔丅偦傟偑抧堟偺巕偳傕傪偮偔傞偨傔偵昁梫側帪戙偵側偭偨偺偱偁傞丅 丂戞係偵丄埲忋偺俁崁傪堦懱揑偵悇恑偡傞偨傔偵抧堟忣曬僱僢僩傪嫽偡偙偲丅慡崙偺愭払偵妛傃丄偦偺忣曬傪抧堟壔偡傞偨傔偺忣曬曇廤儕乕僟乕偑堢偨側偗傟偽側傜側偄丅慡崙忣曬傪抧堟壔偡傞偙偲偼怴偟偄幚慔傪偮偔傞偙偲偱偁傞丅偦偺怴偟偄幚慔偵傛傞敪尒偲憂憿偑怴偟偄抧堟忣曬傪嶻傓丅偙偆偟偰抧堟丒宱塩傪偮偔傞怴偟偄幚慔偑偦偺傑傑屌桳偺抧堟忣曬傪偮偔傞妶摦偵側傝丄悽奅偵岦偗偰偺忣曬敪怣婎抧偵側偭偰偄偔丅偦偺傛偆側怴偟偄廧柉塣摦傪嫽偡偙偲偑昁梫側偺偱偁傞丅 仧擔杮堦偺崅楊幰懞傪偮偔傠偆丂偙傟傑偱抧曽偺宱嵪傪妶惈壔偡傞偲偄偆栚揑偺偨傔偵丄擾懞岺嬈傪摫擖偟偨傝丄帠嬈摫擖偵傛偭偰偝傑偞傑側巤愝傪嶌偭偨傝偟偰偒偨丅偟偐偟丄偦傟傜偼墌崅偵側傞偲埨偄楯摥椡偲埨偄尨椏傪媮傔偰奀奜偵堏揮偟偨傝弅彫偝傟偨傝偟偰丄昁偢偟傕夁慳懳嶔偵偼寢傃偮偐側偐偭偨丅巗挰懞暿偺亀抧堟妶椡恾娪亁乮慡10姫丄擾暥嫤姧乯傪傒傞偲丄80擭戙屻敿偐傜偦偆偟偨忬嫷偵偁傞巗挰懞偑戝曄栚偵偮偔丅丂宱嵪偺妶惈壔傪愭偵峫偊傞偺偱偼側偔丄怴偟偄恖惗80擭帪戙偺儔僀僼僗僞僀儖傪幚尰偡傞応偲偟偰偺抧堟偯偔傝傪愭偵峫偊側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅崱偦偙偵廧傫偱偄傞崅楊幰偑挿庻偲寬峃傪嫕庴偱偒傞惗嶻丄曢傜偟偯偔傝偑愭偱側偗傟偽側傜側偄丅 丂偟偐偟尰幚偵惗偒偰偄傞崅楊幰偼丄峴惌偲儅僗僐儈偺乽崅楊幰偍壸暔娤乿僉儍儞儁乕儞偵傛偭偰丄崱偺幮夛僔僗僥儉偺拞偱峴偒応傪幐偭偰偄傞丅崅楊幰偑擭傪偲傞偵廬偭偰恖岥堏摦棪偑崅偔側傞孹岦偵拲栚偟偨噴俋廈抧堟寁夋尋媶強偱偼乽崅楊幰偼側偤傆傞偝偲傪棧傟偨偺偐乿偺挷嵏尋媶傪暯惉俉擭侾寧偵傑偲傔偨丅崅楊幰偑埨怱偟偰惗妶傪懕偗傜傟傞抧堟偯偔傝傪柾嶕偟偨偙偺挷嵏偱偼丄65嵨埲忋偺崅楊幰偑丄崅搙惉挿婜偵戝搒巗偵揮弌偟偨懅巕丒柡偺傕偲偵屻捛偄揮弌偡傞椺偑媫憹偟偰偄傞幚懺傗偦偺攚宨傪偝偖偭偰偄傞丅壂撽導塝揧巗丒愰栰榩巗偺弌恎幰偑屘嫿偵巆偭偨恊傪屇傃婑偣偨働乕僗偱偼丄師偺傛偆側暦庢傝挷嵏偺寢壥偑曬崘偝傟偰偄傞丅 丂乮1乯媨屆偺忛曈挰偐傜恊傪屇傫偩偑丄弌偰偒偰俁擔栚偵乽搒夛偺惗妶偵朞偒偨丄搰偵婣傝偨偄乿偲偄偭偰婣偭偰偄偭偨丅崅楊偱撈嫃偟偰偄傞偺偼怱攝偩偲屇傫偩偺偩偑丄搒夛偵楢傟偰偒偰傕幵偑懡偄偺偱奜傪嶶曕偡傞偙偲傕偱偒偢丄侾擔拞僥儗價傪尒傞偟偐偡傞偙偲偑側偄丅戅孅偱嬯捝偺俁擔娫偩偭偨偺偩傠偆丅乮2乯搒夛偵屇傫偩恊偑揷幧偵婣傝偨偄偲偄偭偰傕丄懛傕寣墢幰傕揷幧偵巆偭偰偄側偄応崌偼丄恊偵変枬偟偰傕傜偭偰搒夛偵廧傫偱傕傜偆偙偲偵側傞偑丄偡偖偵昦婥偑偪偵側偭偨傝丄懱挷傪曵偟偨傝偟偰偟傑偆丅塣摦晄懌偵側傞忋偵丄榖偟憡庤傕偄側偄偐傜偩偲巚偆丅乮3乯搒夛偵屇傫偩偗傟偳傕丄埲慜偐傜偺崅楊惈抯曫偑偐偊偭偰恑峴偟丄巇曽偑側偔巤愝偵擖傟偨傜偡偖偵朣偔側偭偰偟傑偭偨丅傕偭偲丄揷幧偺偺傫傃傝偟偨応強偱嵟婜傪寎偊偝偣偰偁偘偨偐偭偨偲夨傗傫偱偄傞恖偑偄傞丅 丂屘嫿偐傜搒夛傊偺恖岥堏摦偼丄惗偒偑偄傪幐傢偣丄柦傪弅傔偝偣傞丅偩偐傜丄崱偦偙偵惗偒偰偄傞崅楊幰偑惗偒惗偒偲曢傜偣傞懞偯偔傝偙偦偑廳梫偵側傞丅乽偙偙偑曢傜偟傗偡偄偐傜崅楊幰偑偨偔偝傫廧傫偱偄傞偺偩乿偲嫻傪偼傟傞懞偯偔傝傪悇恑偟側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偼偲傝傕側偍偝偢丄崱儔僀僼僗僞僀儖偺曄妚傪媮傔偰偄傞搒巗崅楊幰偑屘嫿偵婣娨偱偒傞忦審傪偮偔傞偙偲偱偁傞丅 丂擾懞偺崅楊幰偼丄偡偱偵乽惗奤尰栶乿偱偁傝乽僾儘僔儏乕儅乕乿乮惗嶻偡傞徚旓幰乯偱偁傞偲偄偆儔僀僼僗僞僀儖傪幚尰偟偰偄傞丅搒巗偺崅楊幰偼丄偦偆偟偨擾懞偺崅楊幰偺儔僀僼僗僞僀儖傪媮傔偼偠傔偨丅擔杮侾偺崅楊幰懞傪偮偔傞忦審偼惉弉偟偰偒偨偺偱偁傞丅崅搙惉挿婜偵懞偐傜搒巗偵怑傪媮傔偰揮弌偟偨恖乆偼偪傚偆偳掕擭娫嵺偵側偭偰偄傞丅傑偢偦偺悽戙偺摨憢夛偯偔傝偐傜奐巒偟偰丄擾懞偵恖傪屇傃栠偦偆丅 仧乽抧堟偺壙抣乿傪敪尒偟丄崅傔丄
丂擾懞偺搒巗傊偺摥偒偐偗偼抧堟偵妶婥傪傕偨傜偡丅偦傟偽偐傝偱側偔丄崅楊幰傪拞怱偲偟偨僌儖乕僾偑抧堟偺晧偺帒尮偲巚傢傟偰偄偨傕偺傗丄偙偺娫屭傒傜傟傞偙偲偺側偐偭偨帒尮傪尠嵼壔偟偰抧堟偵妶椡傪傕偨傜偟偰偄傞帠椺偑憹偊偰偒偨丅 |
|
偍栤偄崌傢偣偼 rural@mail.ruralnet.or.jp
傑偱 2000 Rural Culture Association (c) |
丂