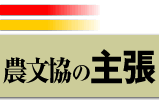 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1998年3月号
|
|
転作をバネに、田畑と体力に 合わせた自在農業 目次 ◆転作を考えるときの4つの前提条件 ◆大きいだけでは損をする ――「大規模農家」はどうするか ◆高齢農家、定年帰農が作る新しい農業経営 ◆昭和一桁世代の第二《経営草創期》 ◆米の産直、米価維持にも必要な転作 ◆教育への支援も視野に入れた農村計画を ◆転作を考えるときの4つの前提条件米の需給均衡回復と生産調整実施者のメリットをうたった「新しい米政策」が平成10、11年の2カ年で実施されることが決定された。平成9年度と比べて17万6000ha拡大した、96万3000haの生産調整を実施するというものである。全水田面積の35.5%に及ぶ転作をどう考えたらよいだろうか。これまでは、転作といえば米以外の何で儲けるかという視点からのみ考えられてきた。しかし今、転作を考える時、かつてと根本的に異なる条件が生まれていることに注目したい。 一つは大規模生産・大量販売で儲けるという論理がまったく通用しなくなったことだ。今までなら専作型産地は既存の作目の経営拡大が正道とされてきたが、それが成り立たなくなったということである。 二つには人生八十年時代になり、農村空間で「人生二毛作」を追求する新しいライフサイクルが動き始めたことである。それは平成7年の10万人の新規就農者のうち六割が定年帰農である事実として現実になっている(「現代農業」1998年2月増刊「定年帰農16万人の人生二毛作」)。 三つには平成五年の米の大凶作以来、燎原の火のごとく広がった「米プラスα」産直の流れである(「現代農業」1997年11月増刊「朝市大発見」)。埼玉県農林部の調査では43都府県で1万カ所を超える直売所がある。このプラスαにとって、転作の位置は大きい。 四つには、この数年にわかに高まってきた、農村が地域の小中学校の食農教育を支援しようという流れである(中教審の第一次答申でいう「ゆとり」の中で子どもたちに「生きる力」を育むことをめざす)。小中学校の「体験学習農園」や障害者・老人施設での「福祉農園」など、減反田をこれまでとまったく異なる発想で使っていこうとする動きである。 ◆大きいだけでは損をする
近年の市場での米価下落はきわめて激しいが、これによる所得減をいっそうの規模拡大で取り戻そうとするのはきわめて危険である。米作りにせよ転作にせよ野菜栽培にせよ、大規模化しさえすれば儲かるという時代ではなくなったのである。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |