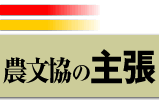 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1999年3月号
|
「答申」の哲学を探る〈結び合いによる安心のある生き方〉とは何か目次◆二つの答申の比較 ◆国民全体の問題として ◆「安心のある生き方」 ◆「結び合い」の文化 ◆社会の持続のためにこそ このたびの「食料・農業・農村基本問題調査会答申」には哲学がある。 その哲学は〈文化格差の是正〉ということである。 株式会社の農地取得や中山間地帯への直接支払い、あるいは自給率目標の明示の是非というような、具体的な政策展開の議論に、あまり性急にかかわらずに答申を読む。すなおに、たんたんと、ていねいに読む。すると答申の底流にあるひとつの哲学が浮かび上がってくる。それが〈文化格差の是正〉である。 もちろん、答申に〈文化格差の是正〉などということばは使われていない。使われていないのは当然で、答申の役割は「食料、農業及び農村に係る基本的な政策に関し、必要な改革を図るための方策に関する基本的事項について、貴調査会の意見を求める」という内閣総理大臣の諮問に答えることだからである。 しかし、「必要な改革を図るための方策」に答えを出すためには、哲学を必要とした。そこがいちばん大切なところだ。昭和35年の答申では哲学などは必要としなかった。 ◆二つの答申の比較「昭和三十五年の答申」というのは、今から38年前、農業基本法の立法に先立って、やはり内閣総理大臣が「農林漁業に関する基本的施策の確立」を、「基本問題調査会」に対して諮問した、それへの答申である。 35年の諮問・答申と今回の諮問・答申と、どこがちがうか。 まず、諮問の内容がちがう。したがって、調査会の名称がちがう。三十五年は「農林漁業基本問題調査会」であり、今回は「食料・農業・農村基本問題調査会」だ。 つぎに会長がちがう。前回は経済学者(東畑精一氏)であり、今回は歴史学者(木村尚三郎氏)である。 こうしたちがいは、形だけのことではない。テーマには、農業だけでなく食料と農村が加わっている。しかも、この三つは併列されているけれど、ただ併列しただけでは問題のありかはつかめないことは自明である。近ごろ教育や健康、ひいては社会のあり方を考える場合に、急速に広がってきた「食と農」、あるいは「食農」というセット的思考が必要になってくる。だから経済学者だけではダメで広い範囲の委員が任命されているし、会長は歴史学者、ということになったのであろう。 実際に出された答申は、食料・農業・農村政策が別々に記されていて、その三位一体であるところは具体的になっていない。農村社会という伝統と歴史をもった土俵の上で、農業生産が行なわれ、その結果として、いのちを養いくらしを成り立たせる食料が生まれる。その総体を、つまりは食料・農業・農村の関係性をこそ把握してほしい。そういう思いが読み進むにつれてわだかまってくる。 たしかに、前回とはわけがちがう。高度経済成長が始まり、その進展につれて農工間の格差は拡大し、農村と都市の所得均衡が失われようとするそのとき、農業政策の目標は、明白に〈所得格差の是正〉であった。そして、目標到達のための手段(政策)は、所得政策・生産政策・構造政策の三つである。それでこと足りたのである。 念のため、前回と今回の答申の目次立てをみると下のとおりである。前回はスッキリ、今回はゴタゴタだ。なにが目標で、そのためにどんな手段をとるのか、論理的な脈絡がみつからない。たしかに今回の第1部4には「食料・農業・農村政策の目標」としてつぎの三点が掲げられている(抜粋)。
一、食料の安定的な供給を確保すること。我が国農業の食料供給力を強化すること。 二、農業・農村の有する多面的機能の十分な発揮を図ること。これは、農村地域社会の維持を通じて我が国経済社会全体が調和をもって発展していくという要請にも対応する。 三、地域農業の発展の可能性を多様な施策や努力によって追求・現実化し、総体として我が国農業の力を最大限に発揮すること。 しかし、この三点を並べられても、いったいこの答申がなにゆえこの三点を掲げたのかがよくわからない。つまり、前回の答申が目標を「所得格差の是正」の一点にしぼって答えを出せたのに対して、今回の答申は一筋なわではいかなかった。食料・農業・農村を併列でなく、三位一体として把握する哲学は見いだせなかったのだろうか。あえて目標として「××格差の是正」というような言い切り方はできないのだろうか。 一呼吸ついて、「まえがき」と「あとがき」を読んでみる。政策についての答えを出すのが答申なのだから、人々の目はまず本文にむけられるのは当然であろう。そして、「まえがき」や「あとがき」は美しい衣装であり、作文であって、政策本体とはかかわりのないことのようにとられやすい。 だが、今回はちがうのではないか。「××格差の是正」という単純な言い切り方を、この「まえがき」と「あとがき」から推測すると、××に入るべき文字は「文化」こそがふさわしいと思われてくる。 ◆国民全体の問題として「文化格差の是正」というとき、その格差はもちろん農村と都市との間にあるものである。ただし、農村が都市より文化的におとっているというのではない。その逆である。経済的、利便的には都市より農村がおとっているかもしれないが、文化的には、都市は農村よりおとっているという認識である。農村には都市に伝えるべき文化的蓄積があり、それがいま日本の社会そのものに求められている――ということである。 それはつぎのような発想に通ずる。 「文明という名のもとに、人間が自然から遊離してしまった感じがしてなりません。農村は文明の僻地だという人がいますが、それならば、都会は自然からの僻地ではありませんか。そして自然からの僻地では、創意と自主性にあふれた人間は育ちにくいかもしれませんね」 これは山岳酪農の草分け、高知県の故・岡崎正英さんが昭和47年に記者に語ったことばだ。都市と農村の文化格差とは、こうした、単純だが真実をつかめている、生活感覚からの認識で言っている。いま流にいえば、“本当の豊かさ”の格差ともいえようか。 答申の「はじめに」と「あとがき」はどちらも一五〇〇字前後の短い文章で、「未来に対する不透明感」とか「文明の大きな転機」とか「危機意識」とか「人々の価値観や生き方」とか「生き方の反省」とかいうことばがちりばめられている。その中に、つぎのような〈ねばならない〉という断定形でむすばれる文章が四つある。 (1)わが国における食料・農業のあり方は、農村のあり方とともに、国民全体・国土全体の問題として緊急にとらえ直されねばならない。 (2)進歩と発展の明るい高度成長期から一転して、世界的に危機意識と不透明感が強まる中にあって、戦後の農政を形づくってきた制度の全般にわたる抜本的な見直し、二一世紀を展望しつつ国民全体の視点に立った食料・農業・農村政策の再構築が、今なされねばならない。 (3)今後も我が国は繁栄を維持し、自由で創造的な社会を築いていくと同時に、国際的にも自らの責任を果たしながら、地球社会の安定と発展に寄与していく必要がある。そのためには、国民全体が、世界の人口・食料・環境・エネルギー問題と我が国の二一世紀のあり方に思いを致し、男性も女性も、そして高齢者も若者も互いに協力し合って、食料・農業・農村の活力ある未来を切り開いていくため、努力を積み重ねていかねばならない。 (4)人々は「くらしといのち」の根幹に関わる食料と、それを支える農業・農村の価値を再認識し、これに対する評価を高めねばならない。 以上はすべて「国民全体」「国土全体」ないしは「人々」にとっての〈ねばならない〉である。 ◆「安心のある生き方」(4)の引用に含まれる「くらしといのち」は、答申の一つのキーワードであって、これ以外にあと三カ所出てくる。つぎのとおりである。 (5)人の意識・価値観・生活スタイルの全般にわたる見直しと新たな模索・創造の営みが世界的に進む中で、誰もが今、自分の足許を見つめ、何よりもまず「くらしといのち」の安全と安心を確保したいと願っている。 (6)「くらしといのち」の基本に関わる安全で安心できる食料の安定的確保については様々な問題が地球的規模で顕在化し、経済社会のボーダーレス化が急速に進展する中にあって、時とともに重要性が高まっている。 (7)人と自然の心地よい関わり、美しい生活空間としての農村の創造に留意する感覚を回復し、「くらしといのち」の安全と安心を確立していくことが、これからは特に求められる。 以上を読むと(5)や(7)にあるような「くらしといのちの安全と安心」こそが目標なのだということがわかってくる。そこでもう一カ所、「安心のある生き方」ということばが使われているところを引用する。すこし長いけれど、重要な部分だから全体を引用する。「おわりに」の冒頭の部分である。 (8)現在、時代は大きな歴史的転換期にあり、人々の価値観や生き方が大きく変わりつつある。 二〇世紀には、人々は技術革新を基礎とする急速な経済的発展の下で物質的な価値を追究してきた。しかしながら技術文明が一巡し、地球資源の有限性や環境問題の重要性、そしてまた食料危機への不安が認識されるに伴い、今全世界が大きな生き方の反省を迫られている。ここから精神的・文化的な価値が重視され、結び合いによる安心のある生き方が切実に求められるようになってきた。 今後は、人間と自然(環境)、人間と人間(国際化)、人間と過去(歴史・伝統・文化)の三つの結び合いがとりわけ重視されるようになる。進歩や発展といった価値観や二〇世紀型技術文明から、調和と共存、健康やくらしの心地よさ・美しさを優先する価値観や文明への、世界史的な転換が起こりつつあるものと考えられる。 このような時代においては(このまま(4)の「人々は ……」につながる) ◆「結び合い」の文化引用を重ねるうちに、答申の哲学が一つの脈絡を持って現れてきた。つぎのような脈絡である。 守るべきものは農業という一つの産業ではなくて、国民の「くらしといのちの安全と安心」である。これを守るのは国民全体としての努力である。「くらしといのちの安全と安心」は直接的には食料の量と質によって得られるが、それだけでなく、精神的・文化的面でも、「結び合い」による安心が切実に求められている。 つまり、目標は「くらしといのちの安全と安心」であり、その手段は「結び合い」なのである。 〈結び合い〉には三つの形があると(8)はいう。 ・人間と自然 ・人間と人間 ・人間と過去 の三つである。いずれも、農村社会が生産と生活のなかでつちかってきた結び合いである。その多様な結び合いこそが文化であり、その蓄積は都市より農村の方が圧倒的に重厚である。そうした「結び合いの文化」の豊かさにおいて農村と都市は数段の格差がある。農村における結び合いの文化を基礎として、人間と自然の結び合いを環境の視点で、人間と人間の結び合いを国際化の視点で現代的に再構築し、人間と過去の結び合い、すなわち歴史と伝統と文化を意義あるものとしよう――。 そういう哲学を、今回の答申で読みとったというわけである。 ◆社会の持続のためにこそこの答申の哲学にしたがえば、まもなく立法されるであろう「食料・農業・農村基本法」は、昭和三十六年の「農業基本法」のポイントになっているいくつかの方向に代えて、次の各項が明示されなくてはならない。 一、「選択的拡大」に代えて「農業の総合産業化」。これは答申本文で「経営の多角化」ということばで示されている(2部の2の(1)のア、同(2)のア、2部の1の(7))。 二、「主産地形成」(単一品目大量生産)に代えて「多品目小量生産」(第2部の1の(7)に使われている)。 三、「生産性の向上」「規模拡大」に加えて、「大・小の経営のネットワーク」。これは「多様な経営形態」ということばで第2部の2の(2)に、「農業者相互の機能分担」ということばで第2部の2の(1)のアに示されている。 そして何より答申のいう「持続的な社会の形成」(1部の1の(3))は、農村地域社会の維持がなければ不可能なことを明示すべきであろう。持続的農業ではなくて、社会の持続である。 木村尚三郎会長は答申後のインタビューで「二一世紀のわが国の方向を「土と共に生きる農型社会にすべきだ」と強調した」という(「日本農業新聞」九八・九・一九)。農型社会という以上、それは社会構造の問題である。 農村とか都市とかの問題を超えて、日本社会の構造そのものが“農”の「歴史・伝統・文化」に基づいたものになっていく。工業の農業化であり、分業のネットワーク化であり、疎外からの回復である。農を軸にして社会を変える。つまり〈文化格差の是正〉である。 インタビューでの木村会長のユーモアにあふれた発言を引用して終わる。 ――「くらしといのち」という言葉は、役所や男の言葉にはありません。「今日を犠牲にしても明日に向かう」生き方でなく、「今日を大事にしながら明日を考える」生き方が、先進諸国の中でもとられてきています。つまり日常を大事にする女性の感覚を入れたいと、大和言葉を使いました。(「農民新聞」九八・一〇・一五) ――くらしといのちの基本法だと考えていながら、いつの間にか男の発想で新農業基本法と言われるようになっています。三年なり五年後に見直しながら変わっていくと、私は思っています。(同) (農文協論説委員会) |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |