原発から農発へ
いまこそ農家・農村力発電を
目次
◆大正の通水開始と同時に発電を開始した土地改良区発電所
◆農村の小水力発電を支援する企業
◆地元住民が運営する農協発電所
◆原発とは真逆の農発の思想
◆農家・農村の発電はむしろ「本業」「本流」
◆原発から農発へ
減反の 余水生かさむ 発電の
夢の叶いて 賦課金下がる
大分県豊後大野市(旧緒方町)、富士緒井路第2発電所。取水槽から発電所に下る山道には、用水路と発電所への感謝の念が刻まれた歌碑が建立されている。
東京電力福島第一原子力発電所の事故による被害が深刻化するなか、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなど、再生可能エネルギーで発電した電力の全量を、電気事業者に一定期間、一定価格で買い取る義務を課す「再生可能エネルギー促進法」が成立した。
この法案の成立を受け、ソフトバンクの孫正義氏が、数百億円を投資してギガワットクラス(1ギガワットは100万キロワットで、原子炉1基分に相当する)の太陽光発電施設を建設する計画を発表し、マスコミはこれを大きく報道しているが、本誌と同日発売の『季刊地域』7号の特集は、農家、集落、農協、土地改良区、自治体による中小水力を中心とした「いまこそ農村力発電」だ。
▲目次へ戻る
大正の通水開始と同時に
発電を開始した土地改良区発電所
農山村における小水力発電の歴史には、これまで3回の画期があった。1回目は発電事業の黎明期である明治・大正期であり、2回目は昭和27年(1952年)制定の「農山漁村電気導入促進法」を受けた昭和30年代、3回目は減反政策の開始とオイルショックを受けて、農業用水の余水活用策として水力発電所が建設された昭和50年代である。
冒頭の豊後大野市富士緒井路土地改良区(「井路」とは用水路のこと)には、第1、第2の2カ所の発電所がある。
富士緒井路開削の歴史は慶応3年(1867年)の大干ばつにまでさかのぼるが、実際に起工式が行なわれたのは明治四十四年。幹線水路総延長15kmのうち隧道が70カ所、10.5kmにもおよび、ダイナマイトや機械力のない時代の手作業による開削は困難をきわめた。
大正3年(1914年)の井路通水と同時に発電を開始した第1発電所の有効落差は25.5mで出力200キロワット。電気そのものが普及していなかった当時、発電所建設をめざしたのは、井路より標高の高い地域に電動ポンプで揚水し、開田を進めるためだった。また近くの竹田市に、明治33年(1900年)、電力会社「竹田水電」が設立されていたことも影響した。西南戦争で町が焼かれた経験から町に防火水道が引かれ、その水道から川に落ちる水の落差10mを利用して水力発電を行なうため、県内に先駆けて商家や医師が設立したもので、60キロワットの発電機を設置して夜間は電灯用の電気を、日中は精米用の電気を供給していた。当時は町でも村でも電気は地域でつくるものであり、大分県では第二次大戦中に九州電力に統合されるまで、地域ごとに四十数社の電力会社があった。
第1発電所による揚水と灌漑は昭和に入るまで実現しなかったが発電は順調で、「水利組合の経営を助けるために電力を売り、財源に充てよう」と、大正10年(1921年)に株式会社「富士緒電灯所」として、周囲の集落に電気を供給し始めた(昭和11年からは電力会社に売電)。
戦後、第1発電所は機械の老朽化と人件費増大のために廃止か改修かの議論が重ねられたが、昭和52年(1977年)に総額6500万円をかけて改修工事に着工、出力380キロワットに増強し、遠隔操作による無人化で再び経営を軌道に乗せることができた。
一方で同時期の土地改良区には水路改修工事のために約10億円の借入金があり、その返済や、減反政策による賦課金対象面積の減少のため、10a当たり1万8000円の賦課金を3万円に値上げしなければならない事態となっていた。その打開策として、第1発電所改修による採算性向上の実績を受け、幹線水路末流の落差100mの地形に着目して計画されたのが第2発電所建設である。
第2発電所は昭和58年(1983年)に総事業費7億6700万円で着工、翌59年に竣工した(最大出力1500キロワット)。第1、第2合計の年間売電額は推計約1億2000万円となり、土地改良区はその収入を借入金の償還に充てるとともに、冒頭の歌碑にあるように、賦課金を昭和60年には8000円に、平成12年には2000円に軽減した。さらに売電収入によって毎年水路を改修して隧道以外の水路の90%を有蓋化し、豪雨時の土砂流入を防ぐことができるようになった。発電所建設のための資金は、25年で償還し終えた。
この特集には、標高1400〜1700mの祖母傾山系に富士緒井路と同じ水源をもつ豊後大野市の長谷緒井路発電所、宮崎県の日之影発電所も登場する。いずれも江戸時代末期に発案され、明治・大正・昭和初期にかけて開削された農業用水を利用して昭和50年代に建設された土地改良区の発電所で、長谷緒井路は落差173m、出力1300キロワットで売電収入年間6000万円を得、日之影は落差209m、出力2300キロワットで1億3000万円を得て、農家の賦課金を大幅に軽減している。
▲目次へ戻る
農村の小水力発電を支援する企業
一方、中国5県(広島・岡山・鳥取・島根・山口)には昭和20年代から30年代に94カ所の小水力発電所が建設され、うち54カ所が現在も健在である。これに大きく寄与したのは昭和27年に議員立法で制定された「農山漁村電気導入促進法」だ。この法律により通産省は売電方式による小水力発電の規制を緩和し、農林省は農林漁業金融公庫から建設費の80%を貸し出すことになった。これは元利均等償還25年という優遇措置で、小水力発電の建設資金確保に大きな道を開いた。
この法律の制定を働きかけたのは、当時の電熱温床による米増産の電源には農業用水路や小河川を利用した小水力発電が最適と考え、中国電力の要職を辞して昭和22年に地域の水力発電を支える「イームル工業」(本社東広島市)を設立した織田史郎(1895〜1986)だった。イームル=EAMLの社名は、electric(電気)のE、agriculture(農業)のA、machine(機械)のM、life(生活)のLからなり、「小水力発電で農業を支え、農家の生活を向上させる」という織田の想いが込められている。
同社は、中国地方の小水力発電所(出力50〜500キロワット)の大半(74カ所)を直接受注建設するとともに、電力会社への売電価格交渉の仲介も行なった。
徹底した現場主義の織田は全国の5万分の1地図1255枚すべてを購入し、各地を歩いて発電可能地点を計算したという。調査対象は、大規模発電所の開発可能性がある大河川を避け、有効落差10〜150m以内の出力10〜300キロワットの範囲に限定していた。織田は、「小水力の使途は大水力のように大都市や工業地帯の大需要を対象とするものではなく、農村の小需要を地元において供給しようとするものであるから、使用効率が非常に高く、農村の需要電力を大水力に依存している従来の非能率的なやり方と比較にならない利益がある」と語っていたという。
▲目次へ戻る
地元住民が運営する農協発電所
1950年から1967年までの18年間にイームル工業が支援し、建設された農山村の小水力発電所は73カ所。そのひとつ島根県奥出雲町(旧仁多町)三沢地区(人口720人・254戸)の出力90キロワットの三沢小水力発電所は、昭和32年(1957年)の稼働開始。建設当初の目的は、地域の産業振興を図り、住民の経済発展に併せて無点灯家屋を解消することにあったが、発電所建設には多額の資金が必要で、当時の村の財政事情では困難だった。そうしたなか、農山漁村電気導入促進法の融資対象が「営利を目的としない農林漁業団体」であったことから、旧三沢村農協が発電所の経営主体となることで着工可能となった。建設費用は1866万円。うち7割は農林漁業金融公庫からの借り入れでまかなったが、残りは地区の農協理事の借入金や、農協組合員からの出資金(1口200円で1万1039口、合計約220万円)が充てられた。
1957年の発電所の稼働以降、運営のすべては農協役員(1962年合併の仁多町農協)に委ねられてきた。だが、創業以降の売電料の据え置きや運転員の人件費上昇で、1975年には100万円の赤字を出し、経営の合理化が求められることになる。
そこで82年、旧三沢村の10の自治会代表で構成する「三沢小水力発電運営委員会」が、農協と業務請負契約を締結。以後、運営は地元住民に任されることになった。
現在は1993年に合併したJA雲南から年間500万円で運営委員会が運営業務を受託。売電収入と請負料の一部を使って、自治会集会所の電気料助成(5万5000円)や、地区の文化活動を行なう福祉振興協議会への助成(25万円)を続けており、その他にも地元の小学校の備品購入などに充てるなど、さまざまな地域振興策の財源となっている。なかでも2002年に発足した農産加工所「味工房みざわ」へは、売電料と委託料の一部から、これまで合計400万円ほどの助成金を出してきた。
味工房取締役の田部和子さん(68歳)は、「発電所の助成金には助けられています。これまでも圧力釜や麹の発酵機、冷凍ストッカーなど、機器の購入に使わせてもらいました。こうした設備投資ができたおかげで、農家の手取りを増やす農産加工の手伝いができるのです」と語る。
▲目次へ戻る
原発とは真逆の農発の思想
こうした九州地方の土地改良区発電所、中国地方の農協発電所の例をみていると、この農家、農村の力による発電、すなわち「農発」は、つくづく原発とは真逆の思想に立つものだと思い知らされる。
原発の寿命は当初30年で設計されていた。しかし経済性を重視した延命を重ねるうち福島第一原発の事故は起きた。また、事故が起きなくても、すべての原発は廃棄物、使用済み核燃料、廃炉の問題など、ことごとく問題の解決を先送りにして運転されており、たかだか1、2世代の経済的繁栄のツケは、未来永劫子々孫々に回される。
一方、土地改良区や農協の発電所の多くは、江戸末期から昭和初期にかけての先駆者たちがひたすら地域と子孫の繁栄を願って開削した用水路を生かしたもので、開削に私財を投じた先駆者のなかには困窮して故郷を離れた一族も少なくないという。しかし、その水路を生かした発電事業のおかげで、冒頭で紹介した歌碑のように、現代を、そして未来を生きる子孫が恩恵を享受する。
原発と農家・農村力発電が真逆であるのはそれだけではない。原発のエネルギー源は地球上の特定地域に偏在する有限かつ希少資源のウランだが、農家・農村力発電のエネルギー源は普遍的に存在する無限かつ希薄資源の「雨」である。「雨は地上に降ると、地形のひだに集まり、せせらぎとなる。小さなせせらぎは沢となり、沢が集まり渓谷となり、渓谷が集まり川となる。単位面積当りのエネルギーが薄い雨粒が、地形と重力によってしだいに集積され、濃いエネルギーとなっていく」(1)。「雨」という希薄資源の「地形と重力による集積」を、人の力が助けるのが農業用水であり、それは農業の本質にもかかわることだ。「『農業とは生きものの力を借りて、再生可能な地球上の希薄資源を集め利用する営みである』、この点が居座りで有限の資源を使っている工業との基本的なちがいなのです」(2)。
(1)�小水力利用推進協議会編・オーム社刊『小水力エネルギー読本』
(2)�西尾敏彦著・農文協刊「自然の中の人間シリーズ」[農業と人間編](1)『農業は生きている――三つの本質』
▲目次へ戻る
農家・農村の発電はむしろ「本業」「本流」
「いまこそ農村力発電」で茨城大学農学部の小林久教授は、水力は「不確実な予測しかできない状態で海上にまで広く展開するような風力発電や、あらゆる土地に敷き詰めることを前提とするような太陽光発電、あるいは深々度まで掘削する地熱発電のような『大風呂敷の開発』を語ることができない。逆説的な言い方をすれば、小水力は推計に見合った開発が確実に見込める堅実な再生可能エネルギーといえる」と述べている。さらに「水力は、水が豊かで、地形の起伏が大きい地域で包蔵水力も実際の開発量も多い。小水力の適地も同様のところである。先人たちは平地や台地を耕し、丘陵地や山麓まで拓き、さらに勾配が急な山地まで水が容易に使え、水を引くことのできる限り谷沿いに集落をつくって農地を拡大した。拡大の限界が、サト(里)とヤマ(山地森林域)の境界である」「つまり、『限界集落』と後ろ向きに表現されることが多いサトとヤマの境界部(里のフロンティア)こそ、小水力開発に適している」と述べ、環境省が開発余力(導入ポテンシャル)として推計した1000キロワット未満の1万8756地点の多くはサトとヤマの境界に近い山間地域に位置しているはずであり、「小水力は農山村地域、とくに水源域に近い山間農業地域の集落においてこそ、最初に開発すべき再生可能エネルギー」だと述べている。
電源別の発電コストは、水力がもっとも高く、1キロワット時11.9円、ついで石油火力10.7円、LNG火力6.2円、石炭火力5.7円、原子力5.3円とされている(総合資源エネルギー調査会電気事業分科会コスト等検討小委員会資料による。むろんこの原子力のコストには、事故処理費用や使用済み核燃料、廃炉等のコストは含まれていない)。しかし、九州の土地改良区発電所、中国地方の農協発電所は、10円以下と推定される売電単価で発電所建設のための借入金を返済するだけでなく、改良区の賦課金を軽減し、地域の農産加工所に助成金を出し、また、地域にさまざまな雇用をつくりだしている。それが可能だったのは、たとえば富士緒井路では総延長15km、長谷緒井路では21.8km、日之影ではなんと35kmにもおよぶ用水路が先人の無償の努力によってすでに完成しており、新たな取水堰や導水路の建設が不要だったからだ。
農家・農村の発電は、農業のかたわらの「余業」ではなく、ある意味で「本業」であり、第二次大戦下の国策による電力会社への統合がなければ、日本における発電事業の「本流」でもあったのだ。
▲目次へ戻る
原発から農発へ
東電福島第一原発事故、再生エネ法の成立を受け、農山村の小水力発電は、4回目の画期を迎えている。その画期とは、原発が象徴する少数・中央の専門家管理の大規模集中型エネルギーから、多数・地元の住民管理の小規模分散型への転換の画期ともいえる。
小林教授はこう続ける。
「大規模集中型電力システムは、中越沖地震の柏崎刈羽原発や東日本大震災の福島第一原発の例をみるまでもなく、災害に対してきわめてもろく、リスクが桁違いに大きい。また、福島第一原発の処理に地元がまったく関与できないという事実が示すように、地域の技術・人材や意思決定を排除して、集権的になりやすい。さらに、これがもっとも大きな罪かもしれないが、資源が生み出される環境や生産の現場を壁の向こうに追いやることで私たちを無知にさせている」
「これ対して、小規模分散型システムは地域の技術や人材を活かすことができる。さらに、住民や身近な関係者で、地域の環境や文化を、あるいは整備や管理を決めたりすることができ、一般的に分権的な意思決定を行ないやすい。このように、分散型は発電にも地域住民が直接かかわれる機会を提供することができる。小規模分散型エネルギーシステムは、私たちを無知にする危険性が少なく、むしろ地域の主体性を活かしてくれる。『地方分権』『地域主権』の実現は、行政や予算の地方への移譲だけではなく、地域が暮らしや産業にかかわる社会構造を、主体的に編み直すものでなければならない。地域性を活かした小水力などの再生可能エネルギー生産は、その実際の取り組みであり、エネルギーの未来と農山村の再生という『地域主権』に向かう具体的な第一歩でもある」
福島第一原発事故は、原発と農林水産業は根本的に共存できないものであることをあらためて明らかにした。避難生活や農産物・土壌の汚染、風評被害に対する補償要求は当然のことだが、ここでは一歩進み、「原発から農発へ」への転換を農家・農村・農協が主導すべきときではないだろうか。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
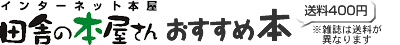
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2011年11月号』
特集:痛快!農家の水&エネルギー自給
緑肥稲作最前線2011/「飽差」でハウスの湿度管理/果樹のポット栽培/キクラゲの原木栽培に挑戦中/畜産 大麦つくってエサ代三割減らしたぞ/味も色も長持ち紅ショウガ・大学イモ/クズ米の流通がモンダイだ/シカを解体する ほか。
[本を詳しく見る] |
 |
『季刊地域7号 2011秋』農文協 編 特集:いまこそ農村力発電
続・東北はあきらめない/復興と脱原発から考える〈生命・自然・労働〉 ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『現代農業 2011年07月号』農文協 編 特集:痛快!農家の水&エネルギー自給
農家は作物をつくって大災害を乗り越える/脱原発・脱経済成長の未来へ/かん水、何時にしてますか?/今年は出穂40日前診断で「うまい米、もう1俵!」/激夏ミカンの水管理/トマトの葉挿し・子葉挿し/野山のもので健康 ほか。
[本を詳しく見る]
|
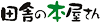
|







