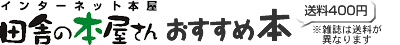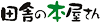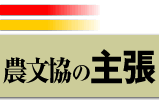 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
2012年8月号
|
「人・農地プラン」を農家減らしのプランにしない 目次 『現代農業』の兄弟誌『季刊地域』10号の編集を終えた。今回は「『人・農地プラン』を農家減らしのプランにしない」という特集を組んだのだが、編集過程で感じたことなどを書いてみたい。 「人・農地プラン」特集を企画「人・農地プラン」のことを初めて耳にしたのは昨年の秋くらいだったろうか。最初は何だかよくわからなかったのだが、どうも気に入らないとは思った。TPP参加検討論議の中で出てきた「強い農業」志向が背景にあるようだったし、「平地で20〜30ha、中山間地で10〜20ha経営が大宗を占める農業構造」にすれば農村の疲弊・高齢化問題が解決する、と思っているみたいなのも気に入らなかった。 年が明け、プランの中身や要件についての情報が詳しく入ってくるにつれ、「これは、むらから農家を減らす方向なのでは?」との思いが強くなった。大ざっぱには、以下のような内容の政策だという。 (1)地域農業マスタープラン(人・農地プラン)をたてる (2)農地集積協力金 (3)青年就農給付金 現場では(3)の青年就農給付金が話題を集めていたし、集落みんなで将来のヴィジョンを話し合うのはとてもいいことだ。「気に入らない」と言っていても世の中はどんどん動き始めるはずなので、『季刊地域』編集部は6月30日発売の次号で「人・農地プラン」の特集をやることにした。春先からさっそく取材開始だ。 とはいうものの、まだプランは呼びかけの段階だ。実際にプランを活用してむらづくりに成功している先進事例があるわけではない。しかたないので、これまで「人と農地の問題」と格闘し、その集落なりの担い手像をつくってきた人たちに、このプランをどう見るかを含めて話を聞いてまわった。 島根・おくがの村で 「むらが続くための組織じゃろう」島根県津和野町の農事組合法人おくがの村代表・糸賀盛人さん(64歳)の話は強烈だった。おくがの村は創立25周年を迎える歴史ある集落営農組織で、糸賀さんは、集落営農界ではカリスマ的存在感を持つ人物だ。その晩はお酒が入っていて、ますます舌好調。
山口・うもれ木の郷で 「法人は儲けを増やしたってしょうがないんです」「集落営農はむらが続くため、地域を守るためのもの。儲けを目的にすると間違う」。この考えは、隣の山口県阿武町・農事組合法人うもれ木の郷でもまったく同様に聞くことができた。うもれ木の郷は全部で約85haを集積している四集落一農場だ。
うもれ木の郷のことは先月の本誌7月号348ページからの記事でも紹介したが、法人の野菜部門はプール計算ではなく、農家一人一人のやる気を引き出す独立採算方式。努力してホウレンソウをたくさん収穫すれば、その分その農家の手取りが増えるシステムなのだが、おかげで法人のほうには野菜部門からの収益はほとんどなし。いいのか?と思ってしまうのだが、「いいんです。野菜をつくって地域の農家が農業で食っていける地域になる。そのことが重要なんです。何のための集落営農組織なのかということを、常に考えてないと間違ってしまいます」と田中事務局長の考えは一貫していた。 宮城・KAMIXで 「農業経営じゃダメ農村集落経営を考えないと」続いて、宮城県加美町の農事組合法人KAMIXの近田利樹さん(54歳)も、「農村集落経営」ということを言った。「農業経営」だけを見るのではダメで、農村集落全体の暮らしも含めて考えていかなくては、という意味だ。
あちこちの現地取材ではっきり見えてきたのは、むらは「人を減らしての効率的な農業」をやりたいとは思っていないということだ。集落営農でなく、個別経営の担い手型大規模農家にも話を聞いたが、「自分たち大きい農家だけが生き残るような形では、むらは維持できない」という意見は共通していた。人と農地の問題を真に解決したいと思ったら、むらに住む人一人一人が、やり甲斐を持って農に関わっていくためのプランを、みんなで考える必要がある。 農水省経営局で 農業は「産業」でなくてはならないか?農水省にもインタビューに行ってみた。人・農地プランの担当は農水省の中の経営局。壁のポスターに「人・農地プラン 農林水産省は本気です」と書いてあるのにはビックリした。 彼らもたしかに本気で日本農業のことを考えて、よかれと思ってやっている立派な人たちなんだとは思う。ただ今回、考え方の根本的な違いを認識することはできた。「むらの暮らしを守りたい」ことを一番に考える農家の感覚に対して、人・農地プラン政策を推進する人たちの感覚はあくまで「経営体作り」。農業を一つの産業として成立させる――そこからしか未来は拓けない、と固く信じているようだった。だからプラン作りはどうしても、「中心となる経営体」と「それに協力する人」という「農家の色分け」が必要になってしまう。 「産業として自立する農業」というと、何か聞こえはいいような気もするが、先のおくがの村の糸賀さんはこうも言っていた。
むらはたかだか30年企業では困るのだ。代々受け継いできたむらを、次の世代にも、そのまた次の世代にも受け継いでいってもらいたい。それさえできれば、人と農地の問題は解決で、別にそんなにバカ儲けするむらにならなくたっていいのだ。トヨタみたいなむらを全国津々浦々に作ることが目的ではないとしたら、何が何でも産業として経営体として成功する方向を目指さなくとも、地域のみんなが楽しく平和に静かに暮らしていける道を考えるプランでいいのではないか? 青年就農給付金支給は、むらに権限があるところで青年就農給付金がすごい人気だ。だがプランを立てないことにはこの給付金ももらえないので、よく話し合いもせず、とりあえず市町村全体で一括してプランを立てて、新規就農者を「中心となる経営体」の名簿に並べてしまおうという動きもあちこちで見られる。 これについては農水省の担当官も「そういうことをすると、あとで苦労しますよ」と少々嫌みを言っていた。しかし希望者多数で予算額オーバーの場合、いったいどうなってしまうのだろうか? 聞いてみると、「当然国としての予算枠があるので上限はあります。それでも枠を超える場合は、担い手がいないところに就農する人、経営の目標が高い人、おカネがかつかつで支援がなければ離農するおそれがある人などは優先してくださいね、ということは県に伝えています」とのこと。 ということは、なんらかの条件で選ぶということがあり得るわけだ。 「はい。子ども手当のようなものとは違いまして、条件が満たされればみんながみんなもらえるというものではありません。……地域で育てるというところが非常に大事だと思っていまして、地域の協力も得られないところにポツンと入っていって、なじめず、土地も借りられずにやめていくという例があるわけですね。技術的な問題もわからないまま、誰にも聞けないとかですね。そういうことがあってはよくないので、地域でちゃんとこの人を育てようという合意のもとにやっていっていただきたい。プランにのせるのが、たんにこの給付金をもらうための手続きだと思われると非常に心外です。地域としてその人を育てていく、そういう人に給付金を出すという考え方なんですね」 この辺り、農水省側の希望により『季刊地域』の記事からは削除した部分なのだが、こちらとしては妙に納得できてしまった。青年就農給付金は新規就農者手当みたいなものではなくて、むらの側で「この人はむらに必要だから、ちゃんとみんなで育てよう」と決めるもの。それがプランへの位置づけであり、その「むらからの推薦」がもらえない人は、150万円はもらえない。青年就農給付金の実質の決定権は、むらにあるということのようなのだ。 記事では大分県豊後大野市の二つのむらが新規就農者を受け入れている様子を取材した。一カ所は研修終了後に若者が定着し、郷土芸能の後継者にもなってむらに溶け込んでいる地域だが、すぐ近くのもう一カ所では若者が来てもなかなか定着しない。違いはどうも、研修中から「むらに住むこと、むらの行事に参加すること」を条件にしているかどうか、などにありそうだ。 農業はむらと結びついて初めてある。農業を「産業」として、むらの暮らしから切り離したのでは、きっと続かない――青年の問題からも、そう感じる記事となった(『季刊地域』10号「青年就農給付金で『むらの後継者』は育てられるか」参照)。 大学で プラン入口は農地ではなく、暮らしから東京大学の安藤光義先生にもお話をうかがった。安藤先生は2007年、担い手のみに助成を絞った品目横断的経営安定対策の時に「選別政策を換骨奪胎して、むらの論理で補助金を活用する」ことを提唱した人だ(本誌連載「『集落営農』とは何か」2007年1〜5月号参照)。お会いしてみると、学者の先生なので話がどうしても抽象的になってしまうのだが、その分、少し大きな気持ちで巨視的にむらのこと・農業のことを、とらえられたような気がした。
安藤先生は、「落ちているおカネは拾ったほうがいい」ので、人・農地プランがたとえ気に入らなくても補助金は上手に利用するのがよい。そしてせっかくなので、自分たちの集落の羅針盤、現代の「村是」のようなものをつくっていく機会としたらよい、と考えておられるようだ。
農家減らしにならない「人・農地プラン」をたてる力をむらはきっと持っている――『季刊地域』10号の編集を終えて今、そんなふうに感じる。 (農文協論説委員会) |
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2012年8月号』
特集:遅出しで当てる |
 |
『季刊地域10号 2012年夏号』農文協編 特集:「人・農地プラン」を農家減らしのプランにしない/「人・農地プラン」について思うこと/早わかり「人・農地プラン」/新人記者A子 農水省へ行く/中国四国地方で一番乗りの「人・農地プラン」を拝見/「人・農地プラン」を地域農業に役立たせるには/おくがの村の糸賀盛人、酒を呑んで大いに語る/その1―東日本型の集落営農/その2―大規模稲作農家/その3―西日本型の集落営農/そしてまた、むらはしたたかに政策とつきあうだろう/青年就農給付金で「むらの後継者」は育てられるか/「担い手2人30ヘクタールび経営体が8割」をめざす ほか。 [本を詳しく見る] |
 |
『地域農業の担い手群像』田代洋一 著 TPP対応型の政府・財界の構造政策を排し、むら的、農家的共同としての構造変革=集落営農と個別規模拡大経営&両者の連携の諸相を見る。併せて世代交代、新規就農・地域農業支援システムのあり方を提案。 [本を詳しく見る] |
 |
『地域農業の再生と農地制度』原田純孝 編著 2009年6月、農地貸借を自由化する農地法の大改正が行われ、さらに所有権取得の自由化にまで議論をすすめている。しかし、法人企業等の参入が地域や農業再生の打ち出の小槌であるはずはない。いま必要なのは、地域に根差し、地域の将来に対して責任をもつ地域農業の担い手をどう確保するかである。農地制度は、そこに向かう地域の努力を阻害するものであってはならない。本書は農地制度と利用の変遷と現状を押さえた上で、各地で地域農業の維持と再生に向けて実際に行われている多様な取組を紹介しつつ農地利用、保全・管理のありようを展望 [本を詳しく見る] |
 |
『進化する集落営農』楠本雅弘 著 「集落営農」とは、農業経営や地域社会がかかえる問題を解決し、人びとがはりあいをもって働き、活き活きと住み続けることができるよう地域住民が話しあい、知恵を出しあう協同活動である。必要に応じて自発的に組織されるので、本来多種多様な組織形態と活動実態をもっている。国の構造政策に対応するのが本旨ではないのである。多様な集落営農は試行錯誤と経験を積み重ねて柔軟に進化し、「地域の再生・活性化」と「効率的農業生産」とを両立する「地域営農システム」としての大きな可能性を備えるに至った農地・労働力・資本・情報の新しい結合体である。農村経済更生運動以来の歴史、政策の流れも整理しながら、全国各地の、農協も含めた具体的な実践事例を紹介、その意味と未来を論じる。 [本を詳しく見る] |
| ■前月の主張を読む | ■次月の主張を読む |