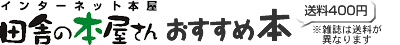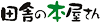新自由主義的復興論を批判する
復興に名を借りた漁業権・農地所有権の自由化を許すな
目次
◆規制緩和路線に沿った宮城県の復興計画
◆集約化とは「あきらめる」人をつくること
◆経団連の火事場泥棒的「復興・創生」プラン
◆お門違いの高齢者農業・農地法犯人説
◆日本的、農家的構造変革の息吹
◆農地をむらから切り離してはならない
▲目次へ戻る
規制緩和路線に沿った宮城県の復興計画
東日本大震災から、はや5カ月が経とうとしている。
被災地の方々が復興に向けて必死に歩み出しているなかで、気になることがある。
復興を好機とみて、漁業や農業の規制緩和を進めようという動きがあからさまになってきたことである。
その典型が、村井嘉浩宮城県知事がすすめようとしている水産業の規制緩和=「民間参入を柱にした水産復興特区構想」だ。「宮城県震災復興基本方針(素案)」は、被災地を単なる「復旧」にとどまらず、県の農林水産業・商工業・製造業の在り方を抜本的に「再構築」するとし、水産業については「水産業集積拠点の再構築、漁港の集約再編及び強い経営体づくりを目指」すとしている。この基本方針を引っさげて、政府の復興構想会議に乗り込んだ村井知事は「漁業の株式会社化を大がかりにやったらどうだろうか」と提案し、沿岸漁業への民間参入や資本導入を図る「水産業復興特区」をぶち上げた。具体的には「県内に約140カ所ある漁港を3分の1から5分の1程度に集約する」「地元漁協に優先的に与えられる漁業権の枠組みを緩和し、国の資金で水産関連施設や漁船の整備を行い、その後漁業権を漁業者や民間企業の資本を活用した会社などに移す」(「日経」5月11日付)というものである。
こうした村井知事の構想は、宮城県漁協をはじめとした漁業関係者から被災地漁民の意向を無視したものだと激しい反発を招いたが、知事はこうした意見を一顧だにしない。
「宮城県震災復興基本方針」は野村総研の全面支援を受けて作成したものであり、県震災復興会議にも野村総研顧問や三菱総研理事長が名を連ねている。財界系シンクタンクの意見を丸呑みすることは、日本経団連や経済同友会の復興への提言(後述)と足並みをそろえることである。
▲目次へ戻る
集約化とは「あきらめる」人をつくること
財界やその代弁者である政治家・学者は、何かというと第一次産業の大規模化・集約化、民間活力の導入を口にする。大規模化・集約化というと聞こえはいいが、漁業や農業を続けることを多くの人があきらめないかぎり、大規模化・集約化はすすまない。漁港を3分の1なり5分の1にしたら、多くの漁民は漁業を捨てなければならないのだ。これは復興といえるのだろうか。そうではなくて、漁業や農業をあきらめる人を一人でも減らすことが、第一次産業の復興のかなめなのではなかろうか。
『季刊地域』6号「特集 東北はあきらめない!」に登場した岩手県宮古市の重茂漁協は「漁師を一人も地域の外に出さない」を目指して復興を進めている。重茂地区には12の漁港があり、天然と養殖のワカメとコンブ、磯漁のウニ、定置網のサケなど豊かな漁業資源に恵まれている。重茂の人々は魚付林として広葉樹とアカマツの混交林を守ることでこの資源を維持してきた。
東日本大震災による大津波で組合員が所有していた約800隻の船はほとんど流されたなかで、重茂漁協では無事だった船、直せば使える船はすべて漁協が借り受け、漁協が所有する新しく造った船とともにすべてそれを一定期間組合員に貸し付けて共同で使い、仕事も分配、収益も分配する仕組みをすすめている。新造船にかかる費用は協業船では船の購入費は国と県、漁協が3分の1ずつ負担する。
6月には、津波にもかかわらず例年どおり成長した天然ワカメから漁を再開。漁には組合員のいる約400世帯中約150世帯が参加。漁船数が不足しているために、小型漁船一隻に数世帯の漁師が相乗りし、ワカメを収穫した。今回のような大被害のもとでは、それぞれの漁民が養殖設備や船を再建、購入するのは二重ローンに陥ることになる。漁協を中心にした協業化は必然だが、それは宮城県の構想のように小さな港をつぶすとか、漁業権を企業に明け渡して、漁民をサラリーマンにするとかいうことではない。
▲目次へ戻る
経団連の火事場泥棒的「復興・創生」プラン
農業についても財界は大規模化、規制緩和路線を押し出しており、漁業で漁業権をターゲットにしたように、農業では農地の所有権がターゲットにされようとしている。
先に触れた日本経団連の「復興・創生マスタープラン」は、その書き出しを「復興の青写真を描くのは、基本的にはそれぞれの地域の住民自身である」としながら、すぐ続けて、「しかしながら、復興は単に元通りの姿に戻すことにとどまるべきではな」く、「我が国にとってモデルとなる力強い農林水産業を戦略的に創生していくことが肝要」として、「(その)視点から復興すべき地域・拠点の認定」をし、「農林水産業の事業資産の権利調整」ならびに「事業主体の体制整備」を行ない、もって農地を集積し「大規模・先進的経営を実践する」と述べている。
要するに「力強い農業」をつくるために「復興すべき地域・拠点」とそうでない地域を分け、小さな農漁家には「事業資産の権利調整」の名のもと利用権や所有権の放棄を迫り、その受け皿として「体制整備」された「事業主体」即ち企業の参入を促す、というものにほかならない。
被災地住民、農漁家が一刻も早い暮らしと生産の再建に苦闘しているときに、これからは企業が入って大きな農業や漁業にするのだからそこのけそこのけ、と言っているわけである。復興の主体は「それぞれの地域の住民自身である」という書き出しは、取って付けた飾り言葉にすぎないことはあきらかだ。
被災地を「復興すべき地域・拠点」とそうでない地域に分ける発想がそもそも驚きだが、震災のどさくさに「権利調整」=利用権・所有権の召し上げを敢行し「先進的経営」をつくるとはいかなる了見か。火事場泥棒とはこういうことを言うのではないだろうか。しかも、震災があって始めてできる「モデルとなる力強い農林水産業」とは、まるで再び三度の大災害を待望しているかの言い方で、その思想、精神は政策論以前の、人の道にもとるものと断ぜざるを得ない。甚大な被災を契機にした「モデル」なるものは、断じて全国に広げられるモデルたり得ないし、「地域の住民自身」を「基本」にした「創生プラン」ではない。
経団連「プラン」はその「おわりに」を「『TPPへの参加』を、震災によって後退させることなく推進する」と締めくくっているが、その一体的狙いに厳重な警戒が必要だ。
▲目次へ戻る
お門違いの高齢者農業・農地法犯人説
財界や菅直人首相が大規模化や強い農業を叫ぶとき決まって持ち出すのが平均年齢65.8歳という日本農業高齢化の実態だ。そして、だからあと10年で農業は成り立たなくなる、だから新しい血、たくましい企業に門戸を開かなければならない、それを妨げている農地法の更なる改正=一般法人への農地所有権解禁が必要だ、それをしないから耕作放棄地がどんどん増える……とくり返す。思いつき総理の名にふさわしい、どんどん飛躍する「論理」である。
第一に高齢化のために農業は成り立たなくなる、という想定は誤りである。そもそも米農家に後継者がいない訳ではない。だが“米では飯を食っていけない”から兼業に出て、定年になったら年老いた親とバトンタッチして米作りに励む。順繰りの世代交代なのだ。「このようにして、高齢農家が次々と新しく生まれてくる。高齢化の構造とは、このようなものである。今後、高齢化が進み、その結果、農業者が激減する、という想定は、こうした実態を見ようとしない者、あるいは、見ることのできない者が犯しやすい誤りである」(森島賢「TPPと日本農業は両立しない」農文協ブックレット1『TPP反対の大義』2010年)。
農地法が一般法人への農地所有権を閉ざしているから企業が参入できず耕作放棄地も増えるというのも事の本質をはきちがえた俗論だ。本当に農業をする気なら「別に農地を所有しなくても借地で十分であり、借地なら農業生産法人方式でもいいし、農業法人の要件クリアが煩わしい、あるいは経営支配を確保したいというのなら、現在では株式会社がストレートに借りることもできるようになった」(田代洋一「日本農業のネックは農地法なのか?」農文協ブックレット2『TPPと日本の論点』2011年)。にもかかわらず所有権に拘るのは農業以外の何か別の目的があるのではと疑われても仕方がないと言わざるを得ない。
耕作放棄地についても、そもそも農外企業が耕作放棄地に進出しないのは採算の見通しが立たないからであって、農地法が関所になっているからではない。
東京大学准教授の安藤光義氏は、全国農業会議所や農水省の各種調査を踏まえ、耕作放棄地が増える原因は直接には高齢化・労働力不足だが、その背景に米価の下落を始めとする「経営環境の悪化」があり、それが「農地需要の縮小となり、耕作放棄地の増加をもたらしている」と指摘している(安藤光義「農地保有の変容と耕作放棄地・不在地主問題」シリーズ地域の再生第9巻『地域農業の再生と農地制度』2011年、農文協)。
その上で安藤氏は長野県上田市の「農地なんでも相談会」や福島県相馬市の、子どもを含む市民を巻き込んだ耕作放棄地削減の取り組みを紹介している。そして、「担い手が不在の地域こそ耕作放棄は深刻な問題なのである。そうした地域では構造再編と耕作放棄地解消を結びつけるのではなく、地域活性化を前面に据えた取り組みのほうが有効ではないだろうか」と結んでいる(安藤、同上論文)。
また右シリーズの続巻である『里山・遊休農地をとらえなおす』(仮題)では日本の里山・草地が生物多様性を維持してきた過程を長い歴史にそってつぶさに振り返りながら、地元農家だけでなく市民と共にそれを維持・再生していく「新しい入会制」=総有を提唱している。農地制度を見直す必要があるとすれば、そんな脈絡でのことだろう。
以上、日本農業の構造問題の一端だが、このように農業や農村の現実は政府や財界が権利調整したり農地法を更に改正すればすむという単純なものではない。そして、単純ではない現実を熟知しているのは、他ならぬ農家農村だ。
▲目次へ戻る
日本的、農家的構造変革の息吹
いま日本の農村は、財界などの言い分とは全く異なる次元から、地域の実情に応じた、いわば「下からの構造変革」を進めつつある。それは地域の中に「あきらめる人」を生み出すのではなく、それぞれの家族構成や年齢、労働力条件に応じ、みんなが持ち味、持ち分を生かした“むらの共同”“むらの知恵”としての「構造変革」だ。
上掲『農地制度』の本の中で大妻女子大学教授の田代洋一氏は、こんにちの農村には農業経営に限らない「多様な担い手」がいて、それが互いに依存し共同しあってむらと経営を守っていると指摘し、次のように述べている。
「グローバル化した時代には『担い手』は『地域農業の担い手』だけにとどまらない。……このように農村の社会的課題が噴出した」時代にあっては、その課題を担う担い手は、「A:『農業経営の担い手』、B:農業経営まるまるは無理だが土日・朝晩なら農機に乗れる『農作業の担い手』、C:農機は危なくなったが水管理・畦草刈りならお手のものという『地域資源管理の担い手』、D:『直売所、地産地消や食育等の担い手』、E:生まれ在所に生き死んでいこうとする者が居てこそ『むら』が守られるという『むら社会の担い手』など、農村社会は住民がそれぞれの『もち味』を活かした『担い手』になることによって初めて定住可能になった。『多様な担い手』論の登場である」。
田代氏のこの論文は上掲書のなかで「土地利用型農業の担い手像」つまりは規模拡大経営について担当し書いたものだが、このテーマに即してもAの「農業経営の担い手」だけでは自己完結せず、B以下すべての「担い手」との連携・共同があって初めて成り立つものであることを明らかにしている。
それは、(法人成りを含む)大規模家族経営にあっては農地の集積はひたすら「待ち」の姿勢であり、黙々と借地をていねいに耕し、あの家なら末永く貸すことができるという信頼感を醸成し、貸し手の農家が年齢や家の事情で行き詰まって農地の買い取りを頼まれれば言い値で買い取る。規模拡大しながら同時に地域農家との共存を願う。農地を丸投げされても手間のかかる地域資源管理はできないからだ。自分の経営を守るためにも地域の農家と共存し、むらを守らねばならない。個人の経営であって単に個人のものではない。日本の農業は「むら農業」なのである。そしてこのような規模拡大は政府、財界がよくするように、あらかじめ何ヘクタールと目標設定されるものではない。A〜Eの多様な担い手の、そのまたむらごとに異なる多様なあり方の関数なのである。
集落営農も同様だ。経理を一元化しただけのプレ集落営農から転作作物の受託のみのもの、水・畦畔管理は地権者に再委託するもの、法人経営体として確立したもの、標高差による作業適期のズレを機械の共同利用でこなす中山間地域の集落営農連合など、その形は集落の数ほどある。それは発展段階ではなく、むらあるいは旧村単位などの「多様な担い手」のありかたを反映した類型差なのである。
こうして「2010年農林業センサスでは5ha以上経営体の農地面積シェアは初めて5割を超えた(00年37%→05年43%→10年51%)。この中には増え続けている集落営農も含まれており、個別経営の規模拡大ばかりではない。いよいよ日本農業はアメリカ型、ヨーロッパ型とは異なる、集落営農という他国に類のない営農主体を含む多様な担い手によるユニークな構造変化に向けて動き出した」。それは「高齢化や過疎化の中で、それに抗するようにして」出てきた「危機と併進する構造変化」であり「新たな挑戦」である(小田切徳美「TPP問題と農業・農山村」前掲『TPP反対の大義』所収)。
かくして明確なことは日本的、むら的構造変革が「多様な担い手」すべての共同ですすめられていることであり、「特定者に農地集積を誘導・強制する構造政策は、農村を知らない財界や一部政府要人の短絡的思考の産物であり、なんら成果をあげていない」(田代前掲論文)ことを悟るべきだ、ということなのである。
▲目次へ戻る
農地をむらから切り離してはならない
このような日本的、むら的農業構造変革の根底には、農地を守ることとむらを守ることを一体的に把握するものの考え方が歴史的に形成されてきたことがあることを忘れてはならない。
同じく『地域農業の再生と農地制度』の著者の一人である早稲田大学教授の楜澤能生氏は、「農地を商品一般に解消してしまうと、農地を農地として維持することができない、というのが少なくとも小農制を歴史として持つ社会の」共通認識であり、だから、「農地を…他の商品とはこれを区別し、一般法とは別途その取引を規制する農地法制」が必要で現に実施してきたのだが、それとは別の次元で「農地を農地として維持するのに不可欠の要素としてむらの維持を念頭に置くという発想、農地をむらと一体的なものとして捉え、この観点から農地制度を構想するという着想は、従来必ずしも意識的には追求されてこなかったように思われる」と自らの課題を設定し、主として大正、昭和、今日に至る「むらと農地」の関係を総ざらいした。
国レベルの立法過程はもとより、全国各地の村や産業組合や各種土地組合などの動向を調べ上げたその結論は、「むらの農地はむらびとの手に、というむらの規範が、農地法制の必要を引き出してきた」ということだった。
「村内耕地ノ村外ニ流出スルヲ防止シ併セテ自作農創定を為サムコトヲ決議」(傍点楜澤氏)した秋田県幡野村を始め多くの実例を挙げ、自作農創設がじつはむらの農地をむらに留め置く施策の一環として位置づけられていたこと、なぜならそれは、むらの土地がむらから流出(所有権が移動)すると、むらの共同性が崩れると観念されていたからであることを、豊富な史料で明らかにしている。
かくして農地管理は、「農地の権利移動のみを意味するのではなく、地域にとって望ましい農地利用一般の実現を課題とする。農地の作付協定、農作業の効率化、合理化のための利用調整等、多様な内容を地域の状況に応じて、地域の自律的な取組みを前提として実現する」ものであり、「農地流動化の加速、流動化率の向上といった、国が設定した目標達成にのみ還元されるものではない」のである。
「むらと農地」を切り離そうとするTPP推進派の新自由主義的復興論を許さず、地域からの「自律的な取組み」を強めることこそ、復興の基本である。�
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
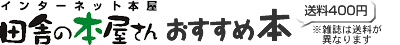
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2011年9月号』
ラクラク秋作業 私の工夫/鮮度保持術/リンゴの葉っぱかじり診断/組み立て式炭化炉/超低投入の草地を三友さんと歩く/わが家の軽トラ活用術/あこがれのドライフルーツ作り ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『地域農業の再生と農地制度』原田純孝 編著 2009年6月、農地貸借を自由化する農地法の大改正が行われ、さらに所有権取得の自由化にまで議論をすすめている。しかし、法人企業等の参入が地域や農業再生の打ち出の小槌であるはずはない。いま必要なのは、地域に根差し、地域の将来に対して責任をもつ地域農業の担い手をどう確保するかである。農地制度は、そこに向かう地域の努力を阻害するものであってはならない。本書は農地制度と利用の変遷と現状を押さえた上で、各地で地域農業の維持と再生に向けて実際に行われている多様な取組を紹介しつつ農地利用、保全・管理のありようを展望
[本を詳しく見る]
|
 |
『季刊地域6号』農文協 編 怒りと決意の飯舘村/だれでもできる復興支援/むらとまち、地域と世界を結び直す/大震災を生き抜いて ほか。
[本を詳しく見る]
|
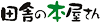
|