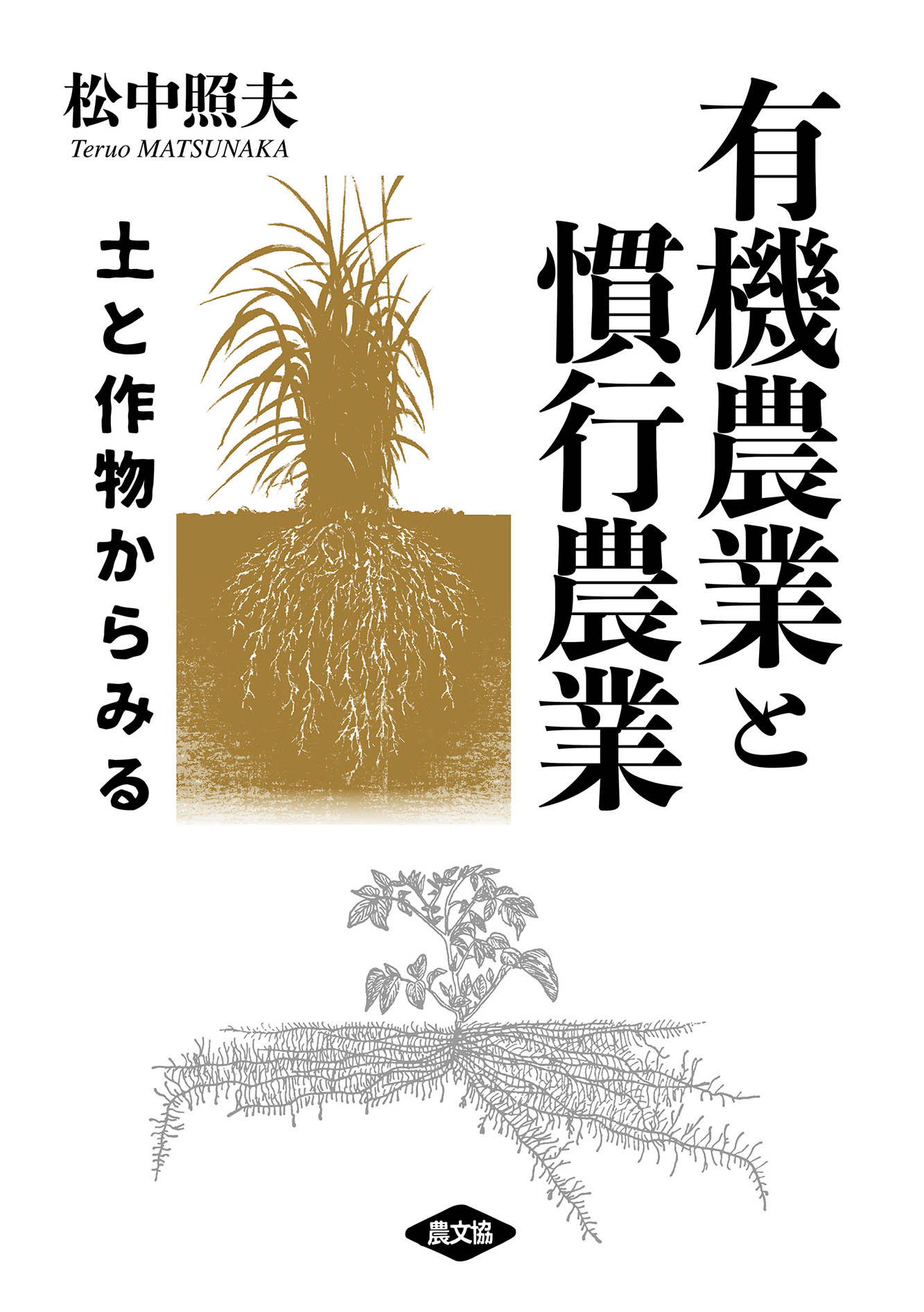主張
広がるオーガニックビレッジ
有機農業の出番だ!
目次
◆有機農業の核心とは
◆イネの自然力を引き出した疎植、への字
◆アイガモが水田の自然力を拡張した
◆イネと水田環境、それぞれの自然力を発見
◆有機農業は本来の農業
いま有機農業の推進に名乗りを上げる市町村が増えている。政府・農水省の「みどりの食料システム戦略」にともない始まったもので、2025年までに100市町村を目指していたのが大幅に前倒しされ、8月末時点で91市町村まで増えている。
今年の夏の猛暑は、地球温暖化対策を自分ごとと認識する人を増やしただろう。本当の「持続可能性」とは何かに世の関心が集まり、有機農業が広まる気運が高まっている。本誌と同時発売の『季刊地域』2023年秋55号(『現代農業』11月増刊号)では「有機で元気になる!」と題した特集で、有機農業推進宣言(オーガニックビレッジ宣言)をした市町村の取り組みを取り上げている。これを機会に有機農業とは何なのか、稲作技術を例にもう一度考えてみたい。
有機農業の核心とは
日本の有機農業にとって、06年12月に成立した「有機農業の推進に関する法律」(有機農業推進法)が画期を成したと言われている。そこには、化学的に合成された肥料や農薬、遺伝子組み換え技術を利用しないことも書かれているが、重要なのは有機農業の基本理念として「自然循環機能を大きく増進し、かつ、農業生産に由来する環境への負荷を低減する」と掲げたことだ。「自然循環機能」については注釈として「農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能」とある。当時、有機農業推進法の成立にふれたこの「主張」欄では、これを担っているのは農家だとしたうえでこう続けている。
「土や作物の自然力は、農家が作物や土に働きかけ働きかえされる(学ぶ)なかで身につけた観察眼や洞察力によって初めて引き出されるものである。無化学肥料・無農薬という前提を据えることで、土や作物、地域の自然力を発見していくというのが有機農業の核心である」(「自給」と「提携」で地域をつくる 「有機農業推進法」が成立――07年10月号主張より)
イネの自然力を引き出した疎植、への字
農家が作物から引き出す自然力の例を挙げるなら、たとえばイネの疎植や「への字稲作」がそうだろう。
1970〜80年代、田植え機の普及は省力化と経営規模の拡大に貢献した反面、病害の多発や冷害などの悪天候に弱いイネを増やした。かつての本葉5〜6葉に育てた成苗の手植えに代わり、初期の田植え機は本葉2〜3葉の稚苗を1株に10本前後、坪70〜80株も植える栽培法を広めた。若苗だからよく分けつするのに、それを密植することしかできなかった。苗が多いと肥料切れが早いので元肥チッソも増やす。これではイネは過繁茂になるしかなく、いもち病などの病気が増えた。ムダに増えた茎を半分近くも減らしながら、ヘトヘトの栄養状態で出穂。そうして残った穂は茎が細くて倒伏しやすいし悪天候にも弱かった。
こんな田植え機稲作の矛盾を明らかにしたのが篤農家の観察眼だ。当時の本誌では1株の植え付け本数を減らす薄播きや植え付け株数を減らす疎植が記事になり、誌面を通じて農家に広がった。また、兵庫県の篤農家・井原豊さんが提唱した「への字稲作」も農家に浸透した。それは初期は茎数が少ない状態で出発して、生育中期に分けつを増やせるような生育コースをたどること、初期から中期にかけて「への字」型に葉色を高めることがイネの自然力を引き出し、倒伏せず安定多収につながる、というものだ。
現在では田植え機の性能向上で、「密苗」のように苗箱1枚の播種量を増やしてもかき取り量を減らして1株の本数を少なくできるようになった。また、用意する苗(苗箱)を減らせるメリットもあり、今や坪当たり36〜40株程度の疎植は珍しくない。それが減農薬と安定多収を実現してきたのだ。
アイガモが水田の自然力を拡張した
イネという作物から水田環境へ視野を広げて自然力をとらえるとどうなるだろうか。その好例は、福岡県の古野隆雄さんを起点に全国に広がった「アイガモ水稲同時作」だ。
最近の本誌では「ホウキング」の古野さんとしておなじみだが、その前には水田にアイガモという新たな仲間が加わるとイネの除草が劇的にラクになることを誌面で知らせてくれた。ただし最近流行りの「アイガモロボット」と違い、本家のアイガモがしてくれるのは除草だけではない。
本誌連載の第1回(90年12月号)に、アイガモ水稲同時作の特徴として古野さんはこう書いている。①じつに愉快に取り組める。②未利用の資源と空間の循環的有効利用ができる。③化学肥料、農薬、除草剤の3点セットに象徴される分断的技術――それは病気とか害虫とか除草とか一つの側面には有効だが、自然の生態系とか生命とかの全体性に対しては対立的――と異なり総合的技術といえる。
アイガモが水田に入ると、厄介だったはずの害虫や雑草はエサに、すなわち資源に変わる。アイガモの効用はじつに多様で、雑草防除、害虫防除、糞による養分供給、中耕(濁り水による養分供給や田面を乾きやすくする)、イネに対する刺激(ずんぐり型の丈夫な姿になる)などがある、とも書いている。
古野さんはこんなことも言っていた。「市販の育苗肥料や特選培土を使用すれば、
古野さんが言う農の楽しさとは、前述の「無化学肥料・無農薬という前提を据えることで、土や作物、地域の自然力を発見していく」ことではないか。アイガモ水稲同時作では、アイガモという生きものが加わって水田の自然力が拡張される。しかもご飯と一緒におかず(肉)もとれる。そんな大発見が楽しくて仕方なかったのではないか。
イネと水田環境、それぞれの自然力を発見
『季刊地域』55号の特集には、有機農業の推進を始めた市町村として茨城県常陸大宮市と岐阜県白川町の事例が登場する。その両方に関わっているのが栃木県上三川町の民間稲作研究所だ。
民間稲作研究所を設立した前理事長・稲葉光國さん(故人)は、農業高校の教諭も務めながらイネの自然を探求した農家だ。その理論は『太茎大穂のイネつくり』という著書(農文協)にまとめられている。稲葉さんの観察眼・洞察力はやはりイネから水田環境へ広がり、『あなたにもできる 無農薬・有機のイネつくり』(農文協)という新たな著書に結実した。
その内容を拾ってみると、たとえばイネの有機栽培の課題である雑草対策は、春の早期湛水と約1カ月の間隔を空けた2回代かきが肝心だ。ヒエは深水栽培だけでも抑えられるが、より厄介なコナギは発芽が遅いため、発芽するのを見極めてから2回目の代かきをする。
それに田んぼから得られる米ヌカやクズ大豆などの有機物施用を組み合わせ、微生物やイトミミズの働きで「トロトロ層」の形成を促進。コナギなどの雑草の発芽生長の抑制とイネへの養分供給に役立てる。多様なミネラルがバランスよく豊富に含まれる米ヌカは、微生物からミジンコ、イトミミズ、害虫の天敵となるカエルやクモまで増やす生きもの循環も生み出す。また、太茎大穂イネの基本である成苗を有機肥料で失敗なく育てるのに、プール育苗との組み合わせを提唱したのも稲葉さんである。
土・水・有機物、そして微生物に始まる生きもの。稲葉さんはそれぞれの自然力を発見し、循環利用し、すでにあった技術を組み合わせ、水田の自然力を総合化することで、いま普及しているイネの有機栽培の土台を築いた。学校給食への有機栽培米の導入で注目されている千葉県いすみ市や兵庫県豊岡市も、稲葉さんのアドバイスをベースにそれぞれの地域条件に応じた栽培技術を組み立ててきた。
有機農業は本来の農業
「みどりの食料システム戦略」は、2050年に耕地面積の25%(100万ha)まで有機農業を拡大する目標を掲げている。それに応じて始まったのが市町村の有機農業推進で、千葉県いすみ市、兵庫県豊岡市、茨城県常陸大宮市、岐阜県白川町、いずれも「オーガニックビレッジ」に名乗りを上げている。今回の『季刊地域』には、有機農業に魅力を感じて「田園回帰」する若者が増えていることや、市町村は有機農業による移住者の増加も期待していることが記事になっている。また、肥料や資材の高騰を背景に、コスト削減の観点から有機農業に期待する見方もあった。
みどり戦略を進める農水省には、IoTやAIを活かしたスマート技術や「幅広い種類の害虫に対応できる有効な生物農薬供給」などトップダウンのイノベーション(技術革新)こそが有機農業100万haのカギ、と見ている節がある。だが、そうだろうか。これらは古野さんの言う「分断的技術」になりかねない。持続可能で楽しい技術はどっちだろうか。
農水省は一方で、今年3月に改定した「生物多様性戦略」という戦略も掲げている。その中にこんな一節がある。「農林水産業は、自然と対立するのではなく、順応する形で働きかけ、上手に利用し、物質の循環を促進することによって、その恵みを享受する生産活動であり、生物多様性が健全に維持されることにより成り立つものである」
ここに書かれている「本来の農業」の先にこそ有機農業はあるのだ。もちろん、有機農業をやりやすい作物とそうでない作物があるだろう。だが「できれば農薬・化学肥料を使わずにつくりたい」と多くの農家は思っている。それは本来の農業の楽しさを知っているからではないか。土や作物、地域の自然力を発見
(農文協論説委員会)
- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。
 現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
現代農業VOICE(YouTubeに移動します)
【主張】広がるオーガニックビレッジ 有機農業の出番だ!【現代農業VOICE】