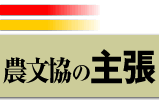 |
|
|
||||||||||||||
| 擾暥嫤僩僢僾亜庡挘亜
1995擭2寧崋
|
|
暷偼夁忚偱偼側偄 崱擭傕巚偄偭偒傝暷傪偲傠偆 乗乗暷嶻捈偺栐傪峀偘怴偟偄惗妶幰宆偺棳捠傪乗乗 仧楌巎揑側戝曄妚偑巒傑偭偨丂嶐擭丄擾壠偼暷傪偨偔偝傫偲偭偨丅乽崙嶻暷傪怘傋偨偄乿偲偄偆徚旓幰偺嫮偄梫朷偵擾壠偼傒偛偲偵墳偊偨丅偲偙傠偑丄婜懸偵墳偊偨搑抂偺儅僗僐儈偺乽夁忚乿乽夁忚乿偺戝崌彞丄乗乗偲傫偱傕側偄榖偱偁傞丅丂傑偢戞堦偵暷偼梋偭偰偄側偄丅嶌嫷巜悢109乮10寧15擔尰嵼乯偺梊憐廂妌検偼1194枩僩儞丄10寧枛偺嵼屔偼崙嶻暷僛儘丄桝擖暷98枩僩儞乮偨偩偟偙偺偆偪庡怘梡偲偟偰巊傢傟傞偺偑15枩僩儞掱搙乯丄偙傟偐傜捠忢擭偺憗怘偄検偲偺嵎丄40枩僩儞傪偝偟堷偔偲崙嶻暷偺嫙媼検偼1154枩僩儞偵側傞丅暷徚旓検傪1000枩僩儞偲偡傞偲巆傝偼154枩僩儞丅惌晎偼150枩僩儞掱搙偺旛拁傪偡傞偲偄偆偐傜丄杮摉偺梋傝偼傢偢偐偵4枩僩儞丄偙傟偼廀梫偺2擔暘偵傕枮偨側偄丅 丂嶌嫷巜悢109偱偙偺悢帤偩丅嶐擭偺傛偆側朙嶌偑懕偔偲偼峫偊偵偔偄丅偵傕偐偐傢傜偢乽夁忚乿偺戝崌彞丄寢嬊偺偲偙傠偙傟偼丄乽夁忚乿仺擔杮偺暷偮偔傝偺弅彫仺桝擖奼戝偲偄偆偡偠彂偒偵崙柉偺悽榑傪桿摫偡傞偙偲傪偹傜偭偨傕偺偲偟偐峫偊傜傟側偄丅 丂偙偺乽夁忚乿愰揱偺崻嫆偵崙柉偺暷棧傟偑恑傫偱偄傞偲偄偆尒曽偑偁傞丅塃偺寁嶼偱偼庡怘梡丄壛岺梡丄儌僠暷丄擾壠徚旓側偳偡傋偰娷傔偰徚旓検傪椺擭暲傒偺1000枩僩儞偲偟偨偑丄嶐擭偼暷偺徚旓検偼尭偭偰偄傞丅怘椘挕偺嵟怴偺挷嵏寢壥偵傛傞偲丄嶐擭7乣9寧偺暷徚旓偼夁嫀嵟戝偺棊偪崬傒傪帵偟丄慜擭摨婜斾偱7.2亾偺尭偩偲偄偆丅偟偐偟偙傟傪傕偭偰丄崙柉偺乽暷棧傟乿偑恑傫偱偄傞偲偼偄偊側偄丅怘椘挕傕崙嶻暷偺晄懌偱僷儞傗傔傫椶偵僔僼僩偟偨棳傟偵丄偙偺壞偺栆弸偑攺幵傪偐偗偨偲暘愅偟偰偄傞丅偟偐偟丄栆弸埲慜偵丄奜暷擖傝偺僽儗儞僪暷傪徚旓幰偑寵偭偨偙偲偑戞堦偺梫場偩傠偆丅暷偺徚旓尭偼丄徚旓幰偑桝擖暷偵傓偐傢側偐偭偨偙偲丄偦傟偩偗崙嶻暷巙岦偑嫮偐偭偨偙偲偺尰傢傟偱偁傞丅側傫傜斶娤偡傋偒榖偱偼側偄丅 丂壽戣偼偙偺堦帪偺暷棧傟傪峆忢揑側暷棧傟偵偟側偄偙偲偱偁傞丅偦偺偨傔偵偳偆偡傞偐丅惗嶻幰偲偦偺慻怐帺恎偑愊嬌揑偵暷傪攧傞偙偲偩丅惌晎偼丄暷傪庣傝擾懞傪庣傞巔惃傕擻椡傕帩偪偁傢偣偰偄側偄丅暷偺斕攧偺帺桼壔丄帺庡尭斀側偳傪惙傝崬傫偩怴怘椘朄偼偄偄堄枴偱傕埆偄堄枴偱傕丄偦偺尰傢傟偱偁傞丅柍愑擟偱偼偁傞偑丄堦曽偱偼丄崙壠偑捈愙娗棟偟側偔偰傕丄惗嶻幰懁偱偆傑偔傗偭偰偄偗傞偲敾抐偟偨丄偲傛偔夝庍偡傞偙偲傕偱偒傞丅 丂偦偆偄偆偙偲偩偐傜丄惌晎側偳偁偰偵偣偢偙偺嵺丄帺暘偨偪偱偆傑偔傗偭偰傒傛偆偱偼側偄偐丅崙壠娗棟偵戙傢偭偰巗応宱嵪偵恎傪備偩偹傛偆偲偄偆偺偱偼側偄丅偳偙偐偵丄偩傟偐偵恎傪備偩偹傞偺偱偼側偔丄帺傜愗傝戱偔丅偦傟偵偼捈愙徚旓幰偲寢傃偮偔偟偐側偄丅 丂偐偔偟偰崱丄暷偺嶻捈偑戝偒偔峀偑傝偮偮偁傞丅暷晄懌偺拞偱丄徚旓幰偺崙嶻暷傊偺偙偩傢傝偑巚偄偺傎偐嫮偄偙偲傕傢偐偭偨丅暷晄懌偺拞偱偙傟傑偱偵側偐偭偨傛偆側徚旓幰偲偺偐偐傢傝傕偁偭偨丅暷偼廩暘偵偁傞丅忦審偼偦傠偭偨丅 丂暷晄懌偺帪偵暷傪憲偭偨徚旓幰偵嵞傃攧傠偆偲偟偨傜乽崱擭偼偄偄傢乿偲抐傜傟偨偲偄偆榖偑偁傞丅峫偊偰傒傟偽摉偨傝慜偱偁傞丅偦偺徚旓幰偼庤偯傞傪偝偑偟偰丄偄傠傫側擾壠偵暷偑側偄偐偲惡傪偐偗偨丅偦偟偰崱搙偼惡傪偐偗傜傟偨擾壠偑乽暷偼偄傝傑偣傫偐乿偲揹榖傪擖傟偨丅偲偄偭偰偡傋偰偺擾壠偐傜暷傪攦偆傢偗偵偼偄偐側偄丅偦偺寢壥偺乽崱擭偼偄偄傢乿偱偁傞丅偦傟傎偳傑偱偵丄崱丄擾壠偼愊嬌揑偵暷傪攧傝巒傔偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅楌巎揑側戝曄妚偑巒傑偭偰偄傞丅 仧傕偼傗擾壠偼尨椏惗嶻幰偱偼側偄丂惛暷婡偑戝曄側攧傟備偒偩偲偄偆丅晉嶳導偺偁傞嬈幰偵傛傞偲丄崱擭偵擖偭偰偐傜偺拲暥偼椺擭偺3攞丄弌壸偑捛偄偮偐偢偆傟偟偄斶柭傪偁偘偰偄傞丅拲暥偼戝婯柾擾壠偐傜偩偗偱偼側偄丅丂帺暘偱惛暷偡傞偲偄偆偙偲偼丄帺暘偱惢昳偵偟偰攧傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅尨椏惗嶻幰偺埵抲偵偲偳傑傜側偄丄枮懌偟側偄丄偦傫側巚偄偐傜丄暷偺懡條側攧傝曽偑偱偰偔傞丅 丂媨忛導偺俰俙拞怴揷偱偼丄抧堟擾嬈妶惈壔偵傓偗丄匑尯暷偱攧傞丂匒惛暷乮敀暷乯偱斕攧偡傞丂匓庰暷傪嶌傝庰憿儊乕僇乕偵斕攧偡傞乮擾彜堦懱偺暷嶌傝乯丂匔庬儌儈偲偟偰導壓偺惗嶻擾壠偵斕攧偡傞丂匘偛斞偲偟偰徚旓幰偵捈愙斕攧偡傞丄偲偄偆5偮偺斕攧愴棯傪宖偘丄幚慔偟偰偄傞丅 丂帺暘偺偲偙傠偱惛暷偡傟偽丄摉慠暷僰僇偑巆傞偑丄俰俙拞怴揷偱偼偙傟傪僉僲僐偺攟梴偵棙梡偟偰偄傞丅暷僰僇偼儃僇僔旍側偳偺婎杮帒嵽偱傕偁傝丄桳婡暷偮偔傝偵傕婱廳偱偁傞丅暷嶻捈偼巚傢偸暃嶻暔傪傕偨傜偟偰偔傟傞丅 丂30擭傎偳慜丄摉帪丄嫤摨慻崌宱塩尋媶強棟帠挿偩偭偨堦妝徠梇巵偑師偺傛偆側嫽枴怺偄巜揈傪偟偰偄傞丅 丂乽擾壠偑攧傞暷偼尯暷偱偁傞偑丄徚旓幰偑攦偆暷偼敀暷偱偁傞丅尯暷傪敀暷偵偡傞偺偼暷壆偱偁傞丅偙偺忬懺偼偄偮偛傠偐傜偺偙偲偐抦傜側偄偑丄偁傑傝偵傕屆偄愄偐傜偺偙偲傜偟偄偺偱丄堦斒偵摉偨傝慜偺偙偲偺傛偆偵巚傢傟偰偄傞丅偟偐偟峫偊偰傒傟偽丄偙傫側晄崌棟側偙偲偑枹偩偵夵傔傜傟側偄偱偄傞偺偼丄傓偟傠晄巚媍偲偡傋偒偱偼側偐傠偆偐丅 丂搒夛偱偼傎偲傫偳昁梫偑側偔丄擾懞偱偼帞椏摍偲偟偰嬌傔偰昁梫側峟偑丄擾懞偵巆傜側偄偱丄暷壆偐傜廤傔傜傟偨傕偺傪擾懞偺懁偱攦偄庢傜側偗傟偽側傜側偄偺偼丄擾壠偲偟偰偼幚偵嬸偐偟偄偙偲偱偁傞丅乿 丂乽偦偙偱巹偼丄擾壠偺偨傔偵傕徚旓幰偺偨傔偵傕丄偦偟偰摨帪偵攝媼嬈幰偺偨傔偵傕崌棟揑偱偁傞偲怣偢傞師偺峔憐傪採彞偡傞丅 丂擾嫤偼憡摉戝婯柾側惛暷巤愝傪拞怱偲偟丄栢偺曐娗巤愝傗敀暷偺曪憰巤愝傪敽偭偨愝旛傪傕偮丅偙偙偱偼擭娫暯嬒偟偰崱悹暷偲偟偰敀暷傪惗嶻偡傞丅敀暷偼戃媗傔偵偟偰丄偦偺戃偵偼柫暱丒梕検摍偲擾嫤柤傪柧婰偟偰攧傝弌偡偙偲偵偡傞丅乿 丂乽偙偺峔憐傪幚尰偝偣傞偨傔偵偼丄尰峴怘椘娗棟偺惂搙婡峔偵怗傟偞傞傪摼側偄丅偟偐偟偙偙偵偍偙側偆怘娗惂搙偵偮偄偰偺榑媍偼丄崱擔傑偱偺怘娗惂搙夵攑榑偲偼堎側偭偨惈幙偺傕偺偱偁傞丅巹偺採埬偼尰峴怘娗惂搙偼偙傟傪慜採偲偟偰懚抲偟丄偨偩偦偺椺奜偺摴偲偟偰丄擾嫤偑偦偺愝旛偱敀暷偵偟偨暷偼丄惌晎偱偼側偔攝媼嬈幰偵捈愙帺桼側壙奿偱攧傝搉偡偙偲傪嫋偡偺偱偁傞丅乮拞棯乯 丂怘椘娗棟偺惂搙偲婡峔偺栤戣偲偟偰偼丄偙偺愝偗傜傟偨椺奜偼丄偦傟偑擾壠丄徚旓幰丄暷壆偺偦傟偧傟偵娊寎偝傟偨尷傝偱揔梡偝傟傞偺偱偁傞偐傜丄怱攝偡傞偙偲偼彮偟傕側偄丅嶰幰偵傛偭偰惙傫偵娊寎偝傟偰丄椺奜偑丄椺奜偱側偄傛偆側幚懺偵側傟偽丄偦傟偙偦傑偙偲偵寢峔側偙偲偱偼側偐傠偆偐丅乿乮亀嫤摨慻崌宱塩尋媶寧曬亁152崋丄1966擭5寧傛傝丄堦妝徠梇挊亀嫤摨慻崌偺巊柦偲壽戣亁乮擾暥嫤姧乯偵廂榐偝傟偰偄傞乯 丂側偐側偐偺戩尒偱偁傞丅30擭傕慜偺巜揈偱偁傞丅30擭慜偲斾傋偰丄忣曬丄棳捠丄慻怐側偳乽帺暘偱暷傪攧傞乿忦審偼旘桇揑偵惍旛偝傟偰偄傞偺偩偐傜丄擾壠帺恎偵傛傞嶻捈傕娷傔偰丄懡條側暷嶻捈偑戝偒偔峀偑傞偺偼丄帄嬌摉慠側偺偩丅堦妝巵偑婜懸偟偨傛偆偵乽椺奜偑椺奜偱側偔側傞乿偺偩丅 丂俰俙拞怴揷偺応崌偼丄惛暷偐傜偝傜偵偮偒恑傫偱丄偛斞傑偱斕攧偟偰偄傞丅乽暷偩偗偑崙撪偱桞1丄弡偑妋擣偱偒傞擾嶻暔偱偁傞乿偲偺娤揰偐傜丄怘昳儊乕僇乕偺儘儞僌儔僀僼偱偼側偔乽僼儗僢僔儏僷僢僋乿傪慡柺偵懪偪弌偟偨丅抧堟偺暷傪丄抧堟偺悈傪巊偭偰悊斞偟偨乽嶻捈偛斞乿偼丄乽傢偑壠偺偛斞傛傝旤枴偟偄乿偲偄偭偨斀墳偑偁傞偖傜偄岲昡偩丅 丂惗嶻偟帺傜徚旓偡傞擾壠偼丄壛岺傕娷傔偦偺嶌暔偺怘傋曽丄惗偐偟曽傪怱摼偰偄傞丅偦偆偟偨擾壠偺惗妶偲媄弍偵巟偊傜傟偰偄傞偐傜偙偦丄嶻捈偺昳暔偼埨慡偱偍偄偟偄偺偱偁傞丅 仧暷嶻捈傪擾懞偺懡師嶻嬈壔偺晲婍偵偡傞丂暷嶻捈偼暷偩偗偵偼偲偳傑傜側偄丅暷傪攧傞偨傔偺嶻捈偑丄懠偺嶌暔傪攧傞忦審傪峀偘偰偔傟傞偺偩丅丂暉壀導慜尨巗偱摿嵧暷偵庢傝慻傓偍曣偝傫偨偪偼丄堦曽偱晛媦強傗栶応偺姪傔傕偁偭偰丄枅寧戞1丄戞3擔梛擔偵乽傆傟偁偄巗乿傪奐偄偰偄傞偑丄摿偵戞1擔梛擔偺偍媞偝傫偑懡偄偲偄偆丅摿嵧暷傪宊栺偟偰偄傞50屗傎偳偺徚旓幰偑1僇寧暘偺暷傪庢傝偵偔傞擔偱傕偁傞偐傜偩丅偦偺偮偄偱偵栰嵷傪攦偭偰偄偭偰偔傟傞丅 丂枅擔怘傋傞暷偺傕偮椡偼戝偒偄丅暷嶻捈偵偼丄懠偺嶌暔偵偼側偄撈帺偺乽偮側偑傝傪峀偘傞椡乿偑旈傔傜傟偰偄傞丅 丂嶳宍導偺抲帓嶻捈僙儞僞乕乮嶲壛擾壠偼栺200屗乯偱偼丄摿嵧暷偵懳偡傞徚旓幰偐傜偺抣壓偘梫朷偵懳偟丄嶻捈昳栚偺奼戝偱懳墳偟偨丅憡庤愭乮搒怑惗嫤乯偺梫朷偼10僉儘600墌偺抣壓偘丅1擭暘1壠懓100僉儘掱搙偺宊栺側偺偱丄偟傔偰6000墌丅偦偺暘傪懠偺擾嶻暔傪憲傝偨偄偲偄偆採埬傪偟偨偺偩丅昳暔偼擭枛偺儌僠偲枴慩丄壥暔乮儕儞僑偲儔丒僼儔儞僗乯丄偦偟偰媿擏丅偦偺採埬偑偆偗偰拲暥傕懡偔偒偰偄傞偲偄偆丅枴慩偼抦傝崌偄偺嬈幰偵僟僀僘偲暷傪搉偟偰偮偔偭偰傕傜偆偙偲偵偟偨偑丄斕攧儖乕僩偑妋棫偟偨傜棃擭埲崀丄尭擾栻偱僟僀僘傪傕偭偲偮偔傞梊掕偩丅傕偪傠傫丄偙偆偠偵偼抧尦偺暷傪巊偆丅 丂抲帓嶻捈僙儞僞乕偺恖偨偪偼丄徚旓幰偐傜偺抣壓偘梫朷傪丄嶻捈奼戝偺僠儍儞僗偲偟偰惗偐偟偨偺偱偁傞丅 丂徚旓幰偲偺捈愙揑側寢傃偮偒偼偝傑偞傑側傾僀僨傾傗岺晇傪傕偨傜偡丅偙偆偟偨娭學偵偍偄偰偼丄抣壓偘梫朷偑偁偭偰傕朶棊偼側偄丅惗妶幰偲偟偰偺擾壠偲惗妶幰偲偟偰偺徚旓幰偑寢傃偮偗偽丄偦偙偵偼帺偢偲屳偄偵崲傜側偄傎偳傎偳偺嬥姩掕偑惗傑傟傞丅 仧嶻捈偺壙抣偼
丂崱丄奺抧偱偔傝峀偘傜傟丄偦偟偰偙傟偐傜媮傔傜傟傞嶻捈偼丄抧堟揑側憤崌揑嶻捈偱偁傞丅暷傕偁傟偽栰嵷傕偁傞丄壥庽傕偁傟偽嶳嵷傕僉僲僐傕偁傞丅弡偺枴傕偁傟偽丄偐偁偪傖傫傗偍擭婑傝丄偦偟偰懞偺壛岺嬈幰偺榬傪懚暘偵敪婗偟偨捫暔傗枴慩側偳偄傠偄傠側壛岺昳傕偁傞丅 |
|
偍栤偄崌傢偣偼 rural@mail.ruralnet.or.jp
傑偱 2000 Rural Culture Association (c) |
丂