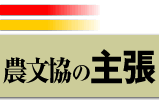 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1995年3月号
|
|
21世紀は自給〈ケイパビリティ〉の時代 生活者=生産する消費者の視点で 自然と人間の矛盾を克服する 本誌昨年1月号主張は「21世紀は『小さい農業』の時代―世界が日本農業の生産革命に期待する」であった。そして、本年1月号の主張は「21世紀は生活者の時代―『企業者の時代』から『生活者の時代』へ」であった。 来たるべき世紀を迎える視点として、ここでさらに「21世紀は自給〈ケイパビリティ〉の時代」という視点をつけ加えたい。 なぜなら、その「自給〈ケイパビリティ〉」の論理は、「小さい農業」の論理と「生活者」の論理をつなぐ論理であり、農業・農村が、21世紀において商工業や都市をも含む社会のあり方全体を導いていくための論理だからである。 ◆ワラと自給〈ケイパビリティ〉いまどき「自給」などと言うと、「自給自足」という言葉から連想されるような、消極的・停滞的なイメージを思い浮べる方が多いかもしれないが、ここで言う「自給」は、21世紀人類の「自由」にかかわる問題である。その「自給」の概念は、アマルティア・センというイギリスの経済学者が、経済合理主義にもとづく経済成長率やGNPなどといった20世紀人類を「支配」してきた価値尺度にかえて、21世紀の価値尺度として提唱している「ケイパビリティ」の概念と密接に関連し、重なりあう概念である。ケイパビリティを辞書で引いても、「能力」とか「素質」という訳語しか出て来ないが、経済史家川勝平太氏(早大教授)は、新しい価値尺度としてのセンの「ケイパビリティ」を、「物を必要条件としつつ、これを生かしていく潜在的・顕在的な主体的能力」あるいは「人間が何かをする自由、何かになりうる自由」のことであり、言い換えると、その能力や自由が生かされて実現される「生活水準の基準」だと解説している(参考文献:NHKブックス『日本文明と近代西洋』)。 その「自給〈ケイパビリティ〉」の概念は、農家が、地域の自然や産物と向き合い、それを活かそうとするときの発想や方法そのものの中にみることができる。 たとえば、1984年の本誌の連載記事「油のいらないハウス栽培」にご登場いただいた福岡県朝倉町の丸林幸夫さんのワラの活用法がそれだ。 ◆ワラのもつすべての力を活かすことが
当時、2重カーテンのパイプハウス540坪でキュウリの無加温・半促成栽培を行なっていた丸林さんは、温床から堆肥まで、4反の田からとれるワラを、足かけ3年、4回にわたって連続的に活用していた。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |