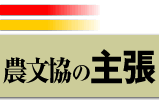 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1995年11月号
|
|
米作りの大変革で 米価は下がらず上がっていく 新食糧法時代の幕開けを前に、「これから米価はどうなるか」と心配されている。大方の予想は、米価は下がるというものだ。今年が平年作なら、来秋には国産米200万tの在庫が出る上に、ミニマムアクセス米も今年と来年で合計80万tも入るから、米価は相当に下がるだろうというわけだ。しかし、この予想は正しくない。なぜなら、すでにこの世の中には右のような事情には影響されない〈新しい米価〉が形成され始めているからである。その〈新しい米価〉は、右のような事情によっては下がらない。また、自主流通米米価といえども、一時的な低落はあろうが、長期的には〈新しい米価〉の影響で少しずつ上昇していくだろうからである。このことを本稿では考えてみたい。 米作りの目的の回復が始まった米作りはもともと、その地域で生きるための重要な糧を得るための生産であった。かつていろいろと支配の道具とされ、また商人の支配下に置かれたとはいえ、家族を養うための生産でもあった。誰に食べさせるための生産かという目的は明確であった。雨が多く地力が消耗しやすい日本で定着農耕を営む上で、水田は山を耕地の地力向上に結びつける要であったし、ワラ、モミガラ、コメヌカ、魚貝類を含め水田の生み出すあらゆる産物が、畑作をも定着可能にする原動力の一つでもあった。食べる人が明確である点でも、地力循環の要である点でも、米作りは農家にとっては具体的な労働目的を持った仕事であり、生き甲斐の根源でもあったわけである。しかし、近年になって、米作りが目的を失いかけていた。何のために増収するのか? かつては米作りには国民的な期待が込められ、米価は高い水準を保たれた。しかし過剰だ、減反だ、米が高い等のマスコミの無責任な論調は、米作りの目的を失わせることになった。 しかし農家の根源的感性はそれをよしとしていない。何のために米を作るのか? それは自分の米を真に喜んでくれる具体的な相手に食べてもらうためではなかったか、と。 一方、消費者は自然から離れ、健康を害する見せかけだけの加工食品に取り巻かれ、食べる真の喜びを失い、その長期の食生活の狂いによって自らと子供の健康にマイナス信号がともり始めた。また、今の生産様式・生活様式が環境というトータルな場を破壊するものであったことに気づき始めた。そして消費者は、食べ物に単なる商品性ではなく、自分と家族の健康を育て豊かな満足が得られる質をもった食べ物・米を、そのような気持ちを込めて作り出される食べ物・米を求め始めたのである。 消費者は味一般、
長野産のコシヒカリが新潟米の増量米として使われてきたという事実は有名であるが、このことを巡って起きている事実から、消費者サイドの思いを見てみよう(9月号334頁)。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |