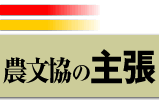 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1995年12月号
|
|
新食糧法が開く「関係性としての米価」が 「商品としての米価」を動かす時代 95年11月1日、いよいよ新食糧法が施行される。半世紀以上、米を政府の管理下においてきた食管法は廃止され、政府が管理するのは備蓄米とミニマム・アクセス米だけになる。農家は出荷数量を食糧事務所に届けるだけで直接消費者に販売できるようになり、単協も経済連を通さず全農、卸、小売に販売できるようになった。日本農業の歴史の中で、はじめて農家や農協が自由に米を売れる時代の幕が開いたのである。 しかし期待も大きい反面、不安も大きい。政府米による米価の下支え機能がなくなってしまうからだ。またマスコミ報道は、昨年の大豊作に続く今年の「平年作」の作柄とミニマム・アクセス米受け入れで、本年十月末の内地米在庫が170万t、来秋在庫が200万tにものぼると見込み、米の値段は相当に下がるだろうと予想する。さらに追い打ちをかけるように、「生産調整の目標達成が困難になれば、米価暴落の可能性もある」とか、「スーパーや商社の価格破壊競争は、卸や産地経済連に仕入価格の引き下げを要求し、ひいては農家に血のにじむようなコストダウンを強いるため、競争力のない多くの農家がふるい落とされるだろう」と解説してみせる。 農家の不安をあおるような報道が氾濫する中で、先月号の本欄は「米作りの大変革で米価は下がらず上がっていく」と主張した。その根拠は、これからの米価には「相手が見えない、商品としての米流通」の中で決められる米価と、「農家と消費者、流通に携わる人々が、どんな米を作り流通させ食べていくのかを合意しながら形成していく関係性としての米価」の2通りがあり、「商品としての米価」は需給バランスによって過剰になれば下がるが、だれに食べてもらうかという明確な目的をもって作られた米は、新食糧法の下で消費拡大に向うことはあっても過剰問題はなく、そうした「新しい米価」=「関係性としての米価」は下がらない、ということであった。そして今後の米価全体の動きについても、たとえば自主流通米が一時的に低迷することはあっても、「関係性としての米価」の影響で長期的には少しずつ上昇していくだろうと主張した。 一言で言えば、これから新食糧法下の米価をリードするのは、「商品としての米価」ではなく「関係性としての米価」ということである。今月は「商品としての米価」と、「新しい米価」=「関係性としての米価」のふたつの米価についてさらに考えてみたい。 ◆商品としての米価米市場に新しく参入できるようになった商社やスーパーは、新食糧法で「米が競争原理の下に置かれる普通の商品になった」と喜ぶ。それが正しいのなら、世の中には「商品としての米価」しか存在しない。しかし私たちはもう一つの米価、「関係性としての米価」があると考える。たしかに米は、もともと基本的な食糧であるというそれ自体の具体的な価値(使用価値)をもつと同時に、抽象的な意味では金銀についで「貨幣」に近い商品、他のどんなものとも交換しやすいという点で、客観的な価値(交換価値)尺度になりやすい商品である。 たとえば江戸時代には、幕府や藩財政の大きさも、武士の家格もすべて米の単位である「石」で表現され、経済の基本は米であった。年貢はまず米で集められ、領主はそれを現金化して支出をまかなったが、家臣団には現物で給付され、札差に依頼するなどして現金化した。分割しやすいとか、保存性があって運搬しやすいなどといった性質をもつ米が、貨幣に準ずる存在だったのである。 さらにまた米は投機の対象にもなった。江戸時代には商人による米投機が原因となって打ちこわしが起き、とくに幕末の江戸・大阪をはじめとする全国規模の打ちこわしは倒幕運動の大きな力となった。また、大正7年(1918)にはシベリア出兵軍用米の需要が投機熱をあおりたてて「米騒動」が起き、食管制度に向けての出発点ともいうべき「米穀法」が大正十年に制定された。「商品としての米価」は、需給バランスの変動などの客観的な市場条件を敏感に反映し、それを商人や資本の投機熱があおり立て、ときに国家権力の存立基盤をも危うくするほど乱高下してきたのである。その変動を、「国や政治のつごう」という面から調整してきたのが食管制度であった。 ◆関係性としての米価一方、「関係性としての米価」は、投機や「国や政治のつごう」で動くのではない。たとえば先月号でご紹介した立川市の米穀店グループ「朝鳥会」の人々が、長野のコシヒカリを「美味い」と感じ、経済連を通して大町市の農協と関係を結び、「長野県大北農協今ずり米」として5kg2850円で扱っている例のように、農家・農協・米屋・消費者のあいだの個別的で具体的な関係の中で決めるものである。この「関係性としての米価」を決めるのは、農家の側から言えば「この消費者や米屋にこそ、この値段で米を売りたい」という思いであり、米屋や消費者の側から言えば「旅行で行ったきれいな水、きれいな風景のあの土地の米だったら」「アイガモや減農薬稲作に取り組んでいるあの人の米だったら」という、それぞれの主観的な思いとその折り合いであって、需給バランスやコストダウン競争などの客観的な条件で動くのではない。新食糧法の下でも、自然、健康、子育てなどを共通のテーマとする農家と消費者との関係が広がれば、客観的な「商品としての米価」も、個別的な関係の中の主観の折り合いによって決められる「関係性としての米価」を無視できなくなるどころかリードされていく、というのが私たちの見通しである。ものの値段は需要と供給という客観的な条件で決まるというのは古い経済学の常識だが、比較的新しい経済学の中には、個別的・具体的な関係の中で買い手と売り手の主観が価格を左右する経済活動を、「不完全競争」あるいは「不完全市場」としてとらえ、それと「完全競争」「完全市場」とが相互に及ぼし合う影響をとらえようとするものもある。 しかし理屈よりも実例や体験から考えるほうがわかりやすい。たとえば、一昨年の「平成米騒動」の際には、都会に出ている兄弟や子供たちといった親族ばかりでなく、「年賀状しか交際のない都会の親戚」やら、「いまではまったくつきあいのない過去の親戚」までも、とにかく何らかのつながりを便りに電話や手紙で「米を送ってほしい」と頼み込んできた。農家は保有米を減らしてまでもその頼みに応えたが、そのとき、テレビや新聞が伝える高騰した都市の店頭価格で譲った農家がいただろうか? 誰もが「だいたいこれくらいでいいよ」と、「適当」に値決めしたはずである。もし一昨年、農家が保有米を店頭価格よりも安く放出しなかったら、5kg6000円などという高値はそれ以上のものになっていたはずである。 また逆に「過剰基調」といわれる現在、ほとんどの産直米の値段が市中価格よりも高く設定されている(ちなみにわが家が所属する産直団体の最新の「お米配送スケジュール」表を見ると、いずれも白米で有機米キララが5kg2480円、有機米コシヒカリが3240円、富山・阿蘇無農薬米が3700円であるが、家計担当官はスーパーなどと比べて高いとも安いとも言ったことがない)。 上記のように「関係性としての米価」は、農家と消費者のどちらか一方のみがトクをするというものではない。「商品としての米価」が高いときには高いときなりに、安ければ安いときなりに、いつの間にか折り合いがついている。米流通全体の中で、「関係性としての米価」の比率が高まれば高まるほど、「商品としての米価」はそれを無視できなくなるのである。 「関係性としての米価」の「商品としての米価」に対するこのような働きは、これまでの食管制度の中で政府米が果たしてきた役割でもある(米価据え置きが続いたこの10年近くは、底値を支えるという片肺的な役割しか政府米が果たしてこなかったとしても)。だから政治が食管制度を廃止したまさに現在の時点で、農家・米屋・消費者自身のさまざまな活動を通して「関係性としての米価」がすでに無視できないものになっていること、米流通の世界が「商品としての米価」1色に塗り潰されていなかったことはきわめて重要なことだ(本年7月号の本「主張」も、「農家保有米を含む全流通量の6〜7割の米産直こそ国民が喜び、米価も下がらない道」としてそのことを訴えた)。さらに、新食糧法の下での2つの米価には、経済だけではとらえきれないもっと本質的な違いがある。 ◆〈貨幣→生産(流通)→増殖した貨幣〉の循環と
新食糧法の施行に先立ち、農文協は「現代農業」増刊として『新食糧法の生かし方――おコメあなたはどこに売る? どこで買う?』を発行した。その冒頭「この本を読まれる方へ」は次のように述べている。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |