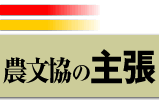 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1998年1月号
|
|
むらを守り農業を守るのは 「習慣と道義による調節」の力 目次 ◆農山漁村空間はいかなる力を秘めているのか ◆日本の米を守っている根本的な力は何か ◆産直の発展は新しい市場原理、生産原理を提起する ◆東アジアの農耕の原則を存続させてきた「習慣と道義による調節」 ◆あらゆる策を講じて、都会に出て定年を迎える息子達をむらに呼び戻そう むらを守り、農業を守る上での経済学上の論理をどのように考えたらよいか。一人の経済学者の経済理論に耳を傾けてみよう。隣国中国の著名な経済学者、北京大学教授・レイ=イネイ氏の理論である。 レイ=イネイは「経済には市場調節と政府による調節のたった二つの調節方法しかないのだろうか」と問題を提起する。そして、第三の調節方法があるとして、それは「一種の習慣と道義による調節」であるとする。そのあらましの論理については本誌356頁に掲載したレイ=イネイの「習慣と道義による調節について」の論文に簡潔に述べられている。中国の日刊紙「光明日報」に掲載された論文である。 レイ=イネイは、「市場調節」も「政府の調節」も「習慣と道義による調節」の補助的役割を無視すると効果を上げられないとして、「習慣と道義による第三の調節」をきわめて重視している。ここにレイ=イネイ理論の根幹がある。 わが国においては、経済を論じる場合「市場の調節」と「政府による調節」の二つの調節だけが論じられているだけで、「習慣と道義による調節」について論じる経済学者はいない。近年、環境問題からのアプローチとしてエコロジーの経済学が論じられるようになったが、「習慣と道義による調節」の論理とは大きな隔たりがある。では「習慣と道義による調節」とは何か、またその画期的な意味は何か、について考えてみたい。 ◆農山漁村空間はいかなる力を
現代は「自由な資本主義」も「市場無視の社会主義」も存在できない時代である。資本主義は五カ年、一〇カ年の長期の国家計画による財政投融資によって支えられる資本主義であり、他方社会主義も市場経済によって支えられる社会主義である。そして経済を考える上での根本問題は、資本主義か社会主義かの対立・選択の時代から、人口・食料・資源・環境といった人類共通の問題の解決が課題となる時代へ、つまり階級矛盾の克服の課題ではなく、「自然と人間の敵対的矛盾」の克服が課題の時代へと、時代は明確に新しい時代に移行したということである。この新しい時代は、自然と人間の調和する空間形成を求めている。そして自然と人間の調和をめざす空間形成において決定的役割を担うのは農山漁村空間なのである。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |