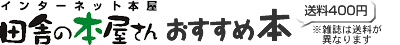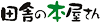|
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
2009年2月号
|
種子のグローバリズムに抗し「農民参加型育種」を興す目次 直売所名人になる品種、肥料や農薬、暖房代を減らせる品種、地粉のパンを盛り上げる品種、業務・加工需要をねらう品種などなど、今月号では、たくさんの品種を紹介した。在来種から外国の品種まで、自家採種による品種づくりも加わって今、農家の品種活用は大変賑やかである。 農家が品種選択や品種づくりに参加して品種の多様化を推し進める。その意味は大変大きい。 バイオ企業が進める種子、品種の独占世界的にみれば、品種の多様化とは逆に、遺伝子組み換え(GM)作物を中心とした品種の単一化、画一化の勢いがますます強まっている。 国際アグリバイオ事業団(ISAAA)によると、2007年のGM作物の栽培面積は1億1430万haで、世界の耕地面積一五億haの八%にあたる。このうちダイズが5824万ha(世界のダイズ栽培面積の64%)、トウモロコシが3552万ha(同24%)、ワタが1225万ha(同35%)、ナタネが540万ha(同20%)。 遺伝子組み換え種子を開発し所有しているのはモンサント社など米国を拠点とする多国籍バイオ企業である。モンサント社は種苗企業の買収を続け、さらには穀物メジャーの種子部門を買収するなど、種子の独占を強めている。 この遺伝子組み換え作物を利用した農業は、「緑の革命」の延長上にある。先月号の主張「世界の小農に宿る『自給の思想』が未来をひらく」では、「『緑の革命』は、自給と相互扶助で成立していた農村を解体し、小農を離村させて画一的でイビツな都市空間を世界に広げている」と述べた。GM作物を活用した大規模農業は、農民から種子・品種を奪い、地域の伝統的な、自給的な農業の破壊に拍車をかけている。 バイオ企業による種子事業の買収には、遺伝子組み換えによって生物に特許をかけることができるようになったという背景がある。モンサント社はGMの特許種子を盾に自家採種を禁止し、さらには交雑によるGM遺伝子の「流出」も特許侵害として、農家から賠償金を取り立てている。その一方では、GM作物の栽培に関連する農業資材(農薬、肥料、機械など)も企業の指導に基づきセット販売される。 「生物特許」を根拠にした種子・遺伝資源の独占化は各地の原種・固定種までターゲットを広げる。企業が有用な原種を持ち出し、その遺伝子を解析して特許を取るというやり方だ。タイの“ジャスミンライス”という香りの良い高級米に対し、企業が特許を取り商標まで奪い、タイの農民がそれを輸出できなくしてしまうという事態も発生した。 在来種、原種は、何世代にもわたって農家が選抜し、守り育ててきたもので、「生物の多様性に関する条約」(日本を含む188カ国およびECが加盟)はこれを認め、原産国の農民にその利益を還元しようという内容なのだが、アメリカはこの条約にいまだ加盟していない。 バイオディバーシティ(生物多様性)は富への指標インドでも、次のような事件が起きている(『Winter 2001』カタログより) 1960年代の「緑の革命」以前、インドでは20万種以上の米が栽培されていた。これらの自生種は独自の進化により、洪水や旱魃を生き延び、高地や海岸でも生育し、より美味しく、薬用効果をもたらすようになった。バスマティ米もその一つ。インドとパキスタンの農家は長年にわたって研究と開発を重ね、さまざまな種類のバスマティを生み出し、インドの輸出品として急成長を遂げてきた。 しかし、米国の企業が特許を取得したことでバスマティ市場が独占され、農家の努力が台無しになるという危機が発生した。1997年、アメリカ・テキサス州に本拠地を置くライステック社は、20種のバスマティ米の種子、苗および穀物に対して特許を取得。バスマティを「新種」の穀類と謳い、国際市場に売り出そうとしたのである。 これに対し、インドの科学・技術・自然資源政策研究財団を含むNGOらが反対運動を起こし、その結果、大半の原種について特許の申請が取り下げられることになった。こうして反対運動は功を奏してきたものの、その一方でシンジェンタやモンサントなど複数の企業が新たな米の特許を取るべく、コメゲノムの配列決定に躍起になっている。 この反対運動の先頭に立ってきた物理学者、哲学者そして環境保護活動家であるヴァンダナ・シヴァ博士(先の財団の創設者であり理事長)は、「増え続ける人口に十分な食料を供給していくために必要とされるのは、化学の強化や遺伝子操作ではなく、バイオディバーシティの強化なのだ」と、企業による種子の独占を批判し、こう述べている。 「真の創造性とは、生物の多様性やそれを維持する農法、そして文化の多様性があってはじめて実現するものである。バイオディバーシティに基づいたシステムは高い生産性と利益をもたらすものであり、環境的、経済的、文化的、精神的、美的理由から、私たちはバイオディバーシティをよりいっそう必要としている。バイオディバーシティはまさに富への指標であり、従ってその衰えは真の意味で貧困を示しているのである」 キューバで進む「農民参加型育種」自然と作物、そして農家が一緒になり、長い時間をかけてつくられてきた品種の多様性、豊富な遺伝資源。それは、一国の農業を左右するほどの大きな価値がある。キューバの取り組みもまた、そのことを教えてくれる。 1980年代までのキューバは、植民地時代に始まった砂糖を中心とする輸出農業に力を入れ、サトウキビ栽培に必要な肥料や農薬の95%を輸入に頼っていた。しかし、ソ連が崩壊して以降、貿易や資材輸入の道が大幅に縮小したため、キューバは大規模単作経営から小規模多品目の自給的な有機農業をめざすことになった。代替肥料や防除手段の開発・普及が進み、一定の成果を収めるなかで課題になったのが「品種」である。 輸出型単作農業のなかで、トウモロコシ、マメ類などの品種は、肥料・農薬などの多投を必要とする限られた品種に置き換わり、国内の品種資源は貧困になっていた。これに対し、育種家をはじめとする関係機関は「安定した高収量には、作物資源の豊かな多様性が必要だ」との仮説に立ち、資材低投入に見合うトウモロコシやマメ類の品種の多様化、改良を目標にしたプロジェクトを立ち上げた。その核心になったのが「農民参加型育種」である。 品種の状況を調査した結果、資材依存農業を進めた地域では品種・遺伝資源の多様性はほとんどなかったが、そこから遠方のいわば孤立した地域では、農家同士がトウモロコシのタネを交換し、あるいは他所から種子を入れて「リフレッシュ」しながら、在来種を守り、品種の多様性を維持していることがわかった。こうしてトウモロコシでは66種の在来種が集められ、これをもとに選抜された実用品種が農家に配布された。配布を受けた農家はそこからさらに多くの品種を選抜して、またたく間に品種・系統を広げてみせたのである。この過程で、資材の低投入のもとでは、資材依存農業で使われた品種より、雑然性に富む在来種系統のほうが成績がよく、その優位性が明らかになった。 この取り組みをリードしてきたウンベルト・リオス・ラブラーダ博士は、キューバでのGM利用についての質問に対し、こう答えている。 「自分たちで品種を管理している農民たちが、多国籍企業の種子生産者から要請されるGM製品に支配力を与えてしまうことなど、ありえそうにありません」 (以上、HP「キューバの有機農業」〈編集人・吉田太郎〉掲載の訳文を参考に記述)。 農業は「生物多様性」に支えられ、豊かになる「生物多様性」とは多様な生物資源の保全にむけて、「個体」「種」「生態系」の多様性と、そのつながりの重要性を述べたもので、日本では2008年5月、「生物多様性基本法」が全会一致で可決・成立した。この法律では、「生物多様性」を「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在すること」と定義し、「豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与すること」を目的としている。 農業はこの生物多様性を貧困にするものと考えがちで、実際、資材依存の単作的農業は生物性多様性を貧弱にする。しかし、農業は「生物多様性」を土台にして成り立っている。そして、「個体」つまり一株一株の作物が多様性をはらみ、「種」つまり品種・作物が豊富・多彩で、作物を取り巻く微生物や小動物その他、生きものが豊かなほど「生態系」が多様だということになる。生物多様性を土台に、人間・農家が加わって品種、作物、生態系が豊かな空間=歴史的生命空間が形成される。「生物多様性」に支えられつつ、多様性を創造するのが農業の本質である。 イネもトマトもリンゴも、作物として世界各地に広がるなかで、各地でその風土にあった品種が生まれた。作物は、人間とのかかわりあいのなかで品種を多様にし、種として繁殖する道を歩んできた。「進化」とは、皆が同じようになるのとは逆に、多様化・地域化するということである。 在来種にみられる驚くほどの品種の多様性は、作物と人間がともに進化してきたことの現れである。その担い手は農家だった。農家がかかわってタネからタネへと生命が再生産されていく。その「タネ」は、もともと「固定種」のことであった。固定種は、何世代もかけて選抜が行なわれ遺伝的に安定した品種で、自家採種によって同じようなタネを増やすことができる。それぞれの地域、農家で自家採種が続けられた結果、在来種がつくられてきたのである。 「緑の革命」、そして遺伝子組み換え作物を使った大規模栽培、品種のグローバリズムは、農家が長年かけて築いてきた品種と農業の多様性を貧弱にし、各国の地域農業と農家を破壊していく。一時的に華々しい成果を上げたとしても、それは生物多様性と農業の多様性を貧弱にするがゆえに、いずれは破綻する。食料・資源・環境という人類史的な課題に、品種のグローバリズムは逆行する。 それゆえ、キューバのように、農民参加型の育種、品種利用で品種の多様性をとりもどし、地域の農業と暮らしを守ろうという動きが世界的に強まっている。 キューバの経験は他の中南米諸国にも波及しつつある。 飢餓を救おうとアフリカで進めれている、低投入型の「ネリカ米プロジェクト」でも、農民参加型の手法が取り入れられている。一方、園芸王国・オランダの育種事情を調査した根本和洋氏(信州大学)らによると、自家採種種子のみを多品目販売する小規模の種苗会社や有機農業の民間団体などが在来種を維持しつつ、農民の自家採種、品種選抜についての知識・技術の研修を行なっているという。 農民参加型育種がつくる品種の雑然性 農民参加型育種が品種の多様性を守り創造する。そして農家がつくる品種は、遺伝的な多様性=「雑然性」を備えている。それは、地域のさまざまな環境の変化に耐えうる形質といってもいい。以下は自家採種を続けている長崎県吾妻町の岩崎政利さんの話。 「私が自家採種を始めて間もない頃、形の美しい特定の姿の五寸ニンジンばかり選んでタネを採っていたら、だんだんにタネが採れなくなるという経験をしました。採れたタネを播いても発芽が悪く、生育も貧弱になってしまったのです。ところが、女性的な美しい五寸ニンジンの母本を揃えた中に、男性的なゴツゴツした感じのニンジンを少し混ぜてタネを採ると、生命力が甦ってきました。このときの経験から私は、固定種のタネ採りでは多様性を大事にしたほうがいいことを学びました」 F1品種はふつう、特定の形質を求めて極度に純粋性を高めた固定種どうしの交配でつくられ、こうして「優秀な」品種が作出されるが、農家のタネ採りは、全体として品種の雑然性を維持しながら、品種自身の可変性に依拠して、自分の品種をつくっていくやり方だ。 「自家採種」というと、なんとなく難しいイメージがあるが自然農法国際研究開発センターの育種部門担当・後藤久美子さんは、「多少交雑してもいいじゃないですか」と言う。 「自分で採ったタネで作った作物は、市販のタネの作物より不揃いかもしれない。でもひょっとしたら、見たこともないようなスゴイものができるかもしれない。そんなワクワク感は、ビシッと同じものしかできない市販のタネでは味わえない」(本号86ページ) 自家採種といっても、何も伝統的な品種にこだわることはない。在来種も、もともとそこにあったわけではない。他所からもってきた種子を自分のものにする。これも農家が参加する育種の醍醐味である。 今月号では「世界のトマト」を特集、そのなかで、(有)ブリティッシュシードの石井賢二郎さんが、エアルーム・トマトのことを紹介している(200ページ)。エアルーム・トマトは、「ガーデナーやその家族が北アメリカに移住した時にもたらされ、アメリカ原住民やアーミッシュによって栽培され続けてきたもの」であり、「家族の中で先祖伝来の宝石や家具のように歴史を持っている品種」である。固定種で、形質が同一ではなく、生育、開花、収穫などが均一とはならない。「多様だからこそ、長い年月を生き延びてきた」のである。種類は豊富で、そのほとんどが有機栽培によって継承されてきたものであり、自家採種により地域や農家に合った独自品種をつくれるのが魅力だ。 品種が、風土を充実した姿に進展させる「弱いはずの金時(サツマイモ)の苗がたくましくなった」というのは、新潟県小千谷市の片岡富雄さんである(194ページ)。 「初めて『金時』を作付けしたのは、25年くらい前です。それまでわが家は『川越』『ムラサキ』『太白』『ベニコマチ』『紅高系』を作っていましたが、金時が土に合うのか、一番おいしく感じられました。一般的に金時の苗は軟らかくて弱く、収量も少ないと言われます。しかしわが家の苗は硬くて強く、収量もたくさんとれるようになりました。繰り返し作りながら選別して良いイモを残していくことで、雪深いこの地域にも合った作物に育っていったのではないでしょうか?」 埼玉県で育成された品種「金時」が、農家の手によって その地の風土にあった品種に生まれ変わる。 昭和のはじめ、世界恐慌の嵐が吹き荒れるなかで、風土産業の旗を高く掲げた三澤勝衛は、著書『風土産業』の「『この土地ならではの』の品種を育てる」の項で、新品種の育成について、次のように述べている(注)。 「それが寒地に耐えるとか、高地に耐えるとかいうていどの品種では、まだ十分とはいえないのである。それが『寒地でなければとか、高地であればこそ、こんな立派な成績があがるのである』という新品種の育成まで進み、『ここで、この品種であればこそ、こんな立派な成績をあげ得る。他の地方へもっていったのではとうていこれだけの成績をあげるわけにはいかない』といったところまで、その研究を進めていくことを期待するものである」 「風土に優劣はなく」、上手に活かせば「無価格で偉大な価値を発揮する」と考える三澤にとって、品種は風土から生まれ風土を体現する個性的な表現体であり、そして品種を研究する担い手は、風土を最もよく知っているその地の農家である。農家、地域民による品種の育成は、「風土そのものをもっとも充実した姿にまで進展させようとする努力でさえある」。 そのための育種には品種の移入・輸入も重要だと三澤はいう。品種育成には、他との交流と風土にあわせてなじませることとの両方が必要である。日本でも世界でも、風土にあった品種を求めて、タネを交換したり「盗んだり」する伝統があり、こうして多様な風土的品種が生まれた。 豊かな「農民参加型育種」を地域から興していきたい。 (農文協論説委員会) (注)三澤勝衛著作集『風土の発見と創造』(全4巻・農文協刊)。詳しくはこちらをご覧ください。 関連リンク |
 |
『三澤勝衛著作集 風土の発見と創造 全4巻』三澤勝衛/三澤勝衛先生記念文庫 今こそ地域の時代!地域づくりの出発点・「地域力」=「風土」の発見と活用の手法を提示。「無価格の偉大な価値」で活気ある産業・暮らし・教育の再生を。 [本を詳しく見る] |
 |
 |
 |
| ■前月の主張を読む | ■次月の主張を読む |