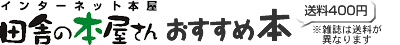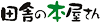「農の福祉力」で、福祉の転換と地域再生
長野県に学ぶ「アグロ・メディコ・ポリス」
目次
◆80代女性が伝統野菜を守る村を訪ねて�
◆�長野県が長寿日本一を達成したベースとは
◆「畳の上で死にたい」という望みをかなえるために
◆住み慣れた村で最期を迎えるために
◆��農業と医療・福祉の複合は地域再生のかなめ
多くの人は、年をとってもずっと元気で、誰の世話にもならないでぱったり死にたいと願う。いわゆるPPK(ピンピンコロリ)だ。しかし、そのような幸運な人はまれで、ほとんどの人は病院のお世話になり、期間の長短はあれ、介護を受けることになる。PPKが無理でも自分の家の畳の上で、いやせめて自分の村で最期を迎えたい――しかしそんな願いは自分の力だけでかなうものではない。
かつて老親が自分で身の始末ができなくなったら、家族が面倒を見るのが当然だった。娘であり息子であり、もっとも献身的にその役目を背負ったのが「いえ」の「嫁」だ。しかし、昔は今ほど寿命が長くなかったから、介護をしなければならない期間はいまよりずっと短かった。現代は違う。70代の妻が同世代の夫と90代の義母を介護する――そんな「老老介護」はざらである。頼りにすべき子どもの数も減った。結果、家族一人ひとりの負担は重くなり、とてもじゃないが介護を家族だけで担いきれない状況になっている。
ではどうするか。今回は高齢者の切実な願いをどうやってかなえるか、そのために地域社会に何ができるかを考えてみたい。
よりよく生きるとはよりよく死ぬこと。それが「福祉」の究極の課題だろう。そのような「福祉」の条件は都会より農村のほうがずっと整っている。農村は福祉の先進地なのである。そのことを長野県でみていこう。
▲目次へ戻る
��80代女性が伝統野菜を守る村を訪ねて
長野県の平均寿命の推移をみると、男性は1970年からほぼ長寿第1位を維持、女性も2010年には沖縄を抜いて第1位となった。いまや男女とも日本一の長寿県だ。
長野県阿南町にお年寄りが元気に働く集落があると聞いて訪ねてみた。そこは和合地区の鈴ヶ沢集落。阿南町の中心地から車で30分ほど入った標高900mの山間地にあり、Iターンで3年前に愛知県から移住してきた椎葉さん夫婦を含め、5世帯9人が暮らしている。この集落で人々は鈴ヶ沢なす、鈴ヶ沢うり(実が太く、断面が三角形のキュウリ)、鈴ヶ沢南蛮(トウガラシ)といった在来品種のタネを守り続けてきた。「南信州おひとよし倶楽部」(和合元気なむらづくり協議会の一部門)の支援を得て「信州の伝統野菜」として販売に取り組み、共同育種も進めている。その中心は松村久子さん、熊谷千里さんら80代の女性たち。熊谷さんは「ナスを植える頃になるとまめになる」と笑いながら語ってくれた。毎年雪に閉ざされる冬は「もう来年は畑はやめにしよう」と思うのだが、雪がとけ、ナスを定植するころになると、しぜんに元気がみなぎってくるのだそうだ。
鈴ヶ沢では「限界集落」と呼ばれるような厳しい条件のなかで、集落の高齢者が特色ある農業と食文化の担い手となっている。農業という仕事は「生涯現役」が可能な仕事であり、農村の人のつながりと適切な支援があれば、充実した暮らしを生涯貫ける可能性があるのだ。
農業の高齢化はゆゆしき問題として語られることが多いが、それは経済効率と労働生産性から見た場合の話だ。鈴ケ沢の伝統野菜は80代の女性たちの手間暇を惜しまない仕事によって守られ、野菜の育種と栽培というかけがえのない仕事は女性たちに誇りを生涯にわたって与えてくれる。「小さな農業」は「福祉力」に富んでいるといえる。
▲目次へ戻る
��長野県が長寿日本一を達成したベースとは
しかし、農業に携わってさえいれば長生きができるかといえば、それだけではない。平均寿命にはさまざまな要因が影響するが、やはり日常の食事や健康管理が大きいだろう。この点、冬の寒さが厳しい長野県では塩分の多い食事を摂ることが多く、高血圧や脳卒中などの病気を引き起こしやすい。それなのに長野県が長寿社会を維持できているのはなぜか。
池上甲一さん(近畿大学教授)の『農の福祉力』(「シリーズ地域の再生」最新刊、農文協)によると、長野県の老人医療費は2000年以降、全国でもっとも低い水準を維持している。高齢者の健康状態が良好なだけでなく、身体的自立の程度が高い(とくに軽度要介護者の認定率は全国でも最低クラス)。そして、健診受診率、高齢者就業率、在宅死亡率がいずれも高い。
いま日本の医療行政は医療費の抑制を目指している。医療費が低く、病床数は少なく、健康で長生きし、高齢でも働き続ける長野県はまさに格好のモデルということになる。しかし、池上さんは長野県がそのようなモデルに到達したのは、けっして医療費を節約しようとしたからではなく、あくまで住民の健康とよりよき生活を求めた地域医療と保健活動の結果だとみる。その典型をつくりだしたのがJA長野厚生連佐久総合病院とそれと連携した佐久地方の保健活動である。
佐久総合病院が、戦後早い時期から、院長の若月俊一医師を中心に農夫病や農薬中毒問題といった農村医療運動を展開してきたことはよく知られている。若月医師の基本精神は「病院に患者が来ない? それには事情があるはず。こっちから出かけていこう」というものだ。終戦間もない1945年12月から無医村対策として出張診療に取り組み、まだ健診や予防といった考え方がきわめて希薄だった1950年代から旧八千穂村(現佐久穂町)と連携して全村健康管理を導入。集団検診を全住民対象に実施し、その結果を個人の健康台帳だけでなく、世帯単位、集落単位にまとめるとともに、そのデータを住民一人ひとりが健康手帳を通して自覚できるようにした。この取り組みは社会的な要因を含めて病気の原因をさぐるとともに、住民一人ひとりの健康増進への意識を高めようとしたものだ。
全村健康管理は旧八千穂村に続いて木島平村でも実施され、JA長野厚生連が1973年に佐久総合病院に健康管理センターを付設することで全県に広がった。農協婦人部を中心に旧八千穂村のような健康診断をしてほしいという切実な声が農協に寄せられ、「組合員の健康を守る運動」の実践として、農協と市町村が連携して集団健康スクリーニングを全県下に拡大していった。
▲目次へ戻る
��「畳の上で死にたい」という望みをかなえるために
住民(組合員)一人ひとりの健康を細かくチェックし、健康意識を高め、病気を未然に防いでいく――その健康管理運動が長野県のお年寄りの元気のもとであることはわかった。しかし、それでも多くの人は病いに倒れ、介護を必要とするようになる。「PPKは無理でも自分の家の畳の上で死にたい」「せめて自分の村で最期を迎えたい」という願いにはどうこたえるか。
ここでも佐久総合病院はパイオニアの役割を果たしている。1980年代以降、病院が力を入れた在宅ケアである。1986年にJA長野厚生連と佐久総合病院は共同で「在宅寝たきり老人状況調査」を実施し、家庭内介護が介護者の犠牲のもとで成り立っている実態を明らかにした。そして、介護者の視点に立って、外出できないとか自分の時間がとれないという悩みにこたえるために老人保健施設を設置するとともに、入浴、排泄、更衣、食事といった介護者の負担を軽減するために在宅ケア実行委員会を設置し、南佐久北部地域の市町村で在宅ケア活動をスタートさせた。
「自分の家の畳の上で死にたい」という望みを果たすためには、それを支える仕組みがないと当人も介護者も共に我慢を強いられる。佐久総合病院はその地域ケアの仕組みをつくろうとしてきたのである。
この在宅ケアの実践もまた、佐久地方のみならず長野県全体に広がっている。
たとえば泰阜村は人口1821人、過疎化の進む中山間地域の小さな村だが、徹底した「在宅福祉」の村として全国にその名を轟かせてきた。1988年には老人福祉と老人医療を無料化。診療所と在宅福祉支援センターを核として、介護を必要とするお年寄りをホームヘルパーと訪問看護師が手厚くサポートする体制を整備し、お年寄りのほぼ5割が自宅で亡くなる「在宅死の村」を実現させた。ちなみに泰阜村は全国でもっとも医療費が少ない長野県のなかでも、つねに医療費が最低クラスである。
2000年4月の介護保険制度の導入は、こうした泰阜村の福祉行政の見直しを迫るものだった。村の在宅福祉を支えてきた国や県の補助金が見込めなくなるとともに、介護サービスの利用者である村民が利用料の1割を負担しなければならなくなったからである。国民年金以外の収入が少ない高齢者にはこの出費は非常につらい。
松島貞治村長は元役場職員。診療所の事務長を務めた経験もあり、「在宅福祉の村」を引き継いできたが、介護保険制度のスタートにあたり、大きくふくれあがっていた訪問看護師やヘルパーの数を減らすなどの苦渋の決断を迫られた。それでも泰阜村はあきらめなかった。在宅を希望する高齢者には介護保険サービスを超過する分を村が負担。松島村長が会長を兼務する村の社会福祉協議会は現在でも正規職員だけで23名にのぼり、臨時職員を含めると46〜48人が在宅福祉サービスにかかわっているという。
▲目次へ戻る
��住み慣れた村で最期を迎えるために
泰阜村では「自分の家は無理でも、せめて、自分の村で最期を迎えたい」という願いをかなえるための、新しい試みもはじまった。2009年にオープンした高齢者共同住宅「悠々」がそれである。入口を入ると掘りごたつのある畳コーナーと薪ストーブがおかれた広いリビングと明るい食堂があり(このスペースが「地域交流センター悠々」)、それを「悠々長屋」と呼ばれる10の個室が取り囲み、ヘルパーが24時間、入居者の生活をサポートする。
「悠々」はまちづくり交付金を活用して村が建設し、国の介護保険制度に頼らず、「高齢者協同企業組合泰阜」によって運営されている。この組織は村内外の六十数人の会員が5万円ずつ出資し、年間60時間のボランティアに参加する企業組合だ。入居費用は1カ月3食ケア付きで15万5000円。泰阜村に30年以上通い、夫とともに村に移り住んだ元高崎健康福祉大学教授の本田玖美子さんが「住み慣れた村で最後まで暮らす」理想の居場所を求めて、理事長としてスタッフと共に奮闘中である。
「悠々」の入居者は特養老人ホームではとても考えられないような自由を満喫している。入居者の多くは認知症を抱えるが、夫婦の片方が倒れて要介護状態になっても結婚生活は継続し、ペットも飼える。地域に開かれた場になっており、村の人が自分の庭の花木を植えかえるなど、施設の維持・管理に村の人が自発的にかかわっている。入居者だけでなく村人も食事もすれば、昼寝もする。つまり、ここは「施設」ではなく、「暮らしの場」であり、むらの「よりどころ」なのだ。
隣の阿南町も福祉では負けていない。阿南町がとくに重視しているのは現在の介護保険制度の弱点となっている要介護度の比較的軽い高齢者のケアである。
家での生活が困難だったり、家族と同居できない事情があって、グループホームに入るほどではない高齢者のために、「高齢者生活支援ハウス」を町内5カ所に設置した。町が建設費を負担し、阿南町社会福祉協議会や宅老所を営むNPOが指定管理者となる「公設民営」の施設であり、入居者はさまざまな介護サービスを受けることができる。収入が国民年金だけの単身者の場合、利用料(居住費)は1カ月5000円、共益費が5000円、食費が3食で3万6000円程度であり、これならこづかいを残すことができる。「高齢者生活支援ハウス」そのものは介護保険制度の対象にはならず、町の委託料を含めても収支はとんとんだが、指定管理者にとっては入居者にまとまった介護サービスを提供できるというメリットがある。
現在の介護保険制度は要介護度の重い高齢者に手厚いものになっている。福祉の民営化が進むなかで、福祉施設の建設はいきおい特養老人ホームに集中し、そこに介護報酬の高い高齢者を集める方向に向かう。そのほうが経営的に安定するからである。家族にとっても、在宅やグループホームでさまざまな介護サービスを受けるより、特老に入れたほうが経費は安くつく。
こうしたなかで、阿南町は「公設民営」によって、要介護度が比較的軽い高齢者を受け入れる施設も用意し、家族ができるだけ親と関わり続けるような働きかけを行なっている。さらに、一人暮らしのお年寄りが、「死ぬのは自分の家の畳の上で」という願いをかなえるために、診療所のかかりつけ医師や訪問看護師、デイサービス、民生委員や隣人と、町外で別居している息子や娘がつねに情報を共有できるような「地域包括ケア」のしくみづくりにとりかかった。そこでは電子カルテやスマートフォン、タブレット型端末も活用される。全村健康管理の現代版である。
国の制度が「福祉は施設から家族へ」というとき、そこには医療費の削減という狙いがちらつく。これに対して、泰阜村や阿南町がめざすのは、「畳の上で死にたい」「住み慣れた村で最期を迎えたい」という高齢者の願いに向き合い、そこでもっとも必要とされる施設とケアを見極め、自治体行政が主体となって提供しつつ、そこに家族とのかかわりをつくっていくことなのである。
▲目次へ戻る
��農業と医療・福祉の複合は地域再生のかなめ
こうした住民の願いを実現することは、じつは町村に貴重な雇用の場をつくることでもある。実際泰阜村も阿南町も、首長が「福祉は産業」と位置づけ、介護やさまざまな老人保健施設でかなりの人数を雇用しており、その多くは地元の住民である。「ユーザー」も町村内にいるが、そこで使われる人件費の多くも町村内に落ちるのだ。
『農の福祉力』で池上甲一さんは佐久総合病院と周辺市町村をモデルに農業(アグロ)と医療(メディコ)が複合する地域社会=「アグロ・メディコ・ポリス」の構想を打ち出している。そこでは「農村・農業のなかにあるさまざまの地域資源が医療・保健・福祉・介護といった領域と緊密に結びつき、地域内で経済的循環と物質循環に基づいた社会関係が有機的・複合的に形成されている」。つまり、「自分の家の畳の上で死ねる」「住み慣れた村で最後まで暮らせる」地域社会をつくることは、施設に閉じ込める福祉の転換になるだけでなく、地域のおカネや資源の循環を生み出し、地域再生にもつながるのである。
ここで大事なことは、「アグロ・メディコ・ポリス」のベースには、その名の通り「住民の多くが農業に携わる条件」がしっかり据えられねばならないということだ。
阿南町では佐々木暢生町長の発案で「ふるさと納税制度」と米を結びつけた農家の支援策を新たにスタートさせた。従来はふるさと納税1万円に対して3000円程度の町の物産品を贈呈していたのだが、今年度は1万円の寄付につき、町産米20kgを送る。寄付する側から見ると、確定申告によって寄付金3万円の場合、2万8000円程度、税が軽減されるから、わずか2000円で60kgの米を受け取ることができる。一方、町は町内の生産者から玄米60kg1万7000円で米を買い上げる。阿南町のふるさと納税の申し込みは七月現在で750件、1700万円にのぼっているという。ふるさと納税を活用した農業振興策は町長の「年金プラス50万円で生涯現役で働ける町づくり」の一環である。本来福祉政策とはこういうものであり、農業を大規模・効率化して多くの農家を農業から排除したり、混合診療で医療を効率化するような政策(TPP参加とそれに伴う規制緩和がそれだ)とは真逆なのである。ちなみに長野県は自給的農家の比率が高く、TPP反対署名者数が全国トップの62万人(長野県選出の篠原孝衆議院議員の予算委員会資料による)だそうだ。
*
前述の阿南町鈴ヶ沢の熊谷千里さんは義母と夫を相次いで亡くして気落ちし、3年ほど田んぼを休んだことがあったという。そんなとき社協に勤め、ヘルパーとして通ってくる宮下恵美子さんに「鈴ヶ沢なすをつくってみたいから、つくり方を教えて」と頼まれた。荒れかけた熊谷さんの畑を借りてナスをつくる宮下さんに教えているうちに、農業をやりたい気持ちが再び起こってきた。ちょうどそのころ息子が帰ってきて手伝ってくれるというので、3年ぶりに田んぼを復活させた。この田は熊谷さんが嫁いできたときに、義母にいわれてカマスで石や土を運んで拓いた田だという。この宮下さんのかかわりに、理想の「介護」のあり方を見たような気がした。
�(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
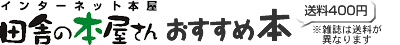
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2013年9月号』
特集:重いはイヤだ
味を落とさない実肥で、稔りよし/農家が見る 秋のイモムシ/草でチッソにブレーキ/収穫の秋 鳥獣を畑に入れない!/冷凍をおいしくする、冷凍でおいしくなる/農家が「地エネ」を生産する時代 「畑で発電」の可能性 ほか。 ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『農の福祉力』池上甲一 著
農の本来的特質である生命の再生産と創造性は福祉を支える力となる。園芸療法や園芸福祉が注目されるなか、高齢化が進んだ農業・農村の先進性を福祉の視点から評価。鳥取県旧東泊町のJAを母体にした介護施設や長野県の厚生連佐久総合病院を中心としたエリアでの農村医療・有機農業・生ゴミコンポスト化の実態分析に住民からの意識調査・ライフヒストリー調査をまじえて、農業と医療・福祉・介護が一体となった地域社会(アグロ・メヂィコ・ポリス)づくりを構想する。
[本を詳しく見る]
|
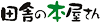
|