家族農業の大義
「和食の世界文化遺産」登録と「国際家族農業年」の意味を読む
目次
◆急浮上した「農政改革」と「世界の良心」
◆家族農業なしには、「和食」を次世代に継承できない
◆「国際家族農業年」と「人類史的な転換」
◆「農政改革」と「農業・農村の多面的機能」は両立しない
◆グローバル企業の世界戦略の禍は地方にも都市にも
◆「人・農地プラン」で発揮 農家・地域の土地利用調整力
▲目次へ戻る
急浮上した「農政改革」と「世界の良心」
「生産調整の5年後廃止」と「経営所得安定対策の定額補助金の減額・廃止」、そして、「農業補助金は主に大規模農家へ手厚く支給する」という方向に向けて「農政改革」がにわかに急浮上した。予期されたこととはいえ、この急発進ぶりは、この農政改革が、TPP(環太平洋経済連携協定)妥結への露払いであることを、鮮明に示している。
ここまで政策が具体化してくると、参院選を目前に政府が発表した「農業・農村所得倍増戦略」は、表向きの掛け声とは逆に、米価下落・農家所得減少政策そのものであることがわかる。つまり、このアベノミクス農政は高齢農家や小さい農家の強制的離農促進政策であり、中山間地域の集落限界化・消滅の促進政策である。TPPの妥結は日米両国原籍の多国籍企業とそれが立地する大都市に富を集中させ、地方にはいっそうの過疎化を強いる。
しかし、こうした農家・農村・地域を衰退させる流れが強まるほど、これをよしとしない潮流も強まる。ここで、「日本の良心」、「世界の良心」ともいうべき、二つの出来事に注目したい。
ひとつは、「和食 日本の伝統的な食文化」がユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界無形文化遺産に登録されること(本号が届くころには正式決定されるだろう)。
もうひとつは、国連・食糧農業機関(FAO)が、2014年を「国際家族農業年」と定めたこと。「家族農業や小規模農家は、持続可能な食料生産や食料安全保障、貧困の根絶に貢献できる」として、各国政府に対して、小規模家族農業を支援するよう要請していることである。
▲目次へ戻る
家族農業なしには、「和食」を次世代に継承できない
食に関する無形文化遺産としては、これまでにフランスの美食術やメキシコの伝統料理、スペイン・イタリア・ギリシア・モロッコの4カ国共同提案の地中海料理、トルコの伝統料理の4つが登録されている。
これに対し、日本の提案の特徴は次のようだ。当初は会席料理を軸に検討されたようだが、最終の正式提案書では「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」から「年中行事との密接な関わり」まで4項目を和食の要件とし、そして、「南北に長く、四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化もまた、これに寄り添うように育まれてきました」とあるように、「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」として「和食」を提案している。海外で日本食ブームになっている寿司など特定の料理(術)ではなく、地域の自然・農業・暮らしが育んできた「食」を「和食」としたことはまさに慧眼と、関係者の皆様には敬意を表したい。
文化遺産への登録では、その伝承・保護にむけた取り組みが求められる。「提案書」の「過去及び現行の保護の取組」の項では、多くの地域コミュニティや集団の活動、「食育」や都市と農村の文化交流の取り組みを挙げ、そして「地域の伝統食の保存に取り組んでいるグループは、全国350地域に住む5000人の年長者からの聞き書きで編纂した、『日本の食生活全集』(最大級の食文化のデータベース)を出版している」と記している。
当会が発行したこの『日本の食生活全集』(全50巻)は、「今、やっておかなければ、永久に失われてしまう」との思いを共有しながら、各県の編集委員会を中心に10年がかりで完結した作品である。
今からおよそ30年前の1984年「岩手の食事」から刊行開始され、足かけ10年、1993年2月に完結した。日本の各地の大正末期〜昭和の初めの食生活を、当時を知るおばあさんたちに、聞き書きしてつくられた極めて貴重な記録である。食文化の国際比較研究の第一人者である石毛直道氏(完結当時、国立民族学博物館教授)は、「一民族の食事文化の、これだけ多くの地点での調査は世界唯一のものである」と評している。
各地域で、数人のおばあさんに集まってもらい、昔の食を思い出してもらい、実際につくってもらいながら聞き書きはすすめられた。当時の主婦たちの「食事つくり」とは、田畑で育てられた農作物、山や川や沼が恵んでくれる山菜や川魚など、そして海岸から運ばれてくる海産物、それらのすべてを頭に入れて、一年中家族全員に不足なく、楽しみながら食べ続けられるようにすることであった。
人間が自然に働きかけ、自然が人間に働きかけ返す(自然に学ぶ)、その数千年に及ぶ積み重ねで日本の食文化は生まれた。「食」が農を育み、「農」が食を育むという日本の伝統的な家族農業がもつ「生産と生活の循環・一体性」のなかに、和食の文化は、その成立の根拠を見なければならない。さらに、その「食」と「農」は日本の「むら」(コミュニティ)の特徴である「自給」と「相互扶助(お裾分け)」の農村社会のなかで育まれてきたものである。
この「和食」を、海外で知名度を上げ、和食に使う日本の農水産物や加工食品を海外へ輸出できるという浅はかなソロバン勘定に貶めてしまってはならない。ましてや、「攻めの農林水産業」で国内農水産物の輸出を増やすというTPP戦略の一環に利用されては、本末転倒である。
山と田畑、川・海の循環、里山里海など、国民一人ひとりが美しいと感じるふるさとが伝統的な食文化の源泉である。それを育んできた家族農業を守ることなしに、「和食」の誇りを次世代に継承していくことはできない。「和食」を国民的財産として保全していく運動は、地域ごとに家族農業が立ち行くように新しい仕組みをつくること、これによって、そこに住むみんなが豊かになる地域再生をすすめる運動なのである。TPPとは真逆の世界なのだ。
▲目次へ戻る
「国際家族農業年」と「人類史的な転換」
もうひとつの「国際家族農業年」。家族農業が国際機関から注目されているのはなぜか。なぜ今「国際家族農業年」なのか。国連の世界食料安全保障委員会の報告書(原題「食料安全保障のための小規模農業への投資」)からいくつか挙げると以下のようである(2月初旬、この報告書の訳本を農文協より発行予定)。
・家族農業・小規模農業は多くの国の食料保障の基礎であり、すべての国の社会・経済・環境面で重要な要素を構成している。その家族農業が、都市化ならびに市場の統合化・グローバル化につれて大転換を迫られている。
・輸出志向型の大企業が優遇される大規模経営偏重政策によって小規模経営は無視されてきたが、史実が示すように、政策と公的投資による適切な支援が行なわれれば、食料保障、食料主権、経済成長、雇用創出、貧困削減、空間的社会経済的不平等の是正に大きく貢献する能力が小規模農業には備わっている。
・多様化した生産システムのなかで家族労働力を活用することによって、単位面積当たりでは高い生産水準を達成し、自然資源の持続的利用と環境負荷の軽減、化石燃料の節減など、効率的で持続的な農業を進める小規模農業の事例が多数報告されている。
今、国際的に農村開発政策や農業政策が見直され、国際社会の政策課題は大規模・企業的経営優先から家族経営支援へ大きく舵を切ったのである。転機となったのは、2008年の食料危機(穀物急騰)と経済危機(リーマンショック)の勃発、さらに、経済危機や財政危機による失業率の高止まりなどだが、この変化は単なる対応を超えた「人類史的な転換」に向かうであろう。
「スモール イズ ビューティフル」で有名なイギリスの経済学者シューマッハは、そもそも、農業生産における人間と自然の関係は、最大利益を求めて世界を移動する自由をもつ企業とは根本的に異なるとして、農業の国際分業論を批判し、農業の目的を次の三つに整理した。
(1)人間と生きた自然との結びつきを保つこと。人間は自然界のごく脆い一部である。(2)人間を取り巻く生存環境に人間味を与え、これを気高いものにすること。(3)まっとうな生活を営むのに必要な食糧や原料を自らつくり出すこと、の3点である。
シューマッハは、現代の危機の打開にむけ、「人間の身の丈にあった技術」を生かした「大衆による生産」こそが、労働と自然の破壊をもたらす現代文明の危機を打開する唯一の道だとした。「世界中の貧しい人たち、農家を救うのは、大量生産ではなく、大衆による生産である」として、農村と小都市に何百万という数の仕事場をどのようにして作り出すかが、現代文明の危機を克服する核心であると主張したのである。この土台にあるのが自給を基礎におく家族農業であり、家族農業を基礎とする農村である。
家族の次に社会の真の基礎をなすのは、仕事とそれを通じた人間関係である。その基礎が健全でなくて、どうして社会は健全でありえよう。そして、社会が病んでいるとすれば、平和が脅かされるのは理の当然だ。大衆をもっぱら消費する存在として拡大再生産していく現代社会を、「大衆による生産」に基づく社会に変革していかなければ人類に希望はない…これがシューマッハのメッセージである。
▲目次へ戻る
「農政改革」と「農業・農村の多面的機能」は両立しない
農業は「地域資源」を活用する生業である。この地域資源の特徴を永田恵十郎氏は次のように整理している(『地域資源の国民的利用』1988年・農文協刊より)。
この地域資源の第一の特徴は、石油などどこへでも自由に移転できる資源一般ではなく、その地域固有の風土・生態系のなかに位置づけられてはじめて意味をもつもので、そういう意味でその地域だけに存在する資源、非移転性の資源である。
したがって第二の特徴は、地域的に存在する資源相互間に有機的な連鎖性があること。山(森林)・川(水)・田畑(耕地)・海(水産)はひとつの有機的連鎖性をもって存在しているのであって、この連鎖性が破壊されたときは地域資源そのものあるいはその機能は喪失してしまうのである。
さらに、その第三の特徴は、以上二つの特徴に規定されて非市場的性格をもっていることである。
非移転性、有機的連鎖性、非市場的性格―こうした性格をもつ地域資源を維持し、豊かにし、永続的に利用するしくみと技術を築いてきたのが農家の生産と生活であり、むら(コミュニティ)である。そこから、いわゆる「農業・農村の多面的機能」も生まれる。
農水省は「農業・農村の多面的機能」については次のように説明している。
「例えば、水田は雨水を一時的に貯留し、洪水や土砂崩れを防いだり、多様な生きものを育み、また、美しい農村の風景は、私たちの心を和ませてくれるなど大きな役割を果たしており、そのめぐみは、都市住民を含めて国民全体に及び」、こうしたお金で買うことのできないめぐみをもたらす農業・農村を支えるために、「農地・水保全管理支払交付金、中山間地域等直接支払交付金等の施策を行っている」。
しかし、その当の農水省も、冒頭で述べたように、「生産調整の5年後廃止」、「経営所得安定対策の定額補助金の減額・廃止」の検討を始める始末である。米政策・水田農業をめぐる「農政改革」が小さな家族農業の離農を促進する性格を強くもつ以上、「日本型直接支払」が目的とする「農業・農村の多面的機能」の維持との両立は不可能である。
▲目次へ戻る
グローバル企業の世界戦略の禍は地方にも都市にも
「農業・農村の多面的機能」の「めぐみ」を受ける国民は、今や、2人に1人が3大都市圏に住んでいる。そして大都市では、少子高齢化(長寿化)のなかで、極小世帯化がいっそう進んでいる。その典型が、世代継承機能を喪失した極小世帯家族が過半を占める都市近郊団地社会である。
この都市型社会は化石エネルギー資源とそれらあらゆる熱源・動力源を変換した電気エネルギーに依存せずには一日たりとも立ち行かない社会でもある。そこに住む住民は容易に移動できないが、巨大企業群は最大利益を求める自由、グローバルな可動性をもっている。2013年7月の、世界的な自動車の街として知られる米ミシガン州デトロイト市の財政破綻がそれを象徴している。
現在、国・経済団体・マスコミをあげてすすめられている成長戦略は、その意図とは裏腹に国土不均衡拡大、内需のさらなる縮小につながる。それは都市と農村の格差だけでなく都市の中の格差を広げ、都市に孤独と貧困をつくりだす。グローバル企業の世界戦略の禍は地方にも都市にも及ぶ。
「農業・農村の多面的機能」として食料・原料生産機能と同時に、自然・国土保全機能、人格形成・教育機能、保健休養機能という3つの公益機能が挙げられている。この公益機能は、家族農業とむらがあってこそ機能する。
和食の世界文化遺産、そして「国際家族農業年」という国際社会の新展開を大いに話題にし、農業・農村の国民的価値を国民的な共有認識にする活動を強める、2014年をそんな年にしたい。
▲目次へ戻る
「人・農地プラン」で発揮 農家・地域の土地利用調整力
今、急浮上している農政改革の直接的なはしりは、2007年、第一次安倍政権の時に実施に移され、戦後農政の総決算ともいわれた「品目横断的経営安定対策」である。担い手への施策の集中化・重点化をはかる観点から面積要件のみによって担い手を絞り込み、10年で40万の担い手を育成し、そこに生産の7〜8割を集積することを想定したものである。この担い手絞り込み路線、小さい農家の離農促進政策は、民主党時代の「人・農地プラン」にもひきつがれた。
しかし、この「人・農地プラン」のビジョンづくりは、政府の意図を超え、農村現場の努力によって家族農業とむらを守る共同活動としてすすめられている。
たとえば、島根県では、「集落の将来のあるべき姿、あるいはこうありたいという姿をイメージしたもの」が集落ビジョンであると定義し、人と農地の課題と併せて、地域での暮らしの視点も含めたビジョンづくりを推進している。集落営農も、むらを守る共同活動を元気に展開し、家畜の再導入、再生エネルギー政策の追い風を生かした山・里山利用、高齢者の外出支援のような地域貢献活動など、さまざまな取り組みが生まれている。
農地利用の調整にもいろいろな工夫がみられる。たとえば長野県飯島町では、全戸参加の「営農センター」のもと、農家が地域農業の再編に参画。営農センターの下には四つの地区営農組合が置かれ、この組合が農地の借り手・貸し手の意向を丹念に聞き取り、それにもとづいて農用地利用計画を作成し、農協を介して土地利用調整を進めている。そして、各地区営農組合にはそれぞれにオペレーター型の法人を設立した。その一つ、田切農産は、農地を借り受けたり、地区内農家の機械作業を全面的に受託するかたわら、直売所や加工の取り組みも進め、地域を活気づけている。この「法人としての利益は残らないが、みんながやる気を出して農業を続けられるしくみ」は、担い手が多様に育つ場をつくることを目標に、JA上伊那と飯島町がサポート役に徹することで実現したものである。
こうした地域による土地利用調整力の発揮、その広がりに業を煮やしたかのように、政府は「むらの話し合い」を促す「人・農地プラン」の法制化は見送って、「農地中間管理機構」法案を閣議決定した。農地利用調整の主体を市町村から「機構」に移し、「公募」による農外企業の参入も含め、農地の八割をTPPに対応する「強い農業」の「担い手」に集積することをねらったものである。
しかし、こんな当事者抜きのやり方は農村をおかしくする。耕地は、非移転性、有機的連鎖性、非市場的性格をもつ地域資源の根源であり、その利用は、農家とむら、これをサポートする市町村や農業委員会、地域のJAが担ってこそ、その持続性が保たれる。
自然とともに生きる農家は自然がそうであるように、個性的かつ自給的な存在であり、それゆえに共同が生まれる。
石油高騰、米価下落など、困難な状況だが、困難な時ほどこの「農家力」は発揮される。そして、これまでもこれからも、農家力が農耕文化、食文化を育み、「多面的機能」をもたらす。個的にして全的な存在―そこに「家族農業の大義」がある。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
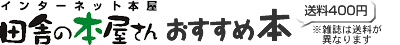
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2014年1月号』
特集:根はいいヤツだ
新米農家、先生のワザを引き継ぐ/炭酸ガス安くスパッと効かせる/果樹の夢のような仕立て2014/山の茶産地を共同の力で守る/ケータイ・スマホでハウスチェック/介護操体の「こんなにラク」を見た/昭和ヒトケタ世代の健康法/菜園修業中、加工もフル回転! ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『日本の食生活全集 全50巻』農文協 編
おばあさんからの聞き書きで、各県の風土と暮らしから生まれた食生活の英知、消え去ろうとする日本の食の源を記録し、各地域の固有の食文化を集大成する。救荒食、病人食、妊婦食、通過儀礼の食、冠婚葬祭の食事等。[本を詳しく見る]
|
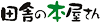
|









