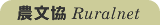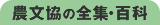「合理的農業の原理」を推薦します
「農業革命」と「産業革命」―テーア農学の時代と意味
京都大学名誉教授、福井県立大学学長 祖田 修
「農業革命」−イギリスからドイツへ
テーアが生まれたのは1752年、主著『合理的農業の原理』全4巻が刊行されたのは1809〜1812年であった。他方アダム・スミスは1723年に生まれ、『国富論』が刊行されたのは1776年である。そしてイギリスの産業革命は1770年に始まるとされている。テーアの方が約30年遅く生まれているが、同じ時代潮流の中にあったといってよい。彼らはそれぞれ、農業革命と産業革命の遂行と連動を、理論的具体的に背負い、代表する存在であった。
時代はまさに封建社会が終わりを告げようとし、資本主義社会いわばスミス流に言えば、自然的自由の制度、自由な個人の時代へと転換しつつあった。産業革命によって、工業は次第に工場制生産となり、生産力は飛躍的に高まり、人口は爆発し、国民の富が増大する基盤が築かれていく時代であった。
だが、先行するイギリスに比べ、ドイツは1800年代に入っても、なお40余の領邦国家に分かれ、互いに関税障壁を設けて対立していた。リストはドイツの状況を嘆き、1841年『政治経済学の国民的体系』を著すが、ついにその行方に絶望し、ピストル自殺を遂げる。テーアの『イギリス農業入門』は、こうした時代の中で、先進的に展開するイギリス農業を賛美するものであった。確かにイギリス農業は、ノーフォーク農業に代表されるように、冬作物―夏作物―休閑をルーチンとする、中世的な三圃式農業から近代的な輪栽式農業と呼ばれる、休閑を廃止した生産力の高い農法を実現しつつあった。
テーアはレッシングに哲学を学び、アダム・スミスの経済学を熟読し、イギリス農業に学び、ドイツを調べ、ドイツ農業の向かうべき方向、近代農学の方向を『合理的農業の原理』として指し示したのであった。
“合理的”の意味
この著作は、まさに「合理的」というキーワードによって、すべてが語られているといってもよい。テーアによれば、合理的とは「計算、熟考、理性、本質、計画」といった語群で表される。M.ウェーバーは、近代資本主義のシステムを、中世的・神学的な「魔術の世界」から「計算合理性の世界」への転換と表現するが、テーアの思想はまさにそうした事態の農学版といってもよい。
『合理的農業の原理』は、目次を一見して分かるように、農業経営・経済学、農業簿記、土壌学、肥料学、農業機械学、水利学、作物学、畜産学など、農学のほとんど全領域を原初的な形で提示し、総合している。テーアはまさに「農学の祖」というほかはない。イギリスは農業の先進国であったが、農学の先進国となったのはドイツであった。
その主要な論点は、フームス(腐植質)肥料論、舎飼い畜産論、作物輪作論である。これらを適切に組み合わせ循環させた時、三圃式経営から脱し、新たな合理的経営、すなわち最大可能な永続的農業利潤の獲得が達成される、というのである。それはまさしく、人為的なシステムの世界であるが、同時に自然の循環システムと連動する、農業・農学の真骨頂を具体化したものである。人間活動と自然の生命活動の織り成す、循環と共生のシステムこそ、農学という実際科学の特徴であり、本質でなければならない。
農学の発想が現代を救う
テーア以後、農学は「人為」の要素を強め、生産力を一層高めていく。しかし同時にそれは、「人間の知の力」によって自然を克服し支配しようとする、工業的技術の世界を目指すベーコン、ニュートン、デカルトの近代科学思想に引きずられ、「農業の工業化」を推し進めた。それがもたらしたものは、今日の食の安全、環境汚染をめぐる問題である。
現代の人口規模、人間諸活動の規模から見て、テーア農学の時代に戻ることは不可能と思われるが、工業的世界が見失っていた人間と自然の適切な関係は、農学的発想の中から最も妥当な形で生まれてくるであろう。テーアがそうした学の原点にいることは、間違いのないことである。
近代農業の原理(物質循環論)に学ぶ現代の課題
―初の日本語訳『合理的農業の原理』発刊によせて―
東京大学名誉教授 熊澤 喜久雄
テーアの生きた時代
テーア(1752〜1828)は18世紀末から19世紀の初めにかけての、ヨーロッパにおける最も著名な農学者として知られている。
彼の時代はゲーテ(1749〜1832)、シラー(1759〜1805)、ベートーヴェン(1770〜1827)あるいはナポレオン(1769〜1821)などの活躍に見られるように、フランス革命を挟んだ疾風怒濤時代であった。社会の様々な分野での新しい動きが、姑息で閉塞した社会の変革に向かっていた。
農業分野においても、生産力の向上を求めて、伝統的な、なかば法的に強制されるようにして営まれてきた農法=三圃式農法に代わる新しい農法を求める動きが活発化しつつあった。
宮廷医から農学者へ
テーアは宮廷医としての業務のかたわら、農業改良をめざして結成された王立農業協会の会員、特別委員として活動するようになった。
改革の進んでいた英国農業の研究をした後、あらためてドイツの農業の現実から出発し、それを発展させるために、1804年にメークリンに土地を取得し、農学アカデミーを創り、農業・農学の研究と教育をした。ここでの多年にわたる調査研究の結果に基づいて、『合理的農業の原理』が執筆された。
地力維持と持続可能性で農法を評価
テーアは農業を営むために、とりわけ必要とされるのは、農業者の能力、資本、土地であるとし、とくに一定の土地利用、資本投下により最大の利得を得るように、自然科学なかでも物理学と化学の成果に基づいた判断により、農法の選択をするべきであるとした。
農業はまた、持続可能でなければならない。土地は資源であり、資本である。一時的な利得の獲得のみを目指して有利な作物のみをつくることにより、土地が疲弊し、荒廃地となる自滅の道をたどることは避けなければならないとして、作物栽培、家畜飼養体系と土地の地力・肥力維持との関係をとくに重視し、それぞれの農法の評価をすることになる。
家畜の舎飼いが地力の基
三圃式、多圃式農法と輪裁式農法の比較をしながら、土地から得られる最高の収益は、舎飼方式と結びつくことによってのみもたらされ、舎飼式経営の利点は農業に必須の農地に対して、最適の発酵状態の厩肥を意のままに施すことができることであると論じている。さらに各種農法における地力増減の計算例を示し、厩肥の供給が地力回復に大きな寄与をするという「地力均衡論」が展開された。
地力均衡論にたち、多くのすぐれた事例の帰納的研究から、「経営全体から最高の純収益を持続的に達成すること」を目標にして、最も合理的な農業経営を営むべきものであるとしたテーアの理論は急速に受け入れられ、三圃式農法から多様な作目選択の自由を持つ輪栽式農法への転換は、農民の封建的束縛からの解放、農業生産力の発展をともないつつ普及していった。
経済至上主義にゆがめられない原理を学ぼう
テーアは『合理的農業の原理』において、個別的な作物・畜産経営を包含した農業技術を全面的に記述すると同時に、それらの考察の中から近代農学的原理を明らかにし、土壌資源維持の国家的意義を含め、物質循環論、地力保全論、作物・畜産生産論などを展開している。
そこでは個別的農業を普遍的原理から理解し改良実践すること、とりわけ堆厩肥と各種肥料の利用による地力均衡あるいは土壌生産性の持続的維持を農業経営原理として確立することの重要性が説かれている。
現在は「腐植説」として知られる土壌有機物質循環論は、リービヒの無機成分循環論に引き継がれ、現在の生物圏における物質循環論の嚆矢となっている。しかし、テーアの認識していた有機物利用の持つ土壌の物理性や微生物性の改良効果は、近代農業の発展過程でも軽視された感は否めない。
合理的農業の発展に貢献したテーアの思想や具体的研究内容を正確に理解することは、環境との共生、土壌資源の保全を基礎に農畜産業の持続的な発展をはかる真の有機的農業のあり方や、経済至上主義にゆがめられない社会的資本の投入の方向性など、現代社会あるいは現代農業の抱える諸問題を考えるうえでも必要とされよう。
農の一部しかとらえきれない「学」でいいのか
百姓・農と自然の研究所代表 宇根 豊
農学に限らず「科学」は狭く深くなりすぎて、全体が見えなくなっている。学問や科学が発展すれば、世界がよく見えてくるというのは、幻想だったのだろうか。
むしろ、学の草創期には、見ようとしていた全容が、なぜ見えなくなってしまったのだろうか。新しい学を構想する者は、知の体系を構築していこうという壮大な見取り図を描こうとしていた。だからこそ、挫折も味わわなければならなかった。
アダム・スミスは百姓仕事がわかっていた
たとえばアダム・スミスは、モノやコトの価値は「交換価値(経済価値)」ではなく、「使用価値」にこそあることを知っていて、使用価値の知の体系を目指したが果たせず、交換価値の経済学の創始者となった。
主著『国富論』は気概にあふれた書であり、なかでも私は次の部分にうたれた。「農業では自然もまた人間とともに労働する。しかし、製造業では自然は何もせず、人間がすべてを行う。」アダム・スミスは、百姓仕事と工業労働の違いがよく見えていたが、百姓仕事を「学」にできなかった。その後の「労働論」や「経済学」が貧しいのはそのためであろう。
現代の「学」は農と自然をとらえきれない
私たち百姓は、新しい農法が登場すると、すぐに「収量」と「労働時間」をたずねてしまう。決して「仕事が楽しくなったか」「自然とのつきあいは深まったか」などとは聞きもしない。最近ではおいしい作物を「糖度が高い」などと、成分で表現するのがあたりまえになってしまっている。あるいは、「農薬の残留がない」というのが「安全性」の証明になっている。他の表現方法もあるのだが、そういう「知」の構築方法に慣れてしまっているからである。それが「科学的」だと言われている思考法であり、「学」の主流である。
しかし、こうした見方だけでは、工業はともかく農の営みの大半が見失われていく。今年もテレビを見ていると、甲子園球場で「赤トンボ」が群舞していた。これは「自然現象」だと思われている。あの赤トンボの99%が田んぼで生まれていて、全国では200億匹になること、などに思いを馳せる人はほとんどいない。
ここでは赤トンボは決して「科学的」に「農学的」にとらえられてはいない。つまり一方で、農学はこうした農が生み出した「自然」をとらえる方法論を形成できていない。
農学の土台には百姓の情念が
田んぼの中の草の多くは、絶滅危惧種である。それなのに、3種も4種も成分を含んだ除草剤が散布され続けている。草の名前をほとんど知らない百姓も少なくない。「生産」からこぼれ落ちていくものへのまなざしが、現代の農学には希薄である。
かつての百姓は草の名前を200種以上知っているのがあたりまえだった。それは「科学」「農学」でとらえていたからではなかったからだ。それを農学でとらえようとすると、なぜ自然の生きものから百姓は遠ざかるようになってしまうのか。「近代化だけを追求するのが農学だ」というのでは、学はやせ衰えるしかない。
農学は、百姓の赤トンボに包まれるときの仕事の充実や、花咲く草への情愛も対象としてもよかったのではないか。そういう百姓の情念が土台となって、科学的なまなざしは成長してきたのではなかったのか。決して、調査データや収入金額だけでは、農の営み全体をつかんで、豊かにすることはできない。このことをもっと認識しておかなければ、学も時代精神に埋没して、その時代の要請に応えるだけの狭量な学になってしまうだろう。
「学」の原初の志と豊かな構想力に学ぶ
自然と一緒に仕事する農、したがって自然の生きものへの情愛に支えられて生きていく百姓の人生を、他産業とは異なるまなざしでつかんでいくのが「農学」ではなかったのか。
他学の土台であった農学の原初の志を、そして創学期の学者の豊かな構想力にもう一度学びなおそうと思っていた矢先に、農学の産みの親であるテーアの本が新しく訳されて出版される。心待ちにしているのだ。
甦る農学に未来を
樺山紘一(東京大学名誉教授、印刷博物館館長)
200年の昔、新設のベルリン大学で農学講座を担当したテーア。この人とともに、農学は前近代を脱して、経済社会に枢要な地位を獲得した。近代とは常識とことなり、農業を侮る社会ではなく、環境と地力とに信頼をよせ、農民に経営の実を寄託できる、希望にみちた社会になるはず。のちに厚顔な科学技術と浅薄な社会政策とに、いくども裏切られながら、いまふたたびテーアの農学は輝きをとりもどす。農学に21世紀の未来を。
現代の課題に生きる「建設の農学」書
磯辺俊彦(元千葉大学教授)
テーアのこの本は、土地耕作の最も生産的な形(農業重学の基準)が同時に経営の最も収益的な形(私経済の規準)であり、さらに社会の全体利益は、こうした経営の自由な競争的秩序から得られる(国民経済の基準)と考えて、この三位一体の構築を努力目標とした「建設の農学」書であった。その「建設」の課題は、現代ではいっそう痛切なものだ。同学の相川哲夫氏が多年にわたって、コツコツと積み上げられたこの完訳書を、確信をもって、お薦めしたい。
深い思索と先駆的な理論をじっくり学べる「古典」
七戸長生(北海道大学名誉教授)
昨今のエタノール化の動きで揺れている世界の食料・農業の問題や、一刻の猶予もなくなった地球規模の環境問題をみるにつけても、こういう時こそ、優れた先人の深い思索と先駆的な理論の展開をじっくりと勉強できる「古典」の有難さを痛感させられる。今、まさに時宜を得た形で、待望久しいテーアの「古典」が紹介され、近代農学の始祖と呼ばれる彼の一連の業績に接することができるのは、誠に御同慶の至りに思う次第である。
フムス理論・輪作原理を学ぶ意義は大きい
有原丈二((独)九州沖縄農業研究センター所長)
江戸時代のわが国は世界に冠たる農業生産性を誇り、農民の生活水準は欧州農民より高かったことが明らかになりつつあるが、それを支えていたのは徹底した有機物投入であった。19世紀以降、世界の農業技術は窒素肥料を中心に展開されてきたが、歪みも顕在化し、わが国の農業にも陰をさしている。この時、テーアの『合理的農業の原理』でフムス理論、輪作原理などを学ぶことは、農業技術者にとっては非常に意義深いものとなろう。
「土の生気の魅力」がテーアを農に向かわせたのでは
津野幸人(鳥取大学名誉教授)
医師としての地位と名声を放擲して、乏しい地力の農場経営にテーアを専念させたものは何であったろうか。それは農地が発する土の生気の魅力、つまり彼のいうNeigung(内的な感激)ではなかったろうか。ここが彼の出発点であり、その具現が到達点であった、と私は理解する。彼を始祖とする農学は、瘠せ地を豊穣の地に変える実用の学でありその体系である。これを、全訳によって再確認する機会をえたのは真に喜ばしい。
減農薬、減肥には輪作が不可欠、参考にしたい
西尾道徳(元筑波大学教授、元農水省農業環境技術研究所長)
かつての畑作農業では輪作が不可欠だった。現代農業は,肥料や農薬によって,地力を高め,連作を可能にして作付自由度を高めた。これは技術の勝利だろう。しかし,そのゆがみとして,食の安全性と環境の保全がそこなわれている。肥料や農薬を節減するには輪作が不可欠だ。テーアの考えが現代にそのまま適用できるとは思えないが,テーアの名著をこれからの農業のあり方を考える参考にしたい。
本書は土地―人間―生物系の統合科学としての農学の原点
堀江武((独)農業・食品特定産業研究機構理事長)
要素還元的な、西欧近代科学の解析手法を用いて発展してきた今日の農学は、様々な学問分野に細分化され、その全体像がかすんできている。一方で、地球環境問題など、その解決には諸科学を統合したアプローチを必要とする重要課題が増えてきている。こういうときにこそ、土地―人間―生物系の統合科学としての農学の原点ともいえる本書に立ち返って考えることが必要ではなかろうか。
畜産問題の根本的打開の参考にも
萬田富治(北里大学獣医学部フィールドサイエンスセンター長、元(独)北海道農業研究センター)
将来世代の自然資源利用の可能性を損なわない、「持続可能な社会」の構築が人類共通の課題となっている。農業についても、物質循環機能を生かし、環境負荷の軽減に配慮した「環境保全型農業」から究極の「有機農業」まで、国民的関心が高まっている。特に、海外飼料に大きく依存する畜産問題を根本的に打開するための、飼料生産と飼養管理についても詳細に述べられており、参考になる点が多い。本書は本来の農業のあり方について執筆されており、環境保全型農業をはじめ、有機農業に関心をもつ多くの方々に座右の書として推薦したい。
農業の近代化は略奪農業から持続可能な農業への転換だった
吉田武彦(元農林水産省北海道農業試験場次長)
リービッヒとテーアは、近代農学の幕を開いた巨人である。そして、テーアとリービッヒは対立的に語られることが多いが、農業の近代化とは、略奪農業から持続可能な農業への転換であり、そのための地力源泉の償還という核心の原理は両者に共通している。農業や産業一般の持続可能性が問題とされている現在は、『合理的農業の原理』に集大成されたテーアの思想は、今なお光を放っているといえよう。困難な時期には古典を学べ、とはまさに金言である。
農学の危機克服へ、テーアを学ぶ意義は大きい
渡部忠世(京都大学名誉教授)
農学の危機あるいは変質がいわれ出してから久しい。しかし、農業が自然と人間と他の生きものとが一蓮托生であるとする営みであり、農学がそれを対象とする学問である限り、これこそ21世紀後半以降の地球を支える領域であることはまちがいあるまい。今、リービッヒやメンデル以前にたち戻って、テーアの考えをあらためて学ぶ意義は小さくないと思う。