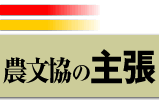 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1995年4月号
|
|
都市と農村は 平素からの親戚づきあいを ――阪神大震災被災者の農村「疎開」に考える 戦後最大の自然災害となった1月17日の阪神・淡路大震災は5300名を超える方々の貴い生命を奪い、兵庫県南部地域に甚大な被害をもたらした。この震災で亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、怪我をされた方々、いまなお避難所生活を余儀なくされている方々にお見舞いを申し上げたい。 この震災に関しては地震発生直後から、国民のほとんどといっていいほどの広範な方々が、それぞれの立場で支援の手をさしのべてきた。全国各地から現地へ飛び、ボランティア活動にたずさわっておられる方も数多い。ここでは、そうした幾多の営みのなかのひとつの動きに注目してみたい。 ◆震災4日後に早くも発表された
震災の衝撃もまださめやらぬ1月21日の朝日新聞「論壇」欄に、ひとつの投稿が掲載された。投稿者は東京農工大学助教授の千賀裕太郎氏。千賀氏は「緊急の提案」として周囲の市町村の協力によって被災住民を「緊急疎開」させることを呼び掛け、その理由を次のように述べていた。「避難生活者が30万人という数字は、その対策について発想の転換が必要であることを示している。被災者の中には、寒中外にテントを張って夜を過ごす人もいるし、避難場所の体育館も超満員である。この大寒の時期では、こうした生活に何日も耐えられるものではない。」 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |