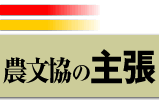 |
|
|
||||||||||||||
| 農文協トップ>主張>
1995年5月号
|
|
認定農家を核に村々にネットワーク農業を
◆認定農家は10〜20ha農家という誤解「無理だよ、オレなんて。だいたい認定農家になんかなりたいなんて思ってないもん」米どころ東北地方の40代の農家Fさんに、「認定農家に手をあげたかどうか」尋ねたときの答。Fさんは、イネ3ha、ナシ80aを栽培し、近所の人から頼まれてイネの苗をつくり、秋には刈取りの手伝いもする。そういう人だ。 そんなFさんが認定農家になるのは無理と思っているのは、「10haとか20haとか大きくやってないし、大きくするつもりもない」からである。町から誘いがあり、認定農家についてのパンフを読んでそう考えた。これはFさんだけでなく、近くの仲間がみんなそう受けとめているという。 この「10〜20ha」が認定農家の基準と思っている人は多いようだ。認定農家について語る際の「枕詞」になってしまっているとさえ思える。 しかし、今回の認定農家制度にはそんな基準はない。もし、大規模化しなければ認定農家の対象にならないと思っているとしたら、それは思い違いだし、そうとしか読めないようなパンフを市町村がつくっているとしたら、その市町村ではすぐにパンフをつくり直したほうがいい。 実際、この2月末現在、全国で1万247経営体(法人を含む)が認定されているが、10〜20ha以上の経営は少数派、むしろ5ha以下の複合経営農家が多いのである。 では認定農家とは何か、どのように決められるのか手短かにみる。 いま日本の農政は、3年前、農水省が打ちだした『新しい食糧・農業・農村政策の方向』(新政策)にそって行なわれている。その「新政策」を推進する核が認定農家というわけだ。法的には1昨年8月に施行された「農業経営基盤強化促進法」にもとづき、将来にむけ農業に意欲をもって取り組む農家が認定される。その認定基準が、都道府県のつくった「基本方針」を受けて市町村がつくる「基本構想」だ。 市町村は、それぞれの置かれた条件をもとに、今後どんな農業を展開していくかを描き、導入作物、販売方法なども検討しながら経営目標を示す。その前提になるのは、〈農業を職業として選択し得る魅力のあるものとするため、労働時間は他産業並みの水準とし、生涯所得も地域の他産業従事者と遜色ない水準とすることを目標とする〉(新政策)。 この目標を実現するために市町村は、地域の先進事例等を踏まえ、所得目標、労働条件など「農業経営指標」を営農類型別に提示する。 この「経営指標」を参考に生産者が、5年後までにこうしたいという「経営改善計画」を市町村に出し、それが認定されると、認定農家ということになる。 つまり、認定農家の基準をあえていえば、地域の他産業従事者なみの所得を農業で実現しようと思うかどうかだけである。地域として、どういう農業にするかが問われる。 ◆大小相補のネットワーク農業つくり具体的にみていこう。長野県駒ヶ根市の野村忠義さんは、昨年6月、経営改善計画が市から認定され、はれて認定農家になった。野村さんは64歳。地域のことをよく知り、肉体的にはまだまだ若い。 野村さんの経営改善計画は、養蚕をやめてその代わりに花(ユリ、チューリップの球根生産)を入れること。その実現のためにパイプハウスを建てようとすると、間口6m、奥行45mのものを3連棟として500万円かかる。ところが野村さんは、国の「リース事業」(経営育成促進構造改善事業のなかの手法の一つ)を利用した。農協が国から補助(最高50%)を受けてパイプハウスを建て、そのパイプハウスを野村さんが借り受けて農協にリース料を払うのである。10年間、毎年30万円程度支払うことでよい。 経営を拡大しようとすると、どうしてもそのための費用が多額にかかる。野村さんが、その費用を少しですますことのできる「リース事業」を利用できたのは、認定農家になっていたからである。 この他認定農家になることのメリットはいくつかある。 ◎まず、野村さんが利用した「リース事業」のように、認定農家支援を目的とした補助事業(経営基盤確立農業構造改善事業)が利用できること。 ◎また、融資を優先的に受けられること。これにはスーパーL資金とスーパーS資金がある。 スーパーL(農業経営基盤強化資金) この資金は今後、規模拡大したり、新規部門を始める際に借りることができる。利用できるのは、田んぼなど農地取得、機械の導入・更新、ハウスなど施設や加工所、直売所などの建設、負債整理(プロパー資金などの借りかえ)など。金利は2.5%(県・市町村の利子助成により、もっと低くなる。駒ヶ根市の場合、この4月から1.25%)。償還期間は25年以内(うち据置期間10年以内)。その借り入れ限度額は個人の場合1億5000万円(複合経営3億円)、法人5億円。なお、このスーパーL資金は担保がなくても借りることができる。 スーパーS(農業経営改善促進資金) この資金は、種苗代、肥料代、機械修理費等の計画達成に必要な運転資金。金利は3.3〜3.8%。償還期間は1年以内。その借り入れ限度額は個人の場合500万円、法人2000万円(畜産・施設園芸の場合は、それぞれ4倍)。 ◎税制面での特例が受けられること。 青色申告をしており、一定以上の経営改善(経営規模拡大など)をすると、普通の償却額の20%を、通常の償却額に加える割増償却が適用される。また、農地を購入するための積み立て金が損金算入できる。 ◎なにより、地域の人たちから農地が借りやすくなること。 市町村や農協などに申し出ると、農地の提供者がある場合、優先的に斡旋してくれることになる。農地を購入する際、助成もある。 このように認定農家になるとメリットがいろいろあるが、これは認定農家にその地域の農業の核になってもらい、地域を引っ張って農業を盛り上げてもらいたいという国としての狙いからである。再び駒ヶ根市の野村さんにみる。 野村さんはリース事業を利用して借りるパイプハウスで、この秋(9月)から花を始めるが、そのハウスでは春先にイネの育苗を行なう。ことしは3000箱。野村さんが作付けている借地も含め4.5ha(自作地は1ha足らず)の他、頼まれて行なう田植えの分も含め1400箱使う。そして残り1600箱の苗は、近所の勤めながらイネをつくっている人に使ってもらう。5俵とか10俵とか、飯米用につくる人が多い。つまり、ハウスは野村さん自身のためと地域のイナ作のためと、両方に使われるのである。 育苗だけでなく、春先の耕起、代かき、田植え、刈り取りと、野村さんが機械作業を引き受けているのは120人以上になる。 野村さんは個人として機械作業を引き受けているが、駒ヶ根市ではどこの集落にも営農組合があり、そこで機械作業を引き受ける。イネを比較的大きくやっている人がオペレーターになり、そのほとんどが認定農家になっている。野村さんと同様、勤めていて土曜、日曜しか作業できない人の育苗、高齢などで機械作業のできない人の刈り取りなどを積極的に引き受ける。自らの経営もよくなり、地域の農業もまわることになる。 勤めが中心の人も安心してイネつくりが続けられるし、お年寄りは毎日、田まわりを楽しむことができる。 また、お母さん方は、機械作業はやってもらえ、田まわりなど日常管理でお年寄りが頑張ってくれる分、野菜つくりに励める。自家用野菜を多様にしかも多めにつくり、食べ切れない分を農協に出荷する。この自家用野菜が、生協の消費者に喜ばれている(後述)。お金も入ってくるから、また励みになる。 このように地域のいろんな人の支えとなり、地域を引っ張る核になるのが認定農家。その認定農家が、より強く地域を引っ張れるよう国が応援しようというのが認定農家制度なのである。 つまり、国は認定農家を支援することを通して、実は地域全体に対し、すなわち勤めの人が安心して勤められるように、お母さん方が野菜つくりに励めるように、お年寄りが農業を楽しめるように応援する。そのように認定農家制度を利用したい。 ◆地域の農業は
そのためにはどういう農業をやりたいか、それぞれの地域に相応しい構想が必要だ。 |
|
お問い合わせは rural@mail.ruralnet.or.jp
まで 2000 Rural Culture Association (c) |