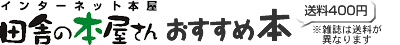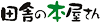TPPをめぐる俗論を反証する
緊急出版『TPP反対の大義』より
目次
◆横行する数字のトリック、おかしな議論への反証
◆「国益VS農業保護」論は、国益に反する
◆「貿易を拡大しないとやっていけない」論のまちがい
◆雇用は守られず、逆に破壊する
先月号に続き、TPPについて考えてみたい。
マスコミのTPP(環太平洋経済連携協定)報道は下火になっているが、政府は今年(2011年)11月に開かれるAPEC(アジア太平洋経済協力)の前に基本方針、行動計画を定めることにしており、TPP問題はむしろこれからが本番である。
農文協ではこの度、『TPP反対の大義』を緊急出版した。「国益VS農業保護」「このままでは世界に乗り遅れる」といった論調をふりまく大マスコミの不見識を糺し、「反対の大義」を明らかにしたいとの考えからである。研究者から生協などの団体関係者、農家まで25名の方々が執筆、いずれも大義にあふれる主張を展開している。その中から、TPPをめぐる「わかりやすい」がゆえに世間を惑わす議論や論調のおかしさ、そのトリック性についてまとめてみた。
▲目次へ戻る
横行する数字のトリック、おかしな議論への反証
(1)前原「1.5%」発言のトリック
今回のTPP論議では、数字を利用した「わかりやすさ」が横行し、それが一定の効果をあげているようである。その象徴が、前原誠司外相の「(GDP)1.5%を守るために98.5%を犠牲にして良いのか?」発言である。これに対し「TPP論議と農業・農山村―前原外相発言を批判する」で小田切徳美氏(明治大学教授)は、「この発言以降、堰を切ったように、テレビ、全国紙において、『農業保護が国益を損なっている』『TPPに参加しなければ二流国家に凋落する』という主旨の言説が流れており、今回のTPP論議において重要な役割を果たす発言となっている」としたうえで、この「1.5%」発言のおかしさを次のように述べている。
「第一に、第一次産業のGDPシェア1・5%という数字の取り上げ方自体が問題である。例えば、産業区分を細かくしていけば、産業界が誇る自動車を中心とした『輸送用機器』でも、そのシェアは2・7%である。それどころか、製造業全体でも実は19・9%と既に2割を切っている。そして、『犠牲』の対象と示唆されている輸出であるが、それもGDPの17・5%にすぎない。仮に数字で議論するのであれば、こうした全体の状況とともに取り上げられるべきであろう。
第二に、農業の関連産業の広がりや農業の多面的機能に関する認識がない発言である。よく知られているように、食品産業全体(農漁業+食品工業+関連流通業+飲食店)のGDPシェアは9・6%であり、また農漁業を除く食品産業の就業者は775万人にも達する。TPP参加の影響は、その業種や立場により様々であろうが、何らかの形で及ぶことは意識されなくてはならない」
そのうえで小田切氏は、「1.5%」発言が及ぼす精神的な影響に注目して議論を展開。こうした発言が「誇りの空洞化」を促進し、地域で動き出した新たな挑戦をおこなう人々の出端をくじいてしまうことの罪を糾弾している。
(2)白を黒といいくるめる「鎖国か開国か」論
菅直人首相が、TPP参加に向け「関係国との協議開始」を表明した際に、「日本は今再び大きく国を開く決断をした」と発言したため、「鎖国か開国か」という「わかりやすい」話がマスコミを賑わすことになってしまった。これこそ、白を黒といいくるめるもので、鈴木宣弘氏(東京大学教授)・木下順子氏(コーネル大学客員研究員)による「真の国益とはなにか―TPPをめぐる国民的議論を深めるための13の論点」では、アメリカの手厚い農業保護(輸出補助金)にふれたうえで、以下のように述べている。
「日本はWTOルールを金科玉条のように守り、課された農業保護削減義務を世界で最もまじめに実行してきた『優等生』である。政府の価格支持政策をほとんど廃止したのは日本だけであり、農産物関税も平均で11・7%と低く、農業所得に占める財政負担の割合も15・6%で、欧州諸国が軒並み90%を超えているのに対してはるかに低い。それにもかかわらず、いまだに日本は最も過保護な農業保護国、しかも、価格支持政策に依存した遅れた農業保護国だと内外で批判され、国内世論の支持が得られないため、農業関連予算も減額され続けているのが現状である」
(3)吹っ飛んでしまった「自給率50%」
食料自給率をめぐるおかしな議論状況も生まれている。
TPP参加で自給率が40%から14%に激減するという農水省の試算に対し、TPP推進派は、関税がゼロになるまでの猶予期間のうちに構造改革で「強い農業」づくりを進めれば、自給率はそこまでは下がらないと反論している。こんな議論をしているうちに、政府目標の「自給率50%」が吹っ飛んでしまったのも、一種のごまかし、トリックである。谷口信和氏(東京大学教授)は「食料自給を放棄した例外国家への道を突き進むのか―TPPへの対応で問われるニッポンの国家の?かたち?」で、この点を鋭くついている。
「注意を要するのはTPPに対する賛成・反対の立場を超えて、日本がTPPに参加した場合、(1)自給率が現在よりも向上することはありえない、(2)自給率向上への強力な政策対応の程度に応じて低下が抑制されるが、自給率は低下して40%から14%の間のどこかに落ち着くだろうという見方については暗黙の合意が存在しているようにみえることである。だが、そこには、(1)そもそも40%という現在の水準をどのように理解すべきか、(2)これがさらに低下するという事態をどのようにみるか、という根本問題が存在している」
こうして、谷口氏は現状の自給率40%、しかも、人口一億を超える大きな国で40%は世界広しといえども全くない超異常な事態であることを明らかにし、飼料イネなどを生かした「水田活用新時代」をひらくことの重要性、大義を浮きぼりにしている。
(4)地域発のまともな試算
こうしたおかしな議論が横行するなかで、地域ではリアリティのある数字で問題に迫る動きが生まれている。本書では「TPP激震地」として北海道と沖縄の状況を紹介しているが、北海道では「地域別試算」という従来にない取り組みが進んでいることを、東山寛氏(北海道大学助教)が「道経連を含む『オール北海道』で反対する」で紹介している。
「地域別試算の取り組みは『TPP問題』を農業も含めた地域の産業・経済全体の問題として捉え返すためのリアリティを提供している。表示した2地域を見比べてみると、農業生産への影響では地域間の基幹作目の違いが鮮明に表われていると同時に、オホーツク地域では製糖・澱粉製造・乳製品工場、上川地域では精米業といったように、地域によって特色ある立地が進められてきた関連産業への影響もまた甚大であることが明らかである。『地域経済』で括られている商工業等への影響はさらに大きいものがある」
北海道では、記事の見出しにもあるように、農業団体、経済団体・消費者団体が足並みをそろえて反対しており、道経連は、TPP推進の中央(経団連)と一線を画する構えを鮮明にしている。輸出大企業とアメリカにしか目をむけない「中央」発のおかしな議論をまともな議論にしていく力は地域・地方にある。
▲目次へ戻る
「国益VS農業保護」論は、国益に反する
TPPをめぐって大マスコミは「国益VS農業保護」という「わかりやすい」構図を描き、それが農家も含め、少なくない影響をもたらしているが、この「国益」は「国益にあらず」として本書の多くの執筆者が問題を提起している。先に紹介した鈴木宣弘氏らは、「『農業保護をとるか、TPPの利益をとるか』ではなく、『一部の輸出産業の利益のために失う国益の大きさ』を考えなくてはならない」ことを実証的に示したうえで、「国益」の基本である「食料供給」についてページを割いて論じている。
「2007年から2008年にかけて起こった世界食料危機は、日本が現在の経済力を維持し続けることができたとしても、食料輸入の安定的保証を取り付けることがいかに難しいかを明らかにした。諸外国と広く協定関係を結べば、輸出規制の禁止も含めて優先的な食料供給を確保できるとの見解もあるが、仮に輸出禁止などの条項を加えることができたとしても、いざというときに自国民の食料をさておいて海外に供給してくれる国があるとは思えない。不測時においてはどの国も、まず自国民の食料確保や自国の市場安定を図るという、国家として最低限の責務を果たさなければならないからである」
「米国は、いわば、『安く売ってあげるから非効率な農業はやめたほうがよい』といって世界の農産物貿易自由化を押し進めてきたため、基礎食料の生産国が減り、米国をはじめ少数の輸出国に国際市場が独占されつつある。少数の売り手に依存する市場構造では、小さな需給変動に反応して価格が急上昇しやすく、逆に低価格化が起こりにくくなる。また、高値期待から投機マネーが入りやすく、不安心理から輸出規制という食料の囲い込みも起きやすくなり、価格高騰がますます増幅される。たとえばコメは、先般の食料危機時にも世界全体の在庫水準は前年より改善していたにもかかわらず、他の穀物が高騰しているなかでコメに需要が流れるという不安心理が増幅され、コメ輸出規制へと連鎖した」
「米国の都合に振り回された典型例がメキシコである。メキシコでは、NAFTA(北米自由貿易協定)で主食のトウモロコシ生産農家が潰れ、米国から安く買えばいいと思っていたら、こんどは価格暴騰で輸入も困難な事態に追い込まれてしまった」
そして、日本は米国の食料戦略の「標的」になっているとして、こんな話を紹介している。
「ウイスコンシン大学のある教授は『食料は軍事的武器と同じ武器であり、直接食べる食料だけでなく、畜産物のエサが重要である。まず、日本に対して、日本で畜産が行われているようにみえても、エサをすべて米国から供給すれば、完全にコントロールできる。これを世界に広げていくのが米国の食料戦略だ。そのために農家の子弟には「頑張ってほしい」と授業で教えていた』と言われる(大江正章『農業という仕事』岩波ジュニア新書、2001年)」
▲目次へ戻る
「貿易を拡大しないとやっていけない」論のまちがい
日本は貿易立国だから、貿易を拡大しなければやっていけないというのも、TPPやむなしの風潮を支える「わかりやすい」話である。しかし、本当にそうなのか。この点を本格的に論じているのが、関曠野氏(評論家・思想史家)の「世界貿易の崩壊と日本の未来」である。そこでは、「WTOやTPPの論理でもある『世界貿易』は常識的な意味での貿易とは別のもの」であり、それは、「米国が第二次大戦後に世界に強要した通商システム」であり、それが今、危機を深め、この延命のための「体制の危機の輸出」こそ、グローバリゼーションの本質だとしたうえで、その崩壊を予測している。だから、「TPPに参加しないと日本は国際的に取り残される」という風潮に対し、「何から取り残されるのか。タイタニックに乗り遅れるのは結構なことだ」ということになる。一方、日本が貿易立国だという見方に対し、関氏は次のように述べている。
「日本は例えば中韓両国のように、国内市場の狭小さや農民の貧困ゆえにアクロバット的貿易立国をやらざるをえない国ではない。世界銀行の統計では、日本経済の輸出依存度は16%、貿易がGDPに占める比率は世界170国中で164番目である。企業が国内市場だけで商売できる?ガラパゴス?が可能な国は世界でも日本だけである。
TPPへの参加は国内市場が飽和して輸出が頼りの大企業の要求だが、大企業は稼いだ外貨を溜めこんだり海外で投資したりしていて国内の経済循環に貢献していない。中小企業がベテラン従業員を失うまいと必死で雇用を維持しているのに、トヨタやキヤノンはさっさと派遣切りをやった」
▲目次へ戻る
雇用は守られず、逆に破壊する
この雇用の問題について、「TPPと日本農業は両立しない―TPPは日本を失業社会にする労働問題でもある」と森島賢氏(立正大学名誉教授・元東京大学教授)が述べている。
「農家の若い人の兼業について、一つつけ加えたいことがある。それは、TPPに乗り遅れると、日本農業は生き残れるが、日本経済は沈没する。そうなれば、農村の若い人の兼業する機会がなくなり失業する、それでいいのか、という脅しについてである」
「TPPは、いうまでもなく、農産物貿易の自由化だけを目的にしている訳ではない。特に問題なのは、EUのように、労働者の、国境を越えた移動の自由化を重要な目的にすることである。とりあえずは、そのための突破口として介護などの特殊な労働者の移動を取り上げるだろうが、こうした政治哲学を容認するなら、やがて、普通の労働者の移動も認めることになる。
そうなれば、自由貿易圏内の労賃は同じになる。例えば、中国の労賃は日本の約10分の1だから、中国の労働者が大量に日本に来るだろう。その結果、日本人の賃金は、中国人の賃金に限りなく近づくことになる。日本人の労働者が、その賃金では生活できないから不満だ、というなら会社を辞めるしかない。会社は代わりに、もっと賃金が安い中国人労働者を雇うだろう。だから、会社は困るどころか、賃金が下がることを歓迎するだろう。それゆえ、経団連会長の発言として伝えられるように、目先しか見えない財界の一部は、日本への移民を奨励せよと主張するし、そのためにTPPに乗り遅れるな、と脅すのである」
「この主張の行きつく先には、これまで先人たちが培ってきた失業率の低い、安定した、安全な日本の社会を根底から覆し、某国のように、わが身は自己責任で守る、という銃社会に変えようという主張が待っている」
*
以上、いくつかの記事について部分的にふれてきたが、他にも、本書の巻頭論文・宇沢弘文氏(日本学士院会員、東京大学名誉教授)の「TPPは社会的共通資本を破壊する―農の営みとコモンズへの思索から」を始め、田代洋一氏(大妻女子大学教授)の「TPP批判の政治経済学」、柳京煕氏(JA総合研究所)の「米韓FTA交渉における韓国政府の農業の位置づけを検証する―日本が韓国の轍を踏まないために」などなど、読み応えのある論文がそろっている。岡田知弘氏(京都大学教授)の「グローバル時代だからこそ地域内再投資力の育成と地域循環型経済づくりを」、蔦谷栄一氏(農林中金総研特別理事)の「協同はTPPを超える」など、地域づくりにむけた提言もある。山下惣一氏(農家・作家)の「農家は『自衛農業』でわが身を守る」も痛快である。
本書は、書名のように批判の書であるが、すべての書き手に共通するのは、「地域の再生」への、そして地域を基礎として、ずいぶんゆがんでしまった「この国のかたち」をまともにしていくことへの、熱い思いである。だから、地域に生き、地域をつくる農家にこそ読んでいただきたい。
今月号では、本書の発行にあわせて、「農家はTPPをこう考える」の小特集を組み、五名の農家の発言を紹介した(358ページ)。TPPをめぐるあまりに短絡・軽率な論議にはどの農家も怒りを感じているが、「反対」だけではすまされない複雑な心情や、今後の農業・経営への想いも綴られている。あわせてお読みいただき、村うちでの議論を広げ深め、軽視され続けている地域からの発信を活発にして、希望のもてる国民的議論の形成をリードしていきたい。
(農文協論説委員会)
▲目次へ戻る
こちらもご覧ください
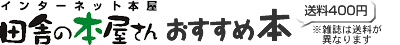
 |
この記事の掲載号
『現代農業 2011年2月号』
2011年 品種選び大特集
冷春・激夏で見えた品種力/緑のカーテンに使える作物大集合/直売所最前線/シェフと拡げる品種の世界/タネ採りしてできた 病害虫に強い品種/小力作物で地域がよみがえる、産地を守る/観光果樹園用小果樹/水田転作をもっとおもしろく/農家はTPPをこう考える ほか。
[本を詳しく見る]
|
 |
『TPP反対の大義』農文協 編 本書では、TPPへの参加がとりわけ暮らしを支える農林水産業や地方経済に大きな打撃を与え、日本社会の土台を根底からくつがえす無謀な選択であることを明らかにし、TPPに反対する全国民的な大義を明らかにします。
[本を詳しく見る]
|
 |
『自給再考』山崎農業研究所 編 マスコミを中心に語られている「食料危機」論に欠けているものは何か、危機の核心はどこにあるのか。産業としての「農業」は暮らしとしての「農」に支えられており、それゆえに「自給率」を論じる前に「自給」そのものの意味を広く深くとらえることが必要ではないか。これに西川潤、中島紀一、関曠野、宇根豊(農と自然の研究所)、結城登美雄(民俗研究家)、塩見直紀(半農半X研究所)らの学者・思想家・実践家(農家)それぞれの立場から考え応えていただいた。市場原理スタンダード、アメリカンスタンダードがグローバリゼーションではない。自然と農と食そして暮らしをめぐる循環と信頼こそが重要であり、すでに地球の各地で運動として展開され実績をあげている。それを世界に共通する価値観(グローバルスタンダード)とすべきではないかと訴える。
[本を詳しく見る]
|
 |
『進化する集落営農』農文協 編 「集落営農」とは、農業経営や地域社会がかかえる問題を解決し、人びとがはりあいをもって働き、活き活きと住み続けることができるよう地域住民が話しあい、知恵を出しあう協同活動である。必要に応じて自発的に組織されるので、本来多種多様な組織形態と活動実態をもっている。国の構造政策に対応するのが本旨ではないのである。多様な集落営農は試行錯誤と経験を積み重ねて柔軟に進化し、「地域の再生・活性化」と「効率的農業生産」とを両立する「地域営農システム」としての大きな可能性を備えるに至った農地・労働力・資本・情報の新しい結合体である。農村経済更生運動以来の歴史、政策の流れも整理しながら、全国各地の、農協も含めた具体的な実践事例を紹介、その意味と未来を論じる。
[本を詳しく見る]
|
 |
『水田活用新時代』谷口信和、梅本雅、千田雅之、李侖美 米価下落、TPP・自由化路線に抗し、水田を地域農業・産業の拠点として活かすための実践的提案の書。
[本を詳しく見る]
|
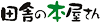
|