|
|
||
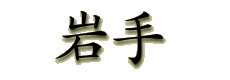 |
|
|
|||
| 成立市町村 | 文書名 |
収録 巻 |
内 容 紹 介 |
| 軽米町 | 遺言 |
2
|
「人と生れて人の道を知らずんば有べからず」で始まる格調高い遺言。人の道、凶作の心得から商人の心得、家族・使用人についての心得にいたる9条からなる。現代に通じる普遍性をもつ。 |
| 軽米町 | 軽邑耕作鈔 |
2
|
南部軽米地方の畑作指針書。飢饉に備え、日常の基本食糧として穀物と野菜を重視し、これらの作物の栽培法と組合せを詳述。東北畑作の基本型がうかがわれる。 |
| 一関市 | 民間備荒録 |
18
|
宝暦5(1755)年、一関藩の藩医による著作。飢饉時の草木の食べ方、飢えた人々への手当ての仕方、農民が飢饉に備えてつくるべき草木を説く。 |
| 盛岡市 | 山林雑記 |
56
|
盛岡藩の山林奉行などの役にあった著者が、植林した木を藩と民間とで歩分けする造林法を奨励するために書いたもの。育苗・植林法、植林地の選定、樹種について実体験をもとに詳述。 |
| 一関市 | 備荒草木図 |
68
|
一関藩の藩医・建部清庵は、領内の大飢饉に遭遇し、『民間備荒録』を出版した。本書はその付録的性格をもち、文字を読めない庶民にも一見してわかるように編まれた図集で、救荒植物を中心に104種を採録している。 |
| 安代町 | 田山暦 |
71
|
絵と記号のみによる絵暦で、南部藩領で200年にわたって利用され続けた。「盲暦」とも呼ばれ、文字の読めない人にも利用できるように工夫されている。農耕にかかわる暦注が詳しく、農耕暦の性格が強い。 |
| 盛岡市 | 盛岡暦 |
71
|
南部藩城下町の盛岡でつくられ、利用された一枚刷の暦。田山暦が明治初年に廃絶してしまったのに対して、盛岡暦は明治初年に一時中断したが、その後復活して今日まで継続している。 |
|
|
 |
秋田へ |
 |
 |
日本農書全集のトップへ |  |
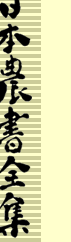
| 分野別農書一覧 | ||
| 県別索引 | ||
|
全国版 北海道 青森 秋田 岩手 福島 山形 宮城 茨城 神奈川 群馬 埼玉 千葉 東京 栃木 山梨 長野 新潟 石川 富山 福井 愛知 岐阜 静岡 |
三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 長崎 大分 熊本 佐賀 宮崎 鹿児島 沖縄 |
|